
子供の落ち着きがない原因と身体の関係性について
子供の落ち着きがない原因と身体の特徴について

発達障がいの子供に限らず、落ち着きがない子供が多いと思います。
よくネットや本などでそのような子供の特徴としては
・先生の話を聞かない
・じっと座っていられない
・動き過ぎてしまう
・覚醒や集中力を維持するために動いている
・身体の感覚が鈍いから動き回って感覚を高めている
などです。
それ以外にも作業療法士としての視点で考えてみたいと思います。
立つ時と座る時の違いで考える
落ち着きなく動いている時は身体全体が動いているように見えると思います。
しかし、姿勢によっては動く身体の幅は違って見えます。
下記がそのような例になります。
・座位の時は割と動きが少ないが、立位の時は極端に足を動かしている。
・椅子に座っている時の方が身体をソワソワさせている。
筋肉をどう動かしているか
動き回る子供の身体は早い動きに慣れてしまっています。
全身の筋肉を素早く収縮させる力は得意ですが、
持続的にゆっくりと筋肉を収縮させる力は苦手だと考えられます。
これを体育の運動に当てはめるとけんけんパーの動き(素早く身体を動かす)は得意ですが、

平均台などのバランスを安定させて歩く(ゆっくり身体に力を入れて安定させる)動きは苦手という事になります。↓

子供の落ち着きがない原因の対処法

あえてゆっくりと動かす運動を取り入れたり、だるまさんが転んだなどのゲームの中でも、身体を一瞬止める動きのある活動も効果的だと思います。
ただ、日常生活の場面では、落ち着きない子供を無理やりに動きを止めさせるのはあまり良くないと感じます。
自分が動いていることに気づくことが大切
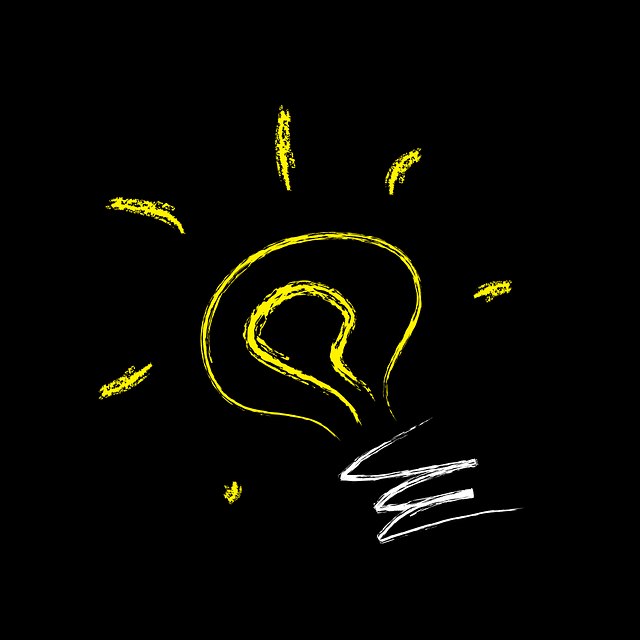
落ち着きがない子供は、覚醒や集中力を維持するために動いていることも考えられるため、無理に止めようとすると居眠りをし始める子供もいるかもしません。
大切な事は動きを止めるのではなく、その場面にあった動きに慣れないといけないことです。
学校で静かな場面で動きすぎると先生に怒られてしまいますが、中休みの時間や体育の時間は動いても怒られない。
その場の状況に合った身体の動きになるには注意をされる前に自分が動いている事で周囲に何かしらの影響を与えている事に気付き、自分の体が静止していることに気付く事が出来れば、落ち着きのなさが改善されるかもしれません。
