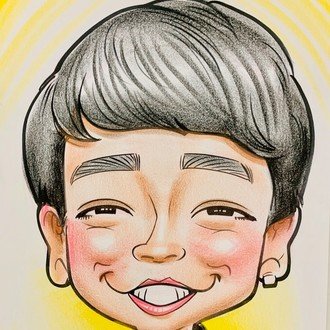腰部脊柱管狭窄症 完全攻略BOOK
No.1 戦える症状と戦えない症状
症状に対する介入はNG
まずは超基礎的な質問を先に回答しておきます。
・腰部脊柱管狭窄症の痺れに対するアプローチはありますか?
・狭窄症の下肢痛はどうやったら治りますか?
このような質問をいただくことが多いのですが、おそらくこのような質問が出る時点で病態理解が甘い可能性があります。
腰部脊柱管狭窄症は、腰椎において脊柱管の続発性退行変化に伴い神経組織と血管のスペースが減少する状態。
そもそも狭窄症はこういった状態のことで、これによって痺れや殿部痛、下肢痛、間欠性跛行が起きています。
そのため、「痺れには神経モビライゼーションだ!」とか「殿部痛にはマッサージだ!」といったそれぞれの症状に対して治療を当てはめてしまうのはNGです。
治療というのは必ず症状ではなく、病態から導き出す必要があります。
ここで最初の質問に戻りますが、
・腰部脊柱管狭窄症の痺れに対するアプローチはありますか?
→いつ痺れるの?
・狭窄症の下肢痛はどうやったら治りますか?
→何をすると痛いの?
ここが明らかにならないと戦えるどうかわかりません。
例えば、何してもどの姿勢でも足が痺れてますとなると、重度の狭窄が起きている可能性が高いため、我々が戦っていけるかどうかは怪しいです。
それこそ馬尾障害があると戦えるわけがありません。
一方で、長時間歩くと足が痛いですとなると、これは歩行中に狭窄が強まっている可能性があるので、我々が歩行の観点からできることはありそうです。
つまり、この症状の前につく状態によって戦えるかどうかを判断する必要があります。
狭窄症のリハで考えるべきこと
狭窄症術後の痺れはどのように改善していますか?
これもよく聞かれる質問なのですが、一旦冷静に考えてみましょう。
先ほどもお伝えしたように、これまた症状に対して介入を考えているという点でまずひとつ考えを改めたほうがいいです。
またここでの一番問題は、手術で回復しなかったものに対して徒手で立ち向かおうとしていることです。
基本的に狭窄症の手術では、狭窄しているものを直接取り除いたり、狭窄しないように固定を施しています。
これでも取り切れなかった狭窄症症状に対して徒手で立ち向かうというのは、どう考えても厳しいわけです。
つまり我々が考えるべきは、その症状を徒手で完全に取り切るということではなく、どのようにしたら少しでも症状の軽減を図れるのか?というところです。
言い換えると、どうしたら狭窄部位へのストレスを減らせるのか?です。
症状ではなく、病態に着目すると、必ずここに行き着くはずです。
・腰椎前弯姿勢
・腰椎後弯可動域
・胸椎回旋可動域
・股関節伸展可動域
・股関節前方不安定性
・モーターコントロール
詳しくは後述しますが、狭窄部位へのストレスを減らすにはこれらが鍵を握っています。
少しでも臨床のヒントになっていれば幸いです!!!