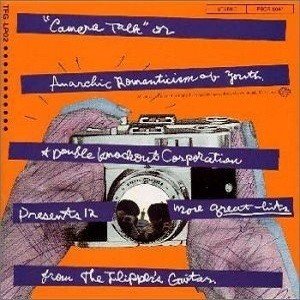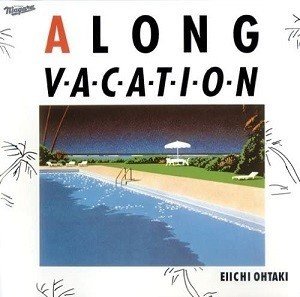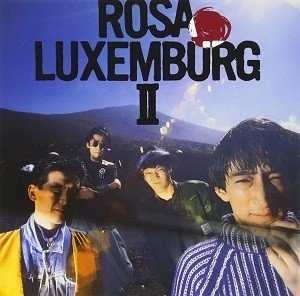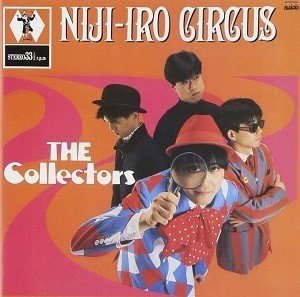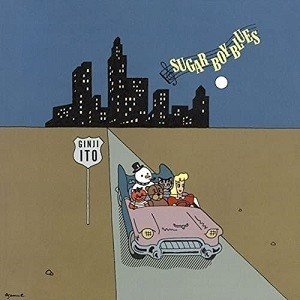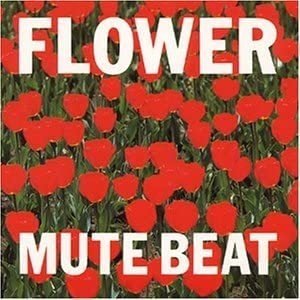#私を構成する9枚(邦楽編)
洋楽編に続いて邦楽編もやるかどうかはちょっと迷った。というのもこっちは佐野元春とか伊藤銀次とか大滝詠一とか僕としてはもうさんざん語ってきたアーティストが入っていて、自分的にはかなり今さら感あるので。
でもまあせっかく9枚選んだんだし、これをきっかけに読んでくれる人があるかもしれないのでやっておくことにした。9枚のセレクション自体は4年ほど前にやったものだが、その時にはラインアップと簡単な短評を付けただけだったので、今回もうちょっとまともなコメントを付けようと思う。
洋楽編の方にも書いたが、「私を構成する」という以上、単に「好きなアルバム」「オールタイム・ベスト」というだけでなく、そこから強い影響を受け、その後の音楽の聴き方とか何ならものの考え方を一部なりとも決定づけたアルバムという観点から選んだので、必然的に10代から20代に聴いた作品が中心になっている。
したがって、このレビューもアルバムそのものの評論というよりは、僕自身がそのアルバムをどう聴いたかというストーリーみたいなものだと思ってもらった方がいいかもしれない。
CAMERA TALK / フリッパーズ・ギター
Polystar (1990)
僕の中で時間軸が歪んでるんだけど、僕としてはこのアルバムは学生の頃に聴いたはずだと思ってたのに、今確認するとリリースは1990年であり就職して社会人2年目の初夏くらいのことで、音楽を聴く余裕が最もなかったころだと思うんだけど、当時の僕はいったいどうやってこのアルバムを熱心に聴いていたのだろう。どんな気持ちで毎日働いていたか、あの頃のことは本当にもう忘れてしまった。そしてこのアルバムだけが手許に残った。
大学には1年余分に行ったけど、それでも自分が何であるか、自分が何をよりどころにして生きながらえて行けばいいのか結局分からず、自分が何ほどの者でもなかったことに打ちのめされ、どうでもいいようなことに真剣に腹を立てながら音楽を聴いていた。その頃の僕にこのアルバムがどのように聞こえたのか。音楽と幸福に寄り添っていた学生時代から切り離され、彼らの音楽はまるでルサンチマンのように響いていたのではなかったか。
このアルバムの解説書を手書きで作ってコピー製本し誰かにプレゼントしたことを思い出した(誰にプレゼントしたかは忘れた)。このアルバムは、僕にとって生きられなかったもう一つの生だったのだろう。性急で、薄い胸と細い腕で、畏れを反語でしか語ることのできない、しかし遙かに遠くまで見えるような特別な目を持ったある短い時期にいることを歌った歴史上唯一のアルバム。誰よりも自分のことを好きすぎる男子のための作品だ。
スピッツ / スピッツ
Polydor (1991)
スピッツが売れるとは思ってなかった。こんなクセのあるアクの強いバンドは一部のマニアに好まれながらいつの間にか消えて行くんだろうと思っていて、それでもこのバンドが好きだったのは、草野マサムネの強烈に歪んだ歌詞と、それをロックの文脈に強引にねじ込んで行く三輪テツヤのギターのコンビネーションがパンクを感じさせたからだし、その中央値や最頻値からの逸脱加減がいかにも取り返しのつかない若気の至りだったからだ。
草野マサムネが書く詞世界はそれだけでは何を言っているかよく分からないほのめかしや符牒や依り代に満ちているが、それは決して思いつきや単なる雰囲気だけの語呂合わせではなく、彼の中の現実とは別の世界線にある彼しか知らない物語のテーマソングだったり挿入歌だったりするからなのだ。誰しもそうした自分しか知らないオレ物語、ワタシ物語を持っているはずで、そのことをひそかに歌うところが草野の信頼の源泉なのだと思う。
そのことは国民的バンドのひとつと言ってもおかしくないくらい売れてしまった今でもまったく変わっていなくて、草野が世界に合わせたのではなく世界が草野を発見したのだし、僕たちもそこに自分自身のオルタナティブなオレ物語、ワタシ物語を発見したのだ。僕たちが草野の描く世界の断片にどこか既視感を抱くとすれば、そうした世界観がなにがしかの普遍性を内包している見間違いようのない証左。若気の至りの勇気についての作品。
A LONG VACATION / 大滝詠一
Niagara (1981)
このアルバムは1981年に発表された日本のロック史、ポップス史に残る不朽の名作であるが、当時「カナリア諸島」がどこにあるか知っていた日本人は人口の1%もいなかったはずだし、「渚をすべるディンギー」がイメージできたリスナーも皆無に近かったろう。ビーチリゾートのプールサイドで休暇を過ごす者すらほぼいなかった時代に松本隆が描き出した「長い休暇」は、そもそも僕たちの生活実感からかけ離れた架空の世界の風景だった。
1980年代前半というのは、高度経済成長が終わり、社会がそれなりの達成感とともに「がむしゃらに働く」「カネを稼ぐ」ということから「本当の豊かさ」とか「幸福感」とかいう目に見えないものに価値を見出し始めた時期である。村上春樹が「羊をめぐる冒険」を発表したのが1982年、糸井重里の「おいしい生活」というキャッチコピーが使われたのは1983年。大衆消費社会の到来に伴う価値観の変化は音楽においても新しい何かを求めた。
それは僕の高校時代と重なっている。田舎の高校生であった僕にとって、このアルバムは自立とか都市生活とかいうものと地続きになっているはずの、大人の世界につながって行くものだったのだと思う。この時はまだ大滝詠一という人のこともほぼ知らず、この作品が彼のキャリアの中でどう位置づけられるものかも当然分かっていなかったが、本作の完成度は文脈を超えたもの。十代のあの時期にこの作品と出会えたのは幸運なことだった。
ROSA LUXEMBURG II / ローザ・ルクセンブルグ
MIDI (1986)
申し訳ないが僕はボ・ガンボスから入ったクチでローザはリアルタイムで聴いてないのが本当に悔しい。どんとは僕より3歳年上で大学の先輩にあたり、僕が大学に入学した時に西部講堂横にあった軽音の部室に様子を見に行ったが何か雰囲気に気後れしてそのまま帰ってしまった。それくらい近くを通っていながら現役のローザのライブを見ていない。ライブ告知のフライヤーとかそこら中にあったのに。とりあえず行っとけばよかったんだ。
とにかくどんとの吐き出すもはや意味性とか関係ないレベルの発語の快感に基づいて書かれたとしか思えない歌詞(「さいあいあい」「あらはちょちんちょちん」とは)、ベースにツェッペリンなどのハードロックの素養がありながら80年代マナーのニュー・ウェーブを意識したリフやカッティングを聞かせる玉城のギター、そしてどんとの自在かつ訴求力と喚起力に富んだボーカルなど、ロックとしての原初的な誘因をすべて具えたアルバム。
どんとはやはり唯一無二の天才だったと思うが、世に出るにはそれを見出し、世界に理解され得る言語に置き換えることのできる媒介が必要だった。本作は人間関係的には限界に近い環境の中で、どんとが玉城宏志という音楽面での強力なパートナーを得て衝動を音楽に結実させた作品。ナゾのメイクや遠慮のない歌詞やコミック・バンドかと思わせる悪ふざけの背後に、驚くほど硬質な音楽への愛情と確かな技量があったことが分かる傑作だ。
SOMEDAY / 佐野元春
Epic Sony (1982)
誰しも多感な時期に熱心に特定のアーティストの音楽を聴くことがあるだろう。人によっては長くその音楽を聴き続け、そこからいろんな影響を受けることもあるだろう。時として、そのアーティストと出会わなければまるで違う人生を歩んでいたというくらい大きな影響を受けたりするかもしれない。僕がそうだった。僕にとってそれが佐野元春であり、そしてその出会いとなったのがこのアルバム。死ぬほど聴いたと言っても過言ではない。
佐野元春を入口として聴いた音楽、知った文学、カルチャーも少なくない。毎週熱心にラジオ番組を聴き、リクエスト・カードを書き、最後にはペンネームを認知してもらえるようにもなった。音源は残らず買い集め、ライブにも当然出かけ、個人がホームページを作る時代が来た時には佐野のデータベース・サイトを立ち上げた。それが縁で本人と会わせてももらったし、CDのブックレットに評論を書かせてももらった。ファン冥利に尽きる。
このアルバムの何が僕を打ったのかははっきりしている。それは、このアルバムで佐野が、自己決定と自己責任を両輪とする「自由」の在り方を、それを足がかりにして都市の中に自分の居場所を見出すべきことを教えてくれたからだ。もちろんそれは簡単なことではない。だが、因襲的な共同体の相互依存に中に僕たちの居場所がない以上それは必然のはず。運命のアーティストが佐野であったことは僕にとって何より重要であり幸運だった。
虹色サーカス団 / ザ・コレクターズ
Baidis (1988)
誰しも多かれ少なかれ世界に対する説明し難い違和感を抱えて生きている。日々の生活の中では何とかそれに折り合いをつけて人の中に紛れているし、理屈で考えればそれが正しいということも分かるのだが、それだけでは収まりのつかないやりきれなさや情けなさや、あるいはやり場のない怒りや苛立ちを僕たちは持て余している。特に十代の頃、僕たちはそのような得体の知れない自分の中の怪物と毎晩闇の中で格闘したのではなかったか。
厄介なのは、そうした理屈では説明のつかない収まりの悪い感情の中にも、いくばくかの真実が含まれているということだ。性欲であったり攻撃衝動であったり何だかよく分からないけど胸のこのあたりでゴソゴソ行儀悪く動き出そうとするもののことを僕たちは知っているし、それが僕たちにとってこの上なくリアルで扱いにくくてバカっぽくて、しかし大事なものだということを僕たちは知っている。コレクターズはそのことを歌っている。
そうした「僕を苦悩させるさまざまな怪物たち」を最も手っ取り早く野に放ち、思う存分暴れまわらせる方法のひとつがロックなのは自明だ。というかロックというのはもともとそのための音楽なのだ。ギターが鳴っている間、僕たちは束の間の勝利を得る。それが朝の光とともに跡形もなく消え去っても、僕たちの中にまるで残像のようにその感覚は焼きついてゆく。それをよりどころに僕は成長してきた。そう、ザ・コレクターズとともに。
SUGAR BOY BLUES / 伊藤銀次
Polystar (1982)
僕は伊藤銀次から何を学んだだろうか。それは例えば佐野元春から教わったビート・カルチャーへの眼差しのような文学的なものでもなく、加藤ひさしが見せてくれたモッズ・カルチャーでもなく、大滝詠一の音楽の背後に広がる広大なポップ・ミュージックの歴史でもなかった。僕が伊藤銀次から学んだことは、いい歌詞といいメロディの曲はいい曲だという本当に身も蓋もないそれだけの事実。しかしそれはポップ・ミュージックの真実だ。
もちろん銀次の音楽の背景にも脈々と受け継がれたポップ・ミュージックの系譜があり、そしてまた同時代の英米のポピュラー・ミュージックの先進的なマナーへの鋭い感受性があった。なによりそこには音楽という表現形式に対する限りない敬意と愛情、それからそれを商売道具に身を立てて行くプロフェッショナルとしての矜持と造詣があった。徹底してメロディの完成度を求められた木崎賢治プロデュース作品においてそれは特に顕著だ。
この作品とこのひとつ前のアルバム「BABY BLUE」は高校生の頃毎日のように聴いた。今でも歌詞カードなしですべての曲を歌える。たとえ甘いラブソングであっても、イージーなダンス・チューンであっても、あるいは気取ったティーンエイジ・ブルースであっても、完成されたポップ・ミュージックにはそれ自体に高い批評性があり、歌い継がれるに値する凄みがある。美しいメロディを優しく、細い声で歌う銀次は僕の永遠のアイドルだ。
FLOWER / ミュート・ビート
Overheat (1987)
インストのレゲエ・バンドというだけで「ちょっと…」と敬遠する人も少なくないと思うが、ミュート・ビートは確かに他に似たバンドが見当たらないワン・アンド・オンリーの存在である。洋楽でも邦楽でも人のボーカルが入った音楽しか好んでは聴かないのが僕もそうだったのだが、このバンドだけは別。初めて聴いたときからその他に類のない音楽に圧倒されもう30年以上聴き続けている。彼らの音楽にしか埋められないものがあるのだ。
まず印象に残るのはこのバンドの中心であるこだま和文のトランペットである。ボーカルの代わりにメロディを奏でる彼のラッパは饒舌だ。歌詞こそないものの、彼のトランペットは間違いなく何かを歌っている。華のあるつややかなトランペットのリード・メロディはインストの先入観を裏切る極めて個的で記名的なものだ。しかし、繰り返し彼らの音楽を聴いているうちに、それを本当に支配しているのが何なのかが少しずつ分かってくる。
それはストイックなバック・トラックの陶酔だ。繰り返されるレゲエのリズムに潜む呪術的な熱、正確無比なビートが作り出す可視化された時間。こだまのトランペットが饒舌であればあるだけ、その背後にあるリズムのクールな発熱が際立つ。このコントラストこそが彼らの骨格だと言っていい。今でも気持ちがざわついたときにはミュート・ビートを聴く。混乱を整理し高ぶりを鎮める一方で、強く何かをひと突きする、これはそんな音楽。
omni / ゴメス・ザ・ヒットマン
Vap (2003)

このセレクションの中では唯一の21世紀の作品。僕としては30代になってから聴いたアルバムで、正直30過ぎてから新しい、それも邦楽のアーティストをこのレベルで好きになるとは思わなかった。もちろんそこにはそれなりの経緯があり、物語がある訳で、それはここでは詳しくは書かないが、ともかく僕の手許にはゴメス・ザ・ヒットマンというアーティストのアルバムが残され、それは僕の新しいフェイバリットになった。ああ、善き哉。
ネオ・アコースティックから影響を受けた爽やかなギター・ポップが彼らの持ち味ではあるが、このアルバムはストレートなポップ・ソングであるよりも、そこに、ある種の内省とか陰りのようなものを含んだブルースに近いもの。精緻に積み上げられた言葉のひとつひとつは日常的なものであるが、そこに描き出される光景は日常の時間の流れがふと止まる一瞬に顔を上げた僕たちが目にするシーンであり、その意味で優れて文学的なものだ。
ゴメス・ザ・ヒットマンは都市の深い闇よりは郊外の明るい住宅地に似合う。郊外は、人々が眠り、目覚め、そこからまたどこかへ「出かけて行く」場所。そこは旅の根拠地であり、予め移動を前提とした場所、そしてまた帰るべき場所。そこには都市とは違った種類のブルースがあり、目に見えない些細な起伏を抱えた日常がある。毎日小さな旅を積み重ねながら生活している僕たちの物語を奏でて行く、これは新しいサバービアのブルース。