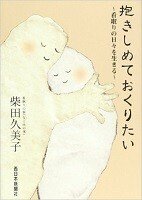第17回「臨終ですと告げられた瞬間に命が終わるのではなく、そこからが魂の受け渡しをする時間の始まりなんです。」柴田 久美子 氏
柴田 久美子(しばた くみこ) 氏
島根県出雲市生まれ。日本マクドナルド(株)勤務を経た後、平成5年より福岡の特別養護老人ホームの寮母に就任。平成14年に人口600人の離島で、看取りの家『なごみの里』をスタート。自然死で抱きしめて看取る実践を重ねる。平成26年に拠点を岡山県岡山市に移し、地域の無償ボランティア“エンゼルチーム”と看取り士とともに、慣れ親しんだ自宅での旅立ちを支える体制を作る。一般社団法人日本看取り士会会長。吉備国際大学短期大学部非常勤講師。神戸看護専門学校非常勤講師。介護支援専門員。著書に『看取り士日記』(コスモ21)、『いのちの革命』/舩井勝仁氏との共著(きれい・ねっと)など多数。
日本看取り士会(なごみの里)

テンプル――
今回はおそらく日本、いや、世界で初めて“看取り士”という職業を始められ、現在は岡山を拠点に、看取り士さんの養成や講演などでもご活躍中の柴田久美子さんにお話を伺います。 先に少し説明をさせていただきますと、“看取り士”というのは、医療や介護サービス、そしてエンゼルチーム*と連携しながら終末期にある方々に寄り添い、ご本人の希望する場所で旅立ちを支援するためのスペシャリストのこと。とくに臨終の際には旅立つ方の手を握り、体をさすって、最期は抱きしめて見送ります。 そうした生から死へと移行していくプロセスのなかで、あちらの世界に旅立とうとしている方々は安心して旅立つことができ、いっぽう見送る人は旅立つ方々からエネルギーを受け取り、魂を磨くことができるということ。柴田さんは、そんな、まさに旅立つ人も看取る人も幸せを感じられるような最期の時をプロデュースされています。
*エンゼルチーム……“日本看取り士会”が進めている仕組みのひとつ。在宅での介護や看取りが必要な旅立つ方々を支えるために、家族や親族、友人、地域の方々(エンゼルチーム協力員)などの無償ボランティアのこと。主に旅立つ方々の見守りと緊急連絡を行います。全国に121支部が展開している(2015年時点)。
柴田――
ありがとうございます。菜央子さんには以前、うちの看取り学講座*にも7日間の内観*にもご参加いただいていて、私の言いたいことをよく理解してくださっているように思います。ということで今日は、私がとにかく今できるだけ多くの人にお伝えしたいことについて、いきなり核心部分から話し始めてしまってもいいですか?
*看取り学講座……柴田さんをはじめ、看取り士養成講座を修了した“看取り士”を講師に、死と生、看取りについての新たな価値観や心構えを学ぶ少人数限定講座。ほかに、看取り士になるために必要な根幹を身に着ける“看取り士養成講座”があり、ともに医療従事者や介護職員なども多く参加しています。詳細はこちら
*内観・・・外界からの刺激が遮断された道場の中に、屏風で狭く仕切った空間を作り、その中で約7日間、朝6時頃から夜9時頃まで母親、父親、兄弟など身近な人に対して、してもらったこと、して返したこと、迷惑をかけたことの3つのテーマにそって思い出していく。
テンプル――
えっ!? 何でしょう。
柴田――
これはもうずいぶん長い間、講演や書籍などで言い続けていて、なかなか皆さんに伝わらないことなんですけれども……。人間というのは赤ちゃんの時にプラスのエネルギーをまとう存在=光として生まれてくるのですが、成長して年をとっていくに従いマイナスのエネルギーを重ね、やがて死を迎えます。その際に積み重ねたマイナスのエネルギーを全て浄化し、誕生の時と同じように再びプラスのエネルギーをまとう存在=光へと転じた後、その愛の光を愛する人々に受け渡して天に還っていくんです。
そうして亡くなる人の愛の光を受け継いだ人は、それによって自分の魂を膨らませ、進化向上していくことができるんですね。私たちはこの命のバトンリレーをするために生まれてきたと言っても過言ではありません。ですから、皆さんには死にいく人の看取りをネガティブなイメージではなく、魂の進化向上の機会だととらえていただきたい。そして、是非ご家族や近しい方などを看取る際にはしっかりと抱きしめたり触れたりして、“魂のエネルギー=光”を旅立つ方から受け取っていただきたいのです。と、もう結論を言ってしまいました(笑)。
テンプル――
いきなり核心からのスタートありがとうございます(笑)。もうこれでインタビューが終わってしまいそうですが、いくつか質問をさせてください(笑)。
まず、人は死ぬ時にマイナスのエネルギーを浄化して……と仰いましたが、それまでの人生で重ねてきた悪行も全て浄化されるんですか? 例えば、善行より人を殺したり、裏切ったりと、生きている間にいくつも悪事を重ねてきた人も亡くなる時にはそのマイナスエネルギーは昇華され、プラスに変換されているのでしょうか? 看取りの方に受け渡されるのは、愛のエネルギーだけなんですか? でも、悪いカルマかカルマとして、その人の魂に刻み混まれて記憶として残っていきますよね・・・?
柴田――
どんな人でも亡くなる時には浄化され、光となって旅立ちます。子供に『悪いことをしたらここへ行くよ』とか言って、地獄絵の描かれた絵本を見せる親がいるそうですね。でも実はそういう地獄やカルマというものはなくて、人間の行動を抑制しようとした宗教観や歴史に基づく「マイナスの念」が、私たちを支配しているだけなのではないかと思います。
テンプル――
イメージすると、たとえその人が生前悪事を重ねてきた人であっても、亡くなるときには、その人の魂は浄化され、魂にこびりついていたホコリや汚れはどんどん削ぎ落とされ、いわゆる『真我』だけが残っていると。だからその人が死に瀕して発しているエネルギーは愛と光だけになっている、いうことですか?
柴田――
自然分娩で有名な吉村正先生*も仰っていますが、人間はみな善で生まれて善で還っていくんですよ。
*吉村正……1961年より愛知県岡崎市にある吉村医院の院長を務める。以降、医療介入を極力行わない自然分娩にこだわり、約2万数千例のお産を手がける。2014年(平成25年)1月以降、吉村医院を田中寧子現院長に継承。著書に、『「幸せなお産」が日本を変える』 (講談社+α新書)など。
テンプル――
では、死のプロセスにいる方を抱きしめたり触れたりすることで、どうしてエネルギーを受け取ることができるといえるのでしょうか?
柴田――
それは、その方々と1つになれるからです。私は抱いて見送るということを始めてから34人目の時にそう確信しました。その時のエピソードをお話しますね。
私に気付きを与えてくださったのは、認知症と高次元機能障害を持つ、社会的には非常にワガママな74歳のお爺ちゃんでした。倒れる前も自分の思うがままワガママに生き、倒れたあともワガママに生きた方でした。その方は、なごみの里に入居してくださっていたんですが、会いたくない人には絶対に会わないし、食べたくないものは食べないけれど1日6食も召し上がる。家族が見舞いに来ても『会いたくない』とガンとして会わなかったんですから徹底しています。
女性スタッフがお風呂で身体を流そうとすると『妻でもないのに触るんじゃない』と怒るetc.……一事が万事その調子。亡くなる前日も、夕方にいらしたかかりつけのお医者さんに『ワシはこんなところ嫌だね。リハビリしてもう一度一人暮らしに挑戦したいんだ。リハビリのいい病院を紹介しろ』と仰るくらいお元気で(笑)。
ところが夜中に容体が急変したので、私はすぐに彼のところに駆けつけて腕に抱きかかえました。そして、真夜中の2時半頃に息を引き取られてから9時頃までずっと抱いていたんですが、体を離すまでの約7時間、ずっとお爺ちゃんの体が熱いんですよ。私はこれまで様々な旅立ちの過程に立ち会い、その方々を腕に抱いて看取ってきた経験から、魂に重さがあるのを知っていました。ですが、ボリュームもあるのだということをこの時に初めて知ったのです。そのお爺ちゃんの魂はそれはもう大きな塊で、まるでキリストみたいだなと思ったことを覚えています。その後、お爺ちゃんが10歳も20歳も若返ったようにとてもハンサムになったのに驚きました。
テンプル――
自分の気持ちのまま自由に生きてこられた自由な方だったから、魂もそんなに大きなボリュームになっていたんでしょうか。言い換えるなら、人に気を使いながら常識的な範囲で生きていくと、魂も萎縮してボリュームが小さくなってしまうってことですか?
柴田――
だから小さな水槽で泳ぐ金魚みたいになるのではなく、みんなで枠から飛び出してもっと自由に生きようよ!と言いたい。もちろん法に触れることをしてはいけないし、何より人生の最期に魂のエネルギーを誰かに渡すというのは大前提なんですけれど。その魂のバトンリレーが人類の進化に繋がるんですから。
テンプル――
次世代に受け渡す愛のボリュームを増やしたいと願うなら「自由に生きよ!」なんですね。それにしても、看取りの際にはそんなに長く抱いているんですか。
柴田――
私や看取り士は旅立つ方が亡くなる前からそばにいて、その方の体が冷たくなるまで触れていますね。その間は魂のエネルギーを受け取ることができるからです。看取りをされるご家族にもそのようにお勧めしています。

一般的に人は亡くなるとすぐに全身が冷たくなると思われているようですが、実は違うんです。個人差はありますが、なかには2日間もずっと温かかった方がいらっしゃるんですよ。顔や手などの表に出ているところはすぐに冷たくなりますが、背中やお腹、脇の下などは比較的温かさが残る部分。ですから体の至るところを触ってほしいんです。体がカチカチに硬直してきてもまたほどけます。
テンプル――
硬直した体がまたほどけるとは驚きです。エネルギーを受け取れているかどうかは、体の温かさが基準になるんですか?
柴田――
そうです。愛する人が触れると、その温もりはまた変わるんですよ。私たちプロが触れるのとご家族が触れるのとでは熱さが違うの。そして、亡くなった方から温かさとともに何か伝わってくるものが必ずあるんです。
テンプル――
ということは、お医者さんや救急隊員、看護婦さんは、魂のエネルギーを受け取る機会が多い職業ということになりますよね。
柴田――
いえ、受け手がエネルギーを受け取ろうと心を開いているかどうかが重要です。こうした真理を知っていれば可能ですが、心をブロックしていれば単なる業務に終わってしまうんじゃないでしょうか。
葬儀屋さんでも二手に分かれますよ。心のある方はどんどん輝いていかれますが、そうでない方はエネルギーを受け取れずに沈んでいくというか。
私は常々『パワースポットは亡くなる人なのよ』と言っています。瀬戸内寂聴さんは『人は旅立つとき、25mプールの529倍ものエネルギーを縁ある人に渡していく』と仰っていますが、もし本当にそうだとしたら、それを受け取らないなんてもったいないと思いませんか。旅立つ人にしたって、命のバトンを受け渡すチャンスは一度きり。そういうわけで、私たちは看取り士メンバーのなかで最高齢の方に、『亡くなる時にはみんなで行って、冷たくなるまでさするからね』とすでに約束しているんですよ(笑)。
テンプル――
私は以前インタビューで、看取りをされているドクターにお目にかかったんですが、その時に私は『たとえばどこかで野垂れ死んだとしても、必ずあの世から迎えが来るから孤独に死ぬなんていうことはない。だから大丈夫なんだ』というようなことをお話したことがありました。でもこう聞くと、たった1人で死ぬよりは、自分が生涯かけてためてきた愛や光のエネルギーを誰かに受け渡しして死にたいと思いますよね。
柴田――
そうでしょう。確かに死ぬ時はお迎えが来ますから、本人的には孤独死ではないのです。でも、周りの人にとってはとてももったいないのよ。魂のエネルギーを受け取る貴重な機会を無駄にするわけですから。
テンプル――
私の友人のお父様が先日、肺炎をこじらせて病院で亡くなったんですが、彼女には看取りの知識がなかったので抱きしめることなく見送ってしまったそうなんですね。身体を拭いたり死化粧を施したりはしたそうなんですが。それくらいでもエネルギーを受け取れたんでしょうか。
柴田――
お友達はお父様と同じお部屋にいらしたんでしょう?だとすると、エネルギーだから目には見えないけれど、お部屋の空気が絶対に変わっていたと思うんですね。とても綺麗だとか居心地がいいとか、何か感じられたんじゃないでしょうか。シャワーと一緒でその場の空気を浴びるだけでも、心がオープンで魂が覚醒していたら十分にエネルギーを吸収できると思います。それに、体を拭いて死化粧をする時に体を触っていますから、きっと受け取られていますよ。
テンプル――
そうですか、それはよかった。でも仮に看取りの知識を持っているにせよ、親を抱きしめるというのは結構ハードルの高いことではないですか? 日本人はとくに「抱く」という行為を普段しませんし。スキンシップの一環でハグを当たり前にする欧米人とは、そもそも習慣が違います。
柴田――
確かに、あの世への移行の段階に入った方を『抱いてください』とご家族に言っても、皆さん抱けないんですよね。お母さんやお父さんは子どもを抱くのに、同じ親子で立場が逆転するだけでなぜこうも難しいことになるんでしょうか(笑)。でも親の側は子どもに抱かれるのを待っているものです。
ある女性のケースですが、64歳になるお父様が余命1か月と宣告されてから3日目に抱いたんですね。そうしたら抱き返されたんです。お父様はきっとその時を待っていたんですね。でもね、どうしても抱くのが無理なら手をつなぐだけでもいいの。

テンプル――
親子だけでなく、夫婦でも抱くのが難しそうな人たちもたくさんいます(笑)。
柴田――
すでに関係性の終わっているご夫婦はたくさんいらっしゃいます。そういう方々はもう別れたほうがいい(笑)。先日も、94歳のご主人と87歳の奥様のご夫婦が離婚したいとお話しなさり、お別れになりました。
テンプル――
ええ~っ!
柴田――
奥様はずっとパーキンソン病だったんですが、旦那様は全く面倒をみてくれなかったそうなんです。それで、旦那様が肺がんで余命1か月と宣告された時に別れを告げたんだとか。
テンプル――
そんな状況で離婚をされるとは勇気のいる決断ですし、周りの方々に大きな波紋を投じたでしょうね。私もある病気を持つ女性と電話でお話したときに、ケイシー療法で対応するなら必ずご主人の協力が必要になりますとお伝えしたら『それは絶対に嫌です!』と。電話口でワナワナ震えているのが分かるくらいでした。
柴田――
そういうご夫婦を私はたくさん見てきましたよ。奥様が我慢しているケースがほとんどでした。だからノホホンとしている旦那さん達は気を付けないと、自分の最期を妻が看取ってくれないことになります。
テンプル――
これからは『最期に抱きしめましょう』という前に『元気なうちに、その人が最期に抱きしめられたい人なのか、抱きしめたい人なのか、相手をよく見極めておきましょう』と伝えないといけませんね(笑)。そうでないならさっさと別れて、臨終の際には看取り士さんにお願いしたほうがよっぽど心安らかに最期を迎えられるのかも。
柴田――
そうなんですよ。それまでの暮らしの中で小さな心のすれ違い、わだかまりの石を心に積み重ねてきたような方には、私はすぐに別れなさいと言うんです。誰でも人生いろいろあるけれど、最期には幸せであってほしい。我慢なんてしなくていいんです。楽しく自由に生きていかないとね。
テンプル――
そういう意味では、先ほどお話に出てきたワガママなお爺ちゃんはまさに生き方のお手本だと言えますね。聖職者だとか学校の先生だとか、何かいいことをしている人だとかいうのではなくて、自由に生きている人だったからこそ、幸せな最期を迎えることができた。そして、柴田さんに気付きを与えるほどの何か大きなエネルギーを溜めていたわけでしょう。普通なら先ほどの奥様みたいに我慢の人生を強いられてきた人に軍配が上がりそうなものですが、そうでないところが面白いというか。
先にお話した友人のお父様も、それは好き勝手に生きてきた人だったらしいんです。でも、お父様が亡くなってからまだ1か月と経っていない時期に、その友人がいわゆる何人かの見える人から口を揃えて『お父さんはもう成仏しています』と言われたんだそうで。それで、『普通、人は49日の間この世をさまよってから浄土に行くといわれているのに、聖人でも善行を積んだ人間でもなく、しかも母や私をさんざん振り回した父が?』とすっかり気が抜け、自分もこれからは好きなように生きようと思ったらしいのです。
柴田――
そのお父様、きっとキリストですよ(笑)。ご友人はお父様から『好きなように生きよ』というメッセージとともに魂のエネルギーを受け継いだということ。だからワガママに生きたらいいの。自分の魂を閉じ込めるのではなくて解放して生きることです。そうすると亡くなる時に魂が光るわけ。
テンプル――
私はエリザベス・キューブラー=ロス先生*に2度お会いしました。彼女も最期は孤独だったようですが、歴史に残るような功績を残した人が『神様なんていない』だとか、それまでの自分のイメージと功績を覆すような毒舌を吐きまくっていたのが何というか潔くて自由でいいなと思いましたよ。
*エリザベス・キューブラー=ロス……医学博士、精神科医。ターミナルケア(終末期医療)、サナトロジー(死の科学)のパイオニア。死を受容していく心理的過程を「否認と孤立」、「怒り」、「取引」、「抑鬱」、「受容」に分類した“死の受容5段階モデル”を提唱。著書に、『死ぬ瞬間』(読売新聞社)、『ライフ・レッスン』(角川文庫)、『人生は廻る輪のように』(角川文庫)等。
柴田――
本来、死というのはプラスとマイナスの両面を持っているのですが、肉体に囚われてしまうと途端に死はマイナスになってしまいます。でも魂の側から見ればプラスなんですよね。キューブラー=ロス先生はずっと魂の側にいたけれど、多分色々と我慢していらしたんでしょうね。それで最期に病気という重荷を背負い、肉体の側に反転してしまった。人間もまた誰もが陰と陽のエネルギーを持っていますが、その調和を図ることが大事なのではないでしょうか。
たとえば体と心や魂のバランスとか、現実とスピリチュアルな世界とのバランス、社会と自分とのバランスetc.……。自由に生きたほうがいいとはいえ、やはりそうしたバランスを上手に取るのは、誰にとっても最期まで課題なんだと思います。だから私は最近、魂を一輪車に例えているんですよ。目に見える世界と見えない世界を繋げるちょうど軸のところにあるのが魂で、どちらかにバランスが偏ると車輪がうまく回らないでしょう。
テンプル――
なるほど。でも現代において死というものは、まだマイナスに偏っているような気がします。子どもに祖父母の死を見せないようにしているという話もよく聞きますし。お葬式から帰ると玄関でお塩をまくのも、穢れの発想からですし。
柴田――
そうなんです。昔はお年寄りと一緒に暮らす家族が多かったから、もっと死が身近なところにありました。私もよく『亡くなった人が火の玉になって飛んで行った』というような話を祖母から聞いたものです。そういう目に見えない世界に触れる機会がたくさんありましたけれど、今は見える世界だけの論理で死を語っている。だから遺体が穢れとして扱われ、故人をゆっくりと見送ることもできない。
テンプル――
かつて、オランダにジョゼフ・ルーロフというシュタイナーみたいなサイキックがいたんですが、彼は人が亡くなってから数日間は、荼毘にふすのを避けるようにと言っていました。魂がまだ繋がっているから、魂のコードが切れるまで待てと。
でも今の日本では、病院で亡くなった途端にベッドから霊安室に移動しないといけないし、かといって病院にもそう長くいられないので、すぐに葬儀屋さんに連絡をして迎えに来ていただかなければならない。それから親戚や関係者に連絡をして、次は葬儀の準備etc.……。そのバタバタとした手続きの中で、故人を抱いて見送るなんてなかなかできませんよね。ようやくひと段落した時には故人はもう棺の中で、そうなるともう何か距離感ができてしまうという。
柴田――
70年前の敗戦とともに、日本は命の重さを知ることよりも“スピードと効率”を大事にする社会になってしまったじゃないですか。病院のベッドを早く空けないといけない、それには葬儀屋さんを呼んで運ばなければいけない。そういう早く早くという風にスピードと効率を求めて、何でもお金に変えてしまった私たちの愚かさ。旅立ちの場面は出産と一緒で、とても神聖なものです。そこで最期に生み出される魂の光を受け取るためにも、私たちはゆっくり待たないといけないの。
看取りというと、皆さんはきっと臨終の前までのことを想像されますよね。でも実はそうではなくて、臨終からが看取り=“魂の受け渡しをする段階”なんですよ。もともと「臨終」とは、「臨命終時=りんみょうしゅうじ」の略語。命の終わる時に臨んで、医師が『家族の皆さん、医療の上ではもうすることがありません。今度は皆さんが命を受け取ってください』と告げると、そこから家族はたっぷりと時間をとってお別れをするんです。それが看取り。この時間をかけるプロセスを省いてしまったら看取りとは言えません。なぜって、目に見える物質としての体しか見ていないから。
私たちというのは死んだら終わりというのではなく、永遠に生きる命そのものじゃないですか。そして、魂のエネルギー=光を子孫に残し、魂を重ねて、人類の進化に繋げていく。それが命のバトンになるのです。こういう本当の旅立ちというものを、もっと多くの人に知ってほしい。そして、臨終ですと告げられた瞬間に命が終わるのではなく、そこからが魂の受け渡しをする時間の始まりなんだということを。

テンプル――
なるほど。臨終にはそういう意味があったんですね。
柴田――
社会学者の上野千鶴子先生がよく仰るのは、“臨終コンプレックス”といって、医師からの「ご臨終です」という宣告の時に立ち会わないといけないように感じている日本人がいかに多いかということ。でも実は宣告の時に立ち会う必要はないんです。むしろその後からでいいから、旅立つ人を抱きしめることのほうが大切なの。だから臨終の時までは、医師や看護師さんにケアをお任せしていたっていい。先にお話したように“臨終”の意味をしっかり理解して、温かいうちに抱きしめることができればそれで十分なんです。
テンプル――
ご著書のなかで、『たとえ介護ができないとしても、最期の1週間でいいから一緒にいれば、その人は幸せな死を迎えられる』と書かれていますね。
柴田――
はい。マザーテレサは『人生のたとえ99%が不幸だとしても、最期の1%が幸せならば、その人の人生は幸せなものに変わる』と仰っています。さらに『5分間抱きしめるだけで、その方の人生はその瞬間に幸せに変わる』とも。私は看取りの活動をするなかで、常にこの言葉を心に刻んでいます。ですから極端に言えば、もし介護ができず臨終の宣告時に立ち会えなかったとしても、最期の瞬間に旅立つ人のそばにいられたらそれでいいのです。
テンプル――
老親の介護をしたいと思っていても、現実となると仕事や自分の家庭の事情などから、そうもいかないというのが現代の悲しい風潮。それで、どこか後ろめたい思いを抱えている人も多いと思うんですよね。でも、1週間付き添っていればいいということなら誰でも気が楽になりますよね。まして最期の瞬間だけでもいいのなら、救われる人がどれだけいることか。ですから、できればせめて臨終の時にはその方のそばに行き、体が温かいう ちに抱きしめましょうと。
柴田――
体が冷たくなってからでも抱いたほうがいいんです。何故かというと、残された家族にとってのグリーフケアを完成させるには、やはり触れることが重要だから。体で感じないとなかなか喪失感って克服できないんですよ。
グリーフケアというと、私たち看取り士メンバーの一人が話してくれたこんなエピソードがあります。彼女があるホスピスの看護師をしていた時のこと。ある女性が亡くなった後にまず自分が抱き、それからご家族に代わる代わる抱いてくださいと促して、ゆっくりとお別れをしてもらったんだそうです。翌朝、ご家族が故人を連れて帰られたんですが、その時に彼女が見た光景に感動して電話をかけてきてくれたんです。『柴田さん、私はもう何十年もホスピスで旅立つ方を見送ってきましたが、あんなに皆で素晴らしい笑顔をしているご家族を見たのは初めてです』と。
胎内内観*によってグリーフケアを行ったケースもあります。自分が旅行に行っている間にお母様が自死をされたある女性は、それからというものずっと自分を責めて生きておられたんですね。でも胎内内観によってお母様の魂と重なったことで、それまでの鬱々とした気持ちがすっかり晴れたと、人生を元気に歩んでいかれるようになりました。
それから胎内内観を通じて、家族の看取り直しをされた方もいらっしゃいます。それは40年前にお父様に旅立たれた看護師さんで、看取り士の研修生でもありました。当時彼女は7歳で、家にお母さんもお兄さんもいないという時にお父様が台所で倒れます。その後、救急車を待つお父様から一言『大丈夫かい?』と聞かれたらしいのですが、返事ができないままお父様は搬送先の病院で亡くなるんですね。彼女はお父様と死に別れてから何年経ってもその場面をずっと覚えていて。父は私に一体何を聞きたかったんだろうという疑問をずっと持っていたんですね。
それで胎内内観をして、当時のことを思い起こします。その時、現れたお父様に『何に対して大丈夫って聞きたかったの?』と聞くと、『一人になるけどお留守番するのは大丈夫かい?』って仰ったんだそうです。彼女が大丈夫よと答えたら、次のシーンに出てきたのはお通夜の日、自宅で白い布をかけて眠られているお父様の姿。『お父さん、お父さん』と呼びかけるとむくっと起き上がって彼女を抱きしめたのでびっくりしたけれど、いま自分はこうして看取りをしている最中なのだと気付いたんだそう。そして、彼女を抱きしめるお父様に『私は大人になったから、一人ぼっちじゃないし、もう大丈夫だよ。お父さん、ありがとう』と伝えることができたというんですね。するとお父様は笑顔になってまた布団に入って眠りにつきました。お父様が離れた後、彼女の体が実際にとても熱くなり、魂を受け取ることを肌で実感したということでした。
*胎内内観……全てを肯定的にとらえ、旅立つ人の愛や思いを受け入れるために行うワーク。柴田さんが福岡の内観道場「感性塾九州」で10回以上経験した内観に、自身の看取りの経験を合わせた独自の手法で、とくに母親との繋がりを重視した内容が特徴。
テンプル――
胎内内観には素晴らしいエピソードがたくさんありますよね。私は以前、胎内内観ではなく、7日間の内観の方に参加させていただきましたが、7日間かけて魂レベルで両親を看取った感じがしました。最初は柴田さんから誰もが3日目あたりから号泣すると聞いても自分は泣かないだろうな、関係ないと思っていたのですが、とんでもない。参加してみたら初日、それも10分もしないうちから脱水するのではないかというくらいに大泣きするという事態に(笑)。7日間ずっと父と母をテーマに内観し続けたのですが、私に振り分けられた日程は、母親は5日半で父はわずか1日半。私は父親と割と仲が良かったので、記憶も思い出もたくさんあるんですが、母親の日数に比べると父親のこの扱い。父親とは、子どもにとってなんとかわいそうな存在なのかと切ない気持ちになったことを覚えています(笑)。
当時、光田が内観に参加した時の詳しい様子は、ブログ「毎日がエドガー・ケイシー日和」下記の記事をお読みください。
私の内観体験―1
私の内観体験―2
柴田――
そうでしたね(笑)。でも菜央子さんに限らず、他の方の場合にも父をテーマにする時間はとても短いの。何故かというと、私が考える“へその緒理論”に基づいているから。要は、へその緒で繋がれていた母との関係が花丸にならないと、他者との関係も花丸になりえない、というのが私の持論なんです。10月10日の間に私たちが育まれるあの胎内はまさに慈愛の世界であり、それをとことん皆さんに体感してほしいというのが、とにかく母という存在にこだわっている理由。
それに、ご飯を作ってくれて、おっぱいを飲ませてくれ、オムツを替えてくれるetc.……。子供の頃はやっぱり一般的に、お父さんよりお母さんから面倒を見てもらう比率のほうが高いでしょう。そういう母の無償の愛に気付くことによって、自分の内なる愛を揺り起こしていくというのが内観の最大のテーマなので。
テンプル――
そういうことなんですね。ところで、柴田さんがこの世界に入るきっかけになったことの1つが、ある夜に聴こえた“声”だったそうですね。
柴田――
はい。これは何冊かの著書にも書いていますが、当時の夫と九州へ移り住んでレストランを開いていた頃の話です。開店をしたものの売り上げが伸びず、その夜も赤字の帳簿をつけながらそろそろ休もうと思ってベッドに横になり、ウトウトしかけたその時。『愛こそが生きる意味だ!』という男性とも女性ともつかないような声が突然聴こえてきたのです。同時に足元には白い光もサーッと降りてきまして。ちょうど夫は入院していて家には私一人きり。ですから声の主が誰なのかは分からないながらも、これがいわゆる天の声というものかと思いました。『そうか。私は人生を間違えていた。もうお金のために働くのはやめよう』とすっと腑に落ちたのです。
それで翌日には経営していたレストランをクローズ。その後、幼い頃に看取った父の幸せな最期を思い起こし、その最期を迎えている方々を支えたいと願って特別養護老人ホームで働き始めるようになりました。後になって、その声のメッセージはマザーテレサが聴いた言葉と同じだということを知り、不思議な気持ちになったものです。
テンプル――
レストランを営んでいらしたことがあったんですね。でもメッセージを受けた翌日に、さっそくお店をたたむというその潔さはすごい。意外だったのは、かつてマクドナルドで社員としてバリバリ働いていた時代もあったということ。そこから看取り士の道に進むという、いわばリアリティからスピリチュアリティの世界への振れ幅の大きさもすごいです(笑)。
柴田――
ええ(笑)。でも最初、私はどちらかというとスピリチュアルな世界が嫌いだったんです。というのも代々出雲大社の氏子である家に生まれた私は、幼い頃から家族に『将来は大社の巫女になるように』と言われていて、いわゆるうち流の巫女教育を父と祖父から受けて育ってきたんです。それで幼稚園にも保育園にも入らなかったため遊び相手がいなかった私は、いつも野の花や蝶々なんかと戯れていましてね。いつしか自然に見えない世界と交流するようになっていました。
それが高じて、たとえば親戚の叔母が来ると、『おばちゃん、そのうちこういう風になるよ』とか『おばちゃんのそばに○○さんがいるよ』とか平気で言うようになってしまって。それを大人が面白がって、私のところに物やお駄賃を持って聞きに来るようになりました。そういう状況がどんどんエスカレートしていったある日、このままこういうことを続けていたらいけないとふと気付いて、それからというものすっかり無口に。学校にも当然のごとく全く馴染めないという時期が続きました。そういう偏り過ぎた世界にいたので、今度はまた真逆の世界にいったんですね。今振り返るとバランスを取っていたのかなあと思います。
テンプル――
今は一輪車にうまく乗れる中庸のところにいるんですね。
柴田――
そうかもしれない、この年齢でやっと(笑)。
テンプル――
柴田さんは以前『私の人生はこれからで、まだ序章だ』と仰っていましたが、いよいよこれから柴田さんにとっての本番が始まるんでしょうか。どんな活動をしていかれるのでしょうか?
柴田――
いま日本は2025年という大きな節目を目前にしています。どういうことかというと、2025年に約800万人の団塊世代がいわゆる後期高齢者の仲間入りをしますが、その中に47万人の死に場所難民がいると厚生労働省が発表しました。つまり、これから高齢化社会と孤独死の時代が到来するということ。そんな状況で、もし膨大な数の命が、たとえば孤独死でそのまま失われるだけだとしたら、人類にとって大きなマイナスじゃないですか。
そうではなく、そのエネルギーをいただいて、人類の進化に繋げていかないといけないんです。それには、これまで一般にマイナスだと思われていた死のイメージをプラスに転換していく必要があり、それをするのが私の役割だと思っています。だから、これまで私が抱きしめて見送ってきた体験や知識を皆さんにお伝えしながら、死の意識改革をしていくことが今後の大きな課題。そしていざ問題の時期に差し掛かったら、看取り士さん達と一緒に死に場所難民と言われる方をどこまで救済していけるか。また、いかになるべく多くの方のお力をお借りしながら進めて行けるか。それが、これからの私の10年という総仕上げの時期にかかっていると思っています。
テンプル――
壮大な目標ですね。でもこれから高齢化社会になり、死に場所難民が増えるとなると、誰にとっても他人事ではない問題になるといえそうです。若い世代が減って老老介護が当たり前の時代になれば、介護はもちろん死ぬのもひと苦労。自宅で家族のみで行う看取りはますます難しくなるでしょうから、看取り士さんの出番はますます増えるいっぽうですよね。
柴田――
すでに現時点で、自宅ではなく病院で最期を迎える人が約8割もいるのです。でも本当は、自宅で介護や看取りをすることはそんなに大変なものではないんですよ。私の祖父は、私が中学校3年生の時に96歳で亡くなったんですが、身長が180cmと当時にしては身体が大きくて。そんな祖父の介護を母と私の2人でしていたんです。当時は今のように紙オムツもないしもちろん布団に寝ていましたけど、別に大した問題が起きることはなくて。だから私には介護が大変だというイメージがないの。
ご家族の看取りに関してよく相談を受けるんですが、先日は福岡にお住まいの67歳の方から、『母の余命があと1週間だから、病院を退院して家に帰してあげたい』と連絡を受けましてね。その方はずっと一人で94歳になるお母様の面倒を自宅でみていらっしゃった方で。お母様も頭がしっかりされていて『家に帰りたい』と仰ったんですね。でも相談員さんが、67歳のお嬢さんだけでお母さんを看取るのは無理だろうという判断をしたの。
私は一体何が無理なんだろうって思いましたよ。なぜなら、もうお母様は点滴もしていないし口からも食べないので排泄物もないわけだし。それなのに、専門職の方がいきなり大変ですと仰ると、娘さんもそうなんだと思ってしまうんですね。たまたまそのお嬢さんのご友人と私が友人で、彼女が私に電話をしてくれたので、お母様のご希望通りに家に帰してあげることができたんですけれど。現実にそれから4日で、穏やかに旅立っていかれました。

そういうわけで、介護や看取りが大変だと仰る方には、どうしてそんなに重たく考えてしまうんだろう。何に囚われているんだろうと言いたい。看取りの時もずっとその方の面倒をみている必要はなくて、寝たければ寝ればいいし、その間は放っておけばいいんです。日本人は真面目な国民性だからか、根を詰めて鬱やパニックになってから私どもに電話をかけてくる人がたくさんいらっしゃいます。
でも、そこまで自分を追い込まないでほしい。親だってちっともそんなことを望んでいないんです。 人間は死ぬということを、もっとちゃんと全員が受け入れるべきですね。死なないと思っているから話がどんどん複雑になってくるんです。人間は誰もが100%死ぬんですよ。
テンプル――
死ぬのは生まれることと一緒で、自然な生の営みということですよね。
柴田――
そうです。ですから私は高齢者の方には、歩けなくなったら“這う”ことをお勧めしています。日本では西洋文化の影響で車椅子やベッドを使うようになってしまいましたけれど、もともと人間は生まれてからしばらくの間は這っていたんだから。無理に立ち上がって歩かなくてもいいんですよ。こういうことからも生死が繋がっているというのを実感し、人間というのはすごいなとつくづく思います。
テンプル――
皆がそうやって生と死を同じようにプラスのこととしてとらえるようになったら、まさに革命だといえますね。死に直面したとき無駄に悲しむ人が減るし。たとえばテレビなどで芸能人の訃報が流れているとき、目にするのが悲痛な面持ちと陰鬱な声で伝えるレポーターの姿。それが死に対するマイナスのイメージに、追い打ちをかけていますよね。
柴田――
そうですね。だから意識改革が必要なんです。実は、高齢者の方が孤独死されているのを見つけるのは東京だとヘルパーさんが多いんですよ。そのショックで仕事を辞めてしまうヘルパーさんも多くて・・・。東京でヘルパーさんが人材不足だというのにはそういう理由があり、それも深刻な問題になっているんです。でも、万一ヘルパーさんが玄関に入って亡くなった高齢者の方を発見したとして、プラスの死生観を学んでいれば別に動揺することはない。先にお伝えしたようにその方にちゃんと触れ、逆にエネルギーをいただくという看取りができれば、旅立つ人も見送る人もともに幸せな最期を経験することができるんです。
テンプル――
なるほど。まずは身の周りにいる人たちから意識改革を図ろうかしら。この人に自分の魂のエネルギーをあげたいと遺言を書いておくことから始めよう。それから逆に、この人の魂のエネルギーが欲しいというのもリストアップしておこうかな。えーと。柴田久美子さん、小林正樹さん、入佐明美さん。一応兄の名前も入れておかなければ・・・(笑)。
柴田――
アハハ、そうそう。物ではなくて魂の遺産相続ね(笑)。私の友人で花作家をしている森直子さんは、こういう話をすべて理解してくれているから、冷蔵庫に「自分がもし倒れていたら柴田久美子を呼ぶように。そして彼女に息子2人を呼んでもらって、私のことを抱かせること」と書いた紙を貼ってあるんだそうです。彼女は私の言いたいことをよく理解してくれていて、「息子たちに魂を受け渡さないと、私の生きてきた意味がなくなる」と言ってくださっているんですよ。
テンプル――
看取るのは家族でなくてもいいんですよね。
柴田――
ええ、そうです。愛おしいと思う人なら誰でも。だから皆で看取りあえばいい。そう思えば今を生きることが不安じゃなくなるし、死ぬ時にも安心して旅立てるでしょう。上野千鶴子先生は、仮に死ぬ時に一人だとしても、どうせ傾眠状態といって寝る時間が増えていくし、目が開いた時にはスカイプを使えばいいからちっとも寂しくない。何も困らないわ、とさえ仰っています(笑)。
テンプル――
いやー、実際に最期が近くなったら人恋しくなるかもしれませんよ。
柴田――
ここに来て手を握って、と言うかもしれない(笑)。私は元気なうちから弱音を吐いて、皆で来てねと言っておきます。そして、その代わりにエネルギーをあげるんだからと、威張って死んでいきますよ(笑)。
テンプル――
そういう風に見送る人、旅立つ人が対等な関係になれるのがいいですよね。看取りをしてくれる人に面倒をみてもらい、お礼にこれまで積み重ねてきた魂のエネルギーを贈るという。だから、私はこれから死ぬんだから親切にしなさいよ、とか言ってね(笑)。
柴田――
そんな冗談を当たり前に言えるくらいに、皆がプラスの死生観を理解する社会になったら、全国の施設にいる80万人のお爺ちゃんお婆ちゃんがどれだけ救われることか。マザーテレサはこれまでに3度、訪日されているんですが、そのときに「この国は愛に飢えている」と仰っているんです。私が最期を迎えた時、マザーに『見てください。日本はこんなに豊かな国になりました』と胸を張って言えるよう、一人でも多くの方と一緒に命のバトンを手渡せるような社会を実現していくこと。それがいま私が持っている大きな夢なんです。
今日は貴重なお話しをお聞かせいただきまして、ありがとうございました。インタビュー、構成:河野真理子 / 写真提供:國森康弘
■柴田さんのご著書