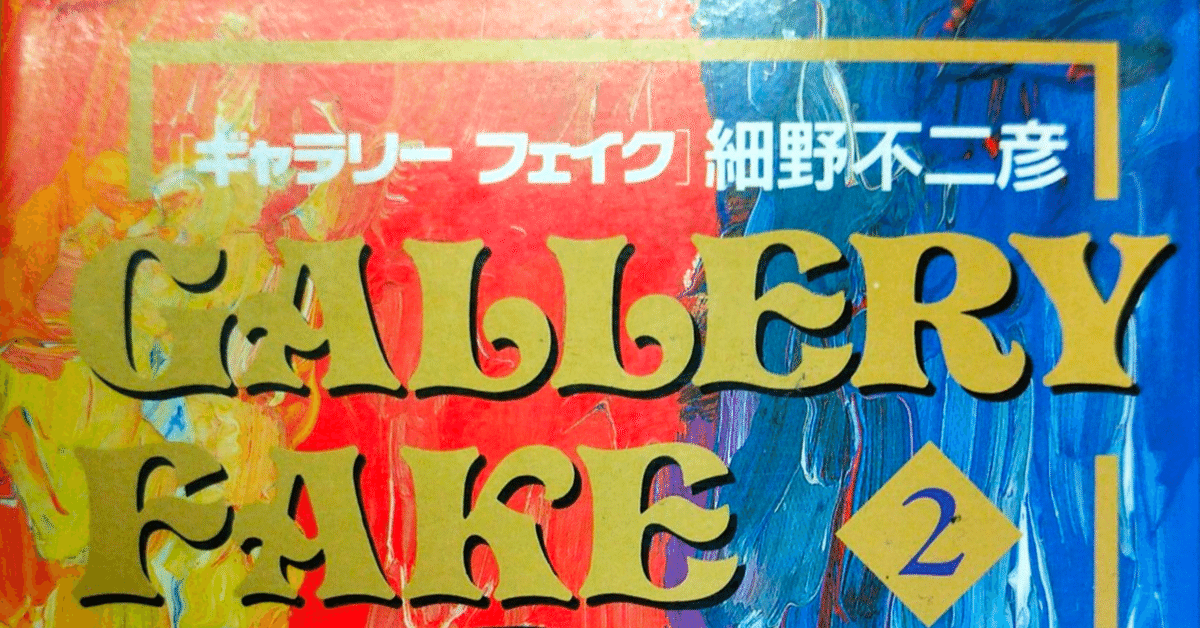
自分がオトナになったと感じたら、この「人を騙してニセモノを高値で売りつける話」を読め
「限りある時の中で 輝けますように」
MAN WITH A MISSIONの"your way"という曲の一節である。
僕はこの曲が好きだ。
浪人している時は、毎日欠かさずこの曲を聴きながら予備校へ行った。
高々人生80年のうちで、今輝けずにいつ輝くのか、そういった臥薪嘗胆の思いを胸に深く刻み込むためだった。
人生には3回のモテ期があるという。
これはただのジンクスにすぎないが、とはいえ誰しもが人生の中に一瞬の煌めきのような瞬間を持つと思う。
その人間が世界で一番に輝ける瞬間を一生の間に一度は持つことができると思う。
同じ様に、名作と言われる作品の中には必ず同じような煌めきが見て取れる。
名シーンという言葉で代用されることもあるが、これでは言葉が安すぎる。
煌めきとは、あまりの眩しさに目を背けたくなるような、それでいてしっかりと目に焼き付けたくなるような、そんな一瞬でなくてはいけない。
僕の好きな漫画に「ギャラリーフェイク」というものがある。
贋作専門画廊「ギャラリーフェイク」とその主人である藤田を中心として話が展開していくオムニバス形式のアート・ミステリーだ。
この漫画を描いた細野氏は、ギャラリーフェイクだけで実に34巻にも及ぶ作品群を作り上げた。
巻数からもお分かりになるように、この漫画は間違いなく日本漫画史に残していいほどの名作である。
しかし、この名作を名作たらしめたのはほんの序盤のある一幕であった。
ミケランジェロの辰
ギャラリーフェイク第2巻の第二話「監獄のミケランジェロ」にその瞬間は立ち現れる。
主人公である藤田は贋作画廊の主人として後ろ暗いビジネスに手を染めているのだが、同時に美術品の天才修復師としての一面も持っている。
そんな彼にも当然下積み時代は存在していた。
この話はそんな彼の回想がメインになる話である。
劇中よりも数十年前、当時一介の美大生に過ぎなかった藤田は、とある監獄の天井に絵を描くというアルバイトを引き受ける。
とはいえ、彼はまだまだ見習いの身。
メインで描くのは彼ではなく、その監獄に収監されていた「下田辰平」という男であった。
下田は元々入れ墨の彫師を営んでいたらしい。
ただの彫師とは言え、ちゃんと絵の勉強も積んだ男だから、仕事はしっかりとしているという紹介を受ける藤田。
しかし、彼の腕に見え隠れする入れ墨にどうしても気後れしてしまう。
下田は、またの名を「ミケランジェロの辰」といった。
♢
天井画作成の作業は困難を極めた。
自分の真上に空を押し込めるようにして存在している天井へ直角に筆を突き立て、常に上方を見上げながら作業を行うその様は、創作活動と言うよりも、むしろ苛烈な肉体労働に近いものがあった。
時が真夏であったことも体力を大きく削る要因となった。
下田と共に仕事をする内に、藤田は彼との親交を深めていった。
自分の弁当と引き換えに、藤田は彼が元々イタリアに留学していたことを知った。
彼の持つフラスコ画への熱意は鬼気迫るものがあり、実際に彼の画才からは非凡なる魅力を感じ取ることができた。
どうやら下田は元々ルネサンス美術に傾倒する美術青年だったらしく、藤田はこれこそが彼を「監獄のミケランジェロ」たらしめているファクターなのだと思った。
しかし、これは大きな間違いであった。
天井画は元々西洋画に特有のものであったが、それに敢えて東洋美術の要素である菩薩をモチーフとして描き込むセンス、艶めかしいほどに肉感的なそのフォルム、そして全てを見通すような慈愛と壮絶さに満ちた眼差し。
これら全てが藤田の目線を、意識を、惹きつけて離さなかった。
厳しい肉体作業から逃げ出したいと思った彼を繋ぎ止めたのは、監獄に繋ぎ止められている男が作り上げようとしている一枚の絵であった。
「われ反り返るはシリア人の弓のごとし!」
ある日、藤田は下田の背中にミケランジェロのピエタをモチーフにした入れ墨が彫り込んであることを知る。
ミケランジェロのピエタと言えば、それまでの「ピエタ」という題材に対する解釈を大きく覆した彫刻の傑作として今なお名高い美術彫刻の一つの頂点である。
しかし、その眼にはどこか天井画の菩薩と重なるものがあることを、彼は見逃さなかった。
同じくして、藤田は下田の罪状が殺人であることを知る。
下田の妻は不貞を働いており、それに逆上した彼は浮気相手ともども殺してしまったのだという。
内臓が元々弱く、この刑務作業により急速に体調を悪化させる下田。
「病んでるのは身体だけではない」という言葉が突き刺さる。
彼は文字通り身も心も削りながら絵を完成させんと、天井へ立ち向かっていた。
「こいつをやり終えねえ限り……オレは死んでも死にきれねえっ!!」
病状悪化を心配する藤田へ言い放った、彼の不退転の決意を表した言葉である。
藤田は、ここからの彼の図画の様子を、ルネサンスの天才ミケランジェロによる、システィナ礼拝堂の天井画製作時の手記の一節を引用しながら振り返る。
我が筆は常に頭上にあり!
絵の具は床にしたたりて豪奢な模様を成す!
わが脚は腰を貫き尻でようやく釣り合えり。
足元は目に入らず、そろりそろりと歩むのみ!
わが面の皮は引き張られ、後方に折られて結ばるる!
われ反り返るはシリア人の弓のごとし!
(ギャラリーフェイク第2巻p42より)
むせ返るような室内、気温は高く、高い湿度は何もせずとも額に汗をにじませる。
最早あらゆる体液が顔から吹き出し、目も霞み、意識が朦朧になったとしても、彼は筆を手放さなかった。
藤田は、確かにここにかつての天才ミケランジェロの姿を見たのである。
これ以降の話については実際に単行本を購入して確かめてほしい。
全てのものには終りがある。泡沫のように浮いては消えゆくものを掴み取るのが下田の仕事であったとだけ残しておこう。
名作の煌めき
初めに話したように、全てのものには煌めきがある。
常に輝き続けるものが無いように、逆を言えば永遠に暗闇に沈み続けるものも存在しない。
それはちょうど、流れる川の水しぶきのように、一瞬かもしれないが、確かにその瞬間の美しさは誰かの目に残るものとなる。
菩薩の天井画を描き続ける下田の姿はお世辞にも美しいと言えるものではない。
汗にまみれ、鼻水は垂れ、よだれをたらしているオジサンの絵が一般的な美のイデアにたらしむるものではないことは分かっている。
しかし、この絵は、漫画における「美のイデア」におよそ最も近づいた絵なのではないかとも思うのだ。
人の命の輝きは、ちょうど星の生命が終わる瞬間に大爆発を起こすように、直視することができないほどに強く激しいことがある。
それから目を背けないというのもまた才能であるし、それを掬い取るのもまた才能である。
このシーンは最大限「限りある時の中で輝いた」人の生きざまを描いたものなのであろう。
細野氏による「ギャラリーフェイク」はこの絵が描かれた瞬間に成功が約束されたものだと思う。
このシーンと出会うことができて、僕は「人生を捧げること」の尊さを知った。
過労死や行き過ぎた滅私奉公の精神が問題視され、己の働き方に対して誰しもが疑問を投げかける現代だからこそ、美術という「経済的に割に合わないライフワーク」に人生を捧げることの尊さを教えてくれる本作は一層読まれるべき価値を持つのである。
いいなと思ったら応援しよう!

