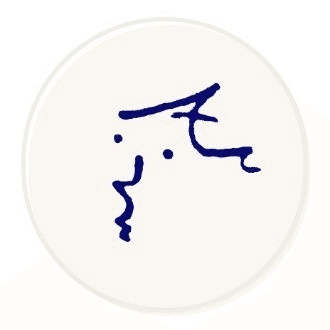ぼくたちは何を基準にサービスを選ぶのか
良いサービスってなんだろう。
ぼくたちは何を基準にサービスを選んでいるんだろう。
どうすればもっと多くの人にサービスを利用してもらえるんだろう。
KPI 全然上がらないじゃん。
そんなことを考えだして、モヤモヤが限界なので、書きなぐります。
結論
ぼくたちは、自分の好きな価値観で自分の世界を埋め尽くすためにサービスを選ぶ
なぜそう思ったのか
自分がサービスを選ぶ感情や好きなサービスに対して抱く感情を探って、みつけた共通点がベースにあります。
サービス選定の共通点
ブランドへの共感
サービス、もしくはブランドの価値観へ共感する。自分らしい、と感じる。それが、強くなると、サービスを利用することに誇りや安心を感じるようになる。
代替のきかない体験
他のサービスでは得られない体験がある。そしてそれは、共感する価値観に基づく体験。より強く価値観を共有するために、ぼくらはサービスを利用する。
期待を超える変化
サービスを利用することで、自分に変化が起きる。ブランドへの共感は、その変化への期待でもある。発生する変化はその期待を超える必要がある。その変化は自分の価値観を肯定するもの、でもある。
ストレスの芽生え
サービスを利用することで、新しいストレスが生まれる。サービス利用前の暮らしには戻りたくない、という感情。それは、単に利便性が失われるから、ではない。サービス利用で得られた充足感がなくなることが大きい。自分の価値観通りに暮らせないストレス、かもしれない。
理解と所有意識
サービスのあり方、使い方が努力なく理解できる。わからないものは、無意識に嫌う。サービスのすべてを理解できた、と感じるとき、強い所有意識と帰属意識が芽生える。所有したと感じるサービスは、簡単には代替えしない。重要なのは、理解した、自分には扱えるぞ、という実感。実際には、知らない、もしくは理解できない機能があっても、自分がそう認識していなければ問題ない。
たとえば、Google の場合
わかりづらいので、特定のサービスで考えてみる。
ブランドへの共感
なぜ Yahoo! ではなく、Google なのか。
トップページに検索しかないミニマムさ。自分から検索しないと何も起きない能動性。何かを知りたい、学びたい、という欲求をより強く満たしてくれるのは、Google。自分と似た思想や価値観に基づいて設計されている、と感じることが、共感を生む。
代替のない体験
代替はない。類似サービスはあるが、Google と同じ価値観のもと、同じ規模と品質でサービス提供する競合を、ぼくは知らない。
期待を超える変化
何かを知りたい。その期待に Google は大抵答えてくれる。知りたい情報への高いアクセス性は期待を超える。ググって無理なら諦めてしまうほどに、信頼している。何かを学ぶために検索する、その行為と意思が肯定されているようにさえ、感じる。
ストレスの芽生え
Google のない世の中はストレス。知りたいことへ最短でアクセスできる。無駄な情報が一切省かれた操作で。検索結果だけをみれば、Yahoo! でも同じ結果は得られる。しかし、それは自分の価値観と一致しない。価値観と行動の不一致は大きなストレスになる。
理解と所有意識
Google はきっと誰でも使える。言葉を入力するだけ。(実際には知らない機能もたくさんあるが、)簡単すぎて、ツールとさえ、感じない。Google は、第二の脳。外部脳。もはや自己の拡張にさえ思えてくる。価値観にも共感して、すべて理解したと感じるサービス。もはや、代替先を探す理由がない。
結論再び
ぼくたちは、自分の好きな価値観で自分の世界を埋め尽くすためにサービスを選ぶ。
ぼくのなかでは、ほぼ事実。ぼくと似たような感覚は、多かれ少なかれ、多くの人が抱いているのでは、と思う(そんなことないです??)。
だからぼくはこう思いました。
ずば抜けたサービスを作りたいなら、
『 つべこべ言わずに価値観ドリブン。 』
普段、サービスの改善案を考えていると、どうしてもデータやフレームワークに頼るときがある。KPI を確実に上げなければならないときは、特に。
数字をもとに検証することは、とても重要。でも実際には、それだけじゃ、KPI は大きく伸びない。失敗しないことを前提とした、ありきたりな改善だと、KPI の伸びも想定の範囲内。
大きく KPI を伸ばす = ユーザーさんにもっと利用してもらうには、きっと、サービスの魂ともいえる価値観や哲学をベースにした変化が必要。もっとサービスへの共感を抱いてもらえるような。
しかし、雇われデザイナー・マーケッターにとっては、結構それは難しい。どれだけ論理的に説明しても、価値観は価値観。感性の域をでない。ぼくの考え方が間違ってるんじゃないか、どデカイ失敗になるんじゃないか、とか余計な心配ばかり先にくる。
だけど、そればかり繰り返していると、きっとデザイナーとしても、マーケッターとしても成長しないのでしょう。なにより、面白みのない大人になってしまいそう。
雇われとか、創業者とか、部下とか上司とか、デザイナーとか、エンジニアとか、誰の担当だとか、責任だとか、細かいことはさておいて。
良いサービスを作るために、誰よりもサービスについて考えて、サービスの実現したい世界感を描いてカタチにする。その過程で恥をかいてもよし。周りが許してくれるなら、全力で挑戦する。三振してもいい。誰かが挑戦してたら、全力で肯定する。絶対そのほうが、良いものを作れる。
サービスの価値観を大事にしよう。
***
共感したぞー、という方、シェアやスキ頂けると素直にとてもうれしいです。
ではでは、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!