
「福祉実験ユニット『ヘラルボニー』の双子の兄弟が挑む新しい福祉と社会のつなぎ方」松田崇弥さん文登さん(後編)
柿次郎:
Dooo!今回もヘラルボニーの松田双子の兄弟に話を聞くぞ~~~!!!
Dooo!!今回も3分違いで生まれた双子の兄弟「ヘラルボニー」の松田崇弥さん、文登さんにお話を聞きます。

知的障害のあるアーティストの作品をプロダクトにして世の中に発信する「ヘラルボニー」。プロダクトの一つでもあるネクタイは、あの、乙武洋匡(おとたけひろただ)さんも、愛用しています。


また、最近ではアートに限らず、手話を使ったラップイベントの企画など
様々な観点から社会と福祉をつないでいます。現在はそれぞれ岩手と東京で暮らしながらヘラルボニーの仕事をつくり続ける松田さん兄弟。そんな双子ならではの苦労や、お互いの存在に助けられたことなど、後編では松田さん兄弟の人生にフォーカスしてお話を聞きます。

双子で東京・盛岡の2拠点生活
柿次郎:
お二人は双子でしかもまぁ、東京、盛岡っていう二つの拠点でヘラルボニーっていうものが機能していて、そこを初め、それぞれの土地でやろうと思った理由というか。
文登:
僕らは岩手県出身だったってところと、一番最初に、岩手県花巻市にある「るんびにぃ美術館」っていうそこのアーティストさんと、一緒に契約を結ばせてもらってスタートしているっていうところがあるので、「その時の思いというものを忘れないようにしようね」っていうところから花巻市に会社としての登記を置かせてもらっていて・・・

柿次郎:
それ、実際にやってみて、ありますか?メリット。
崇弥:
やっぱりメリットはありますね。

文登:
確かにそうですね。
柿次郎:
そっか、そっか。それって結構仕事の起点は東京の方が大きかったりするんですか?
崇弥:
そうですね。やっぱり何やかんや東京の方がチャンスは転がっているなっていうのはすごく感じますけど、やっぱりアイデンティティとして、岩手に根差しているっていうところのアイデンティティは大切にしていきたいって思いはあるので。
柿次郎:
いや、凄く羨ましいんですよね。このお話を聞いて。僕は一人の会社で、一人で東京と長野の二拠点生活をしているんですけど、ずっと一人なんですよ。だからこう、東京で人と打ち合わせする、飲んだりするっていう時に、いろいろな機会が生まれる。で、長野で暮らしたい。長野の仕事もちょっとずつ、動かしているんですけど、その回数が一人なんですよね。で、これは結構、人間関係って「今度飲もうよ」って話が急に仕事の話に発展したりするじゃないですか。こう、機会のセンタリングみたいなものがその瞬間上がるわけですよ。サッカー言葉であれですけど。東京だとすぐ、上げたセンタリングが3か月ごととかに帰ってきたりするんですよね、あの時の話、本当にしようよ、と。でも、長野で一人であちこちに行っていると、特にローカルってそのセンタリング、いつ帰ってくるかわからないですよね。5年後なのか、10年後なのか。それを双子で・・・ほぼ同じ顔!!
崇弥:
笑。たしかに!でも、すごく助かるんですよ、本当に。東京ですごく親しくさせていただいた方が「ちょっと岩手行きたいんだよね」って言われた時に文登に「ぜひ、アテンドよろしく!」みたいな。
文登:
絶対電話がかかってきて「〇〇さん来るから、岩手の〇〇に案内しておいて!」みたいな、僕が・・・。
崇弥:
「案内しておいて!」なんて言ってない!「案内してくださいね」って。
柿次郎:
そこで役割がちゃんと分かれて、そこを聞いてて羨ましいのと、あらゆる経営者とか活動している代表とかは「自分の分身が欲しい!」って絶対思っているんですよね。
崇弥&文登:
分身・・・確かにそれはあるかもしれないですね。
柿次郎:
めちゃくちゃ羨ましい~~!!
文登:
こっちが岩手でやったものが、こっち(東京)で生きるときもありますし、東京でやったものがこっち(岩手)で生きるので、こっちのセンタリングがそのまま岩手に来て、「俺がゴール打つ!」みたいな。
双子ならではの苦労
柿次郎:
それは何かめちゃくちゃいいな。でも言うても、双子で、その一緒に育って、仲はいいから今、一緒に会社やられているんだと思うんですけど、双子ならではの苦労とか?
文登:
そうですね、例えばほかのスタッフの人には本当に優しく出来るのに、崇弥には本当に小さいこと、些細なことでも、すごく強く言ってしまって、そもそもの小さいことからおかしくなるよね?
柿次郎:
許せなくなっちゃう?まぁ家族という距離がね。
崇弥:
許せないんですよ、よく!
柿次郎:
お互いいつも言っているけれども、本当によくこの場を通して、これを直して欲しい!な、みたいな。癖とか・・・。
文登:
あの・・・
クサイというか、すごく高尚な文章にしようと仕掛ける、というか。いいことなんですけど。それがあまりにも、これはちょっと、やりすぎなんじゃない?っていうのを、結構攻めたがるところはあります。
崇弥:
僕は逆に、(文登は)文章下手くそなんですよね。だから僕がたまに文登がFacebookとかで書いているやつを勝手に編集するんですよ。双子が描いているヘラルボニー日記を。
文登:
それは言っちゃダメだろ。笑
柿次郎:
なるほど、確かに表現の仕方とかも違うし、ある意味、お兄ちゃんの方が盛岡にいてもっとこう、平易なフラットな言葉を使った方が、届きやすかったりするじゃないですか。
崇弥&文登:
そうですね。
柿次郎:
東京でかたや「イケすかねぇ」と。「イケすかねぇ文章書いているんじゃねえぞ」と。
文登:
あはは。(笑)教えてあげているんですよ、岩手から。
崇弥:
いや、でも僕がまぁもともと広告系だったので、そういうのをすごく頑張ってやっていたので、あんまりわからないんじゃないですか。感覚が。
柿次郎:
ここでもちょっとイライラが溜まったりするんですね。
文登:
そうですね~。でも、仲はいいです、すごく。
二人とももともとサラリーマン
柿次郎:
お互いその、大学出られて、どういうこう・・・職歴というか?
崇弥:
僕はもう、大学のゼミの先生が小山薫堂さんっていうクマモンとかを作って「おくりびと」の演出をした、すごい有名な人がゼミの先生だったんですよ。

・・・懇願して、入って。

柿次郎:
5年!?結構ゴリゴリやってたんですね。
文登:
だから仮囲いとか、そういった知見が自分の中であったりするので、自分の中で昇華させようと思ってやっています。
柿次郎:
なるほど。結構真逆の。
文登:
ほんとですね。全然違う畑を。歩んできて。
柿次郎
結構生きているんですか?それぞれの経験は?広告的なものはまさにこういった冊子(会社案内など)をどうつくるかとかコピーとか、わかりやすくどう伝えるかって文脈だと思うんですけど。ゼネコンの経験って・・・どちらかというと、仕事をつくることというか?
文登:
そうですね。仕事をつくる、営業する・・・結構自分たちでアプローチをしてっていう形は強かったりするんですけど、だから数字を常に見続けるっていう仕事が多かったりはしたので、そういう数字関係は一応、僕の方が会社としては担っているっていう。
崇弥:
文登:
お前、社長アピールしてんなよ(笑)あはは!
崇弥:
直属の部下なので。笑
柿次郎:
そうですか。なかなかありそうでないっすよね。
文登:
確かにそうですね。逆に近しい仕事でなくてよかったな、っていう。そこでバチバチしないで済むというか。完全別だったので畑が。
柿次郎:
逆に二人とも東京で同じ事務所に週5日とか、いたら・・・
文登:
もう、息が詰まりますね!
崇弥
あはは!
ヘラルボニーの活動を家族は・・・
柿次郎:
お二人の活動っていうのは、お父さん、お母さん、家族?とか、どうとらえている?
崇弥:
あ、でも家族はすごく応援してくれていて、めちゃくちゃ。ただ最初はすごく反対されましたけどね。その、障害のある方のアートを使用させていただいて、株式会社っていう営利企業としてやっていくっていうのはなかったんですよね、今まで。NPOとか、社会福祉法人っていう非営利セクターがやるっていうのはあったんですけど・・・

文登:
リアルなアドバイスを頂いたりして。でも今はすごく大応援団です。
柿次郎:
結果を出しながら・・・
文登:
徐々に徐々にですけどね。
柿次郎:
でも、まぁ僕も地方創生だローカルという文脈も、もともと補助金に頼っていたりとか、ところがやっぱりいかに自力で稼ぐか。それがないと持続性がないというか。やっぱりこういう一つの旗を振って活動していくのは営利目的という文脈を持ちつつも、彼らをフックアップする!才能を見つけて引っ張り上げて、適切な場所を・・・これ(ハンカチ)だったらトゥモローランドの場所に置くっていう行為で彼らは絶対に嬉しい、で、お金が入る!お金・・・大事っすね?
崇弥&文登:
お金大事です。それは本当に思います。
柿次郎:
なるほど、会社作って1年くらい、稼げてますか?
崇弥: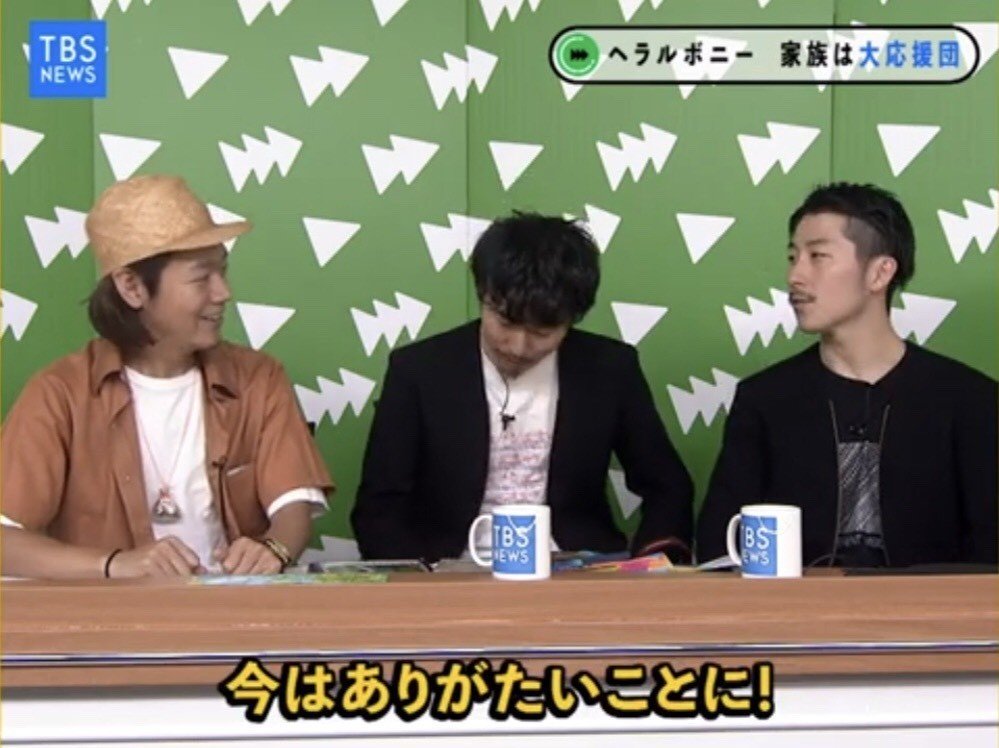
柿次郎:
結構?
崇弥&文登:
結構ではないですけど!。笑・・・それなりにやっていけてますけど。
柿次郎:
言いづらいっすよね。仮に稼げてたとしても言いづらいっすよね?
文登:
バレないようにポルシェ乗る、みたいな!
崇弥:
そうなったらいいですけどね!
苦労・困難の乗り越え方
柿次郎:
言うても、誰もやってないことをやる、というのは凄く大変なことで。ここに至るまでというか。そもそも、10代とか困難?どういう風に乗り越えてきたとか?
文登:
会社のベクトルでいうと、例えば中学校くらいのタイミングから兄とかのことを「障害がある」っていう違いに対して、馬鹿にする人も中には出てきたことがあって、その時に僕自身もあまり強い人間でなかったので、なかなか反発が出来なかったと。で、僕もこの彼らとどう付き合う方がいいんだろうと思ったときに、だとすれば、このグループに入ってしまえばいい!ってところも頭で思うときがあって、そういう時にいわゆる不良グループじゃないですけど、そういったグループの人たちとよくつるむようになってたんですけど



柿次郎:
それはもう、崇弥さんも共通認識ですか?
崇弥:
そうですね、確かに・・・。困難・・・。共通認識ですね。僕としても結構、中学校時代辛かったですね。もう、卓球部だったんですけど、小学校とかは野球とかやってて、兄貴のこととか普通に連れてくるじゃないですか、母親とかが。中学校の部活とか。
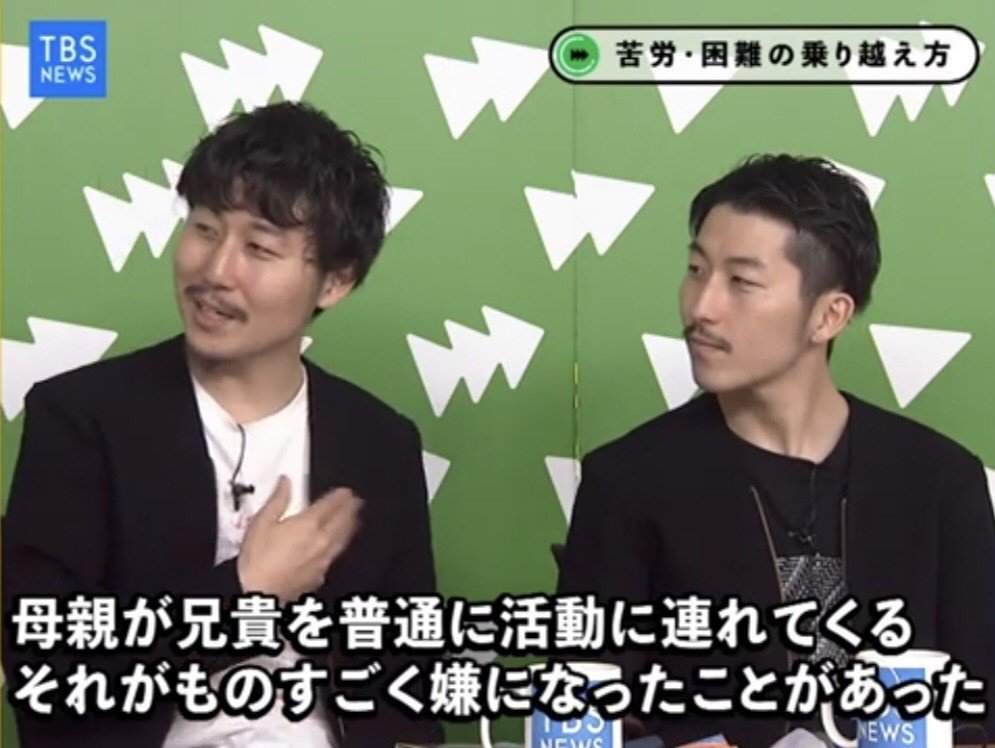
兄貴がもう、結構謎の言葉遊びとかを「崇弥!!〇〇する!」とかめちゃめちゃ話しかけてきて。「もう、本当にやめてよ・・・」と。
文登:
それ、関係なくてもやめてほしいよね(笑)
崇弥:
それでもう、来ないでくれ!って母親に強く言ってたんですけど、それでも、どうしても連れてきてしまうっていうのがあって・・・
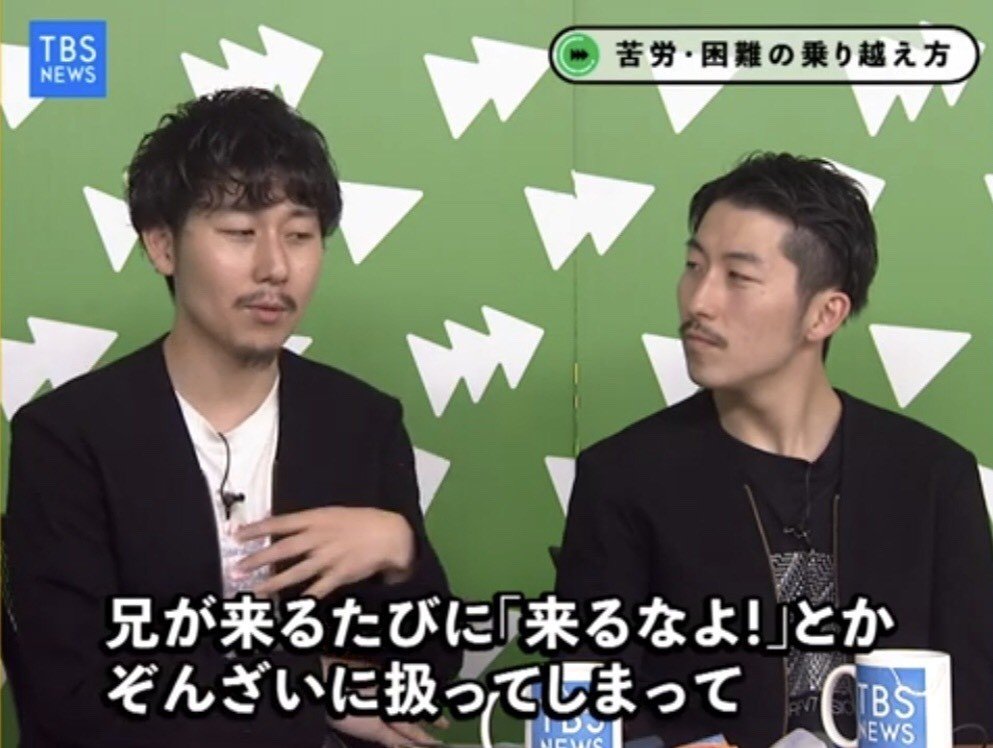


だから1階で母親と父親と、兄貴は生活する。ご飯を食べ終わったら2階の僕らが呼ばれて、兄貴と入れ替わる、みたいな。一緒にいられなくなっちゃったんですよね。その時はもう、母親も辛かったでしょうね。
柿次郎:
それって何かこう、家の中で普通に小学校の時とかお兄ちゃんの言動とかも普通に受け入れていたのが、自分たちが外に出て、他者から違う物差しをぶつけられたときに、ちょっと恥ずかしい。であるとか、嫌だなっていう気持ちが芽生えてしまったっていうのは、ある種周りの環境、その時代、その土地の障碍者に対しての気持ちが、まだまだ鋭かったというか。まぁ結構無邪気ですもんね。中学生とか、ひどい言葉を平気でぶつけるというか。それを若者、あらゆる人がそういうこと起こりうるじゃないですか。ちょっとしたお父さんの仕事だったりとか、お母さんの仕事だったりとか、片親ってだけでイジられたりする。でも、そういう経験って今振り返ると糧になっているというか?
崇弥:
めちゃめちゃありますよ!
文登:
「見返してやりたい」なんだ・・・笑
崇弥:
あ、違う?
文登:
俺は思ってなかった。
柿次郎:
それはまぁ、ある種、ヒップホップっていう文化自体が過去の体験とか、経験を表現活動に変えて自分たちで得たもの。キツかったものとかを持っているからこそ、こうした活動に生かせるというのは。Doooっていうのは若い子に・・・スマートフォンで閉じこもって見てるかもしれないのでそういう経験があってもヘラルボニーの活動を見ていてちょっとでも影響を与えられたらいいですよね。
文登:
うん、確かに。
柿次郎:
うん!みんな!SEEDAを聞こう!
崇弥&文登
あはは(笑)確かに。母親が大好きだし。
収録を終えて
柿次郎:
はい、収録お疲れ様でした!双子に挟まれるのもなかなか緊張しますね。どうでした?収録?
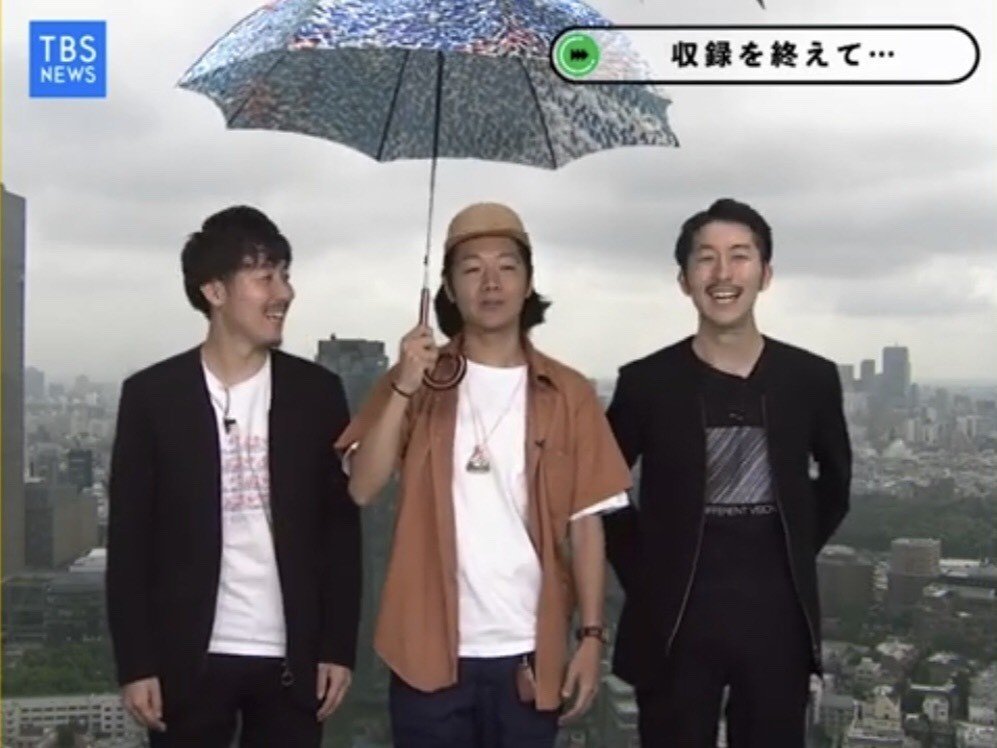
文登:
ちょっと緊張しましたね。
崇弥:
最初、(文登が)すごく緊張してました
文登:
いやいや、(崇弥が)こっちがすごく緊張してた(笑)
柿次郎:
こうサラウンド的に双子がしゃべるっていうのがいいですよね。今後、何かやりたいこととか?目標とかありますか?
崇弥:
ああ、そうですね。結構新しいことはチャレンジしていこうと思っていて。今年は海外展開したいと思って、海外の展示会とかもどんどん出していきたいと思ってます。
柿次郎:
お!なるほど!
文登:
あとはインテリアとか、ファブリックとか、カーテンとかクロスだとか。
柿次郎:
じゃあ、あらゆるものにヘラルボニーが入っていくって感じですね。気軽にご相談ください!と。
崇弥&文登:
ほんと、そうですね。お待ちしております!!
柿次郎:
よ~し、じゃあいつものやつ行きましょ!
崇弥&文登:
はい!!
柿次郎:
せ~~の~!!
柿次郎&崇弥&文登:
Dooo!!!!

【前編はこちら】
