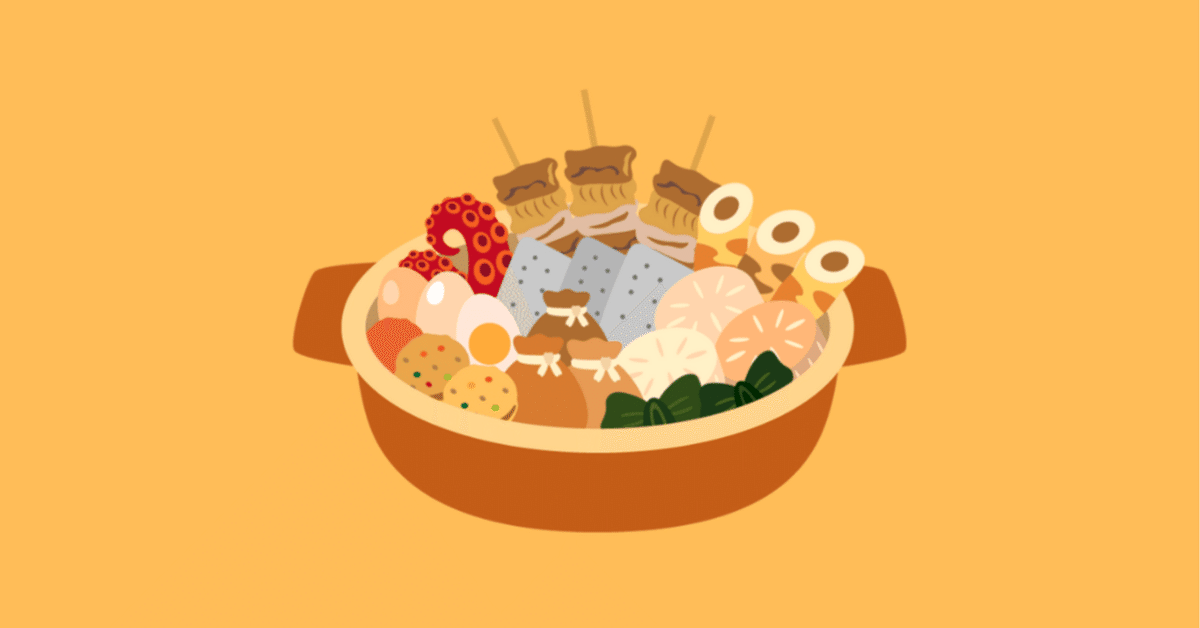
【小説】おでんくんとおでんちゃん
「餅田〜、レジ入る時におでんの具材補充しといて。もう結構売り切れ始めてるからさ。」
コンビニの控室でシフト表をチェックしていた私に店長がそう言った。時計に目を移してみると、5時になりかけていた。急いで出勤記録をして、控室からレジに出る。
店長のお願いを無視するわけにもいかないので、嫌々おでんの補充を始める。
季節が冬になったせいで、人々は温かいものを求め、コンビニへおでんを頻繁に買いに来るようになり、そのせいでおでんは1日に3回は補充しないといけないくらい、よく売れるようになった。
レジ前にあるおでんのケースの蓋を開ける。おでんの熱い湯気が出汁の香りを乗せて、私の顔を包む。おでんのくせに少しいい香りだったのが、なんだか悔しい。温かくて、いい匂いがする。そんなおでんが私は大嫌いだった。
昔から私は顔の肉つきがよく、尚且つ唇が厚かった。そして笑うとえくぼができた。
生まれた時からそうだったらしく、小さい頃はほっぺもちもちだね〜、えくぼかわいいね〜なんて甘やかされ、周りの大人たちに可愛がれられることも少なくなかったし、私もそれが嬉しかった。だけど、あることをきっかけに自分の容姿が嫌いになっていった。それは私の容姿が、あるキャラクターに似ていると学校で言われ始めたことだった。
私の顔はおでんくんに似ていたのだ。
おでんくんとは、おでんの具材である餅巾着が擬人化したキャラクターで、小学生の頃にアニメが放送されており、学校で大流行していた。そんなおでんくんの特徴とも言えるのが、厚い唇とその両端にあるえくぼ、そして小さな目だった。
その特徴が全て当てはまるように、顔の肉つきがまるで餅巾着のようで、唇が厚く、笑うと深いえくぼができる小さな目の少女であった私が、おでんくんに似ていると周囲に気付かれるのは時間の問題だった。
小学3年生のある日の昼休み、クラスの中心的存在だった男子におでんくんに似ていると指摘され、クラス中から笑われた。
もちろん傷ついたし、悲しかった。だけど、反抗してみんなに変に思われるのが嫌だった。だから嫌な気持ちは表には出さずに、クラスのみんなと同じように私も笑った。なんともないように、私も笑った。
その瞬間から、自分の顔が嫌いになった。もちもちと言われていたほっぺも、可愛いと言われたえくぼも、少し厚い唇も、小さな目も、全てが嫌になった。だからなるべくマスクをつけるようにして、顔を隠した。顔を見られたくなかった。
元々はよく笑う子だった。だけど、笑うとおでんくんみたいなえくぼができてしまうから、人前であまり笑わないようにした。自分を見られるのが、また笑われるのが怖かった。
そうしておでんくんに似ていると気付かれた私は、いつしか周りからおでんちゃんと呼ばれるようになった。本当はおでんちゃんなんてあだ名、自分の容姿をずっとイジられているようで嫌だった。だけど、なんともないように振る舞った。
もう既におでんちゃんとして社会に組み込まれてしまった以上、自分を殺してでもおでんちゃんを全うするしかないと思った。嫌だと言って仲間はずれにされたり、一人ぼっちになったりすることの方が怖かった。だから私は、小学校を卒業してからも、誰かに指摘されるよりも先に、自らをおでんちゃんであると自己紹介することにした。
自らおでんちゃんというあだ名を広めることによって、誰かにおでんくんに似ていると言われて傷つくのを避ける。そんな思惑だった。
おでんちゃんとして生きようと決めた私に残ったのは、抱えきれないほどの自己嫌悪と、そのきっかけとなったおでんへの憎悪だった。おでんさえなければ、おでんくんなんていなかった。おでんくんなんていなければ、笑われることはなかった。
おでんを見るたびに、おでんくんに似ていると言われクラス中から笑われたことを、おでんちゃんと呼ばれ、指を刺された日々を思い出す。
自分の容姿を馬鹿にされ、自分のことが嫌いになったきっかけであるおでんが憎かった。
おでんの補充が終わり、レジに戻る。
今日のシフトは5時から21時まで、あと4時間頑張るか〜と手をさすりながら自分を鼓舞し、自動ドアの開閉音に合わせて「いらっしゃいませ」と「ありがとうございました」を自分の口から自動再生しながら、淡々とレジをこなして時間が過ぎるのを待つ。
今日もおでんがよく売れる。何度もおでんの蓋を開け、何度もその香りと湯気を顔面に浴びる。そのせいか、しばらくしているうちに、顔を見られないようつけているマスクが少し濡れていることに気づいた。
そのマスクを交換するために、ズボンの後ろポケットに潜ませている予備のマスクを取り、顔を見られないよう、体を後ろに向けてマスクを交換する。
「あの、すみません。」
レジ前にお客さんが立っているようだ。急いでマスクを交換した私は、そのお客さんと対面する。
「おでん貰ってもいいですか?」
そう尋ねる彼は、ここ最近毎週のようにおでんを買いに来る、クラスメイトの根本くんだった。
根本くんは同じ高校の2年4組のクラスメイトだ。丸刈りで、少し肌が焼けている。過去に何かスポーツをしていたような容姿をしているが、少なくとも今はどうやら部活には入っていないらしい。
教室では一日中、自分の席で小説や漫画を読んでいて、移動教室とトイレの時以外はほとんど席を立つことは無い。友達もあんまりいないみたいで、お昼も1人で黙々と食べている。しかし、かといってクラスの男子と全く交流がないわけではないようで、漫画の貸し借りをしていたりとか、たまにクラスの男子の会話の輪に入って話していたりすることもある。
クラスで少し浮いているような気もするけど、馴染んでいないわけでもない。そんな不思議な男子だ。
根本くんは冬になってから、毎週のようにおでんを買いに来るようになった。
何故かはわからない。だけど、毎週の同じ時間、ちょうど私が働いているこの時間におでんを買いにくるのだ。初めの方は、おでんを買いにくるお客さんと、おでんを売る店員同士でしかなかったが、何週間か経って、根本くんが私の名札を見てクラスメイトであることに気づいてからは、会話をするようになった。会話と言っても、初めは会計をする際に少し言葉を交わす程度だったけれど、たまにバイト終わりまで根本くんが待ってくれていて、二人で駅まで一緒に帰ることもあった。だけど、学校では話すことはなかった。それでも私は根本くんと話せることが嬉しくて、毎週のバイトのちょっとした楽しみになっていた。
「おでんね、ちょっと待ってて。」
そう言いながら、またおでんの蓋を開ける。そしてまた出汁の香りと湯気に包まれる。今日だけで何回こんな目に遭うんだ、なんて苛立ちはそっと胸にしまい、どれにする?と尋ねた。
「うーん、なんかおすすめある?」と根本くんが聞いてくる。
おすすめなんて聞かれたのは初めてだった。これまでは無難に大根とこんにゃくと卵を毎回買っていた根本くんだったが、どうやら今日は違う気分らしい。
「おすすめかー、何がいいかな。なんか好きな具材とかある?」
おでんが嫌いな私におすすめの具材なんてあるわけもなく、とりあえず質問で返した。
「好きな具材?そうだな〜、どれだろう。う〜ん。」
まるで難事件を解く探偵かのように、根本くんは腕を組み、真剣に好きな具材を考え始めた。腕を組むのは根本くんが考え事をする時の癖だった。
「厚揚げも好きだし、がんもとかも好き。でもやっぱり大根とこんにゃくは外せないよなー。でも一番ってなると、むずいな…。」
腕を組み小さな声でぶつぶつ呟きながら、一番好きなおでんの具材を真剣に考えている根本くんの様子がなんだかおかしくて、危うく笑いそうになってしまった時、根本くんは、あ!と何かを思い出したかのように顔を上げ、
「餅巾着!餅巾着が一番好き!」と無邪気な笑顔でそう言った。
餅巾着と聞いた瞬間、私の頭に真っ先に思い浮かんだのはおでんくんの姿だった。おでんくんは餅巾着のキャラで、おでんくんは私に似てる。だから私はおでんちゃんなのである。
おでんちゃんと呼ばれていることを、同じクラスの根本くんが知らないはずはない。
もしかしたら、私を揶揄するために餅巾着と言ったのだろうか。
毎週おでんを買いに来ていたのも、遠回しに私をイジるためだったのだろうか。
私は根本くんをクラスの誰とも群れずに、我が道を行く一匹狼のように思っていた。
ある日のバイトの帰り道、根本くんにどうしていつも一人でいるのか聞いたことがある。すると根本くんは、腕を組みながら少しの間考えて、そしてこう答えた。
「なんか、みんなのノリにあんまりついていけないんだよなー。みんながなんで笑ってるのか、何を面白がってるのか、わかんなかったりすることも多くて。あとさ、自分はゆっくりものを考えたりするタイプだから、話の流れについていけなくて、よく置いてけぼりになっちゃうし。だから一人でいることの方が楽なんだ。」
私は他人の目を気にすることなく、自ら一人でいることを選択できる根元くんをどこかかっこよく、羨ましく感じていた。でも、そんな根本くんも結局は他の人たちと同じなんだと思うと、ものすごく悲しく、寂しかった。なんだか裏切られたように感じた。勝手に期待して、勝手に傷ついている自分にも腹が立った。馬鹿にされているに決まっているのに、根本くんとの会話を楽しんでいた自分がいたことにも、恥ずかしさと苛立ちを覚えた。考えれば考えるほど、色々な感情が浮いては沈み、やがて混ざっていき、私の心はぐちゃぐちゃになっていった。
そんなぐちゃぐちゃが私の体を乗っ取ろうとしている間に、どうやら時間は経っていたらしく、「あの…」と根本くんが小さな声でつぶやいた。
ぐちゃぐちゃな感情の私は、もう根本くんの顔が見たくなかった。
「あぁ、おすすめの具材だよね。ええと、じゃあこれで。」
そう言って、私は今日2度目の補充で入れたばかりの、まだ固く出汁も染みてもいない大根を根本くんのおでんの容器に入れた。――自分でも気分が悪い嫌がらせだなと思った。
でも、もし彼が本当におでん食べたいだけなら、この固くて不味い大根を食べて心底ガッカリし、今後は別のコンビニに美味しいおでんを買いに行くようになるだろう。そうしたらもう二度と話すことはない。そう思った。
彼は何も言わず私からおでんを受け取り、支払いを済ませ、そのままコンビニを後にした。
私の嫌いなおでんの匂いと、ぐちゃぐちゃになった私の心だけが、コンビニに置いて行かれた。
あれから1週間が経った。
本来なら今日も、いつものように根本くんはおでんを買いにくるはずだ。だけど、あんな嫌がらせをした以上もうくることはないだろう。そう思いながら、またいつものようにレジを淡々とこなしていると、見慣れた制服と、緑色のマフラーを巻いた男子が、自動ドアから入ってきて真っ直ぐ私のレジの前に立った。
「あの、おでん買ってもいいですか?」根本くんは今週もおでんを買いにきた。
「餅田さんは何が好き?」
私の嫌がらせなど何もなかったように、腕を組んで、おでんのメニュー表をじっと見ながら、根本くんは私に好きな具材を聞いてきた。
「え?何が?」
「いや、おでん。どの具材が好きなの?」
「好きな具材なんか別にない。おでん嫌いだし。」
そう呟くと、彼は目を見開き、
「おでん嫌いなの?!」と、コンビニにはそぐわない、天まで届くような声量で驚いた。
大きな声を発した根本くんに、コンビニ中の視線が向く。そして視線は根本くんを貫き、その奥にいる私にも向けられた。
集まる視線が怖くなった私は、下を向いて根本くんに囁くように「静かにして」といった。
「ごめん。」と根本くん。
ほんの少しの間沈黙が流れ、根本くんが改めて聞いてきた。
「おでん嫌いなの?本当に?」
「嫌い。」
「え、あ、そうなんだ。え、でも…」と根本くんが会話を続けようとした時、私はレジ待ちの列ができ始めていることに気がついた。バイトが終わる15分前くらいであるこの時間は、いつも何故だかコンビニが混むのだ。
「ごめん。それはまた後でね。それでどのおでんを買うの?」
「後で? まぁわかった。じゃあ、大根とこんにゃくと卵、あと餅巾着一つ。」
レジ待ちの列の人の視線が鋭くなってきているのを肌に感じ、餅巾着というワードを気にする暇もなく急いでおでんを容器に入れ、根本くんに渡す。
おでんを受け取った根本くんは、
「んじゃあ、外で待ってるね。」と言い残し、コンビニを後にした。
21時になり、今日のバイトが終わった。
「お疲れ様です。」と次のシフトの人に声をかけ、帰ろうとすると、おでんの容器を両手で包み、白い息を吐きながらコンビニの駐車場で座って待っている根本くんが目に入った。
コンビニから出てくる私を見た根本くんは、おっ、と呟いてから少し微笑んでゆっくり立ち上がり、おでんを大切そうに抱えながらこっちの方向に歩いてきた。
「何してるの?」
「待ってたの」
「誰を?」
「餅田さん」
「なんで?」
「また後でって言ってたから」
確かにさっき、また後で、とは言ったけど、それは根本くんの会計が早く済むよう、彼を適当にいなすために放った言葉だった。
「言ったけど…」
「でしょ?だから待ってたの。詳しく聞きたいから。」
「何を?」
「餅田さんがなんでおでん嫌いなのか? てか質問ばっかだね。」
そう言いながら笑っている根本くんに対して、わざわざ私の口からそれを聞いて、馬鹿にするためにそんなことを知りたがっているのか、それともほんとに知らないから聞いているのかわからず困惑し、動揺した。
そんな私を見た根本くんは、
「まぁ、とりあえず、どっかで座って話そうよ。おでん冷えちゃうから早く食べたいんだ。」
と言い、私たちは一旦コンビニの近くにある小さな公園に行くことにした。
公園に到着した。夜の公園は明かりがほとんどなく、街灯に照らされるベンチとブランコの周り以外真っ暗だった。じっとしていると、あっという間に体が冷えてしまうので、私が迷わずブランコに座ろうとすると、「おでんがこぼれちゃったらどうするのさ」と根本くんが言ってきたので、仕方なく私たちは並んでベンチに座ることにした。
根本くんはコンビニを発ってからずっと大切そうに両手で包み込んでいたおでんの容器を、ようやく膝の上に置いて蓋を開き、大根をつまみながら話し始めた。
「それでさ、本当におでん嫌いなの?」
「嫌いだって。」
「なんで?」
「わかるでしょ?」
「全然わからない。むしろ好きなんだと思ってた。」
「え?なんで?」
「だっておでんちゃんって呼ばれてるじゃん。」
卓球のラリーのような素早い会話で、彼がなんの躊躇もなしに放ったおでんちゃんと言うワードに動揺し、少し顔が引き攣った。私本人を目の前にして、こんなに真っ直ぐにおでんちゃんと呼ばれるのは久しぶりだった。
「だから嫌いなの。おでんちゃんって呼ばれて、おでん好きでいられると思う?」
「おでん好きだからおでんちゃんって呼ばれてるんじゃないの?」
「違うよ。本当になんでおでんちゃんなのか知らないの?」
「知らない。本当に知らない。」
真っ直ぐな目で私を見ながら話す彼の言葉には、嘘がないように感じた。どうやら彼は本当におでんちゃんと呼ばれる理由を知らなかったようだった。
「おでんちゃんって呼ばれてるのは、私がおでんくんに似てるからだよ。」
「おでんくん?」腕を組み、おでんくんがなんだったのか思い出す根本くん。
「あー、あれか。小学校の頃なんか人気だったやつか。」
「そう。それに似てるって小学校の時に言われてさ、だからそれ以来ずっとあだ名がおでんちゃんなの。おでんくんの女の子バージョンでおでんちゃん。」
「なるほどね、おでんちゃんはそこからきてるのか。それでおでんくんに似てるって言われたから、おでんが嫌いになったんだ」
「そう。」
「じゃあずっとマスクつけてたのも、おでんくんに似てるって言われるのが嫌だったから?」
「そう。」
なるほどなーと、頷きながら、根本くんは大根の最後の一口を口に入れ、また腕を組み何かを考え始めた。
自分の顔がおでんくんに似てるからおでんちゃん。改めて理由を聞くと、なんて単純で幼稚なあだ名なんだろう。こんなあだ名くらいに苦しんでいたことに、少し虚しくなった。
根本くんにおでんちゃんの意味を教えてしまったことを少し後悔し、根本くんにもそう思われたら嫌だなと思いながら、無意識に自分の顔に触れた時、自分がマスクをつけていないことに気づいた。普段コンビニでバイトしている時はマスクをつけている、しかし、バイト終わりはいつもあえてマスクを外して、他人の視線からの解放感を味わっているのだ。
マスクをつけていない。根本くんに顔を見られた。おでんくんに似てる私の顔を。
根本くんにもおでんくんにも似てると思われてしまう。
すると、根本くんはボソッと
「おでんくん可愛いけどな〜」と呟き、今度はこんにゃくを食べ始めた。
おでんくんが可愛い?そんな訳ない。私に似ているおでんくんが可愛いわけない。根本くんは何を言っているんだろう。そう思いながらも、少し頬が緩んでいる自分がいた。
やがて根本くんは腕を組むのをやめて、話し始めた。
「俺はさ、てっきりおでんが好きだから、おでんちゃんってみんなに言われてると思ったんだ。たまにあるだろ?虫が好きだから虫博士とか、そういうのかと思ってた。」
「もしそれでおでんちゃんだったら、根本くんこそおでんくんじゃん。おでん毎週食べてるし。」
そう私が少し笑いながら言うと、根本くんは一度箸を置いて、何かに納得したように
「確かに、じゃあ今日から俺がおでんくんだ!」と胸を張って言った。
満面の笑みで自分がおでんくんだと言い張る根本くんがなんだか可笑しくて、私はおでんくんにそっくりのえくぼのことなんて気に掛ける暇もなく、声を出して大笑いした。そんな私に釣られて根本くんも笑い出し、おでんくんとおでんちゃんは二人で顔を合わせて笑った。誰かとあんなふうに笑ったのは、小学生ぶりだった。
ベンチに降り注ぐ街灯の明かりを反射するように、私たちの笑顔は輝いていた。
笑いの波が引いていき、2人が落ち着きを取り戻し始めると、根本くんは膝に置いたおでんに視線を移し、「やっぱり可愛いんだけどな〜」と呟きながら、おでんの出汁を口にした。 おでんの出汁をじっくりと味わう根本くんの頬は、私のと同じように赤くなっていた。おでんで温まったからだろうか。それとも、私と同じ理由だろうか。
「じゃあ今日からおでんちゃんは、おでんが好きだからおでんちゃんってことにしよう。」
根本くんは突然そんなことを言いだした。
「でも私おでん好きじゃないし。」
「今日から好きになればいいじゃん!」
そういって、彼はおでんの容器に残っていた餅巾着を箸で取り、「ほら、」と私の目の前に差し出した。
「餅巾着?よりにもよって?」
「そう、餅巾着。餅巾着美味しいよ?」
根本くんの箸に挟まれ、私の目の前に浮いている餅巾着が、まるであのおでんくんのように見え、そこにおでんくんにそっくりな自分の影が見えた。目を閉じ、首を振った。食べれない。食べたくない。
おでんを見るたびにおでんくんに似ていると笑われた日々を思い出す。
おでんくんにそっくりな、大嫌いな自分を思い出す。
おでんなんか食べたくなかった。目にさえしたくなかった。
「大丈夫。ただのおでんだよ。美味しいから、大丈夫だよ。」
根本くんが優しく声をかけてくれる。そっと目を開けると、そこには餅巾着とおでんくんがいた。私に似ているあのおでんくんじゃない。おでんが大好きなおでんくん。根本くんだ。
根本くんの差し出す、餅巾着を口に入れる。風に当たり、少し冷えた餅巾着を噛むと、巾着の中の餅が口に溢れ出した。その瞬間、巾着の中の餅のように、私の心の中から何かが溢れ出たような気がした。
気がついたら泣いていた。涙が止まらなかった。餅巾着を食べて泣くなんて、可笑しくてたまらないだろうに、私の横に座るおでんくんは、私の背中を優しく撫でてくれた。
はい、と根本くんがおでんの容器を私に渡してきた。中を覗いてみると、おでんの出汁がちょっとだけ残っていた。それを口に入れる。少しぬるかった。けれど、どんなものよりも温くて、美味しかった。
涙が止まり、呼吸が落ち着いてきたころで、根本くんが行こっか、と立ち上がった。
凍えるような空気が、泣いた後でヒリヒリしている私の目に突き刺さる。少し痛み、目を掻くと、大丈夫?と根本くんが顔を覗き込んできた。
大丈夫だよ、と私も立ち上がり、駅までの夜道を二人で歩きだした。
「おでんくん」
「なに?おでんちゃん」
おでんちゃんと呼ばれて嬉しかったのは初めてだった。
「おでんくんはなんで毎週コンビニにおでんを買いにくるの?」
「ん〜」とおでんくんは腕を組んで、考え出す。
しばらくの沈黙が、わたしたちを包む。
そしておでんくんは少し歩くスピードを緩め、私の方を向いて言った。
「おでんちゃんに会いたかったからかな。」
そう言い放つと、すぐ彼は顔を逸らした。私も、赤らめた顔を見られまいと、首に巻いていたマフラーをどうにかして顔を覆い隠すようにできないか結び直そうとした。
ふと彼に目線を移すと、彼も同じことをしていた。彼と目が合った。これもマフラーを結び直している。二人とも全く同じことをしていた。
「おでんくんとおでんちゃんやっぱそっくりだね」なんて言いながら、私たちは笑い合った。
私はおでんちゃんであることが、おでんくんとそっくりであることが初めて嬉しかった。
私のすぐ横を歩くおでんくんの手が、何度も私の手に当たる。
思いきって、私はおでんくんの手を握った。おでんくんの手は、おでんなんかよりも、何よりもずっと温かく、私を芯から熱くした。
冬の寒さをのせた冷たい風が、おでんくんとおでんちゃんの赤く火照った頬を撫でながら、夜道を駆け抜けていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
