
惑星を統べる老紳士-サー・エードリアン・ボールト
【注意書き】
筆者の完全な主観が多く含まれます。その点はお含みおき下さいませ。
ホルスト:組曲《惑星》
指揮:サー・エードリアン・ボールト
演奏:ニュー・フィルハーモニア管弦楽団&アンブロジアン・シンガーズ
録音:1966年7月21日 & 22日、キングスウェイ・ホール(ロンドン)
レーベル:Warner(旧EMI)
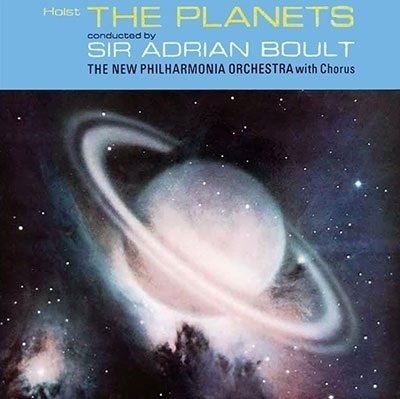
はじめに
1918年9月、ホルストの代表作である組曲《惑星》が作曲者臨席の下で非公開初演が行われた。この時に指揮を執った人物はエードリアン・ボールト。当時は30歳になったばかりだった。
生涯に渡り、エルガーやヴォーン=ウィリアムズなど自国の音楽を積極的に取り上げていたボールトはこの後に《惑星》を5回も録音している。EMIで1966年に製作された4回目の録音(ニュー・フィルハーモニア管弦楽団)と1978年の最後の録音(ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団)は数多く存在する《惑星》の音盤で今でも定番として愛されている。
今回は、ボールトによる《惑星》より4回目の録音をレビューする。

老いてなお血気盛んな名盤
EMIにおける4回目の録音は1966年7月21日~22日、ロンドンのキングスウェイ・ホールで行われた。ボールトはこの時すでに77歳を迎えていたが、自家薬籠中の物としていた《惑星》をニュー・フィルハーモニア管弦楽団とたった2日間のセッションで完成させている。とまれ、その演奏はいわゆる「やっつけ仕事」のような内容では決してない。
ボールトは1912年にライプツィヒ音楽院に留学した際、同地のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団で音楽監督として活躍していた指揮者―アルトゥール・ニキシュに指揮を私淑する。だが、ボールトはニキシュの「主観的な」指揮ぶりを忌避して、堅実で武骨な叙情に流儀を求めた。
本CDでは正真正銘、ボールト流の《惑星》が収められている。じっくりとしたテンポを取り、アーティキュレーションから華美な要素を出来るだけ排しながら、楽曲の構造を鮮やかに提示する。各楽曲の性格づけや楽想の切り替えにメリハリがあり、聞き手を一瞬たりとも飽きさせない。特に「火星」や「土星」は血気盛んな迫力に驚かされる。
この録音に賭けたボールトの想いに人並みならぬものがあったことを窺える点として、自身の文章でホルストから《惑星》の初演を依頼された経緯や楽曲解説をライナーノートに寄せている。
初演指揮者による楽曲解説(邦訳)
本節では、ボールトによる楽曲解説の邦訳を以下に示す。訳文は筆者がかなり意訳している部分があり、内容の正確性はあまり自信がないのでご了承ください(英語原文は輸入盤などを参照してください)。
第1曲:火星、戦争をもたらす者
ホルストがこの曲を作曲したのは1914年の夏であり、この曲に描かれているようなことは経験していなかった事実は記憶しておくべきだろう。勢いのあるリズムは楽章全体を貫き、長い音符が行ったり来たりするテーマと対立する。リズムはゆったりとした中間部でも、まず小太鼓が、次いでトランペットや他の楽器が小節ごとに聞き手に印象づける。7分間の楽曲はA-B-A形式に基づいて作曲されている。それぞれ3つのセクションは全てクライマックスに向けて高揚し、第2部の終わりではオーケストラ全体のユニゾンによってfffで主要主題が示されて再現部に突入する。私はホルストが戦争の愚かさだけでなく、他のあらゆる恐ろしさについても主張していたことをよく覚えている。この楽章はあまりに速く演奏すると、落ち着きがなくエネルギッシュになりすぎて、容赦なく残忍で愚かなパワーを失ってしまうように感じる。
第2曲:金星、平和をもたらす者
この9分間の純粋な美しさは、私たちが今まで聴いてきた衝撃的な音楽と見事なコントラストを成している。平和はいくつか異なる形で表現されている。最初は穏やかに、次は活発に、最後は非常にゆっくりと静かに。最後に冒頭の主題を豊かに膨らませて幕を閉じる。
第3曲:水星、翼のある使者
ホルストはこの曲で、オーケストラに翼が生えたような軽やかさと疾走感を完璧に印象づけることに成功している。音の低い楽器はもちろん、主要な箇所(6小節のフレーズが11回半も繰り返され、クライマックスに向けて後退する)では沈黙し、ほとんど全ての小節が複数の調性で同時に演奏されていることが分かる。音楽は和声的に可能な限り、互いにほとんど離れた和音の間を急速に揺れ動いている。このことから、4分間を通して水銀のようにつかみどころのない、不思議な感覚が現れている。
第4曲:木星、快楽をもたらす者
ホルストはファルスタッフ的なユーモアのセンスを持っていた。私は作曲家が木星をこう表現していたことを覚えている。“人生を楽しむ陽気な太っちょ”と。“木星”の愉しさに疑いようがなく、その8分間は幸福を放っている。音楽の構成を読み取ることが好きな聞き手に向けて記すと、木星には複数の主題があり、それらは全てバランスを保っている。おそらくABACABAが大まかな形式になっているが、最初のAパートと3度目は2つの異なるセクションがある。最後のリピートはCパートが力強く提示されることによって、かなり影が薄くなっている。イモジェン・ホルスト嬢は後に、緩やかな中間部であるCパートを愛国的な言葉と結びつけないように警告している。この曲は木星のユーモアを過不足なく反映したものである。
第5曲:土星、老いをもたらす者
ホルスト嬢によれば、彼女の父はこの楽章を好んでいたとのこと。ホルストにとって、この曲ほど突き抜けた音楽は他に無かったのだろう。この9分間の楽章は老いの悲しみを描いた感動的な心象で始まる。陰鬱なフルートにハープが触れるように絡まり、低弦のゆったりとした陰鬱な音楽の背後に流れる。この曲はゆっくりとしたテンポによる行進曲に発展し、トランペットに引き継がれながら、さらに図太い鐘が鳴り響く恐ろしいクライマックスへと導かれる。それが数小節の後で収まり、私たちは突然、太陽が雲を落ちていくような感覚に襲われる。低弦が再び冒頭の主題を奏でるが、それが微妙に変化して、やはり老いとは美しく穏やかなものであることを示してくる。トロンボーンや弦楽、オルガンによって旋律は引き継がれ、音楽は完璧な平穏さを伴って終わる。
第6曲:天王星、魔術師
ファゴットによるスタッカートが、まさに魔術師の精神を反映しているように思えるのは興味深い。この曲はデュカス『魔法使いの弟子』が最も分かりやすい例として思い浮かぶが、この曲を作曲した時にホルストはデュカスの作品を聞いたことも無ければ、楽譜を見たことすらなかったことは注目に値する。楽章を貫く4つの音符が3回強引に繰り替えられた後、ファゴットに始まり、時に打楽器やピッコロが絡んでくる。その後、3本のファゴットに引き継がれ、オーケストラの大半が徐々に加わり、弦楽のユニゾンによる軽快な曲が始まる。ファゴットの踊るようなリズムに乗ってドラムが大きく叩かれた後、音楽はつかの間に抱き起され、突然チューバによる新たな旋律が背後で奏でられる。そして、オルガンによるグリッサンド音階が突然、全曲に静寂をもたらす。これはホルストが作曲したトゥッティの中でも至芸に値する。オーケストラ全体による悲鳴の後、ハープが4つの音符を示す。この和音は6分半に及ぶ魔術師の愉悦を表した後、魔術師がよくやるように何度も色彩を変えながらpppで示され、ついに無に消えていく。
第7曲:海王星、神秘主義者
この最終楽章では、全ての楽器が終始ピアニッシモで演奏するよう指示されており、音色は「死んだ」ものとなっている。ただし、終わりに近い一瞬だけは、クラリネットが旋律と呼べるような音符を並べて演奏する。それ以外は無調で、表情がなく、形がなく、曇ったようなハーモニーが続き、これは時を超えた永遠の無限のヴィジョンを暗示している。音楽が終わらないということがあり得るとすれば、この曲はその点を示している。遠く離れた2つの和音間のゆっくりとした不規則な揺れが3+2の5拍子のほぼ全ての小節を埋め尽くし、気づかぬうちに女声がオーケストラに加わっている。やがて楽器は徐々に消え去り、女声は2つの揺れ動く和音を歌い続ける。聞き手がまだ音を聴いているのか、それとも記憶の中に留めているだけなのか、不思議に思うほどディミヌエンドが長く続いていく。
■ 参考文献
「レコード誕生物語 その時、名盤が生まれた」
「レコード芸術」編 音楽之友社(2021年)
