
行動する心、感じる心:DoingモードとBeingモードの秘密
はじめに
マインドフルネスにおけるDoingモードとBeingモードについて整理しました。いつでも思い出せるように、構造化しておきます。

1. Doingモードとは?

Doingモードは、日常生活において私たちが何かを達成しようとする時や、目標に向かって努力する時の思考や行動のパターンです。このモードでは、過去や未来に意識が向きやすく、問題解決や成果を追求する姿勢が強調されます。Doingモードは、日常生活の中で頻繁に見られる状態で、私たちが目標を達成したり、問題に対処したりするために必要なプロセスでもあります。
1.1. Doingモードとは?
マインドフルネスにおけるDoingモードは、物事を「する」ことに焦点を当てたモードです。このモードでは、問題を解決するために行動し、結果を出すことに注力します。例えば、宿題を終わらせるために計画を立て、時間を管理しながら取り組むことや、試験に向けて勉強する際に目標を設定して達成に向かって努力することが挙げられます。このモードは、目的志向であり、達成感を得るために行動を続けるという特徴があります。しかし、Doingモードに長時間とどまることで、ストレスやプレッシャーが生じることもあり、心が不安定になることがあります。
次に、具体的な例やその活用法について解説していきますが、Doingモードは私たちの生活に欠かせない一方で、そのバランスが重要です。
1.2. Doingモードの例
マインドフルネスにおけるDoingモードは、何かを達成するための思考や行動のモードです。目標やタスクを達成するために心や体を集中させる時に発揮されるため、日常生活の中でよく見られます。以下に3つの具体的な例を挙げて説明します。
例1:テスト勉強におけるDoingモード
中学生がテスト前に勉強する際、Doingモードに入ることが多いです。例えば、数学の試験に備えて、問題集を解いたり、時間をかけて苦手な分野を復習したりします。この時、目的は「テストで良い点を取る」ことであり、そのために様々な手段を講じます。Doingモードでは、時間を計画し、進捗を確認し、次にやるべきことをリストにして取り組むという特徴があります。ゴール志向であるため、目標達成に向かって一直線に努力する姿勢が強調されます。
例2:部活動の練習におけるDoingモード
部活動で、試合に向けた練習をしている時もDoingモードに入ります。例えば、バスケットボール部で次の試合に勝つことを目標に、毎日シュート練習や体力トレーニングを行います。Doingモードでは、「シュートの成功率を上げる」や「試合に勝つ」という明確な目標に向かって、効率的に動き続けます。このモードでは、結果が重要視され、目標に向けて短期間で成果を上げるための集中力と努力が求められます。
例3:友達との問題解決におけるDoingモード
友達との関係でトラブルが起こった時、解決策を考える際にもDoingモードが働きます。例えば、友達と喧嘩をした時、「どうやって仲直りすれば良いか」を考え、具体的な解決策を練ります。相手に謝る、誤解を解く、仲直りのために一緒に遊びに行くなど、行動に移して問題解決に取り組みます。Doingモードでは、問題を解決するための計画やアクションを重視し、ゴールに向かって動き出すことが特徴です。
1.3. Doingモードを活用するには?
Doingモードを上手に活用することで、効率よく目標を達成し、ストレスを軽減することができます。以下に、具体的にどのようにしてDoingモードを活用できるかを解説します。
例1:勉強計画を立てる
Doingモードを勉強に活用するためには、まずは計画を立てることが重要です。例えば、試験前に勉強スケジュールを作り、一日に何時間勉強するか、どの教科を優先するかを決めます。具体的な目標を設定し、その目標に向けて段階的に進んでいくことで、効率的に勉強を進めることができます。Doingモードを使うことで、ゴールに向かって一つひとつのタスクを確実にこなすことができます。
例2:運動やトレーニングに取り組む
スポーツやトレーニングでもDoingモードは有効です。例えば、毎日のランニングを習慣にしたい場合、「今日は何キロ走るか」「どれだけのペースで走るか」といった具体的な目標を立て、その目標に向けて行動します。Doingモードを使うことで、日々のトレーニングが効率的に進み、結果として持久力や筋力を高めることができます。トレーニング計画を立て、それに基づいて実行することで、Doingモードを活用して結果を出すことが可能です。
例3:問題解決の手順を明確にする
Doingモードは、問題解決にも効果的です。例えば、友人関係や学校生活で困難に直面した時、解決策を見つけるためにDoingモードに入ります。まず、問題を明確にし、それに対する解決策をリストアップし、それぞれを実行に移します。Doingモードでは、ゴールを設定し、そのゴールに向けて行動を計画し、次々と実行していくことが求められます。このプロセスを通じて、難しい状況でも解決策を見つけることができ、ストレスを減らすことができます。
これらの例を通じて、Doingモードを上手に活用する方法を学ぶことで、目標達成に向けたプロセスを効果的に進め、心身の健康を保ちながら成果を上げることができます。
次の章では、Beingモードについて解説します。このモードは、Doingモードとは異なり、「今、この瞬間」に存在することに焦点を当てたモードです。
2. Beingモードとは?
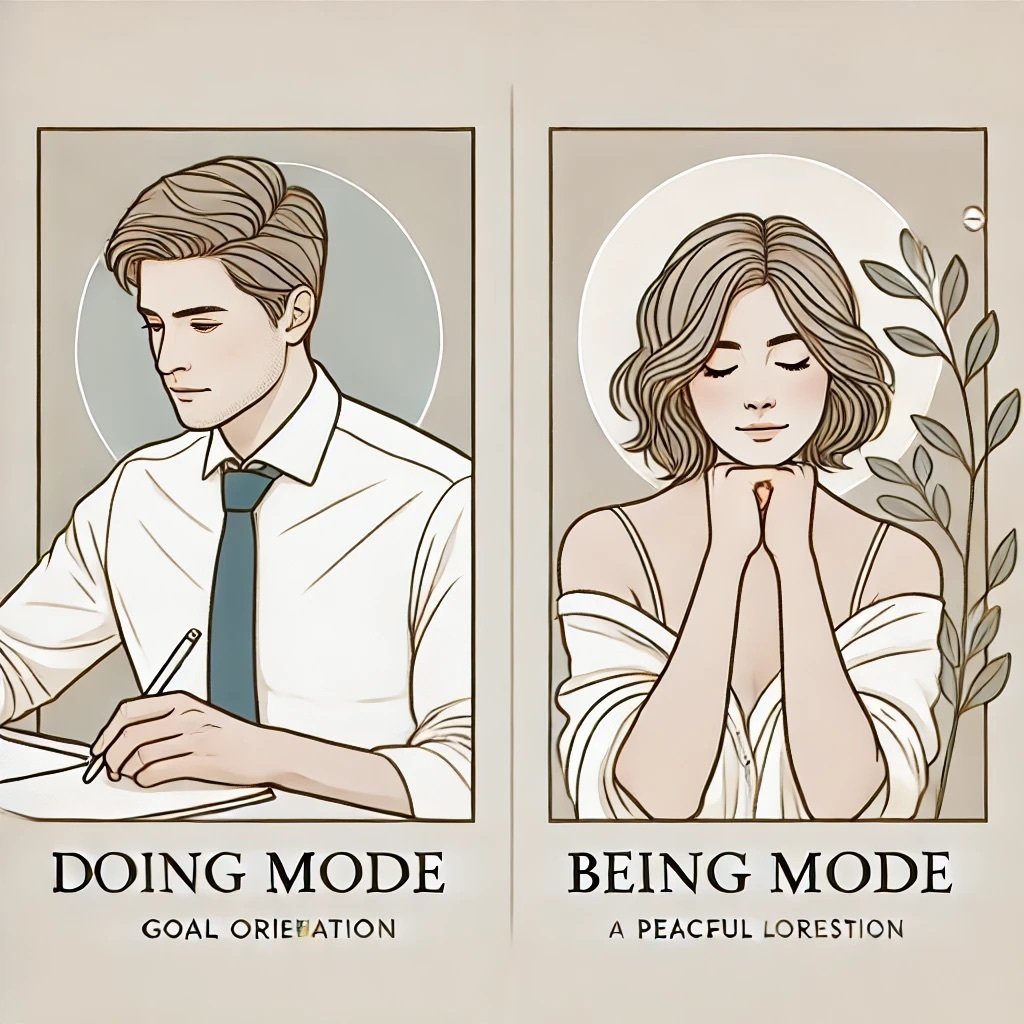
Beingモードは、Doingモードとは異なり、何かを達成しようとするのではなく、ただ「今この瞬間」に存在することに重点を置いたモードです。このモードでは、未来の計画や過去の反省に意識を向けるのではなく、現在の体験や感覚に意識を集中させることが求められます。Beingモードは、リラックスし、心の平穏を保ちながら、現在の瞬間をそのまま受け入れる状態を意味します。このモードでは、結果や成功を追求するのではなく、「ただ存在する」ということが大切です。
2.1. Beingモードとは?
マインドフルネスにおけるBeingモードは、「今ここ」に集中する心の状態を指します。Doingモードのように問題解決や目標達成を目的とするのではなく、ただ今の瞬間をありのままに受け入れることが重視されます。このモードでは、現在の体験や感情、思考を評価せず、ありのままに観察し、受け入れることが大切です。例えば、自然の中で深呼吸をしながら、風の音や鳥のさえずりを感じることや、目を閉じて自分の呼吸に意識を集中させることがBeingモードの具体的な例です。
Beingモードでは、未来の不安や過去の後悔にとらわれることなく、今この瞬間を楽しむことが可能です。これにより、ストレスが軽減され、心身の健康を保つ効果が期待できます。
2.2. Beingモードの例
Beingモードは、Doingモードとは異なり、「何かを成し遂げる」ことに焦点を当てるのではなく、「ただ今にいる」ことを強調するモードです。Beingモードの具体的な例を3つ挙げて、その特徴を詳しく説明します。
例1:自然の中での静かな時間
Beingモードは、自然の中でリラックスして過ごす時に最もよく体験されます。例えば、公園や山に出かけて、木々の音や風の感触、鳥のさえずりに耳を傾けながら、ただその瞬間を味わうという体験です。このような体験は、目標達成や問題解決を意識せず、ただ自分の周りで起こっている出来事や感覚に注意を向けることで、心をリフレッシュさせる効果があります。Doingモードでは「何かを成し遂げる」ために行動しますが、Beingモードでは「何もしない」ことが大切で、自然の音や風景をそのまま感じることが重要です。
例2:深呼吸と呼吸の観察
マインドフルネスの基本的な実践のひとつに、呼吸に意識を向けるという方法があります。これはBeingモードの一つの形です。例えば、静かな場所で目を閉じて、深呼吸をしてみます。その時、息を吸う時の感覚、肺に空気が入っていく感覚、息を吐き出す時の体の変化に意識を集中させます。Doingモードであれば「正しく深呼吸をしよう」「リラックスしなければならない」といった考えが浮かびますが、Beingモードでは「ただ呼吸を感じる」ことに注力し、呼吸をコントロールしようとはしません。このように、現在の瞬間を感じるだけで、心の平静を保つことができます。
例3:感情をただ感じる
私たちは日常的に様々な感情を抱きますが、それらをコントロールしたり、問題として解決しようとすることがよくあります。これがDoingモードです。しかし、Beingモードでは、感情をただ感じ、その感情がどのように体や心に影響を与えているかを観察します。例えば、怒りや悲しみを感じた時、その感情を「何とかしよう」とするのではなく、その感情がどこから来ているのか、どのように感じられるのかを静かに見つめることが大切です。このプロセスを通じて、感情を無理に抑え込んだり解決しようとするのではなく、自然にその感情が過ぎ去るのを待つことができます。
2.3. Beingモードを活用するには?
Beingモードを生活に取り入れることで、心の平静を保ち、ストレスを軽減することができます。以下に、具体的にどのようにしてBeingモードを活用できるかを説明します。
例1:毎日のマインドフルネス瞑想
Beingモードを活用する最も効果的な方法の一つは、マインドフルネス瞑想を日常生活に取り入れることです。1日5分でも、静かな場所で目を閉じて呼吸に意識を集中させ、ただ今この瞬間を感じる練習をすることが大切です。瞑想中は「何かを成し遂げる」ことを考えるのではなく、ただ自分の呼吸や体の感覚に注意を向け、心の中に浮かんでくる思考や感情をただ見つめることが目標です。これにより、日常のストレスやプレッシャーから解放され、心のバランスを保つことができます。
例2:食事に集中する
忙しい日々の中で、私たちはよく「ながら食べ」をしてしまいます。テレビを見ながら、スマートフォンを操作しながら食事をすることが多いですが、Beingモードを活用するためには、食事に集中することが効果的です。例えば、食べる前に一度食事の香りを感じ、最初の一口を噛みしめながら、その味や食感に集中します。この時、食事を「早く終わらせよう」とか「他に何をしよう」といった考えを排除し、ただ食べる行為に全神経を集中させることが大切です。これにより、食事の時間が充実し、満足感が高まるだけでなく、心も落ち着きます。
例3:日常の中で小さな瞬間を楽しむ
Beingモードは、特別な時間を取らなくても、日常の中で実践できます。例えば、通学中に周りの風景に注意を向けたり、道端の花や木々の香りを感じる時間を持つことです。Doingモードでは目的地に早く到着することに意識が向きがちですが、Beingモードでは途中の景色や風の音に意識を向けることで、その瞬間を楽しむことができます。このような小さな瞬間を大切にすることで、毎日の生活がより豊かになり、ストレスが軽減されます。
次の章では、DoingモードとBeingモードの違いについて解説します。これにより、どちらのモードもバランスよく取り入れることが、心身の健康にとって重要であることを理解できるでしょう。
3. DoingモードとBeingモードの比較

3.1. DoingモードとBeingモードの比較
DoingモードとBeingモードは、日常生活において私たちが使う2つの異なる思考や行動のモードです。どちらも必要なモードですが、その違いを理解することで、より効果的に自分の心と体を使うことができます。ここでは、DoingモードとBeingモードのそれぞれのメリットとデメリットを比較し、表形式でまとめます。

3.2. DoingモードとBeingモードのバランス
この2つのモードは互いに補完し合うものであり、バランスよく取り入れることが大切です。Doingモードだけに頼ると心が疲弊し、Beingモードだけだと物事を進める力が弱まることがあります。次の章では、両者のバランスを取るための具体的な戦略について解説します。
4. DoingモードとBeingモードのバランス戦略
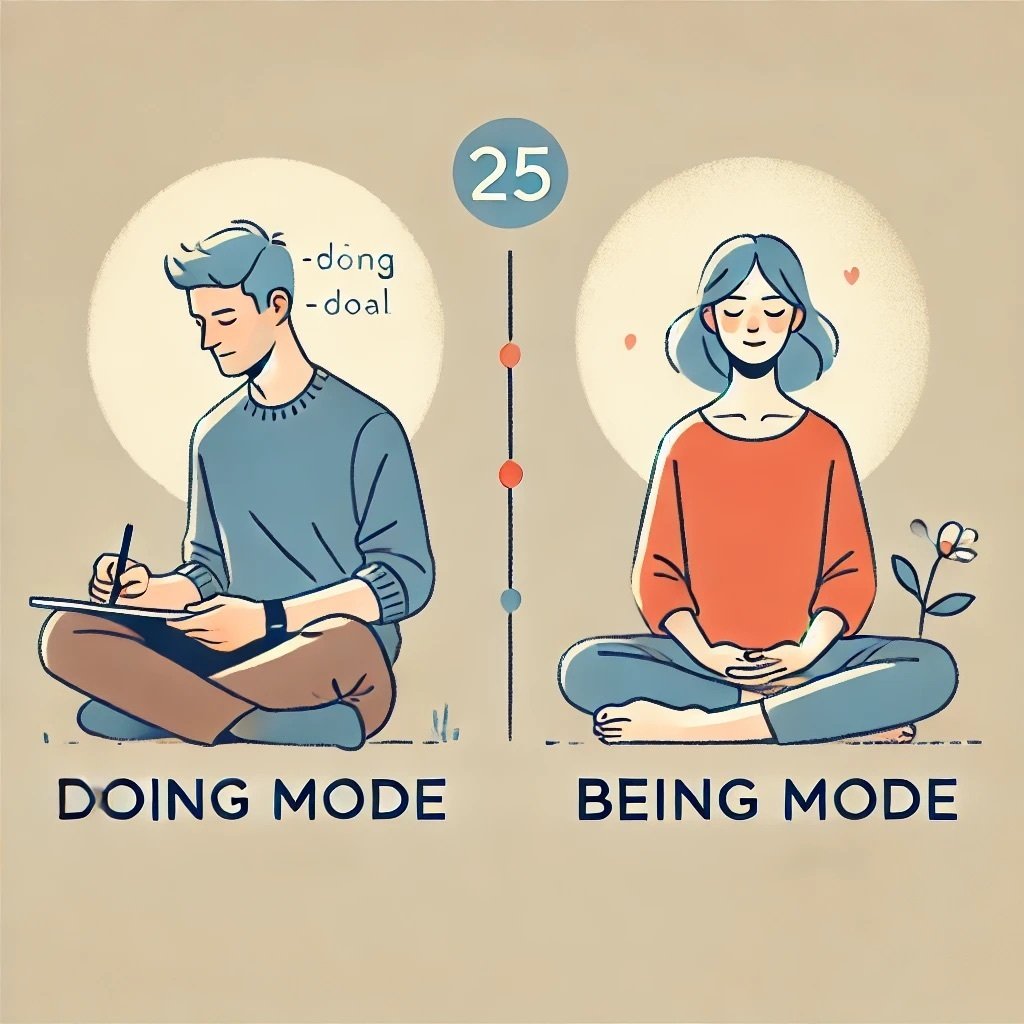
DoingモードとBeingモードのバランスをとることは、心身の健康を保ち、より充実した生活を送るために重要です。Doingモードは目標達成やタスク遂行に役立ちますが、過度に依存するとストレスや疲労が溜まります。一方、Beingモードはリラックスや自己観察に役立ちますが、やり過ぎると生産性が落ちることもあります。この章では、両者をバランスよく活用するための3つの戦略を紹介します。
戦略1:1日の中でDoingモードとBeingモードを交互に切り替える
1日の中でDoingモードとBeingモードを意識的に切り替えることで、効率的な作業とリラックスした時間の両方を取り入れることができます。例えば、授業や宿題をDoingモードで集中して行い、休憩時間にはBeingモードを意識して「今この瞬間」を楽しむことができます。ここでは、以下のようなサイクルを取り入れることができます。
勉強や作業(Doingモード):25~50分の集中した時間を確保し、勉強や宿題に取り組みます。この間は目標達成に集中し、Doingモードに入ります。
休憩時間(Beingモード):5~10分の短い休憩を取り、深呼吸をしたり、外の空気を感じたりして、心をリラックスさせます。この時はDoingモードから解放され、何かを成し遂げる必要がないと感じることが大切です。
このように、DoingモードとBeingモードを交互に取り入れることで、集中力を維持しつつ、ストレスを溜めずに過ごすことができます。
戦略2:日常の中にマインドフルネスを取り入れる
Beingモードを意識的に日常生活に取り入れることは、Doingモードでの活動を支える効果があります。例えば、食事の時間や移動中、ちょっとした合間にマインドフルネスを実践することで、心の余裕が生まれ、Doingモードに戻った時の集中力が高まります。
食事の時間:スマートフォンやテレビを見ながら食べるのではなく、食べ物の香りや味、食感に意識を向けて、食事そのものを楽しむ時間を作ります。これがBeingモードの実践です。
移動中:通学時に歩いている時や電車に乗っている時も、景色や風、周りの音に意識を向けてみましょう。Doingモードに戻るためのリフレッシュになります。
こうした小さなBeingモードの瞬間を日常に組み込むことで、心身のバランスを取りながら、Doingモードでの活動を効果的に進めることができます。
戦略3:目標達成後に意識的にBeingモードに入る
Doingモードでの活動が終わった後には、意識的にBeingモードに切り替える時間を取ることが重要です。例えば、試験勉強や部活の練習が終わった後、リラックスする時間を設けて、体や心を休めることが必要です。Doingモードは成果を求めるモードですが、結果を出した後には、その過程を振り返ることなく、ただ「休む」ことに集中することが大切です。
例:試験が終わった後、家に帰ってからリラックスするために、音楽を聴いたり、静かな場所で深呼吸をしてみる。Doingモードの「結果」から離れ、Beingモードで心を落ち着かせる時間を作ります。
目標を達成した後に、リフレッシュする時間を取り入れることで、次のDoingモードに入る際に心身のエネルギーが回復され、より良い結果を生み出すことができます。
