
【短編】あなたが好きだと言ったそれに僕はなりたい【第二話】
放課後は、鋭く高鳴る。一番聴覚が敏感になるような時間。見えなくても、触れなくても、十分に感じられて、ひどく気分が沈む。何かが僕らにもあるかもしれないと思い、なんとなく帰宅部は学校に残る。
けれど、たいていそこには何もなくて、いつでも何かが起こっても良いようにその時を待つ。そのための無為なおしゃべりは、たまに迷子になったりして、その隙間を埋めるために、必死に言葉を探す。
僕はそうはならない。その裏側に、また別の時間が流れているのだ。中学生同士の秘密の時間。たいてい、放課後は安祐美と体育館の入り口に伸びる階段に腰掛けている。
ここは、飛び交う硬式ボールや、何度も揺れるゴールネット、どんなものでもみえる。耳だけ澄ましていると、瞼の向こうからくる謎めいた光で眩しい。
けれど、いざ五感を使ってみると、本当は眩しいだけじゃないことがよくわかる。彼らは、何度だってこけてしまうし、ボールだってほとんど上手くとれていない。ほら、いま、泥のはねたユニフォームに、まだ新しい泥がシミをつくっている。
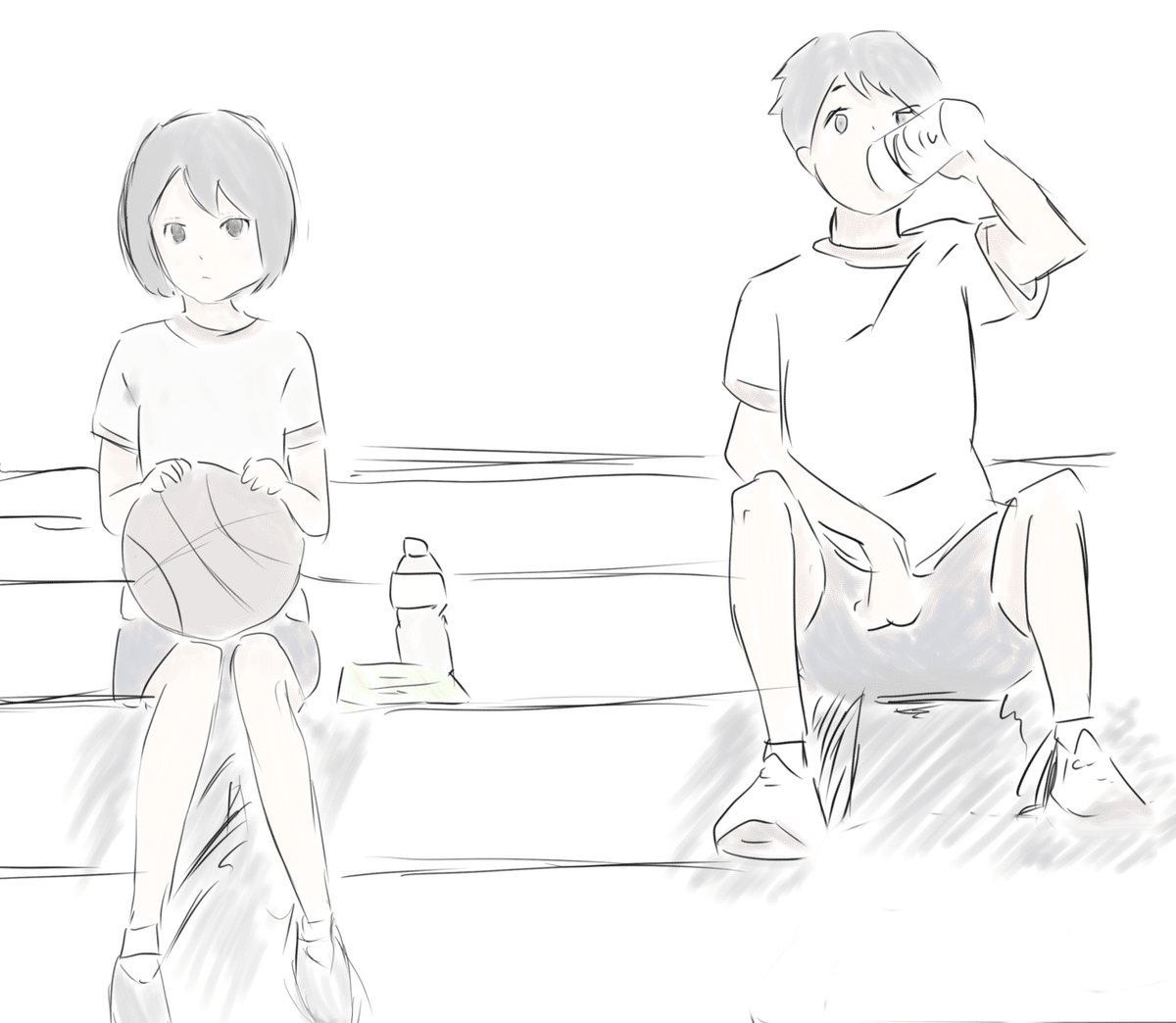
「ね、悠斗君」
同級生と比べて、少しだけ高いと思っていた僕の声。安祐美の声は、その上をいく。
「国語の時間ね、笑っちゃった」
「え?」
今日の国語の時間、先生から指名されて朗読したことを思い出す。
「木村、ってきいたら、全部悠斗君みたいに思えてきてさ」
どうやら物語の登場人物の名前がツボに入ったらしい。
冬の終わりに木村一家は火事に見舞われ、家財の一切を失う。無一文になった木村家は、それまでは薄情だった家族のひとりひとりが互いに向き合うことを試されて、そして経済的には不足があるものの、精神的には充足された形で終わる。悲惨な話なのかもしれない。しかし、物語の中で、木村一家は一つ前に進んだようだった。
「僕を貧乏にしたいの?」
僕は微笑みかける。あと数センチで理想になるはずの、この顔。
「そうじゃないけどね。でもさ、好きな人と登場人物を重ねると、ストーリーが入ってくるんだよ」
「それはわかるかも」
安祐美が話をふって、盛り上げて、沈黙がおとずれる。この手続きをいつも何度か繰り返す。会話が嫌なわけじゃない。けれど、いつだって言葉は出てこない。
「日曜日、あいてる?」
本当は安祐美の日曜日の予定はどうでもよかった。でも、こうして予定を訊くと、安祐美は大概、身を乗り出して僕のことを見る。
「ごめん、日曜日は家族と出かけるから」
想定した返事と違って、僕はその次の日曜日は、と訊きかけるが、返答が怖くて、舌を強く噛む。家族。その言葉に、僕はひどく敏感になる。急に安祐美がいじわるな人間に思えてきて、腹が立つし、虚しくもなる。
ヴッとスマホが震える。
「ちょっと、ごめん」
近づいた瞳になんとか笑いかける。
『お弁当、どうだった?』
一瞬、叔母からだと思ったが、叔父からだった。なぜ叔父からお弁当の感想を求めるメッセージがくるのだろう。
『おいしかったよ』
指を素早く滑らせる。
「誰から?」
安祐美は覗き込まないようにして、僕に鋭い声で訊く。両手を組んで、それをきちんと畳んだ膝の上に置き、上目遣いで僕をみている。
「お父さん」
「お父さんとやり取りするの? 珍しいね」
珍しいね、の「ね」が強く止まった。気味悪がられているのだろうか。でも、少ない日常会話の中の、ほんの一つなのだ。安祐美の目の前で、僕は叔父からのメッセージが嬉しくもあった。
「たまにね」
「たまに」
普通はお父さんとなんか連絡しないでしょう、という安祐美の表情を想像する。
「お父さんとのやり取りのほうが多かったりして」
「それはないよ」
僕は叔父とのやり取りを安祐美にみせる。あくまで操作しているのは僕で、安祐美の顔の前に慎重に差し出す。スマホをスクロールする僕の手つきは必要以上に速くなってしまっている。安祐美は、ふうん、と言うと、ゴールネットへと顔を向けた。
そろそろ帰ろうかな。
そう思うものの、口には出さない。安祐美もきっとそう思っているのだろう。よく知らないキャラクター達が一斉に首を吊っている鞄、それはずっと安祐美の肩にかかったままだから、いつでも立ち上がり、この場を去ることはできる。
でも、そうしない。そうしない二人が、結局ここで無為に時間を過ごしていることに気づく。運動部をひたすら見続けるなんて、その視線の先に好きな人でもいなければ全く退屈な行為だろう。
「ねぇ、悠斗君ってさ……」
湿った風が吹いた。かなり長くなってしまった髪の先が、口元にふれた。
「ずっとここにいるんだよね?」
安祐美が僕にそう訊ねた。たぶん、僕の顔をみている。いくつか数を数える。数字が大きくなるにつれて、ここがどこなのかが、わかるようになっていく。
また、湿った風が吹いて、ぽつ、僕の太ももに水滴が落ちる。今朝の、無念のひじきを思い出す。次の水滴が落ちると、また次の水滴が落ちた。そうした調子で雨は僕らを急がせた。ちゃんと帰る理由ができた。僕は身体を持ち上げて、雨だ、ときちんと呟いた。
「帰る?」
「きっとこれから強くなるから、いまのうち帰ろうよ」
「もう?」
もう? の、「う」が高く上がって耳を引っ掻く。少し前まではこんな言い方はしてこなかった。
そうしている間にも、雨音は強くなっていっている。このままどこかに雨宿りはごめんだ。
「わかった。帰ろう。傘、あるの?」
「あるよ」
「わたしの傘大きいよ。入ってく?」
「いいよ。大丈夫。自分の傘で帰るから。それに帰る方向違うでしょ」
安祐美の表情はここからはみえない。その手は確かに大きい傘を開こうとしている。中学生の女の子には似合わないくらい、ずっしりと、暗い色の傘の柄を安祐美が持つ。
大きな傘から伸びる細い足が、僕とは違う方向へ歩みだすのを確認した後、僕は僕の帰り道を進んだ。遠くで雷が鳴りだして、あたりは暗くなっていく。雨がぼとぼとと頭上に礫のようになって落ちる。僕はまだ小さな水溜まりをいくつか飛び越えて、早足で駅へ向かった。
枯草色の椅子に腰かけて、雨に濡れた街が流れていくのを見つめる。今朝よりもずっと軽快に電車は走っているみたいで心地よい。
雨に打たれながら自転車を走らせる人を車窓から見送ったころ、どさりと人の頭が僕に垂れてきた。髪のない頭が左肩で重たい。
僕はピンボールをはじくみたいに左方に力を込めて跳ね返した。その頭は急激に失速して、ちょうど良い具合に垂直になった。ごく普通のおじさんの顔がそこにはりついていて、眉をぴくりと動かしている。
起きるか、起きるか、起きるか、と見守っていたが、結局起きず。次にこちらに倒れてくるのかを気にすることが、いちいち面倒に感じる。
この顔に、僕がキスをしたらどうなるのだろう。
ふと浮かんだ想像が、何やら危険めいていて、少しだけ怖くなる。たまに、自分の発想が突拍子もないときがある。きっと意味はもってないけれど、意味が生まれてしまいそうな感触を持つ。
僕の口はおじさんの口を塞ぎ、途端に苦しくなったおじさんは目を覚ます。そこには僕の顔があって、おじさんは一瞬戸惑うも、僅かに力を抜いて受け入れる。それを見た僕は、満足げに舌を入れていき、出せるものを全て吐き出して舌を引っこ抜く。抜け殻のおじさんに、どうだった? と訊く。おじさんは何も言えないで息を整えようと努める。
活発に出てくる自分のストーリーが怖い。後はもう実行するだけで、引き金は簡単にひくことができる。その現実味が狡いとさえ思う。
もしかしたら、いつのまにかそんなことを実行しているのかもしれない。いつの日か、そんなことをしてしまったのかもしれない。
軽快なメロディとともに車内のドアが開く。おじさんはそれを知っていたかのようにぱちりと目を開き、咳払いを一つして、二歩三歩ぐらいで出て行ってしまった。髪のない頭が雨に濡れて、その後は車窓の枠から途切れて終わり。見知らぬおじさんは見知らぬおじさんのまま見知らぬ街へ消えていった。
僕にキスをされたほうのおじさんは、果たしてそのままのおじさんだったのだろうか。きっとまだ電車に乗っていて、僕のことを見つめはじめる。どうする? 視界の隅で僕をみて、そんなことを言う。僕は、どうでもいいよ、とだけ言い放つ。雨が止んだどこかの駅で、僕たちは二人揃って降りる。おじさんは僕の肩を抱き、僕に向かってこう告げる。
ねぇ帰るところあるの?
心憂う僕はさもありなんといった顔をして、駅から見える誰かの家、家、家、家、家へと、視線を移していく。
踏切の前で、スマホが震えた。カンカンカンカン。遮断機が下りてきて、眩しく赤と赤が交互に点滅する。自転車のブレーキ、駅へ急ぐ人の舌打ち、車のエンジン音が僕の辺りでとどまる。スマホを取り出すと、光の中に叔父からメッセージがぼうっと現れている。
『日曜日、空いてるか?』
日曜日、空いているか?
そのメッセージの少し上には、また別の、日曜日、空いているか、がある。
直接訊かれない日曜日の予定に手の動きを止めてしまう。これに対して、空いている、と素直に答えたことがなく、少しだけ申し訳ない気持ちになる。叔父はずっと歩み寄ってくれている。あの人は、不器用なだけなのかもしれない。
遮断機が上がって、滞留していた空気が拡散していく。この流れにのって、前に進まないと、この狭い道は人でつまってしまう。僕は『空いてるよ』と打ち込み、街のペースに戻った。
叔父や叔母は後悔していないだろうか。僕のために稼ぐことを、ごはんを作ることを、休みには僕と密にかかわるということを。
たまには思春期の僕に頭を抱えることもあるかもしれない。たいして思春期らしさを出してはいないつもりだけど、かえってそれに頭を抱えていることもあるかもしれない。
僕にはわからないことがたくさんある。叔父と叔母にとっても、僕はわからない存在なのだろう。例えば、それ自体が、喜びだということはあるだろうか。一体、親とはどういうものだろうか。そういうものだろうか。僕がそんなことを考えるのは驕りだろうか。
来年、僕は十六になる。あの家を出るかどうか、ということを、頻繁に考えるようになった。この機会を逃すと、次の機会は三年後までやってこない。勿論、誰一人として頼る親族は他にはいない。あの時、受け入れてくれたのは、叔父夫婦だけだったから。だから、いざとなれば一人で生きていくしかない。
きっと、僕はここにいるということが、ひどく下手くそなのだと思う。無邪気に過ごすことも、何も知らない顔でいることも、ただ狡く生き続けることも、どれも僕にとっては難しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
