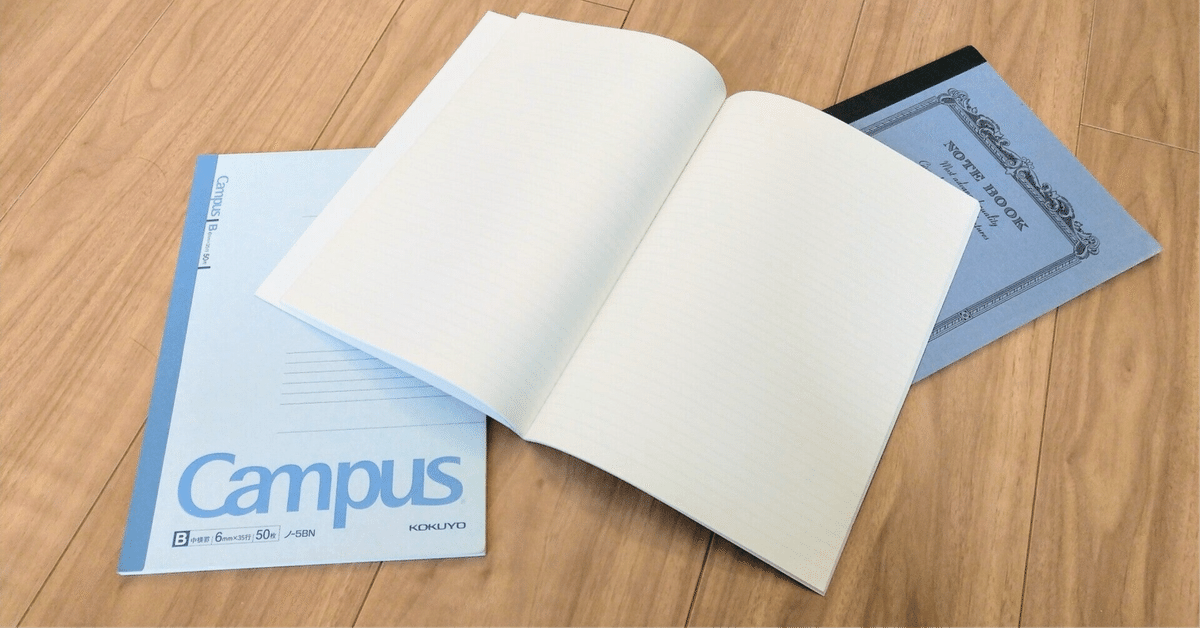
雑文:「まじっく快斗」を読んで思った、架空の職業と学生の相性の良さについて
現実を舞台にした作品において、主人公が学生の場合に多いのが、架空の職業(?)との兼業です。
ざっと例を挙げてみると、
『学生×怪盗』⇒「まじっく快斗」・「神風怪盗ジャンヌ」
『学生×魔女』⇒「カードキャプターさくら」・「おジャ魔女どれみ」・
「魔法少女まどか☆マギカ」『学生×能力者集団』⇒「結界師」・「BLEACH」
ほかにも様々な作品が、このケースに該当するはずです。
作品の入り口としての「学生」
「学生×架空の職業」という設定の汎用性の高さには理由がある
(と思います)。
まず第一に、読者が作品内に入り込めます。
皆さんご存じの通り、魔女や怪盗といった職業は明らかに架空であり
フィクションです。
したがって現実には存在しないわけですが、そんなことは読者も
わかりきっています。
だからといって主人公が「勇者」や「魔女」の一本調子にすると、
『この主人公は架空の職業であり、この作品の世界は偽物です』という
メッセージを読者に強く与えかねません。
これでは読者も興ざめというもので、作品を読む気がなくなってしまいます。
※ちなみに、ファンタジーやサイバーパンクといった世界観で勝負している作品は最初から読者に「この作品はフィクションです」と提示しているようなものです。ただし、作品の世界観を徹底的に緻密にすることで、偽物の世界をまるで本物と見紛うように作り上げてしまうのです。
この問題の解決策として有効なのが、『学生』という現実の職業の導入です
(学生が職業か身分かという違いはおいておくとして)。
読者は学生という身分に抵抗がありません。
なんせ世の中にとってはありふれた存在だし、かつては自分だってそうだったのですから。
この学生という現実との接点を通すことで読者は作品への警戒感を解きますし、この接点から読者を作品へと導くことが出来ます。
つまり学生は「〈読者〉と〈作品〉を、〈現実〉と〈架空〉をつなぐ架け橋」になるのです。
ストーリー上の利点
ストーリーを展開させていく上でも、「学生×架空の職業」という設定は都合がいいです。
二つの職業を掛け持ちしている主人公が進む道を二つに絞ることが出来ます。
一つ目は、それぞれの職業を交わらせない方針。
この場合、主人公は学校の友人たちに自身の「架空の職業」について隠しています。
その理由は色々ありますが、例えば「まじっく快斗」だと主人公は怪盗のため、自分の正体がばれると逮捕されてしまいますし、「おジャ魔女どれみ」では、魔女という存在が人間に分かった瞬間、カエルになってしまうという
ペナルティが存在します。
こういった「ばれてはいけない」という制約をつけることで、その後の物語が展開しやすくなるのです。
親友にも恋人にも、自分のもう一つの正体をバラすことが出来ない苦悩や孤独。
自分が平凡な学生ではないという優越的で背徳的な喜び
「学生」と「架空の職業」で揺れる自分のアイデンティティー
ひた隠しにしつつもふとした瞬間に自分の正体がばれてしまう時のハラハラ感……
等々いくつもの選択肢を物語に持たすことが出来ます。
※区別するタイプの物語において、主人公の活動する時間帯は夜中が多いように見受けられます(例:「まじっく快斗」「結界師」等々)これは、夜に動かした方が人目につかないという実際的な理由があるのでしょう。
二つ目は一つ目の反対で、学生生活と架空の職業をかかわり合わせる方針です。
このタイプの代表的な作品といえば「新世紀エヴァンゲリオン」
主人公碇シンジは「学生」かつ「エヴァンゲリオンパイロット」として使徒と戦いますが、周囲の人間は彼の特殊な経歴を知っています。
「碇シンジがエヴァに乗って戦うのは平和な学園生活を守るためであり、そして凡庸な少年である彼が学園で注目を浴び美少女と同居するのは彼がエヴァのパイロットだからだ」
というのは批評家の宇野常寛の指摘で、
学生生活と架空の職業の深い関係性について述べています。
作品の構造上碇シンジは皆の注目の的にならざるをえないわけですが、
ここで「碇シンジは引っ込み思案な性格であり、あまり前に出たいとは
思っていない」という設定を足すのがエヴァの妙味です。
こうすることで、主人公の葛藤を描くことが可能となり、
物語に深みが増します。
学生にあってサラリーマンにないもの
こうして考えてみると、主人公は『学生』でなくても『サラリーマン』のような現実にありふれた職業であればなんでもよいのではないかという気になります。事実そういう作品もあるわけですが(例:「いぬやしき」「中年スーパーマン佐江内氏」等々)、それでも学生という設定にはほかの職業にはない利点があると考えます。
それは、ずばり「時間」です。
学生というのは基本的に自由な存在です。仕事に追われることもないし、
残業や出張の必要もありません。極端に言えば、学校に行かなくても
学生でいることは可能なんですから。
主人公たちはこの空いた時間を用いて架空の職業に勤しむことが可能です。
これがサラリーマンだと勝手が違ってきます。
毎朝会社に通わなければならないし、仕事はつねに納期がつきまといます。外回りの営業でもなければ中々社外に出ることはできません。
「学生気分では困る」というのは、会社側から新社会人に言われるお小言の一つですが、この言葉一つとってもサラリーマンという存在は学生とはまったく違った存在だということがわかります。
サラリーマンが、架空の職業で活躍するには、時間的空間的制約が
多すぎるんです。
ちなみにサラリーマン以外の職業だと、
『個人商店主×殺し屋』⇒「SAKAMOTO DAYS」
『新聞記者×ヒーロー』⇒「スーパーマン」
『CEO×ヒーロー』⇒「アイアンマン」
等々サラリーマンに比べてかなり多い印象があります。
これは、サラリーマンよりも暇な職業だから…
ということではなく、サラリーマンに比べて全体数が少ないため(詳しく調べてませんが、まさか個人商店主がサラリーマンより多いということはないでしょう。他も同様です)、読者が職業のイメージがつかないことを逆手に、
自由に書くことができるということでしょう。
制約を逆手に—「中年スーパーマン佐江内氏」—
上記で述べたサラリーマンにおける制約の存在を逆に上手く使った作品が「中年スーパーマン左江内氏」です。
中年サラリーマンの主人公佐江内氏(この名前も)がスーパーマンになってそれなりに活躍するというのが物語のすじですが、
会社員たる佐江内氏は無暗に人助けができません。
虫の知らせが来た時には上司の顔色をうかがいつつ、昼休みやトイレ休憩といった空き時間で会社を抜け出さざるをえません。
おまけに、問題の大半は人間同士のいざこざ。悪の組織や怪人といった非日常的な存在はまったくでてきません。
査定やら左遷やら日常の細々したことにおびえながら、佐江内氏は今日もヒーローとして活躍する。作者藤子・F・不二雄によるこの日常と非日常のブレンドの巧みさには脱帽せざるをえません。
(この人会社勤めしたことないはずなのになんでこんな漫画がかけるんでしょうか)
藤子・F・不二雄の隠れた名作として有名なこの作品、ぜひ読んでみてください。
