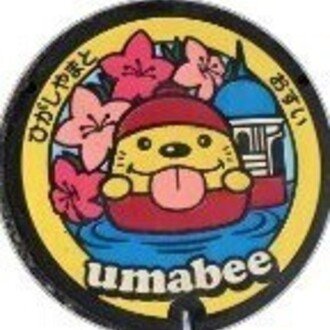牡丹餅とお萩の名前の由来
もうすぐ秋の彼岸がやってくる。「暑さ寒さも彼岸まで」といわれて、酷暑に別れを告げる季節となる。例年台風がやってくるとそれを機に季節が変わることが多い。
2024.03.24に自作のよもぎの牡丹餅の記事を投稿した。
多摩湖の蓬で春の香りをいただく

その時、タイトルに「牡丹餅」と「お萩」のどちらを使うか迷ったが、春秋に咲く花に関係があるとなんとなく知っていた。ネットで調べてみた。
季節ごとに名前が違う
餅米をすり粉木で突いて団子状態にした餅には、季節毎にいろいろな名前が付いている。
春:牡丹餅
秋:お萩
夏:夜船
冬:北窓
春の「牡丹餅」の名前の由来
春の牡丹の花のように丸く、こし餡で包んだものを牡丹餅と呼ぶ。江戸時代に春のお彼岸に食べられていたので、牡丹餅と呼ぶ。江戸時代は、小豆は春には皮が固くなるので皮を取り去ったこし餡で作るのが普通だった。

秋の「お萩」の名前の由来
秋の呼び名「おはぎ」は、牡丹餅と同様に小豆あんの様子を秋の彼岸に咲く小ぶりで細長い「萩の花」に見立てたことから名前がついた。秋のお彼岸の時期は、小豆の収穫時期で採れたてで皮が柔らかい小豆は皮もつぶした「つぶ餡」が使われていた。

夏の「夜船」の名前の由来
夏の呼び名は、おはぎの作り方と言葉遊びに関係がある。おはぎを作るときには、餅つきのように臼を使わず、すり粉木で米を潰して作る。餅を作る時にはすり粉木で作るので音は出ない。隣人にいつ「ついた」か分からないということから、暗い夜にいつ着いたかわからない「夜船」になぞらえて「夜船」と呼ばれるようになった。

冬の「北窓」の名前の由来
冬の呼び名「北窓」は、こちらも言葉遊びで、北にある窓からは「月」を見ることができないことによる。搗き知らず→月を知らない→月が見えない、「北側の窓」から月が見えないということから由来している。

言葉の変化
牡丹餅とお萩という言葉は子供のときから彼岸になると使われて覚えがあるが、夜船と北窓は今では知っている人も少なくなり、そのうち消失してしまうかもしれない。言葉が時代と共に変化していく理由は何だろうか?
言語は、発音の負担を軽減させる方向へと変化している。また、記憶の負担を軽減 させる方向へと変化すると言われている。
まとめ
NHKの大河「光る君」の平安の時代から、人々は短歌で言葉遊びを楽しんできた。終戦後、欧米の文化とカタカナ言葉が入ってきた。「夜船」や「北窓」のような昔の言葉が急速に消失している。「言葉遊び」を楽しみながら、少し心に余裕を持った生活をしていきたい。
【リンク】
いいなと思ったら応援しよう!