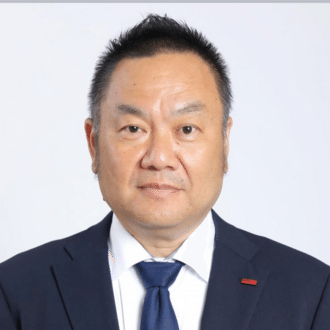数字と観た感と
たまには、フットサルの監督みたいなことを!! 書きましょう。
毎回のトレーニングでの紅白戦を数値化するようにしています。
(これが、かなり時間が掛かります…アシスタント大募集中です 笑)
主に
決定機を作り出した回数
阻止した回数
ボールをロストした回数

勿論、その中に局面もあり
どの場所で、どんな局面で、どんな状況でを数字にする。
紅白戦という一回一回のゲームの中で、ゴールと言うゲームにおける圧倒的な主導権を握れるものを目指し、その後はリードしていたら? 負けていたら? で、コンテキストを共通理解してプレーの優先順位に変動を起こす。
目指すはそういうゲームの中でも勝つことである。
勝つとは、ゴール数で上回ることである。
保持率でもなければ、シュート数でもない。
ゴール数なのだ。
を目指してプレーする中で、監督として
観た感じの選手のプレーと、数値で表した選手のプレー結果。
定性化と定量化
これが、大事だと思ってて….
観た感じだけど、どうしても主観が入りやすくなることもあるし、ある意味の基準がブレる事もある。
頑張ってるね。
それだけを基準にしているのであれば、みんな合格かもしれないが、それと同時にその頑張った結果の数字も観なくてはいけない。
ただ、自分の直感も含めた選手のプレーを観た時に、その数字には見えない背景(心理的なもの、コンディション的なもの、社会的な影響、生活環境)など、数値化しにくいものが影響しているのもある。これをある種少し抽象的ではあるが、それを把握し、選手のプレーにより良く働きかけることも大事であるし、プレーの意図、技術的、戦術的な改善、アプローチをしていきながら定性化されたものを観ること。
一方で、それだけではある種の基準が設けることも出来ず、ゴールゲームをする中でのデータは必要になる。
僕らは、結局は数字で勝ち負けが決まるスポーツをしているのであり、何だかんだ最後は数字なのだ。
誰が、チャンスを作れるのか?
誰が、献身的に守備出来るのか?
誰が、ボールをロストし相手にボールを渡してしまっているのか?
そういうものを数値化することで、様々なゲームにおける可能性を高く広げることも大事だ。
勿論、オープンなゲームの中で、多少のトライによるロストもあるし、チャンスを作れたとしてもゴールに繋がらない事もある。相手がそれを阻止するわけで、簡単ではない。だからこそ、数字的な定量化だけで見るのではなく定性化されたもの、そしてその意図や狙いを汲んで観る事も大事である。
いずれにしても、何かを決める役割としては、両方の観点から何かを決めなくてはいけない。
定性化されたもの
定量化されたもの
そういう基準を整理することで、選考、決断の基準を設け、自分の決断の材料にする。
それは、選手にも伝えやすくデータ化しておけば、定性化されたアプローチの中で数字、そのプレーを見せることで、より良く改善も出来ると思う。
調子が良さそうな選手のプレー数値
調子が悪そうな選手のプレー数値
これをデータとして自分で持つことは大事なことだと思っている
ただ、僕はそれをすべての選手に見せることはない。
観たい選手、欲しい選手には見せるように準備しておく。
一人一人呼び止めて見せることはしない。
みたい人は直接言ってきて
それぐらいで話しして終わる。
元プロ野球選手GG佐藤氏がアメリカで経験した話。
— 續池均(Kin Tsuzuike)@MTR Method Lab™️ (@kintsuzuike) August 26, 2024
「求めてこない者に対して教えても意味がない」
行動こそが内発的動機付けの結果。育成なら、子どもたちが自ら行動を起こすようにサポートする。ティーチングも当然必要だが、より成長を促すのはコーチング。#育成のヒントpic.twitter.com/HYvC4GkMtH
僕のコーチングの土台になるのは、主体性である。
これは、スクールだろうとTOPカテゴリーだろうと同じである。
自ら課題解決したい、成長したいと思って自らドアを叩く事が一番大事な事。
iPhoneだって16になって、OSもアップデートする。
自らアップデートすることに意味と価値はある。
リンクに貼ったGG佐藤さんの動画が、少し前流れたきたが、まさにこれと同じ感覚である。
ただ、それだけでは駄目だと思ってて…
若手には呼び止めて見せることもあるし、少し悩んでいるような選手には良いプレーの動画も見せることもあるし、個別にラインで送ることもある。
ある種少し強制的にアップデートの機会を創ることも大事で…
すべてが主体と言う訳ではなし、状況によっては変化する。
そのケースケースで変えなくてはいけない。
コーチングとティーチングを織り交ぜながら、選手が進化するキッカケが創れたらいいと思っている。
そういう小さな試行錯誤と準備の先に、選手の成長があり、定性化されたものと定量化されたものにより良く変化があれば良い。
数値化されたもの
数値化されないもの
そう思えば….
数値化されたもの、数値化されないもので、人生決めること、決められることが沢山ありますよね…
そんな時にも、2つの観点から物事を見れるようになるといいなぁと思います。
果たして、その決断は
定性化されたものとしてはどうなのか?
定量化されたものとしてはどうなのか?
では、これについてもまた書きますね!!
いいなと思ったら応援しよう!