
稲盛和夫 カリスマの遺訓 2022.09.12 2/3
【『日経ビジネス』の特集記事 】 #2
✅はじめに
⭐『日経ビジネス』の特集記事から、私が特に関心を持った個所や重要と考えた個所を抜粋しました。
⭐ Ameba(アメブロ)に投稿していた記事を再編集し、加筆修正し、新たな情報を加味し、再投稿した記事は他の「バックナンバー」というマガジンにまとめています。
⭐原則として特集記事を3回に分けて投稿します。
「私にとって、noteは大切なアーカイブ(記録保管場所)です。人生の一部と言い換えても良いもの」です。
(プロフィールから)
日経ビジネス電子版セット(雑誌+電子版)を「らくらく購読コース」で、2022年9月12日号から定期購読を開始しました。
日経ビジネスの特集記事 #2
稲盛和夫 カリスマの遺訓 2022.09.12 2/3
<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>
PART 2 苦悩の末にたどり着いた「無私」の境地
PART 2では、稲盛和夫さんの経歴を時系列で見ていくことにしましょう。
尚、かなり大雑把な記述となることをご了承下さい。
下記の内容は、京セラ創業者の稲盛さんの「信念」を語った部分です。
自信と裏腹な不安も抱いていたことでしょう。
「社会が必要としているもので、開発不可能なものはない、というのが私の信念です」
1973年7月9日号の本誌に京都セラミック社長として登場した、当時41歳の稲盛和夫氏はこう語っていた。自信たっぷりのようにも見えるが、実際には、開発できなければ、生きていけないという悲壮感から生まれた「信念」だったはずだ。
「みじめだった」米国行脚
「語学はダメ」だという稲盛氏だったが、足を棒のようにして米国中を歩き回った。東部から西部へ。西部から東部へ。ホテルも食事も切り詰めての御用聞き。それでも63年、64年の訪米時の注文はゼロ。稲盛氏は「みじめだった」と述懐している。
それでも諦めなかった稲盛さんは、「3度目の訪米で果実を得た」そうです。
65年の3度目の訪米で果実を得た。当時、日本の技術や製品を導入しないことで定評があったという米半導体大手テキサス・インスツルメンツ(TI)から米航空宇宙局(NASA)の宇宙計画で使うセラミック部品の受注を勝ち取ったのだ。西ドイツのメーカーとの競争の末での初めての受注。これを突破口に京セラは米国進出の足掛かりをつかみ、成長の土台を築くことになる。
それ以来、京セラは破竹の勢いで成長していくことになります。
急成長を遂げた京セラは、71年に大阪証券取引所第二部と京都証券取引所に、翌72年には東京証券取引所第二部に株式を上場。セラミック部品の急成長企業として一躍注目を集めるようになる。
それでも稲盛氏は浮かれなかった。73年7月9日号の記事では稲盛氏のこんな言葉を紹介している。
「京セラの今日を築いたのは信頼に基づく人の和である」
ここでのキーセンテンスは、もちろん「京セラの今日を築いたのは信頼に基づく人の和である」です。
「企業は人なり」とはよく言われますが、実際には社員を大切にしない企業は数多くあります。コスト削減のために、正社員を減らし、非正規社員を雇う企業はザラにあります。
創業に関する解説があります。お金が乏しかった稲盛さんは創業資金を募ることになりました。
仲間たちで「一致団結し、世のため人のためになることを成し遂げる」と、誓いの血判状を押した逸話が残る。創業資金は、稲盛氏が持つ技術力と人柄にほれ込んだ人々が援助した。「この金を思い通りに使え。しかし、この金に使われるな」。出資者は稲盛氏にそう助言したという。こうした人たちの決意と助けがあったから京セラは誕生した。だから稲盛氏は「信頼に基づく人の和」を大切にしてきた。
出資者は稲盛さんに全幅の信頼を寄せていたからこそ出資したのです。
しかし、創業時の稲盛さんは27歳でした。
西郷隆盛の教え
稲盛さんは鹿児島市で生まれました。そのため同郷の西郷隆盛を尊敬していました。
子供の頃に父母や小学校の先生から教わった「人間として正しいことを判断の基準にする」ということ。「経営術を知らない私にとって、そんなプリミティブな道徳観、倫理観しか持ち合わせていなかったというのが本当のところです」と稲盛氏は述べている。
(中略)
稲盛氏の心に深く入り込んだ思想がある。同郷の西郷隆盛(雅号は南洲)の教えだ。
時に藩主の怒りを買って島流しされるなど、艱難辛苦(かんなんしんく)の人生を歩んだ西郷隆盛。その思想の根幹に稲盛氏は「敬天愛人」があると考えていた。自然の道理、人間として正しい道、すなわち天道をもって善しとせよ、己の欲や私心をなくし、利他の心をもって生きるべし──。「敬天愛人」はこう説く。
「敬天愛人」は京セラの社是になっています。
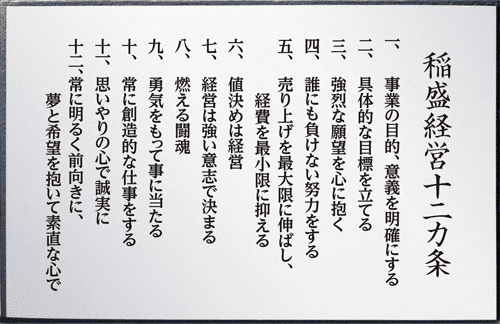
日経ビジネス 稲盛和夫 カリスマの遺訓 2022.09.12 p.020
(2022.10.12 追加投稿)
稲盛さんは社業に打ち込む傍らで、勉強を怠りませんでした。
稲盛氏は社業に打ち込む傍らで、日本を代表する名経営者、松下幸之助や本田宗一郎の本を熱心に読むことも忘れなかった。経営の「素人」だと自覚しているからこその向学心。中国の古典、孔孟の教えや仏教も学んだ。
「それらを繰り返し読むうちに、経営者として、また、悩み苦しみながら生きる1人の人間として、日々遭遇する出来事に照らし合わせてみると、人の考え方がしっかりしていなければ何事も立派に成就することはない、これは世の中の絶対的な真理だと確信を深めていった」(05年12月5日号「敬天愛人」より)という。
稲盛さんの哲学
次の記述から稲盛さんが哲学を大事にする理由が伝わってきます。
稲盛氏が哲学を大事にするのは、「成功することよりも、成功を持続させることの方がはるかに難しい」との考えに至ったこととも関係がある。05年10月24日号の「敬天愛人」で稲盛氏はこう強調している。「リーダーには哲学が欠かせない。成功に驕(おご)らず、謙虚に、自分を律する克己心を持ち続けられることが人間としての本当の偉さなのです」
「リーダーには哲学が欠かせない。成功に驕(おご)らず、謙虚に、自分を律する克己心を持ち続けられることが人間としての本当の偉さなのです」
現在の政治家たちに聞かせたい言葉です。
彼れには哲学に基づいた信念がないのです。
訳の分からない宗教団体の名称を隠れ蓑にした反社会的団体と深い関係を結び、国民を騙し続けるとは政治家失格です。
単なる政治屋にすぎません。
稲盛さんのお人柄
稲盛さんは他人にも厳しいですが、自分にはもっと厳しい人でした。
そんな稲盛さんでしたが、別の一面もありました。
稲盛氏は自らを「シャイで泣き虫」と評する「普通の人」の面も持ち合わせていた。88年12月19日号では稲盛氏の兄で当時、京セラ専務を務めていた稲盛利則氏のこんな話を紹介している。「小学校入学当時は、独りでは学校にもよう行かんという子でした。ノロノロしているので、私が置いて先に行くと、その日はもう学校に行かないということもありました」
そんな稲盛氏は「大義名分を持つことによって、弱虫だった私は勇気を引き出しているんです」と吐露している。そしてこう続ける。
「生きるためには、優しさも要るけれど、残酷な面も要る。もし信念にまで高まった大義名分がなければ、とても生きていけないでしょう。さいなまれてしまってね。例えば『お前は首だ』と言うとしたら、それは相手にとっては大変非情なことです。しかしそれより大切な大義名分が自分にあって信念にまでなっていれば、非情さも勇気を持って乗り越えられるのです」(88年12月19日号)
やはり信念が必要なのです。右を向いたり左を向いたり、ふらふらしていてはダメです。岸田首相は信念が欠落しているのではないかと思ってしまいます。
動機善なりや、私心なかりしか
「動機善なりや、私心なかりしか」
この言葉は、稲盛さんを語る上で欠くことのできない考え方です。
第二電電を設立する際に、「動機善なりや、私心なかりしか」と考え抜いた末に設立を決断しました。
「動機善なりや、私心なかりしか」。本当に国民のためを思ってのことなのか。きれいごとを言っているだけでないのか。この機会に京セラを大きくしたいとか、自分がもうけたいという私心はないのか。自分が目立ちたいという邪心があるのではないか──。「自分自身に刃を突きつけるように厳しく問い続けました。そして『いささかの濁りもない』と自分の良心に誓って断言できるようになった時、私は打って出ることを決断しました」。05年10月31日号の「敬天愛人」で稲盛氏はこう明かしている。
稲盛さんと孫正義さん
意外に思われるかもしれませんが、孫正義さんは稲盛さんが主宰する盛和塾で学んだそうです。
盛和塾で学んだ孫氏にとって、稲盛氏は師匠筋に当たる。孫氏が通信機器事業に参入してまず、商品を売り込んだ相手も、当時、第二電電会長だった稲盛氏。ソフトバンクが2012年に参入したメガソーラー事業では太陽光パネルを京セラから調達した。
稲盛氏と孫氏を結びつけた経営塾は19年末をもって、36年に及ぶ活動を終えた。塾生は国内のみならず、中国など海外にも広がった。そんな稲盛イズムを伝える活動の終了を前に、19年7月17日から2日間、横浜市のパシフィコ横浜の大ホールで盛和塾の「世界大会」が開かれた。
JAL再生に導いたアメーバ経営
アメーバ経営という考え方を聞いたり本で読んだりしたことはありますか?
最後に、アメーバ経営の概要をお伝えしたいと思います。
アメーバ経営は、会社の組織を10人前後で構成するアメーバという小集団に分け、独立採算を徹底させるもの。その神髄は「全員参加の経営」にある。その実現を促す仕掛けが、アメーバが独立採算を行うために用いる「時間当たり採算」という指標だ。
なぜ10人前後で構成するアメーバという小集団で分けて独立採算を徹底させるのでしょうか。
少し考えてみてください。
小集団に分けることによって、問題点がどこにあるかを明らかにするためです。
大集団だと問題点がなかなか見つけにくくなります。本質的な問題点が見つからなければ、解決はできません。対症療法に終始することになってしまいます。
破綻した当時のJAL(日本航空)は、胡座をかいていたのです。そして、本質的な問題点がどこにあるのか見つけ出す努力を怠っていたのです。
稲盛さんがJALに導入したのは、実は手法だけではなく、考え方だったと私は思います。その考え方に基づき、徹底することで問題点を一つずつ解決することで復活することができたと考えています。
各アメーバには、時間当たり採算の数値を最大化することが求められる。その方法は基本的に「売り上げを増やす」「経費を削減する」「総労働時間を短縮する」の3つだ。
ここでポイントとなるのが、アメーバを構成するメンバーの人数が10人前後の少人数である点だ。どの方法を選んでも、メンバー全員が知恵を絞って方策を考え、実行においても力を合わせなければ、時間当たり採算を大きく改善することはできない。それに人数が少ないから、手を抜いている人がいれば、周囲にすぐ分かる。一部のメンバーの頑張りにほかのメンバーがただ乗りすることを許さない仕組みになっている。
「破綻前のJALは収支に責任をもつ部署が明確でなく、コスト意識が低かった」
図体が大きいと責任の所在が曖昧になり、責任のなすり合いになりがちです。
稲盛イズムが浸透するに連れて、コスト意識が共有され、業績が回復しました。
破綻から2年後、12年3月期の営業利益は2000億円超となった。業績がV字回復した後も、アメーバ経営で財務基盤を強固にしていった。
20年に新型コロナウイルス禍が発生して世界の航空業界が苦境に陥った。経営破綻する事例もあったが、JALは利益重視の経営で自己資本を手厚くしていたため、大幅な減収を乗り越えられた。アフターコロナの航空市場で生き抜くため、部門別採算を軸としたアメーバ経営が一層重要になっている。
🔷 編集後記
名経営者と称賛される稲盛和夫さんは自分に厳しく、他人にも厳しい人だったことがわかります。
世の中には、自分に甘く、他人には厳しい人が少なからずいます。
稲盛さんの3つの考え方を常に念頭に置いて行動すべきだと、つくづく思いました。
「人間として何が正しいか」
「動機善なりや、私心なかりしか」
「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」
今回は、稲盛さんの考え方の重要な点を中心にお伝えしました。
JAL再生を託された時、稲盛さんの周囲の人は皆反対したそうです。
稲盛さんの今までの業績に傷が付き、晩節を汚すことにもなりかねないから引き受けないほうが良いということだったのです。
周囲の反対を押し切って、難しいJALの再生を予想より早く実現しました。
やはり、名経営者あるいは経営の神様と評される稲盛さんは違う!と思いましたね。
⭐ 私の回想録
⭐ 私のマガジン (2022.09.16現在)
いいなと思ったら応援しよう!

