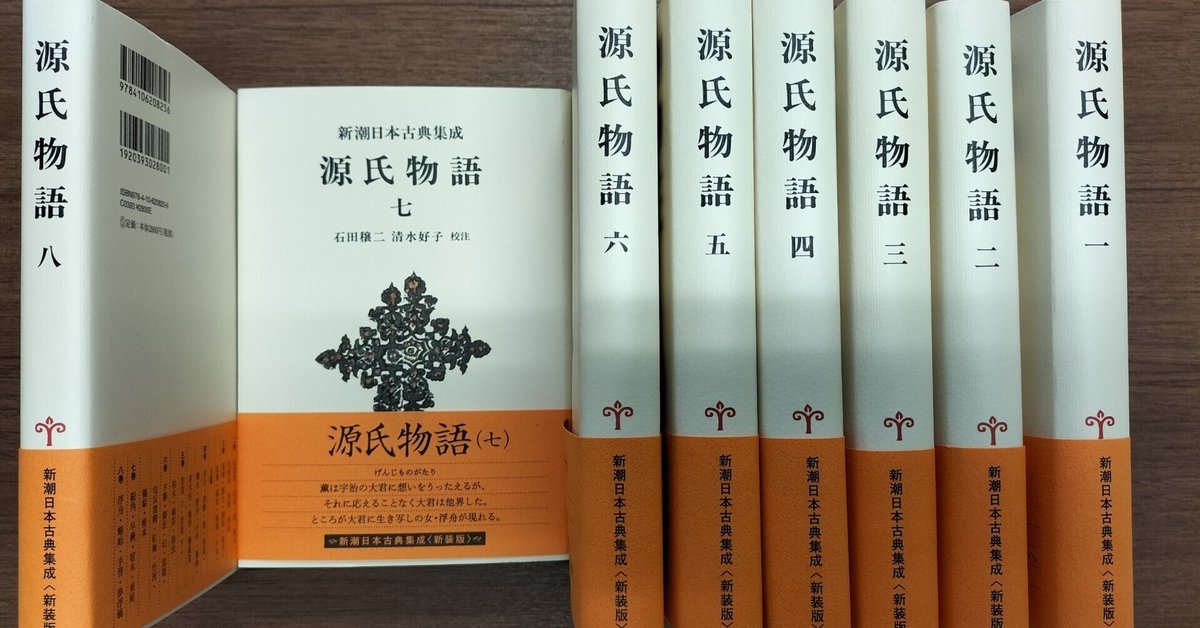
毎週一帖源氏物語 第四十九週 宿木
宇治の実家に泊まりがけで帰っていて、記事をまとめるのがふだんより遅くなった。頼まれた用事を片づけるだけで精一杯で、『源氏物語』に縁のある場所を訪ねる暇はなかった。
宿木巻のあらすじ
藤壺女御は今の帝に最初に入内したが、勢いでは中宮に押されていて、帝とのあいだには女二の宮一人だけがあった。この宮が十四で裳着を済ませる直前、女御は急死する。帝は姫宮の先行きを案じて、源中納言以上に適当な人はいないと思い定める。中納言としては、本意ではない。噂を聞きつけた右大臣は、六の君を中納言に縁づけようと目論んでいたのを諦めて、兵部卿の宮を当てにする。中宮からも説得され、宮は右大臣の後見を受けるのもやむを得ないと承知する。
年が改まり、右大臣は婚儀の仕度を急ぐ。二条の院の対の御方は、やはり自分は軽んじられる身なのだと嘆く。五月頃からは、気分もすぐれず臥しがちになる。八月になり、いよいよ婚儀が間近に迫るが、兵部卿の宮はそのことを対の御方には言い出せず、急な夜離(よが)れで悲しませないように、宮中で宿直を務める日を増やす。中納言は中の君を宮に譲ったことを悔やむ気持ちを抱いたまま、宮の留守中に二条の院に出向く。八月十六夜、兵部卿の宮は六条の院に迎え入れられる。宮は対の御方に変わらぬ心を誓いはするが、六の君の容貌にも惹かれる。
顧みられなくなった対の御方は、中納言に文を送る。翌日、中納言は二条の院に渡り、御簾のうちでの対面となる。思いを抑えきれなくなった中納言は女君の袖をとらえるが、「腰のしるし」(203頁)に気づいて自制する。兵部卿の宮は、移り香によって中納言の来訪に気づく。警戒心を起こした宮が二条の院にいることが多くなったため、しばらくは中納言も文を送ったり衣料を届けたりするにとどめる。
それでも中納言は宮の留守を衝いて二条の院を訪れる。宇治に御堂を建てて亡き人に似た人形(ひとがた)を祀りたいと漏らしたのに誘われて、対の御方は「あやしきまで、昔人(むかしびと)の御けはひにかよひたりし」(222頁)異母妹の存在を明かす。中納言は興味をそそられる。なぜ今まで打ち明けてくれなかったのかと恨めしげだが、対の御方としても、その異母妹は父宮が表に出しておらず、最近まで遠国にいたため、この夏に訪問を受けるまで縁遠かったのである。
九月二十余日、中納言は宇治の宮を訪れ、阿闍梨に寝殿の移築を諮って賛同を得る。弁の尼からは、故宮の忘れ形見の素性を聞く。故北の方の姪に当たる中将の君が産んだ女子(をんなご)で、長く陸奥や常陸にいたのが、この春に上京したらしい。中納言は弁の尼に、何かの折があれば自分の意向を伝えるように頼む。辞去する前に、紅葉した宿木(蔦)に「宿りき(泊まった)」を掛けた歌を詠む。
年が明けて二月、中納言殿は権大納言になり、右大将を兼任する。昇進を祝う宴が開かれ、兵部卿の宮も招かれるが、御方の具合が気になって早々に退出する。その暁、二条の院では御方が男子を産む。方々から祝意が寄せられ、御方の心も晴れる。二月二十日過ぎに女二の宮の裳着が遂行され、その翌日に右大将が婿入りする。四月初め、女二の宮が三条の院に移る前日に、帝が藤壺で藤の花の宴を催す。
四月二十日過ぎ、右大将は宇治に赴く。東男を引き連れた女車が近づいて来るのが目に入る。「常陸の前司(ぜんじ)殿の姫君」(257頁)が初瀬参りの帰途に立ち寄ろうとしているという。右大将は自分の来訪を伏せさせ、一行の様子を覗き見る。姫君の様子は亡き人によく似ていて、ぜひとも近づきたいという思いを強くする。
感謝と困惑~薫に対する中の君の気持ち
匂宮が夕霧右大臣の婿になったことにより、中の君の苦悩は深まる。浮気性な匂宮との対比で、薫の誠実さが引き立つ。中の君からすると、薫は物心両面で支えてくれるありがたい存在である。その感謝は伝えたい。「常に隔て多かるもいとほしく、もの思ひ知らぬさまに思ひたまふらむ、など思ひたまひて」(197頁)とあるように、恩知らずとは思われたくない。この辺りの心理は、死期を悟った大君が「むなしくなりなむのちの思ひ出でにも、心ごはく、思ひ隈(ぐま)なからじとつつみたまひて」(総角、101頁)薫と対面したことと似ている。姉妹そろって、薫への感謝の気持ちは強い。
その一方で、薫から好意を寄せられることに困惑するという点でも、中の君は大君と同じ悩みを抱えている。相手が親切なだけに、邪険な扱いもできかねる。
ひとへに知らぬ人ならば、あなものぐるほしと、はしたなめさし放たむにもやすかるべきを、昔よりさま異なるたのもし人にならひ来て、今さらに仲あしくならむも、なかなか人目あやしかるべし、さすがに、あさはかにもあらぬ御心ばへありさまの、あはれを知らぬにはあらず、さりとて、心かはし顔にあひしらはむもいとつつましく、いかがはすべからむと、よろづに思ひ乱れたまふ。
薫の機嫌を損ねないようにしつつ、無理な要求には応じない。そして匂宮に疑われないようしなければならない。中の君には高度な外交手腕が求められている。
浮舟、登場
この巻より、浮舟が登場する。まだほんの顔見せといったところだが、この後の展開を詳しく知らない私でも馴染みのある名前であり、宇治十帖における最重要人物の一人であろう。しかし、紫式部の構想に最初から入っていたかというと、やや疑問に思われる。
浮舟は八の宮の三女で、大君や中の君とは腹違いである。八の宮は北の方を思う気持ちが強く、北の方が産褥で亡くなった後も、再婚の勧めを断っていた。
故君(こぎみ)の亡せたまひにしこなたは、例の人のさまなる心ばへなど、たはぶれにてもおぼし出でたまはざりけり。
人々はそうした八の宮の謹厳実直ぶりを咎めていたが、「聞こしめし入れざりけり」(同)。女を近づけようとはしなかったのである。
それなのに、誰かに産ませた子があったのか。しかも、年齢設定からすれば、浮舟は中の君より五つか六つ年下なのである。もうそろそろ八の宮の気持ちも落ち着いている頃だろうに。何かと不自然に思われてならない。作者もそこは気にしていたのか、弁の尼の口を通じて浮舟の素性を説明的に語らせている。
故宮の、まだかかる山里住みもしたまはず、故北の方の亡せたまへりけるほど近かりけるころ、中将の君とてさぶらひける上﨟(じやうらふ)の、心ばせなどもけしうはあらざりけるを、いと忍びて、はかなきほどにもののたまはせけるを、知る人もはべらざりけるに、女子(をんなご)をなむ産みてはべりけるを、さもやあらむ、とおぼすことのありけるからに、あいなくわづらわしくものしきやうにおぼしなりて、またとも御覧じ入るることもなかりけり。〔……〕かの君は、二十(はたち)ばかりにはなりたまひぬらむかし。
八の宮が認知していなかったために浮舟の存在がこれまで知られていなかったという説明にはなっているが、八の宮が中将の君に目をかけるに至った内心の動きの描写としては物足りない。「はかなきほどに」と言うからには、本気ではなくちょっかいを出したら子ができてしまった、ということなのだろう。当時はとくに珍しくもなかったのかもしれない。
それにしても、やや苦しい書きぶりだという印象を私は抱いた。薫が中の君に「などか今まで、かくもかすめさせたまはざらむ」(222頁)とこぼす場面があるが、読者から作者にそう言いたい気分である。橋姫巻を書き始めた段階では、紫式部の頭のなかには浮舟はまだ存在していなかったのではないか。そんな想像をめぐらせてみたくなる。
玉鬘か浮舟か
浮舟のイメージが玉鬘に重なる。父方の血筋は確かながら、訳あって父のもとでは養育されず、地方暮らしを余儀なくされた。長じて都に上り、貴人の目に留まる。初瀬詣でをするところも同じである。浮舟は初瀬で何を願ったのだろうか。
生き写し
薫が浮舟に惹かれるのは、大君によく似ているからである。大君の面影を宿した人であれば、身分が低くても構わない――そんな願望が繰り返し表明される。
くちをしき品(しな)なりとも、かの御ありさまにすこしもおぼえたらむ人は、心もとまりなむかし
故君(こぎみ)にいとよく似たまへらむ時にうれしからむかし
いずれの文も推量の助動詞「む」に終助詞「かし」が添えられた形になっていて、実際にはそんな人はいないだろうけれど、いたらいいのになあ、という薫の願いが滲み出ているようだ。
だからこそ、中の君から浮舟の存在を知らされたときは、夢を見るような心地がしたことだろう。「あやしきまで、昔人の御けはひにかよひたりしかば、あはれにおぼえなりにしか」(222頁)と伝えられていた姿を、薫は垣間見る機会を得る。
まことにいとよしあるまみのほど、髪(かむ)ざしのわたり、かれをも、くはしくつくづくとしも見たまはざりし御顔なれど、これを見るにつけて、ただそれと思ひ出でらるるに、例の、涙おちぬ。
ただでさえ垣間見は次の段階に進むきっかけになりやすいのに、まして相手が大君と瓜二つとなれば、薫は万難を排して浮舟を手に入れようとするだろう。それで浮舟が幸せになれるかどうかは別の話であるが。
横笛
藤壺で藤の花の宴が開かれた折に、薫は横笛を演奏する。「笛は、かの夢に伝へしいにしへの形見」(251-252頁)である。実父柏木の遺品で、落葉の宮の母御息所から夕霧に贈られたところ、柏木が夕霧の夢枕に現れて「思ふかた異(こと)にはべりき」(横笛、第五分冊、333頁)と恨んだ例の笛である。夕霧の話を聞いた源氏が「その笛は、ここに見るべきゆゑあるものなり」(同、340頁)と言って引き取っていたが、薫が当たり前のように吹いていることからすると、薫の手に渡るように源氏が生前に道筋をつけておいたのだろう。
按察使の大納言の鬱屈
紅梅大納言は公私ともに不満を抱えている。かつては麗景殿女御に懸想していて、その後は娘である女二の宮をいただきたいと願っていたのに、薫に降嫁された。公的な地位は按察使の大納言のままである。薫は権大納言に昇進したので、その差はほとんどない。竹河巻では「藤大納言、右大将かけたまへる右大臣になりたまふ」(竹河、第六分冊、245頁)とあるが、後続の巻では大納言という設定が変わっていない(同様のことは夕霧にも言える)。薫は同じタイミングで宰相の中将から中納言に昇進していたので、紅梅大納言と地位の差が大きいのが本来の姿であろう。
宇治十帖の碑、訪ね歩き(五)宿木
宿木の碑は、宇治川の左岸にある。早蕨の碑からは、宇治神社の境内を通って朝霧橋を渡り、中州の橘島と塔の島を通って、喜撰橋を渡って上流に向かうと、ほどなくして見えてくる。今では安全に歩いて行けるが、以前は車に注意が必要だった。宇治から大津へ抜ける道が喜撰橋のたもとを通っていて、しかも歩行者用には路側帯しかなかった。天ヶ瀬ダムまでは行かないにしても、大型車が行き交う道をそれなりに長い時間をかけてやっと辿り着ける「行きづらい場所」という記憶が残っている。大人になって歩いてみると、塔の島からこんなに近かったのかと驚くほどだ。

場所の選定理由は、宿木巻を読んだ後でもよく分からなかった。この巻は宇治を舞台にする場面が少なく、ゆかりの地と言えそうなところがない。碑の近くでヤドリギが多く自生しているのだろうか。
