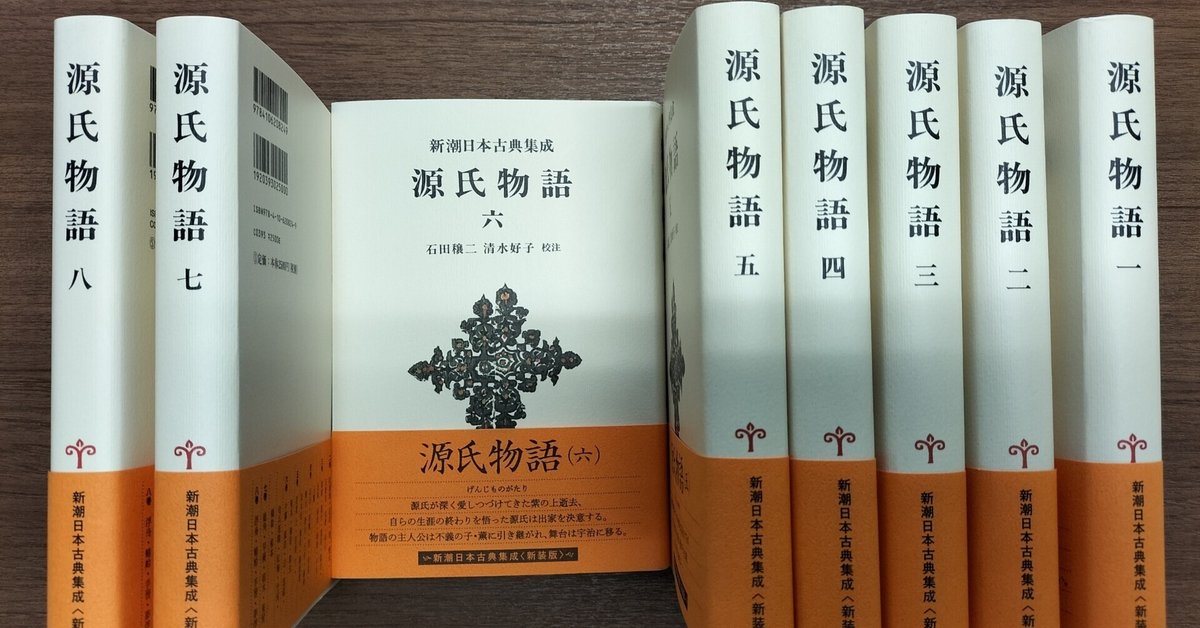
毎週一帖源氏物語 第四十五週 橋姫
宇治十帖の始まりにあたって
これより宇治十帖が始まる。前口上で記した通り、私は宇治で生まれ育ったので、『源氏物語』の気配を何となく感じていた。
私の実家は、宇治川の東(右岸)、源氏物語ミュージアムの近くにあった(厳密に言えば、私の実家の近くに源氏物語ミュージアムができた)。「あった」と過去形にしたのは、今はもう私の実家だった建物は跡形もなく、そこは京都翔英高校の施設になっている。
子供の頃の私は、『源氏物語』を空間的にとらえていた。家の近所に『源氏物語』にちなむ石碑が点在していたからである。たとえば、実家から北に歩いて五分くらいの場所に蜻蛉石が立っている。そこから先にどんどん進むと三室戸寺があり、その境内に浮舟の碑がある。反対に実家から南に向かうと、大吉山に登る道の起点に総角の碑が見える。さらに進んで、宇治上(うじがみ)神社と宇治神社のあいだに早蕨の碑がある。『失われた時を求めて』になぞらえて言うと「蜻蛉のほう」と「総角のほう」があって、私の空間認識と結びついた『源氏物語』の世界では、浮舟は蜻蛉のほう、早蕨は総角のほうに位置づけられていたのである。
そうしたとらえ方は私の実家がそこにあったという偶然の産物にすぎず、『源氏物語』に内在する秩序とは無関係である。私は宇治十帖が橋姫巻より始まるということすら知らずにいたが、これから原文に分け入ることで、私の身体感覚と結びついた宇治十帖の地図がどのように更新されてゆくかを楽しみにしている。
橋姫巻のあらすじ
世間から忘れられた宮がいた。北の方とは仲睦まじく、姫君が二人相次いで生まれたが、北の方は産褥で亡くなった。宮は出家を願いつつも、姫君の行く末が気にかかってそれも叶わない。この宮は「源氏の大殿(おとど)の御弟」(262頁)で、大后が冷泉院の代わりに春宮に立てようと画策したことがあり、情勢が変わってからは不遇をかこっているのである。邸は荒廃し、ついに焼失する。「宇治(うぢ)といふ所に、よしある山里持(も)たまへりけるにわたりたまふ」(263頁)。宇治山には阿闍梨(あざり)がいて、宮はその指導を受けて俗体のまま仏道専心の日々を送り、俗聖(ぞくひじり)と呼ばれている。
この阿闍梨は冷泉院とも親しく、京に出向いた折には八の宮の様子を伝えている。院がその姫君に関心を示す一方、中将は宮に惹かれる。宮もまた、順境にある若者が道心を起こしていることに感心する。
宮と親交を結ぶようになって三年目の晩秋、中将は夜のうちに京を出て宇治に向かうが、宮は山籠もりをしていて不在である。姫君たちが琵琶と箏を掻き鳴らしているのが聞こえたので、中将は宿直人(とのゐびと)に手引きさせて、その様子を垣間見る。しかし、来客に気づいた姫君たちは簾を下ろして室内に入る。中将は案内されるが、応対する大君は言葉少なである。代わりに出て来た老女は、自らを弁と名乗り、藤大納言の兄で右衛門督だった方の乳母子であるという。中将にぜひ聞かせたい昔話があるとかで、中将も興味をそそられる。
夜が明けそうになり、中将は心を残しながら京に帰るが、その前に橋姫に事寄せた歌を詠みかけ、取り次ぎの宿直人には御衣を賜る。翌日、姫君には文を、宮のいる寺には布施を贈る。
中将は三の宮に、宇治の様子を語る。「山里めいたる隈(くま)」(289頁)に好ましい女がいると焚きつけたかと思えば、そんなことに心を留めてはならないと水を差す。
十月、中将は宇治を訪れ、久しぶりに宮と語らう。宮は自分の死後の姫君二人の身を案じ、中将に後事を託す。宮が暁の勤行に出た機会をとらえて、中将は弁の君を呼び出し、「故大納言の君の、世とともにものを思ひつつ、病(やまひ)づき、はかなくなりたまひにしありさま」(294頁)を聞く。ずっと気がかりだったことで、涙をとどめられない。弁は反故(ほぐ)を渡す。大納言が死ぬ前に弁に託した文を手許に残しておいたものである。京に戻って中を確かめると、故大納言と女三の宮のあいだで交わされた文が何通かある。紙は黴くさく、男の筆跡は鳥の跡のように乱れているが、墨の色は鮮やかである。中将は、何もかも自分の心一つに籠めておこうと決意する。
八の宮と姫君たち
橋姫巻は「そのころ、世にかずまへられたまはぬ古宮おはしけり」(255頁)という一文で始まる。ぼんやりした書き方であり、その宮の血筋などは、すぐには明かされない。しばらく経ってから、「源氏の大殿の御弟」(262頁)と書かれ、その少し前に言及された「父帝(ちちみかど)」(同)が桐壺帝であることが分かる。そして阿闍梨が「八の宮」(265頁)と名指すに及んで、紅梅巻で匂宮が通う「八の宮の姫君」(紅梅、196頁)と接続する。冷泉院が「十の御子(みこ)」(266頁)であることも合わせると、系図が明瞭になる。
八の宮には娘が二人いる。大君と中の君である。歳の近いこの二人については、作者は性格や容姿を描き分けようとしているようだ。
姫君は、らうらうじく、深く重りかに見えたまふ。若君は、おほどかにらうたげなるさまして、ものづつみしたるけはひに、いとうつくしう、さまざまにおはす。
姉は思慮深く、妹はおっとりとしていてかわいらしい。薫が惹かれるのは大君のほうである。世をはかなきものと思い定めている憂鬱質の若者の相手としては、そちらでなければならないだろう。匂宮が言い寄るのは妹のほうらしく、それはそれで色好みの宮様らしい。
八の宮の山荘と宇治山
八の宮の山荘は、どの辺りにあるのだろうか。「網代(あじろ)のけはひ近く、耳かしかましき川のわたり」(263頁)ということは、宇治川からそれほど離れてはいないようだ。薫が京からやって来たときに「川のこなた」(272頁)に山荘があるという設定なので、右岸である(地元では「川東(かわひがし)」という言い方をする)。私の実家からも、それほど離れてはいないような気がする。そうであってほしいという願望でしかないけれど。
一方、阿闍梨が住んでいるのは「宇治山」(264頁)である。頭注では「喜撰法師を連想させる書き方」と述べ、宇治山を喜撰山に同定している。その通りであればかなり奥まっていて、八の宮の山荘からの往来は容易ではない。少なくとも、姫君たちには無理だろう。
一方、文化庁が史跡名勝天然記念物に指定したときの定義では、「宇治山は,その谷口を巡って峰を連ねる仏(ぶっ)徳(とく)山(さん),朝日山(あさひやま)などを含む丘陵地の総称である。」仏徳山というのは、私が上に記した大吉山の正式名称であり、八の宮の山荘のすぐ裏手くらいに当たる。それではさすがに近すぎるので、阿闍梨がいるのは喜撰山と見なすのがよいだろう。
動かぬ証拠
薫は自分の出生の秘密に悩んでいる。そのことは匂兵部卿巻ですでに語られていたが、薫の思い過ごしでなかったことが橋姫巻で判然とする。生き証人が現れたのだ。八の宮に仕える弁の君は柏木の乳母子で、女三の宮とのあいだに何があったかを間近で見聞きしていた。薫が宇治に通うようになって三年目の秋、弁の君はようやく薫と言葉を交わす機会を得る。そのために生きながらえてきたような人である。
老人の昔語りを素直に受け止める薫の心理状態も不思議だが、本人が思い描いていたことと合致していたからこそ、何の反発も生じなかったのだろう。実際、弁の話には矛盾はない。そして、柏木と女三の宮のあいだで交わされた文が動かぬ証拠として薫の手に渡る。そのやり取りを読み、薫の内心に兆していた疑念が確信に変わる様子は、私自身が身震いするほどだった。極めつけは、生まれたばかりの薫を思って柏木が詠んだ歌である。
命あらばそれとも見まし人知れず
岩根(いはね)にとめし松の生(お)い末(すゑ)
二十余年の歳月を経てこの歌に接した薫を、心の奥底から揺さぶったにちがいない。
宇治十帖の碑、訪ね歩き(一)橋姫
この記事の最初に記したように、私の実家の近くには宇治十帖の碑が点在していた。子供にとっては、物語の筋とは何の関係もなく、スタンプラリーのように制覇するのが楽しみだった。『源氏物語』宇治十帖を読みながら、改めてその跡を訪ねてみよう。今年四月末に用事で宇治に帰省したのだが、そのときに撮ってきた写真を紹介したい。
宇治十帖の古跡をまとめたサイトは、インターネット上にいくつか存在する。京都観光チャンネルのサイトはコンパクトにまとまっていて見やすいが、場所が示されていない。宇治市のサイトはやや見づらいが、地図があるので便利である。
まずは橋姫の碑である。宇治川左岸、県(あがた)通りに面して橋姫神社がある。県通りは小学校の通学路から外れていたこともあって、私にとってはやや馴染みがうすい。

神社といっても驚くほど狭く、説明板がなければ間違えて入ったのではないかと思うほどだ。小さな祠が二つ並んでいるにすぎない。

私が訪れたとき、境内に人の気配はなかった。観光客がいなかったというだけでなく、神社を管理している人も見当たらなかった。ほとんど廃屋である。

意外なものもある。「平成十八年十月」という日付を持つ説明板の白さとは対照的に、高浜、大飯、美浜、敦賀の原発からの距離を記した看板はくすんでいる。『源氏物語』との取り合わせが異様だが、二十一世紀の現実を伝えているとも言える。説明板にある「平成十八年」は西暦2006年であり、東日本大震災よりも古い。この看板が震災前から据えられていたのか、説明板が材質的に黒ずまないのか、内容はそのままに立てかえられたのか、どうもよく分からない。
それはともかく、橋姫は宇治橋の守護神と言い伝えられているが、似たような由来を持つ寺院もある。橋寺(はしでら)である。放生院(ほうじょういん)とも言うが、橋寺のほうが通りはよい。京阪宇治駅のすぐ近くで、川の東側にある。つまり、八の宮の山荘からも近いはずで、ここに碑があってもおかしくはない。橋姫神社はなぜ今の場所に建っているのだろうか。
