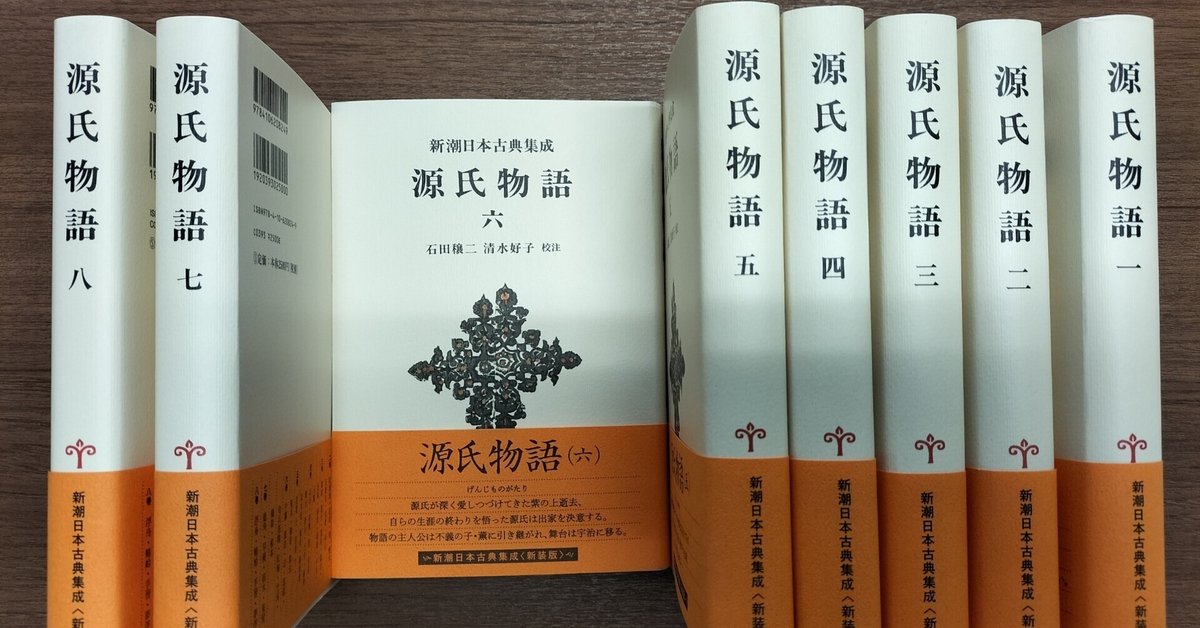
毎週一帖源氏物語 第四十六週 椎本
宇治十帖は長い。巻数では『源氏物語』の二割に届かないが、頁数では三割近くを占める。一巻あたりの分量が多いということだ。紫式部が興に乗って筆が進んだのかどうかは知らないが、最初の二巻を読んだだけでも、宇治十帖では作中人物たちの心理や行動が複雑さを増しているように思う。
椎本巻のあらすじ
如月二十日のほど、兵部卿の宮は初瀬に詣でて、その帰途、宇治に中宿りをする。迎えに来た宰相の中将などとともに、宮は川向こうにある右大臣の別邸で管弦の遊びをする。その音は対岸の聖の宮のもとにも聞こえ、「致仕の大臣の御族(ぞう)の笛の音にこそ似たなれ」(307頁)と思わせる。八の宮は歌を贈り、それに応えて中将は出向く。気軽に川を渡ることもできない兵部卿の宮は、せめてもの思いを歌に込める。その返りは、中の君が書く。これを機に、宮はたびたび文を遣わし、中の君が色めかぬように注意しながら返事をしたためるようになる。
宰相の中将は中納言に昇進し、七月には久しぶりに宇治を訪れる。八の宮は姫君たちの後見を頼み、中納言も「変らぬ心ざし」(314頁)を誓う。宮はこうした対面もこれが最後ではないかと感じ取っている。秋深く、宮は姫君たちに甘言に惑わされてはならないと言い残して、山に籠もる。
八の宮は山で病に伏せ、八月二十日、帰らぬ人となる。姫君たちは死に目にも遭えず、悲嘆に暮れる。法要などは、中納言が滞りなく手配する。兵部卿の宮もたびたび弔問の文を送るが、返事はない。ひと月の忌が明けた頃に長文の手紙があり、さすがにこれ以上放っておくのは失礼だと思って、大君は中の宮に返事を促す。しかし、中の君はどうしてもその気になれず、大君が代筆する。兵部卿の宮はこれまでと筆跡が違うので、どちらがどちらなのだろうと考え込む。
姫君たちはわびしさを抱えたまま、年の瀬を迎える。中納言が宇治を訪れ、兵部卿の宮は噂ほど軽々しい人ではないと請け合い、意中の人は中の君であると告げる。さらに重ねて、大君に寄せる自分の思いも訴えるが、大君は取り合わない。塵の積もった仏間を眺めるにつけ、我が師と頼りにしていた八の宮が偲ばれ、中納言は「立ち寄らむ蔭(かげ)とたのみし椎(しひ)が本(もと)」(345頁)と詠む。
年が改まり、兵部卿の宮はは前年の宇治の桜を思い出して歌を贈るが、中の君からはうわべを取り繕った返事しか届かない。宮は中納言を責めるが、かえって浮気性を咎められる。
三条の宮が焼けて、入道の宮は六条の院に移る。中納言は忙しさに紛れていたが、夏になって宇治を訪れる。簾が風に吹き上げられた折に、中納言は姫君たちを垣間見る。
八の宮は姫君たちの将来をどうしたいのか
後ろ盾のない宮家は、時とともに落ちぶれる。八の宮も、自分の死後については悲観的にならざるを得ない。姫君たちはどうなってしまうのか。
期待を寄せる相手は、何といっても薫である。人物は立派である。いや、立派すぎる。色めかしいところがなく、結婚など眼中にないのではないか。「宰相の君の、同じうは近きゆかりにて見まほしげなるを、さしも思ひ寄るまじかめり」(307頁)と思われる。
条件を少し下げても、うまく行きそうな気がしない。「なのめに、さても人聞きくちをしかるまじう、見ゆるされぬべき際(きは)の人の、真心(まごころ)に後見(うしろみ)きこえむ、など、思ひ寄りきこゆるあらば、知らず顔にてゆるしてむ」(312-313頁)とさえ思うが、真剣な相手は見つからない。
まして、匂宮のような高貴な方が本気だとは思えない。「いと好きたまへる親王(みこ)なれば、かかる人なむ、と聞きたまふが、なほもあらぬすさびなめり」(311頁)という具合に、ほんのお遊びだと決めてかかっている。
結局、八の宮は薫を頼る。「亡(な)からむのち、この君たちを、さるべきもののたよりにもとぶらひ、思ひ捨てぬものに数まへたまへ」(314頁)というのは、事実上、結婚の許し(お願い)である。
ところが、八の宮は姫君たちに独身のまま山里で生涯を送れと諭すのだ。
軽々(かるがる)しき心どもつかひたまふな。おぼろけのよすがならで、人の言(こと)にうちなびき、この山里をあくがれたまふな。ただかう人に違(たが)ひたる契り異なる身とおぼしなして、ここに世を尽くしてむと思ひとりたまへ。
甘い誘いに乗ってはならない。皇族の姫は結婚などしないものだという「常識」は、落葉の宮の母御息所も繰り返し述べていた。
一体、八の宮はどうしたいのか。どうなればよいと願っているのか。上に引いた戒めの言葉には、「おぼろけのよすがならで」という留保がつけられていた。「よくよく頼りになる人でなければ」ということは、「薫のようなしっかりした人であれば結婚してよい」という含意であろう。ただ、八の宮は薫にその気がないと思っているので、姫君たちには「独身を守れ」という言い方になるのだ。八の宮の内心では筋道が通っているが、姫君たちには結論しか与えられない。父宮の遺言に違わぬようにと思えば、大君は薫の求愛を斥けるしかない。
宮様の不自由
匂兵部卿は帝の三の宮だが、将来的な立太子も視野に入っている。薫ほど気軽に行動できない。だから初瀬参りの帰りに宇治に中宿りをしたときも、八の宮からの誘いに応じて対岸に渡ったのは薫たちだけであり、匂宮は夕霧が保有する別邸に留まっていなければならなかった。薫は八の宮の弔問を口実に宇治に足を運べるが、匂宮にはそれも許されない。
匂宮と宇治の姫君たちとの接点は手紙に限られていて、その文面や墨つきで人となりを判断するしかない。八の宮の忌明けに届いた文の筆跡がそれまでと違っているのを見て、匂宮は自分が誰に惹かれているのか(惹かれるべきなのか)分からなくなってしまう。何か間違いが起こるのではないかと心配になる。
夕霧は気の張る相手
匂宮にとって、夕霧は気の張る相手である。「大臣(おとど)をば、うちとけて見えにくく、ことことしきものに思ひきこえたまえり」(306頁)とある通りだ。系図を確認しておくと、匂宮の母は明石中宮、祖父は源氏である。夕霧は源氏の嫡男で、明石中宮の兄だから、匂宮からすれば伯父に当たる。外戚の統領で、右大臣という権勢を誇る人だから落ち着かないというだけでなく、「まめ人」という実直な性格も煙たく感じられるのだろう。
そういうわけで、匂宮は夕霧の婿にはなりたくないと思っている。それが夕霧には不満である。「大殿(おほいとの)の六の君をおぼし入れぬこと、なまうらめしげに、大臣(おとど)もおぼしたりけり」(348頁)。これまでの『源氏物語』の常道からすれば、権勢家の婿になったうえで恋する相手のもとにも通うという道しか、匂宮には残されていないように思われる。匂宮はこの慣習に逆らうことができるのか。
宇治十帖の碑、訪ね歩き(二)椎本
椎本の碑は、彼方神社にある。いや、これといった碑はないと言うべきかもしれない。「椎本之古墳」という石柱も説明板も、鳥居の手前に立っている。

式内彼方神社。この神社の名前は、知らなければ読めない。昔の私もそうだった。「しきうちかなたじんじゃ」? 何それ、という感じだ。中学か高校くらいのときに、延喜式に記載されている神社のことを「式内社(しきないしゃ)」と呼ぶことを知った。それだけ古い格式を誇り、朝廷から認められていたという証である。今の規模からは想像しにくいが、彼方神社はその一つだったのだ。
そして「彼方」だが、こちらは「かなた」ではなく「おちかた」と読む。つまり、「しきない おちかたじんじゃ」が正しい読み方である。
八の宮が対岸の人々に詠みかけた歌、
山風に霞(かすみ)吹きとく声はあれど
へだてて見ゆるをちの白波
に見える地名「をち」がこの神社の名前につながっている。現在、この辺りは「乙方(おつかた)」と呼ばれていて、地元民にとってはその音の響きに馴染みがある。
不思議なのは、川東(右岸)にこの地名が伝わっていることだ。夕霧の別邸は平等院がモデルらしいが、それは宇治川の左岸にあり、京から来ると「川の向こう」である。だから、「川より遠(をち)に」(305頁)と説明されているのだ。ならば、「をちかた(遠方、彼方)」は平等院側の左岸にこそふさわしい。もしかすると、視点は大和に置かれていて、「宇治川の向こう」だったのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
