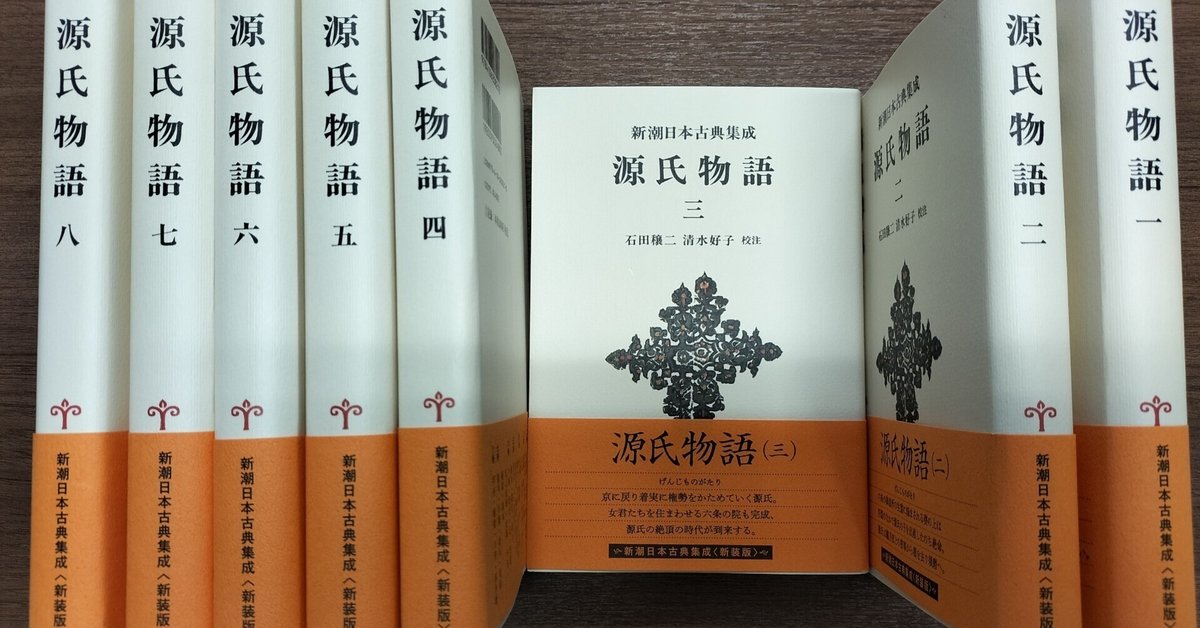
毎週一帖源氏物語 第二十一週 少女
この巻で六条の院が落成するが、その模型が宇治市源氏物語ミュージアムにあるらしい。見たことがあるはずだが、記憶にない。私のもとの実家から歩いて五分とかからない場所にできたこの施設は、私がフランスに留学しているあいだにオープンした。帰国後に見に行ったものの、印象に残っていないのだ。知識がないと、同じものを見ても感じるところが少ないのだろう。『源氏物語』を通読したあとで見学すれば、きっといろいろな発見があると期待している。
少女巻のあらすじ
故宮の一周忌が過ぎた衣更えの頃、源氏は前斎院に文や品を贈るが、前斎院の気持ちは変わらないままである。
大殿腹の若君が元服したが、源氏はわが子を四位にするのを思い止まり、大学に入れることにする。養育に当たる大宮は不満を述べるが、源氏は自分の考えを伝える。当の「冠者(くわざ)の君」(229頁)は祖母の大宮のもとを離れて学問に励む。
その頃、弘徽殿女御を差し置いて、源氏の養女となっている斎宮女御が中宮に立てられた。源氏は太政大臣に、右大将は内大臣に昇進する。
冠者の君は、同じ邸で育った姫君と深い仲になっていた。このことが内大臣の耳に届き、その不興を買う。娘を春宮の后にしたいという思惑もあり、内大臣は姫を自邸に引き取ることにする。大宮は冠者の君に肩入れしており、内大臣の措置をうらめしく思う。若い二人は、事の成り行きに戸惑うばかりだ。姫は「雲居の雁もわがことや」(246頁)とひとりごつ。いよいよ住まいを移すというその日、大宮のはからいにより、二人は対面する。
前年は見送られた五節の舞が、この年は奉納される。源氏は惟光の娘を舞姫として差し出す。その姿を見た大学の君は、「心移るとはなけれど、ただにもあらで」(258頁)気を引こうとする。君は文をしたため、舞姫の男兄弟に届けさせる。惟光は自分の娘が源氏の息子の心に留まったことを喜ぶ。
源氏は、息子の後見を二条の東の院の西の対に委ねる。冠者の君は、対の御方の容貌がすぐれていないにもかかわらず、こうして大事にされていることを間近に見て、思うところがある。大宮からは睦月の装束が届けられるが、六位のものなので気が晴れない。源氏が自分をあまり近づけないことも、辛く思われる。
「きさらぎの二十日(はつか)あまり、朱雀院(すざくゐん)に行幸(ぎやうがう)あり」(266頁)。大学の君はこの日進士に及第し、秋の司召では侍従に任じられる。
源氏は広々とした邸宅をしつらえようと思い立ち、「中宮の御古き宮のほとりを、四町(よまち)を占めて造らせたまふ」(272頁)。一年ほどかけて、八月に六条の院が完成する。未申(西南)の町は中宮の住まいだったところで、秋の趣に仕立てられる。辰巳(東南)の町には殿が上とともに住まい、春の花が多く植えられる。丑寅(東北)の町には花散里が侍従とともに移り、夏を旨とする。戌亥(西北)の町は明石の御方のために取り置かれ、冬の風情である。春と秋の優劣をめぐって趣向を凝らした歌が交わされるなど、思い描いた通りの風雅な暮らしぶりである。
少女と書いて「をとめ」と読む
五節(ごせち)とは、十一月の中の丑の日から辰の日までの四日間、舞姫が舞を奉ずる儀式である。その舞姫のことを、歌語で「少女(をとめ)」と言う。頭注にも引かれていたが、百人一首にも採られている「天つ風雲の通ひ路吹き閉ぢよ少女の姿しばしとどめむ」は舞姫を詠んだものだ。
この舞姫には割り当てがあって、位の高いほうから順に、公卿、殿上人、受領から出すべき人数が決まっている。源氏はもちろん公卿の枠だが、自分の娘ではなく、家司の惟光に娘を出させる(「殿の舞姫(まひびめ)は、惟光の朝臣(あそむ)の、摂津(つ)の守(かみ)にて左京の太夫(たいふ)かけたる女(むすめ)」(256頁))。その一方で、惟光と同じく源氏に仕える良清が殿上人の立場で娘を差し出している(良清、今は近江(あふみ)の守(かみ)にて左中弁(さちゆうべん)なるなむ、たてまつりける(同))。源氏に尽くす立場としては、惟光と良清はほぼ同格と私は思っていただけに、この扱いの違いはやや意外だった。乳母子の惟光は、源氏にとって身内のようなものなのだろうか。
夕霧、登場
表向きは源氏にとって唯一の男子である夕霧が、この巻で本格的に物語の世界に姿を現す。源氏が先々のことを見すえて、あえて六位という低い位にとどめて大学に入れたため、夕霧はつらい思いをする。しばらくは夕霧に焦点を当てた叙述が繰り広げられ、その間は源氏が後景に退く。源氏についての言及が長く途絶えることは、これまでなかったのではないか。紫式部が「源氏以後の物語」を見通しているようだ。
それにしても、夕霧とは不思議な名前である。男は官職で呼ばれるのが普通なので、女の名前としても通用しそうな呼び方は異彩を放っている(ように私には見える)。少女巻を読む前の私が「源氏の息子の名前は何でしょう?」というクイズを出題されたなら、選択肢の中に「夕霧」が入っていても正しく選べなかっただろう。かなり先のほうに「夕霧」の名を冠した巻があり、そこまで読めば名前の由来は明かされるのだろうが、現時点では「冠者の君」や「大学の君」さらには「侍従」と呼ばれるばかりである。雲居の雁の由来が早々に明らかになるのとは対照的だ。
血は争えないのか?
雲居の雁との仲を切り裂かれた夕霧は、惟光の娘を見初める。雲居の雁を忘れたわけではないにしても、切り替えが早すぎるように感じられる。さすが源氏の息子である。旺盛であることは、公卿にとって重要な資質なのだろう。
親も息子を警戒しているのか、源氏は夕霧を紫の上には近づけない(「上の御方には、御簾の前にだに、もの近うもてなしたまはず」(257頁))。その点、花散里なら安心と思っているようだ。
皇后は藤原氏から
聖武天皇の時代より、皇后は藤原氏から立てるしきたりであるらしい。例外はあっても、それが続くのはよくないという認識がある。藤壺中宮も斎宮女御も皇族なので、「源氏のうちしきり后(きさき)にゐたまはむこと、世の人ゆるしきこえず」(230頁)という次第になる。藤壺(桐壺帝の后)と斎宮(冷泉帝の后)で二代続けてということは、間の朱雀帝の時代には立后がなかったことになる。在位が短いと、そういうところにも影響が出るようだ。
内大臣(もとの頭中将)が、娘である弘徽殿女御が立后争いに敗れたことで悔しがるのはよく分かる。不思議なのは、内大臣の母である大宮の心情だ。藤原氏から皇后が出ないはずはない(「この家にさる筋の人出でものしたまはで止(や)むやうあらじ」(234頁))と、亡き夫の言葉を引いている。しかし、大宮は皇族出身(桐壺院の妹)なのだ。自分の出自よりも、嫁ぎ先に同化している。葵の上の気位の高さは母が皇族だったことによって説明されていただけに、大宮が藤原氏の価値観を内面化していることが不思議に思われた。
六条の院と河原の院
源氏が数寄を凝らして造営した六条の院は、四町の広さを誇る。田の字の形を思い浮かべればよいだろう。その西南が斎宮女御の旧居、すなわち六条御息所の邸宅があった場所である。どういう方法を用いたかは不明だが、源氏はその近辺の区画を手に入れたようだ。
歴史的事実との関連で言うと、「源融(とおる)の造営した河原の院に模したものか」と頭注は『河海抄』を引きながら指摘する。その通りなのだろうが、『源氏物語』の内部で辻褄が合っていないように思えてならない。
ここで夕顔巻を思い起こしてみよう。冒頭は「六条わたりの御忍びありきのころ」(夕顔、第一分冊、121頁)であった。六条御息所の邸宅のことだ。その手前の「五条なる家」(同)に惟光の母が住んでおり、その隣家に夕顔がいた。源氏は夕顔を「そのわたり近きなにがしの院」(同、144頁)に連れ出す。新潮日本古典集成の頭注は、この「なにがしの院」についてこう記す。「ここは、五条に近い所から、「河原の院」をさすのであろう。六条坊門南、万里小路(までのこうじ)の東にあり、左大臣源融の邸として有名であった」(同)。夕顔巻の叙述においては、「六条わたり」と「なにがしの院」は別物である。六条御息所の邸を拡張して造営された「六条の院」が歴史上の「河原の院」に対応したのでは、夕顔巻の「なにがしの院」が宙に浮いてしまわないか。あら探しをしたいわけではないのだが、当時の読者は気にならなかったのだろうか。
六条の院の春夏秋冬
六条の院に関しては、もう一つ考えておきたいことがある。春夏秋冬の配置である。源氏と紫の上が住む春の町が辰巳(東南)にあることが、直感的には受け入れにくいのだ。
四季を方角に当てはめれば、春は東、夏は南、秋は西、冬は北、となる。四町に分割するとき、まさか対角線を斜めに引いて直角二等辺三角形を四つ作ることはしないだろうから、田の字に割って正方形を四つ出現させることになる。すると、四季を東西南北にぴったり合わせることはできない。四十五度ずれるのは仕方がない。
参考になるのは、大相撲の土俵の吊り屋根からぶら下がっている四つの房である。青房、赤房、白房、黒房は、それぞれ春夏秋冬を表している。屋根の四隅に配置するので、やはり四十五度ずれている。テレビ中継で確認できることだが、春の青房は東北(テレビ画面なら左手前)、夏の赤房は東南、秋の白房は西南、冬の黒房は西北にある。この配置と六条の院の四町を比べてみると、春(源氏と紫の上)と夏(花散里)が入れ替わっていることが分かる。これが、私にとっては謎なのだ。どうして、源氏が住む春の町は東北ではなく東南なのだろうか。
明確な答えは出せないが、大相撲を引き合いに出したことで、書きながら思い浮かんだ仮説がある。大相撲の正面は北であり、テレビ画面は北から南を眺めた状態を映している。天子南面を取り込んだ視線の向きだ。現在の私たちは北を上にした地図を見慣れているが、平安時代の方向感覚はその逆だ。南が上で、北が下だろう。いや、俯瞰的に捉えているとは言い切れないので、南が奥で北が手前と言うべきかもしれない。そのように方向を把握すると、六条の院は内裏から見て左奥に位置する。四町のうち、最初に辿り着くのは西北の冬の町で、東南の春の町はいちばん奥まっている。この遠さが大事なのではないだろうか。これまでの源氏の邸である二条の院は、内裏からは目と鼻の先である。政権の中枢を担う立場としては、内裏の近くに邸宅を構えているほうがよい。しかし、隠遁して風雅の道に遊ぶなら、離れているほうが好ましい。だから、源氏が住むのは内裏から最も遠い東南なのではないだろうか。
