
大げさにいえば戦後住宅のふる里|「滋賀の家展」を読む
滋賀県立美術館の開館40周年記念企画展「滋賀の家展」がスタートしました。会期は2024年7月13日から9月23日まで)。
「滋賀の家」といったとき、たぶん想像するのは、湖国の歴史と気候風土につちかわれた古民家、あるいはそうした文化や技術を継承した現在の家づくりではないでしょうか。海外の住様式をいちはやく普及したヴォーリズの業績などを連想される方もいらっしゃるかと。
でも、今回の「滋賀の家展」では、時間軸は戦後に限定されていて、しかも1960年代以降にプレハブ住宅の生産工場が立地しはじめた状況をとりあつかっています。

(大阪府住宅協会『千里丘陵プレハブ住宅』)
そうした設定のなかで言う「滋賀の家」とはなんなのでしょうか。
本展は、1960年代の日本の住宅産業と滋賀県の強いつながりを示す事例から、現代建築家による最近のプロジェクトまでを、幅広く紹介する展覧会です。(中略)建築に専門的な関心を持つ人だけでなく、滋賀での暮らしについて関心を持つ人にとっても、興味深いものになるはずです。本展が、「滋賀の家」と、私たちの未来の生活や環境を考えるきっかけになれば幸いです。
展覧会の主旨を想像するに、なにか強い主張でもって「滋賀の家」はこうでござい!と打ち出すのではなく、あくまで「これからの家」を鑑賞者それぞれが考えていくための手がかりとして、滋賀を舞台に建てられた家たちを紹介するといった位置づけなのでしょう。
それゆえ、ここで「滋賀の家とはですな…」みたいなことをエラそうに書くのは無粋なわけですが、あくまで「わたしはこう読んだ」といった意味合いでなら書いてもいいかなということで、ちょっと書いてみます。
滋賀の語られ方
さて。考えてみるための補助線として、滋賀県・滋賀県観光連盟が編集・発行した『SHIGA滋賀』という観光パンフ(発行年は不明)をとりあげます。このパンフは「滋賀県」を次のように紹介しています。ちょっと長いですが。
本県は、京都、三重、岐阜及び福井の一府三県に境を接し、近畿、中部の両地域の連絡上重要な位置を占めている。
観光資源を代表する日本一の琵琶湖の水は県民の生命線であるばかりでなく、優秀な品質を誇る江州米の生産をはじめ、水産、発電、繊維、化学等各種近代産業を培養し、京阪神への飲料水、工業用水をまかない、その恩恵は広大無辺である。
古くから詩の国、絵の国として歌われ、あるいは描かれた美しい風景とそれを彩る数多くの史蹟、名勝、重要文化財、伝説などによって総ての日本人から愛され親しまれてきた土地である。
ほうほうなるほど。まず圧倒的な存在感の「琵琶湖」。地理的にも歴史的にも新旧さまざまなモノやコトがあふれた魅力ある土地であることがうかがえます。そして、この文章のあとこう続きます。
東の富士山が一夜の間に噴出してその秀麗な姿を現出したのと同時に西の琵琶湖が満々たる水をたたえて出現したという伝説は、藤戸琵琶湖が山と水とをもって形成されたる日本の景観を代表しているところから出たのであろう。湖上に浮かぶ緑の島々、周辺至るところに四季折々の季感を見せて繰りひろげる景観が人々の心をやわらげ、こよなく魅力のあるものとしてくれる。湖国 滋賀県―美しい風景が、なごやかな人情が―世界の人々を招いている。
「観光」的な言説で美しく語られた文章に登場する「湖国」。「近江」の語源と同様に滋賀を語る際に琵琶湖がとても大きな存在感をもって迫って来ることがわかります。

(京阪電車ほか「伊勢よりびわ湖へ」リーフレット、戦前)
しかも「近江」の地はもともと京から”近い”淡海(遠い淡海は「浜名湖」)というように京からのパースペクティブのもと捉えられました。

(「京阪バス観光案内」リーフレット、京阪自動車)
ただ、滋賀県に属する多様な土地が総じて琵琶湖と結びつけられるものなのか。むしろ前半で書かれた“多様な滋賀”像が薄らいでしまっています。滋賀が「湖国」の大きな引力に引き寄せられてしまう。ひとびとの生活や生業それ自体ではなく、ややもすると観光用に編成された言説や、外部からのまなざしを地元民までが内面化してしまっていたりする側面もあるでしょう。多様な滋賀へ向けた学びほぐしが求められます。
プレハブ生産の楽屋裏
西山夘三いわく
そういえば西山夘三は、晩年に画文集『滋賀の民家』(かもがわ出版、1992年)を出版しています。住まいの“近代化”に心血を注いだ西山が、いわば封建制の結晶でもある“古民家”を丁寧かつ愛情こめてスケッチしているのです。
この画文集の巻末では、民家の意義とともに、「なぜ滋賀なのか」について西山自身が記しています。まずは滋賀についての個人的な思い出話から。それにつづけて、滋賀がもつ学術的な意味をこう書き記しています。
…住生活、住宅問題、都市・地域計画の研究をしてきた専門家としての興味である。滋賀県が京阪神大都市圏の外周にあり、最も先端的な地域変革の圧力を強く受け、そのさまざまな兆候がいち早く読み取れること、同時に日本の代表的農業地帯で、琵琶湖には漁業もあり、広大な穀倉地帯と言える湖東平野から周辺の山地に至るまでの地域構造、その中にはかなり不便な古い生活をそのままついこの間まで残していた山間僻地もあるといった、日本の多様な地域をワンセットに凝縮してかかえこんでいる縮図のような地域であり、私の専門である「すまい」の状況を勉強するのに、とても魅力的なテーマだと思ったからである。
日本の社会と住まいの近代化を凝縮した縮図。それが「滋賀」だというのです。まさにこの位置づけゆえに、滋賀は戦後「プレハブ生産工場のメッカ」として、日本の住宅大量需要を支えたのでした。
工場立地上から内陸型生産工場、港湾型生産工場と2大別すれば、プレハブ住宅生産工場は前者であろう。最近活発に工場建設が行われている滋賀県が立地の好例である。すなわち名神ハイウェイを輸送の根幹として、栗東町、石部町、八日市町、湖東町にそれぞれ鉄骨系、木質系の工場が建設されている。大阪、名古屋という大都市のほぼ中間に位置し、プレハブ住宅部材を運搬するのに便利なことと労働力の確保が出来やすいという点から、プレハブ生産工場のメッカとなったのである。

(すでに操業停止しているものも含む)
たとえば、いまも東近江市でヘーベルハウスをつくる旭化成住工は、もともとは東芝の住宅事業、東芝住宅産業(東芝メイゾン)のプレハブ生産工場「東芝住宅工業」としてスタートしました。
白洲正子いわく
そういえば白洲正子が「近江は日本の楽屋裏」と『近江山河抄』(駸々堂、1974年)で評したのは近江クラスター(?)界隈では有名な話だそうで、実際に『近江山河抄』を読んでみると、たしかに「近江は日本文化の発祥の地といっても過言ではないと思う」という表現とともに、「前に私は『近江は日本の楽屋裏だ』と書いたことがあるが…」という一文がでてきます。
琵琶湖の水が未だに京・大阪をうるおしているように、近江は日本文化の発祥の地といっても過言ではないと思う。
そこには一種の寂しさも感じられる。原産地がいつもそうであるように、奈良や京都に匹敵する文化も美術品もここには残っていない。これは近江商人についてもいえることで、彼らの大部分は他の土地で活躍している。前に私は「近江は日本の楽屋裏だ」と書いたことがあるが、簡単にいってしまえば、私の興味をひいたのもそのひと言につきる。
じゃあこの「前」に書いた文章ってなんだろうかというと、同じく白洲正子の著書『かくれ里』(新潮社、1971年)のことのようです。そこで白洲正子はこう書いています。
…奈良や京都に対して、いつも楽屋裏の、お膳立ての役割をはたしたのが近江の地であるが、そのわり一般には知られていず、専門的な研究は進んでいない。未だに多くの謎をふくんだ歴史上の秘境、それが近江の宿命であり、魅力ではないかと私は思っている。
「近江は日本の楽屋裏だ」という表現ではないですが、たしかにほぼ同様のことを述べています。ところで、この『かくれ里』の文章は、初出となった「藝術新潮」での連載(第8回、1969年8月号)にはあった一文がカットされています。その部分はこう。
…奈良や京都に対して、いつも楽屋裏の、お膳立ての役割をはたしたのが近江の地で、大げさに言えば日本文化のふる里と名づけてもいいのだが、そのわり一般には知られていず、専門的な研究は進んでいない。未だに多くの謎をふくんだ歴史上の秘境、それが近江の宿命であり、魅力ではないかと私は思っている。
「日本文化のふる里」は勇み足ということでカットしたのでしょうか。『かくれ里』での「近江は日本文化の発祥の地」と似た表現でもあり、本人は「大げさ」と言葉をくわえつつも、やはりそう言ってしまいたい思いがあったのもうかがえます。白洲正子自身は近代化が進む近江の地を複雑な思いでみていたようです。でも、戦後の滋賀が果たした大きな役割を思うと、白洲の言葉をこう言い換えてみたくなります。「戦後の住宅大量供給に対して、いつも楽屋裏の、お膳立ての役割をはたしたのが滋賀の地」であり、「大げさに言えば戦後住宅のふる里と名づけてもいい」と。
実験場としての滋賀
滋賀の地はさまざまな時代でいわば「楽屋裏」としての役割を果たしてきたことを、今回いろいろお勉強する過程で知りました。「楽屋裏」は準備・段取りをするだけではなく、本番をひかえて試行してみる「実験場」でもありました。
日吉東照宮は日光東照宮の雛形としてつくられたといいます。また、1970年に開催された「日本万国博覧会」(大阪万博)に先立つ1968年に滋賀で開催された「びわこ大博覧会」は大阪万博の「模擬博」として実施されたといいます。会場内には大阪万博の特設館「万国博がやってくる展」を開催。「びわこ博音頭」はもちろん三波春夫が歌いました。

(びわこ大博覧会協会編『びわこ大博覧会』1968年)
いきなり私事ですが、三重に生まれ育った自分がはじめて滋賀を意識したのは、びわこ温泉ホテル紅葉・紅葉パラダイスのTVコマーシャルです。
戦後開業した紅葉館が徐々に鉄筋コンクリート造のホテルとなり、さらにはヘルスセンターや遊園地、ボーリング場まで併設していくダイナミズムは、戦後のレジャーブームの先陣をきった展開だったはず。

(「湖畔の宿・紅葉館」「レィクホテル紅葉」リーフレット)
ほかにも、湖西線は高速走行の実験をするのにも活用されているとか、ユニット住宅の代表格として知られる積水化学工業「ハイムM1」の試作棟第2号は、琵琶湖畔になかばゲリラ的に建てられたとか多数の事例が挙げられます。
都会と田舎、あたらしいものと古いものが入り乱れる滋賀は、ときには伝統的な、また別のときにはこれからの時代をリードする実験的な住宅創作を許容してきた土地。京都や大阪ですぐさま社会実装しづらいものが、まず滋賀で試行されるという構図をいくつも確認できるのです。
実際、1年間に着工された新築住宅に占めるプレハブ住宅の割合は、全都道府県で常に滋賀県が一位を占めてきた歴史があります。1980年時点では20%を超えるのは滋賀県のみ。以降、徐々に他の都道府県にも広がっていくが、一貫して滋賀県はプレハブ住宅の比率が高いことがわかります。

滋賀県は一貫して高いプレハブ率を誇った
その時代ごとに「実験場」としての場を提供し、その後の住まいのあり方の「ふる里」となってきた「滋賀」(「近江」でも「湖国」でもない)。そこで織りなされた家々のありようから、これからの住まいを考える。そういう企画展が今回の「滋賀の家展」なのでは中廊下と。
この企画展が「滋賀の家」であって「滋賀の建築」でなく、英文表記でも副題”Life and Connection with the Environment”とあって、「建築」も「Architecture」も登場しないことは要注目でしょう(ここでのEnvironmentが狭い意味でのそれでないことはもちろん)。
少なくとも、かつて界隈で語られたような「住宅は建築ではない」といった世界観からは自由となった(そして、建築家とハウスメーカーが対立図式では描かれない)地平から鑑賞する場となっているのだと。
このスタンスは「足軽屋敷プロジェクト」はじめ「周縁とのつながり」と題して出展されている諸作品(であり諸活動であり諸生活・諸人生)が展示会場の終盤に登場することで、うわナルホドなと了解されます。それと同時に「家」づくりにかかわる建築家の職能が変化してきた様子も、たくさんの展示を順に眺めていくことでみえてくるのも面白いです。
くりかえす小屋と縁側
今回、美術館の前庭に伊礼智による「湖畔の方丈」が、そしてエントランスわきに竹原義二による「素の縁側」が設けられていて、来場者をお出迎えするしつらえになっています。”小屋”と”縁側”は時代の節目で何度も再読されてきました。
あたらしい縁側
敗戦まもないころ、今和次郎はかつての封建性の証だった”縁側”の読み替えを試み、『住生活』(乾元社、1945年)のなかで、復興日本のあるべき住生活モデルを「縁側社交」として提案しています。
これまでの都市生活では別々になっていた「事務的な社交」と「親密な社交」が自然と混ざり合い、格式にとらわれない健康な住まいを実現するのが「縁側」だと説きました。
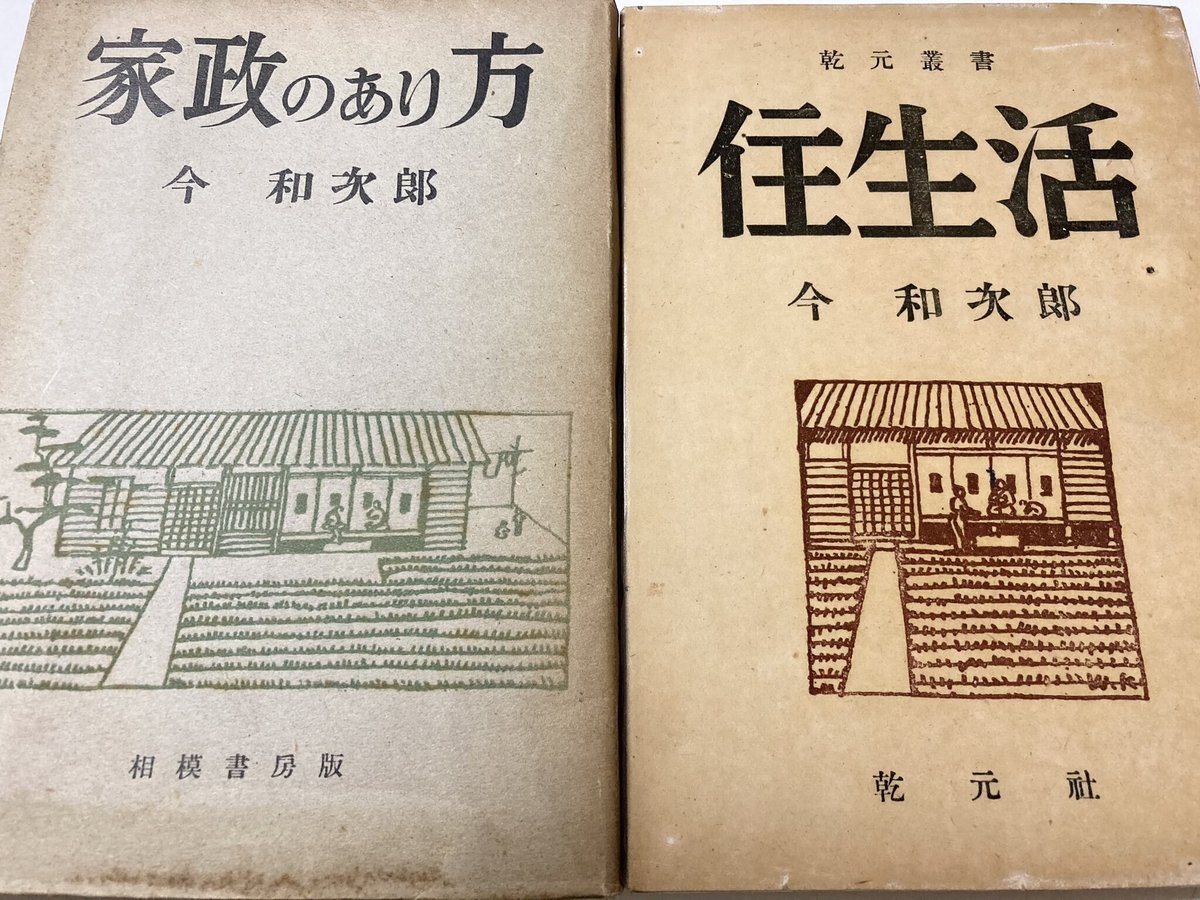
(今和次郎の『家政のあり方』と『住生活』)
…各戸の茶の間に開かれている縁側を、かゝる事務的社交の行はれる場所としたらいゝと思ふのである。そしてだんだん話がこみ入つて来たらば、漸次に茶の間に上つてもらうといふ順序でよからうと思ふのである。
格式表現としての縁側は、戦後復興期の貧しさのなかであたらしい役割を担ったのでした。
そういえば滋賀県立美術館は2021年から「公園のなかのリビングルーム」「リビングルームのような美術館」をめざすべき美術館像として掲げています。それは以前、初代館長によって掲げられた「あなたの応接間に」のバージョンアップ版。「素の縁側」を堪能した後、来場客は「リビングルームのような美術館」にあがりこむのだと思うと、今和次郎を思い出してニンマリしてしまいます。
はじまりの小屋
「湖畔の方丈」のもとはコロナ対応・ステイホームの小屋。高度成長期の人口台風で母屋にいられなくなった子供たちの離れ「ミゼットハウス」とゆるやかに呼応しています。こうしたよく似たモチーフが、時代背景の変化のなかで異なる価値をまといながらも繰り返されてきました。

(商品リーフ 大和ハウス工業 1960年代はじめ頃)
プレハブ住宅が、特に家屋に対しては保守的な考えが根強かった日本社会に受容されたのはなぜか。その勝因の一端は、それが離れ(=母屋ではない)だったこと。一人前の住宅は社会的に認知されたつくり方(=在来木造)でなければ世間体が悪い。プレハブ住宅という見たことない家は、まず“おためし用”として離れ・勉強部屋という”小屋”である必要があったのでした。
これからの時代を占うあたらしい”小屋”は、1970年代はじめにも登場します。それが主にレジャーハウスとして広がったカプセル建築です。「家」の転換期には、まず”小屋”がその尖兵として登場してきたのでした。
戦後の住宅大量需要・大量供給に対応するため構築されたプレハブ住宅は、その後の時代の変化にあわせて徐々に縮退しつつあります。非木造系大手ハウスメーカーが続々と在来木造に進出しているのもその証左。では、かつてのプレハブ住宅の試行錯誤は無価値なのかというとそうでもない。やっぱり同じように繰り返されるよく似たモチーフにあふれてもいる。
住宅史上くりかえされてきたモチーフの代表である”小屋”と”縁側”は、まさにあたらしい「家」への導入部としてふさわしい。来場者はまず”小屋”に出会い、その後に”縁側”にふれ、そして多様な「滋賀の家」に立ち会うことになります。しかも会場はリニア―な鑑賞順序でなく、何度も何通りもループできるようになってる。そして「滋賀の家」を満喫したあと、”小屋”と”縁側”に見送られて家路につく。
*******************
「滋賀の家」とくくったとき、たぶん「あれがない、これがない」という話もあろうかと思うのですが、むしろ「これも滋賀の家だよね」と鑑賞したひとびとがそれぞれに思いつき、その家について考えをめぐらせることがなによりも大切なのでしょう。
展覧会の最後には、鑑賞者それぞれが、自分が思い描く「家」を描くワークショップスペースも設けらています。さまざまな「滋賀」的実験マインドにふれて感じたこと、考えたことを表現し展示できる企画になっているのがとても秀逸です。
思い思いに描かれた「あなたの家・わたしの家」を眺めつつ館をでて、ふたたび縁側、そして小屋に対峙すると、来館したときとは違う景色にみえるのではないでしょうか。
(おわり)
いいなと思ったら応援しよう!

