
2022年、『フリクリ』を振り返る
20年余りを経て、チェンソーマン・村上春樹・ギリシャ悲劇・他
〜FLCL Frictional Essay〜
※本記事では『フリクリ』並びに、取り扱う関連諸作品についてネタバレとも思われる記載がございます。読まれる方は予めご了承ください。
序章 『フリクリ』の糸
クモの巣を想像して欲しい。
『フリクリ』を中心として、周囲には幾多の関連するトピックが点として浮かんでいる。それらは糸で繋ぎ合わされている。
中心となる『フリクリ』と、周囲の点たちを結ぶ放射状の糸がある。それらは必ずしも一定方向とは限らない。相互に作用しうる場合もある。
そうかと思えば、中心の『フリクリ』とは無関係に、点Aと点B同士を結ぶ、横の糸もまた存在する。
この試論は、そのようなクモの巣を這って、あらゆる点と点を行き交う形で展開していくものである。結果、読者には散漫とした印象を与えるかもしれないが、お赦し願いたい。論文でもないのに、一貫したテーマがなければ文章として成立しないなどといったルールはどこにもないだろう。複雑なものを無理にシンプルにまとめようとすれば、そこにはかえって齟齬が生じるものだ。
『フリクリ』概説
まずは形式的にウィキペディアの引用から入る。
『FLCL』(フリクリ)は、2000年から2001年にかけて全6巻のOVAとしてリリースされた、日本のアニメ作品である。『新世紀エヴァンゲリオン』の次作品である『彼氏彼女の事情』以降は、原作付のアニメ化しか制作していなかったガイナックスによる、久々のオリジナル作品。また、『FLCL』は『新世紀エヴァンゲリオン』で副監督を務めていた鶴巻和哉の初監督作品である。 一般的にビデオ・DVDのパッケージには作品解説・あらすじなどが記載されるものであるが、『FLCL』のパッケージはそれらを徹底して排したデザインになっており、同様にテレビコマーシャルでも内容に関する言及は全く無かった。

主人公の名前はナンダバ・ナオ太(画像右)。小学6年生の少年である。性格はまあまあ強気だが、当時としてはまだ新しい『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジをパイオニアとする、内向的、等身大型主人公の系譜に連なると言ってよい。
名前にクセがあるが、これは本作全体に関して言えることで、ストーリーや設定、映像から音楽まで、クセのない箇所を探す方がかえって難しい。しかし、本作の特徴であるそれらの「クセ」を剥いでいくと、かなり普遍的なテーマも見えてくる。それについては後述する。
謎の女ハルハラ・ハル子(画像手前、本作のメインヒロインでありシンボル的存在)との出会いを機に、ある「特別」な力に目覚めたナオ太が何を思い、どのように成長してゆくかの過程が、一歩間違えればクリエイターの自己満足に陥りかねないほどの戯画的なタッチで描かれている。OVA(オリジナルビデオアニメーション)であり地上波での放送はないにも拘らず、今なおニッチなファンから熱狂的な人気を誇る。
タイトルの意味 “NEVER KNOWS BEST”
このような性質の作品は往々にして、ファンとの間に、ある種の完結した世界(空間と言ってもよい)が形成されるものだ。『フリクリ』の場合、ハイテンションなハイテンポストーリーを「頭を空っぽにして」楽しむというのが、ファンの間の共通認識となっている節がある。
さらに、第5話次回予告の中で、作品タイトル『フリクリ』の語源と思われるキーワード(いずれもスペルを省略すれば「FLCL」となる)が、その意味と共に、一瞬のカットとして何度も挿入される。以下はその例だ。
flip clock n.1 安物の時計. 2 転じて、見た目だけで役に立たないたとえ.
fool'ish clev'er•ness 一見利口そうに見えて実は愚かな考え. 馬鹿の浅知恵.
これらのキーワードは、作品の性質の説明とも受け取れる。つまり、作品の側からも視聴者に向けて「深く考えるな」とのメッセージを発しているのである。

よって、筆者のようなにわか者がそこに土足で踏み入る行為にはタブー感が禁じえない。
しかし、作品の発表から20年余りが経った。その間に後続の作品が生まれた。『フリクリ』に先んじてGAINAXより生まれた『エヴァンゲリオン』シリーズもいよいよ終劇を迎えた。その中で『フリクリ』の空間は時が止まったように、『フリクリ』のままであり続けた。それは悪いことではない。あるモノを良いと感じる者たちにとって、それがただ良いモノとしてそこに存在していれば構わないという価値観を否定はしない。
しかし改めて振り返ることで、見えてくる事柄もある。煮詰まった空間は、若い感性によって時折風を通してやらなければ、やがて衰退の一途を辿ることもある。だが果たしてこの試論がベストなやり方なのかは、筆者自身にもわからない。
藤本タツキが『フリクリ』に見たもの 〜チェンソーマン〜
2018年12月から2020年12月にかけて『チェンソーマン』第一部が週刊少年ジャンプにて連載された。『チェンソーマン』連載中に、作者の藤本タツキが、気になるコメントを発している。
「チェンソーマンは『邪悪なフリクリ』『ポップなアバラ』を目指して描いています!」
出典:「チェンソーマン」300万部突破、藤本タツキからのコメント&イラストも/コミックナタリー
「邪悪なフリクリ」とはどういうことだろう。筆者はこの時点で『チェンソーマン』のファンだったものの、実は『フリクリ』は未視聴だった。『フリクリ』の発売当時、筆者はまだ小学生に上がるか上がらぬかの年齢であり、マニアックなアニメ作品とは無縁だった。
(しかし、当時はそれを言語化する能力こそなかったものの、筆者が2000年前後という時代を肌で体感した最後の世代であることは、ここで予め述べておく。というのも、『フリクリ』が普遍的なテーマを奥に秘めながらも、時代の精神とも呼べる何かを切り取った作品であるからだ。筆者が『フリクリ』の世界からノスタルジーを喚起されるのもそのためだろう。)
話を戻すと、藤本タツキの「邪悪なフリクリ」発言こそが、視聴の最も主な動機となった。2021年12月某日、つまり『チェンソーマン』第一部終了からほぼ1年が経った頃、Amazonプライムビデオで『フリクリ』が公開されているのを発見すると、これはもう観ないわけにはいかなかった。現在(執筆時点)も公開中である。
順序が逆になり、「邪悪ではないチェンソーマン」とはどんなものかを観る気持ちだった。なるほど確かにポップである。人が乗り物に轢かれてもギャグ演出で済むが、『チェンソーマン』の世界だったら血を吹いて死んでいるだろう。
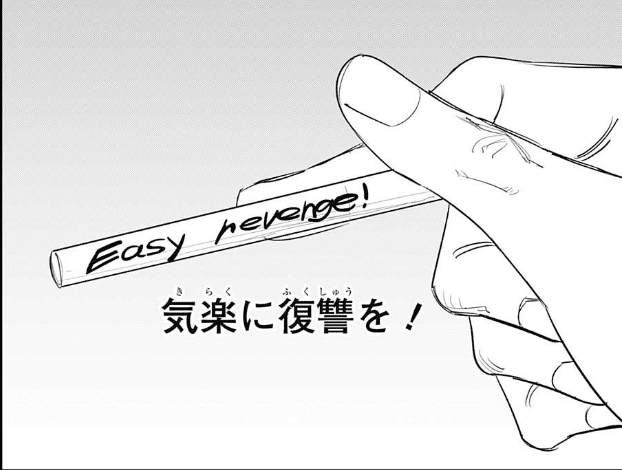
とはいえ、ここで重要なのは、邪悪か否かの二元論よりも、両作品の共通項だろう。藤本タツキが『フリクリ』の一体どの辺りを参考にしたのかが、観ている間は正直、うまく読み取れなかった。実際、タバコに書かれた手書き風文字や、敵の居場所に反応するトランシーバー的ガジェット、脇キャラの新車が破壊されるギャグなどのパロディは認められるのだが。それでも視聴を続け、第6話(最終回)に辿り着き、実は最初からある仕掛けが構想に仕組まれていたことに気づくと、『チェンソーマン』との深い部分での相似が浮き彫りになった。
それは、両作品ともに、主人公の少年に母親が存在しない点である。『チェンソーマン』において、主人公デンジに母親がいないことは、第1話の時点で本人の口から明言されている。一方で、ナオ太の場合、ストーリー上の必要性から、兄の不在ばかりが強調されているためあまり気にしなかったが、やはり母親が居ないのだ。そしてさらに重要なのは、恋愛対象としてのヒロインが、主人公よりも歳上の成人女性に設定されている点だ。
藤本タツキは、『チェンソーマン』連載終了直後のイベントで、ヒロインのマキマの名前について次のような主旨の発言をしている。(コロナウイルスの影響でオンラインでの開催だったが、残念ながら動画は残っていない)。
由来はママです。 最終話ではクサくなるので書けなかったが、チェンソーは木を切る道具であり、マキマの中のキを切ると、ママになって、デンジがマキマに求めていたのは、実は恋愛ではなくて、母性だったと分かる話にしたかった
出典:「キャラの名前の由来は?」ジャンプフェスタ『チェンソーマン』 作者の藤本タツキ先生にインタビュー/あっとゆーまの日記/はてなブログ
なるほど、『フリクリ』の鶴巻監督はじめ、製作陣がどのような思いでナオ太とハル子の関係を描いたかは詳らかではない。しかし、少なくとも藤本タツキは、ナオ太のハル子に対する思いの中に母性を読み取ったと類推できる。これを元に第1話を観てみると、まず、ナオ太は自分の唇を奪った(人工呼吸なので的確な表現ではないが)ハル子を異性として少なからず意識する。次に、「家政婦」として家に乗り込んで来た時点でハル子はナオ太にとって「義母」のような存在とも化す。ついでに、ハル子が父親と「できている」ことを匂わせると、ナオ太は嫉妬を覚える(ただ『チェンソーマン』においては、父親とヒロインの間に直接的な関係はない)。この時点で、ナオ太の母親への恋慕を想起することは十分に可能だ。描き方はそれぞれ異なるが、ヒロインとの衝突を通してラストに到達する点でも両作品は符合する。
ただしナオ太は、第1話のクライマックスでは、ハル子に兄の姿を重ねている。これについては、ナオ太の成長にまつわる、「母親への恋慕」とはまた別の「兄への羨望」というテーマに繋がっていく。
カジュアルなオイディプス 〜エヴァンゲリオン〜

上記した第5話次回予告における作品のキーワードの中に、以下のようなものも含まれる。
Flem'ing,Clem'ent 《人名》19世紀の心理学者. 少年期の自我形成についての研究で知られる.
しかし、この“Fleming Clement”なる心理学者は、筆者の調べた限りでは実在しない可能性が極めて高い。このことは、「心理学」的見地における「少年期の自我形成」が、『フリクリ』のテーマの一つである証左だ。そうでなければ、わざわざ架空の人名を創作してまでこのような説明を取り入れないだろう。
さて、「母親への恋慕」と聞き、真っ先に連想されるのがエディプスコンプレックスだ。
エディプス‐コンプレックス【Oedipus complex】
〔心〕男の幼児が無意識のうちに母親に愛着を持ち、自分と同性である父に敵意を抱くことで発生する複雑な感情。父と知らずに父を殺害し、生母と結婚したギリシア神話のオイディプスにちなんでフロイトが提唱した用語。↔エレクトラ‐コンプレックス
出典:広辞苑
ただし、これについて厳密に考え始めると非常にややこしくなる。なぜなら、実際に恋愛の対象とされるのが実の母親ではなく、母親を投影した別人であることなどを踏まえると、『フリクリ』にしても『チェンソーマン』にしても、描かれているものが学問的に正しいエディプスコンプレックスなのかどうか、専門家などからすれば疑わしいと思われるからだ。そのため、この試論では定義を狭め、「エディプスコンプレックスから着想を得たとおぼしき題材」程度のカジュアルな意味合いでこれを用いる。
そもそもエディプスコンプレックス含むフロイトの理論は、性的なものとの結びつきが激しく、常に批判の的となってきた歴史がある。しかし、偶然か必然か定かではないが、『フリクリ』の作中にも露骨な形で男根のメタファーが登場する。このことから、エディプスコンプレックスをむしろ積極的に援用する方針で書かせていただく。
『新世紀エヴァンゲリオン』を思い出して欲しい。碇シンジは、自らが搭乗するエヴァ初号機=母親(=碇ユイ)との「シンクロ」を果たし、また、碇ユイのコピーであるヒロインの綾波レイにも恋慕する。綾波と親しげに会話する父親の碇ゲンドウに嫉妬する場面も印象的である。
これがエディプスコンプレックスでなくて何だと言うのだろう。さらに『フリクリ』以前に公開された旧劇場版(1997年)では、自らが駆るエヴァ初号機で碇ゲンドウの頭を食いちぎってしまう。父親を実際に殺してしまうこの件などは、エディプスコンプレックスの語源となったオイディプスの神話そのものを彷彿させる。
しかし、『エヴァンゲリオン』シリーズの旧劇場版における結末は、ファンの間にも監督である庵野秀明自身にも、長い間しこりとして残った。紀元前にソフォクレスの手で最高傑作として結実したギリシャ悲劇の文脈を用いてまでも、作品を真に完結させることができなかったのである。そもそも『オイディプス』が最高傑作とされる所以が、近親相姦や父親殺しといった題材自体よりも、その作劇術にあったことも挙げられるが、それとは別に、鶴巻監督にはできて庵野監督にできなかったあることに注目してみる。
それは、主人公の少年を成長させることである。
エディプスコンプレックスには元々、幼児の心的発達の通過点としての側面がある。エディプスコンプレックスを抱えた少年を主人公にするからには、その克服までがセットである必要があるのだが、碇シンジは父親を殺すことで、むしろその状態を受け入れてしまう。(予定調和的なものをあまり好まない筆者としては、それはそれで構わないとも考えるのだが。)
一方で鶴巻監督はといえば、『フリクリ』において、ハル子≒「母親」との失恋という形でその克服をあっさりと描いてしまった。小学生だったナオ太が、最後に中学校の制服を着て登場する場面などは象徴的だ。ハル子は言う。
「私はタッくん(=ナオ太)の少年の日の心の中にいる青春の幻影」(第4話)
傍若無人な性格に加え、ふざけた口調も相まって、ハル子の発言は常に真実味が乏しい。しかし、例えば初登場時に自らを宇宙人と紹介したことが真実だったように、実はほとんど設定と齟齬がない。そのため、上記のセリフも脚本家による意図的なものと判断してよい。一見難解と思われる『フリクリ』に秘められた普遍的なテーマとは、まさにこのことである。2004年〜06年に同監督に作られた『トップをねらえ2!』でも、少年少女の成長が一つのテーマとなっており、エディプスコンプレックスとは別の観点から『フリクリ』と通じてくるのだが、それについては後述する。
〜『エヴァ』で描かれた成長〜
庵野監督について言えば、エヴァの『新劇場版』シリーズにも触れておかなければフェアではないだろう。

2021年に公開されたその最終章『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は特記に値する。本作では碇シンジの母性への執着は鳴りを潜め、さらに驚くべきは、庵野監督の自己投影の対象が、子であるシンジから父親のゲンドウに移行したことだ。父親は殺されるものとの固定観念に囚われた筆者は、観賞後しばらくこれをどう捉えるべきか悩んだが、今なら整理できる。昔からの感傷を引きずったままの碇ゲンドウは「大人になりきれなかった」大人の姿であり、すなわちシンジの別人格、または分身でもある。(『エヴァ』と共に育って来たファンや監督自身と重ねてもまあよい。)このことから、劇中で展開される世界の命運をかけた親子喧嘩は、単なる父子の対話に留まらず、碇シンジの自己理解の過程でもあり、即ち大人になるための一種の通過儀礼なのである。このように、シンジを成長させることで漸く真に『エヴァ』シリーズの幕を閉じ、また、その手段として監督自らがエディプスコンプレックスに囚われることなく、これを克服したことは評価に値する。
(追記:以上の父子の対話は、和解に至るための「精神的な父親殺し」であり、真のエディプスコンプレックスの克服であるとの見解もある。一理あるが、筆者はそれには肯首し難い。なぜなら、シンジの父親への敵意は一方的な物ではなく、それまでゲンドウが恨まれて当然の「毒親」として描かれてきた経緯があるからだ。これが子供の側から寄り添い、かつ相手の愚行を許すことでしか克服され得ぬエディプスコンプレックスとして描かれたのならば、グロテスクであり、現実の「毒親」家庭に育つ者に救いがない。そのため、ここで筆者は勝手ながら、ゲンドウを父親としてよりも、「シンジの別人格」と見做したいのである。)
『海辺のカフカ』概説
やや唐突だが、この辺りで村上春樹の『海辺のカフカ』に触れておく。後々、折に触れて本作を援用するだろうことを予想し、どこかでまとまった解説をしておく必要を感じたからだ。
(図らずも賛否のはっきり分かれがちなトピックばかりを取り上げることとなり、筆者の指に緊張が走り始めている。)
「君はこれから世界でいちばんタフな15歳の少年になる」――15歳の誕生日がやってきたとき、僕は家を出て遠くの知らない街に行き、小さな図書館の片隅で暮らすようになった。家を出るときに父の書斎から持ちだしたのは、現金だけじゃない。古いライター、折り畳み式のナイフ、ポケット・ライト、濃いスカイブルーのレヴォのサングラス。小さいころの姉と僕が二人並んでうつった写真……。
出典:村上春樹『海辺のカフカ(上)』あらすじ

『海辺のカフカ』(うみべのカフカ)は、村上春樹の10作目の長編小説。 ギリシア悲劇と日本の古典文学を下敷きにした長編小説であり、フランツ・カフカの思想的影響のもとギリシア悲劇のエディプス王の物語と、『源氏物語』や『雨月物語』などの日本の古典小説が物語の各所で用いられている。15歳の少年「僕」が、不思議な世界を自ら行き来しながら、心の成長を遂げていく物語である。
出典:
『海辺のカフカ』は今から20年前の2002年に書かれた作品である。それまで主に青年や中年を主人公として来た村上春樹の長編には珍しく、15歳という若さの少年を主人公に置いている。1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件は、少年による最悪の犯罪ということで社会を震撼させた。そんな時代背景の下に書かれたためか、主人公の田村カフカの内面には暗い渦が巻いている。彼の心の中だけに存在する「カラスと呼ばれる少年」は印象的だ。基本的に一人称小説の形を採るが、語り手が「カラスと呼ばれる少年」と入れ替わる時、地の文の「僕」は「君」となって、二人称という珍しい形式に変質する。これは「僕」自身が現実の直視に耐えられない時に起こる現象のようである。
特筆すべきは、先ほどからしつこく取り上げているオイディプスの神話をベースにしていることだろう。このことは作中でも明記されており、田村カフカは、自らに予言されたオイディプス王と同様の運命(父親を殺し、母親と交わる)から逃れようと、東京の自宅から四国まで遠い家出をする。
余談だが、『海辺のカフカ』の最も面白いところは、「村上ワールドの初心者にもうれしい、最高のプレゼントだ」とシカゴ・トリビューン紙が評するように、村上春樹がどのように考えながら長編を書いているのか、その方法論が自然な形で、時に面白おかしく解説されている点だ。例えば、漫画的なキャラクターが登場するのは毎度お馴染みだが、『海辺のカフカ』に出てくる「カーネル・サンダーズ」は自らの設定について語る。
「さっきも言ったように、私にはかたちというものがない。純粋な意味でメタフィジカルな、観念的客体だ」
「とりあえず、カーネル・サンダーズという、資本主義社会のイコンとも言うべき、わかりやすいかたちをとっているだけだ。ミッキーマウスだってよかったんだが、ディズニーは肖像権にうるさい」
こんな調子である。
外骨格としてのメタファー“思春期心因性皮膚硬化症”
次のテーマに移るため、ナオ太の持つ「特別」な力を具体的に説明する。まず、第1話でハル子にギターで殴られたナオ太の頭部からは、ツノが生えるようになる。そのツノからはなぜか2体のロボットが同時に現れる。片方は敵としてナオ太らに襲いかかり、もう片方はそれを倒す味方(?)のロボット(後に「カンチ」と呼ばれる)だった。第2話以降ではナオ太がカンチに取り込まれる形で合体し、敵のロボットと闘う展開が続く。これだけでは結局どのような「力」なのか不明だが、クラスの女子を中心としたサブエピソード的な第3話を過ぎると、後半で縦軸のストーリーが加速し(この構成術は『トップをねらえ2!』にも見られる)、第4話で「力」の正体が明らかにされる。
「“エヌオー”さ、人間の右脳と左脳の思考ディファレンスを使って、超空間チャンネルを開き物質を引き寄せるのさ。時に何万光年もの距離を一瞬にしてね」
「どこでもドア」のような機能だが、用途は「四次元ポケット」のそれに近いだろう。結局よくわからないが、同エピソード内でハル子がナオ太の頭から強引にギターを引っ張り出すと、それを見た「特殊入国管理官」の女性オペレーターたちが、「大きい」などと口走りながら一斉に鼻血を吹き出す。これは男根の暗喩と見てよい。
第1話を振り返ると、「看護婦」に変装したハル子が、ナオ太の病状(=ツノ)を「思春期心因性皮膚硬化症」と診断している。病名はハル子によるでっちあげだとすぐにわかるのだが、これは明らかに勃起のことだろう。主人公がまだ小学生という若さであることを合わせれば、肉体の発育過程によって精神的に戸惑う子供の姿が浮かび上がってくる。
『フリクリ』は、「メディカルメカニカ」と「光域宇宙警察フラタニティ」間の抗争、それを監視する政府などといった煩雑な設定や、突飛な展開から、「難解」や「意味不明」との評価を払拭しきれない。しかし、極言すると、作品の本質を理解する手段として、それらストーリーの表層的なものはすべてメタファーか、あるいは製作陣の遊び心の産物に過ぎないと見るのもひとつの選択肢だ。「轢かれる=惹かれる」というように。

では、なぜメタファーでなければならないのか。『海辺のカフカ』より引用する。
「いずれにせよあなたは、あなたの仮説は、ずいぶん遠くの的を狙って石を投げている、そのことはわかっているわよね?」
僕はうなずく。「わかっています。でもメタファーをとおせばその距離はずっと短くなります」
村上春樹はメタファーを多用する作家として知られる。そんな彼がメタファーについて言及した、それなりに説得力のある台詞である。
メタファーを駆使することで、自分のアイデアが相手に届くまでの距離が縮まるということを述べているわけだが、それはつまり、時間に換算しても短くなることをも意味する。
『新世紀エヴァンゲリオン』のTV版シリーズを思い出して欲しい。『エヴァ』もまたメタファーに富んだ作品と言える。しかし、碇シンジの心情描写においては、特にシリーズ後半に顕著だが、極めて直接的かつ、生々しい内容だった。結果、物語の全容は2クールの尺に収まらないまま、最終回を迎える。『フリクリ』は全6話だから、1クールのさらに半分の尺だ。いかにして、その短い物語で複雑な少年の心情描写を可能にしたのか。それが巧みなメタファーの賜物であるのは言わずもがなだ。
メタファーには相反する二つの性質がある。一つは「説明されなければ理解できない」ことだ。これはやはり物語を難解とするデメリットとして働く。もう一つは「説明した時点でメタファーではなくなってしまう」こと。説明する必要があるのなら、はじめから直接説明すればよい。しかしそうすることによって、ストーリーが複雑であればあるほど「遠くの的を狙って石を投げる」ことにも繋がってしまうのである。
上記のように、作中では様々な組織が動いているが、それらがみな「大人たちの集団」のメタファーに過ぎず、そんな「大人たちの都合に振り回される少年」という構図さえ描ければ、組織のディテールなどはどうでもよいのである。実際にそれを意図してか、組織の細部までいちいち明示されることはなかった。この構図もまた『エヴァ』と符合するが、やはり対照的に「ネルフ」と「ゼーレ」は設定や思惑が緻密に練られており、その全貌を把握している視聴者がどれほどいるのか定かではない。
書き忘れていたが、『フリクリ』の中でも、ナオ太による父親殺しがある。このシーンについては、エディプスコンプレックスの項目で、その理屈を補強するために取り扱うことも可能だったかもしれない。しかし、表現としてあまりにダイレクトすぎるために、かえってどう理解すべきか悩んだのだ。
ここで、『海辺のカフカ』より、大島さんという登場人物の台詞を借りる。
「また繰りかえすことになるけれど、世界の万物はメタファーだ。誰もが実際に父親を殺し、母親と交わるわけではない。そうだね? つまり僕らはメタファーという装置をとおしてアイロニーを受け入れる。そして自らを深め広げる」
つまり、『オイディプス』はメタファーなので、エディプスコンプレックスの少年が父親を殺すわけではないというのである。これは逆説的には、メタファーを介せば殺せることも意味する。父親のメタファーとして父親を殺すことは不可能だが、ハル子をメタファーとして母親に恋することは可能であるように。ここで、ナオ太がエディプスコンプレックスの少年であるなどとは、作中では一切明示されていないことを思い出してみる。すると、「エディプスコンプレックスのメタファーとしての父親殺し」というように、恣意的な解釈も可能になるのである。物語の受け手に多様な解釈の余地を与えられることも、メタファーの大きな利点である。
“すごいことなんてない” 〜トップをねらえ2!〜
「特別」な力を得たナオ太だが、作品全体を通して観ると、彼自身はこの力を能動的に使うというより、ほとんど持て余し、振り回されているに等しい。なぜならば『フリクリ』は、「特別」な力を得た主人公が爽快に活躍する冒険活劇ではないからだ。先に述べたように、この作品の本質は、「特別」な力に目覚めた(自分を「特別」と勘違いしたと言ってもよい)少年が何を思い、どのように成長してゆくかの描写にこそある。
監督・脚本・キャラクターデザインのメンバーを継承した『トップをねらえ2!』を参照する。本作では「超・能力」を持つ「トップレス」と呼ばれる少年少女たちが登場し、成人することでその能力が失われる現象を「あがりを迎える」と表現している。この設定について、脚本の榎戸洋司が興味深いコメントをしている。
あがり
ある一定の年齢に達すると微熱が続くようになり、それを合図にこの能力は失われる。これが「あがり」と呼ばれる。トップレス能力の喪失は脚本家の榎戸によると「幼児期特有の万能感が失われること」と言う表現で示される(また榎戸によると企画当初は監督の鶴巻から「20歳を過ぎるとバスターマシンを動かせなくなる」と言うプロットが提示されていた)。
出典:
「大人に成長すること」=「幼児期特有の万能感が失われること」と、脚本家自らが定義しているのだ。これは『フリクリ』にも援用可能だろう。(両作品の間には、他にも「フラタニティ」という組織名や、能力を使う間「頭が空っぽになる」設定、全6話構成のOVA作品であることなど、様々な共通項が見られる。)
「特別」な力=「万能感」だと考えると、ナオ太にもそれが当てはまる。もう一人の主要人物を紹介する。元は兄・タスクの恋人でありながら、アメリカへ飛んだタスクの代わりとしてナオ太を弄ぶ女子高生のサメジマ・マミ美(見出し画像左)である。あるとき「力」を使って街を救ったナオ太は、第5話にて、友人たちの前で有頂天になる。そのせいで強気になったナオ太は、最近自分に素っ気ないマミ美の気を惹こうとし、空回りしてしまう。この時、ナオ太の後頭部から生えた銃の撃鉄が起こされる演出は、やはり「暴発」のメタファーという風に解釈できる。これも、自分の「特別」さに酔いしれていると考えれば、やはり力に振り回されている一幕だろう。
ナオ太の「特別」さへの憧れは、上記の「兄への羨望」ともイコールで結ばれる。なぜならば、先ほども述べたように、一時的に自らの「特別」さに陶酔したナオ太は、強引にマミ美の気を惹こうとするからだ。兄・タスクのように、マミ美と対等になれると考えたのである。しかし、それでも自分を子供扱いするマミ美に強い不満を抱くことで、自分の「特別」さが、望んでいたものとは違うことに気がつき始める。これを機に、「『特別』ではない自分」=「兄とは違う、子供の自分」を少しずつ受け入れ始めるのである。
『チェンソーマン』の中でも、少年デンジが夢を一つ叶えるたびに、それが自分の理想とは異なることに疑問を抱き、自分が本当に望むものを探求するという筋書きが取り入れられている。ここにも藤本タツキの『フリクリ』からのオマージュを読み取れる。
最終的に、ハル子との失恋と同時に、ナオ太は「力」も喪失する。そしてナオ太は、「特別」さに憧れるのを諦めて、現実に直面することで漸く大人の階段を登り始める。鶴巻監督としては、主人公の成長の過程としては、先述したエディプスコンプレックスの克服よりも、こちらの方がより真意に近かったのではないか。
〜『トップ2!』とギリシャ悲劇〜
『トップ2!』を取り上げたついでに、この作品の悲劇性にスポットを当ててみたい。

主人公ノノは、「ノノリリ」なる人物に憧れている。ノノいわく、「“ノノリリ”は普通の女の子」だという(また、「努力と根性」の人だったとも)。ここで強調すべきは、ノノはあくまで「普通」に憧れている点である。これはナオ太の主人公像と明確に相反する。そして同時に、ノノは「バスターマシン」と呼ばれるロボのパイロットになることも夢見る。しかし、『トップ2!』の世界で「普通」であるということは、「トップレス」能力を持たない存在を意味する。「バスターマシン」は、「トップレス」にしか操縦できないのだ。このチグハグさはなんだろう。その謎は、物語の後半で、ノノが失っていた過去の記憶とともに明らかになる。ノノは、実は「トップレス」などとは比較にならないほど「特別」な存在であり、「宇宙怪獣」に対抗するための、人類の切り札だったのだ。
「人が運命を選ぶのではなく、運命が人を選ぶ。それがギリシャ悲劇の根本にある世界観だ。そしてその悲劇性はーーアリストテレスが定義していることだけどーー皮肉なことに当事者の欠点によってというよりは、むしろ美点を梃子にしてもたらされる。(中略)オイディプス王の場合、怠惰とか愚鈍さによってではなく、その勇敢さと正直さによってまさに彼の悲劇はもたらされる」(太字=筆者)
『海辺のカフカ』より、再び大島さんの台詞である。
どうだろう。ノノが人類の切り札であったことは歓迎されて然るべき「美点」だが、皮肉にも、それによって「普通の女の子」への憧れは儚く打ち砕かれるのだ。
『トップ2!』のOPテーマは「渋谷系」音楽ユニットのROUND TABLE featuring Ninoが担当しており、かなりガーリーでキュートな曲調である。ノノの悲劇性が浮き彫りになることで、このOPは印象が大きく変わる。
ノノは一人、他の「トップレス」(=やがて損なわれる「特別」な子供)たちとは別の文脈で、「普通」と「特別」にまつわる物語をつくり上げたのだ。また、本作では「永遠のトップレス(=子供)」であり続けようとする者もおり、その描き方の是非は別として、注目に値する。
“ただ当たり前のことしか起こらない” 〜チェンソーマン〜

ナオ太は心の奥底で「特別」さを望みながらも、「普通」な日常に辟易しつつそれを甘受している、いわゆるどこにでもいる少年だった。そんなナオ太がいざ「特別」な力に目覚めると、現実はしかし思い通りにいかない。そして、周囲には様々な大人が登場する。サメジマ・マミ美をはじめ、「光域宇宙警察フラタニティ」のハル子、それから政府。
「普通」と「特別」の間に揺れる少年の心とは裏腹に、その力を巡って彼は周囲の大人たちに巻き込まれていく。
この構図は『チェンソーマン』とも符合するのだが、「普通」と「特別」に対する主人公のスタンスが異なってくる。さらに、他の作品では自明のように扱われるが、「普通」とはそもそも何なのかを考えていく内容も特徴だ。デンジもまた、『トップ2!』のノノと同様に「普通」を夢見るのだが、その意味するところがまるで違う。ここで、物語が始まる時点までのデンジの生い立ちを説明する。
デンジは、心臓病で亡くした母親の顔を知らず、幼少期に自殺した父親が残した借金をヤクザに取り立てられながら、ホームレス同然の生活を送っている。借金返済のために何度か体の一部を売ってきたし、犬のような姿の「チェンソーの悪魔」ポチタの力を借りて、ヤクザからの依頼で不法に悪魔退治「デビルハンター」の仕事もこなしている。そのため、義務教育も受けていない。
そんなデンジの夢見る「普通」とは、「食パンにジャム塗ってポチタと食っ」たり、「女とイチャイチャしたり」という庶民的な願いに留まる。
「すごいことなんてない。ただ当たり前のことしか起こらない」
とはナオ太のモノローグである。これはデンジからすれば、「すごいこと(=『普通』のこと)なんてない。ただ当たり前のこと(=苦しいこと)しか起こらない」というように、一段下にスライドされる。「邪悪なフリクリ」とされる所以の一つだろう。
〜「等身大型主人公」の在り方〜
冒頭の方で、筆者はナオ太について、碇シンジと並べて「等身大型主人公」という表現を用いた。ここで言う「等身大」とは、その時代の若者のあり様を筆写した姿という意味で用いている。しかし、20年以上が経った今から見れば、その姿にはステレオタイプの感が漂い出している。シンジ型の主人公が量産されたことも原因の一つだろうが、やはりその時代固有の匂いが拭いきれないのである。
筆者は『チェンソーマン』にハマりたての頃、デンジの姿が新たな「等身大型主人公」を編み出してくれる期待に胸を膨らませた。作者の発言を聞いているとどうもそのような意図はなさそうなうえ、他の読者からの賛同も得られにくそうだが、今でもそう考えているどころか、むしろ確信を強めている。
まずは若者の経済状況である。ナオ太の場合、家にそれほどの稼ぎはなさそうだが、それでもまあまあ立派な一軒家に暮らし、生活に困窮する様子は一切見られない。それが同時代の若者にとっての「普通」の暮らしだった。翻って、現代の若者の消費モデルは、多額を使って大きな夢を買うよりも、そこそこの値段の贅沢で満足する傾向がある。これは「特別」さなど眼中になく、庶民的な暮らしを望むデンジの姿と重なる。
次に精神構造として、内向的なナオ太に対して、デンジの神経は異様なまでに図太い。今の若者が彼ほどに図太いとは、流石に考えない。しかし、デンジの図太さは、内向的であることを諦めた結果でもある。デンジの心象風景として度々描かれる「ドア」の奥には、彼自身のある「弱み」が隠蔽されている。また、デンジはその図太さとは裏腹に、自分にとって有益とみなした強い権限を持つ相手には、犬のように従順になる一面もある。昔から言われることで、自己の弱さと向き合うことができない人間は、強い権力と一体化して安心感を覚える。しかし、これは現代の若者に特に顕著な傾向でもある。
よって、筆者はデンジを現代版「等身大型主人公」と説くのである。
〜現代的な「普通」〜
さて、『チェンソーマン』の物語は、デンジが実際に権力者を盲信し、自らの思考を放棄した末に、悪い方向へと突き進んでゆく。デンジがそれを自省する場面がある。
「これから生き延びれても俺はきっと…犬みてえに誰かの言いなりになって暮らしてくんだろうな」
その場にはたまたま、東山コベニが居合わせる。彼女もまた複雑な家庭事情と貧困をバックボーンとしており、その意味ではデンジに最も近しいキャラクターである。しかし、デンジよりはまだ一般的な感覚を持つ彼女は、こう答える。
「それが普通でしょ? ヤな事がない人生なんて………夢の中だけでしょ……」
『チェンソーマン』もまたギリシャ悲劇的皮肉に満ちた作品だが、この箇所はその最たる例の一つだ。
「現実を見よ」 〜彼氏彼女の事情〜
さて、アニメほど観る者に夢や希望を与えるのに適した媒体は珍しい。しかし、なぜ鶴巻監督は、『フリクリ』と『トップをねらえ2!』を通じて、あえて少年少女の成長過程における「現実との直面」を強調したのだろう。そもそもなぜ、物語の中で若者たちの心情を克明に描きたかったのだろう。ここで、余計と思われるかもしれないが、『フリクリ』の発表された1999年・2000年に至るまでの若者の精神の変遷を辿ってみる。
政治の季節と呼ばれる60年代、多くの若者たちの魂は、学生運動という形で外側へエネルギーを発散していた。それに敗れると、時代は政治的無関心(ここでは無気力と表現したい)に包まれていく。1972年に連合赤軍の活動が、あさま山荘事件という最悪の形で終えたことも、この気運に追い討ちをかける。しかしバブルが到来すると、無気力は引きずったまま、しかし活発な消費運動という形で若者の魂は一時的な享楽に解放される。いつ頃からか定かではないが、今、80年代カルチャーがリバイバルを起こし続けている。しかしその原因は、今の若者が当時と同様の精神性を持つからではなく、むしろ羨望ゆえだろう。文壇における村上春樹や吉本ばなな、俵万智らの台頭に象徴されるように、個人的な感傷を抱えつつも、それをファッショナブルに表現するだけのおおらかさが、あの頃にはあった。それが現代の若者の目に魅力に映るのも肯ける。このように、時代とカルチャーは表裏一体である。
一転、90年代を思い返すとき、そこには常に苦々しさが付き纏う。
(失われた30年と称されるように、経済状況的には90年代以降、現在に至るまで日本は地続きである。2000年、ジョージアのCMソングとして「明日があるさ」が起用されると大ヒットした。続編CMでは歌詞も時代に合うものに変更され、社会人同士で互いの傷を舐め合うかのようないたたまれないものになった。まだ幼かった筆者だが、当時を思い出すとき、あのCMに登場するサラリーマンたちのスーツのような色彩の欠けた風景が浮かび、空々しい気持ちになる。しかし、あのCMがコカ・コーラという大企業のものであることや、吉本興業の芸人が出演していることには、嘘臭さを感じる。そしてその種の欺瞞は今なお様々な場所から匂いを放つ。村上春樹は『ダンス・ダンス・ダンス』の中で「CMなんて根本的にはみんな屑だ」とキャラクターの口を通して言っているが、これには完全に同意する。)
90年代、バブルが弾けると、若者の魂は、無気力によって外側へと向かうことを拒み、消費運動も停滞したことで、次に内面世界の探究へと向かう。この時期に現れたのが、オウム真理教である。1995年のあの事件についてここでは詳しくは触れないが、文化的側面を指摘した文章があるので引用する。
村上春樹は麻原の、周囲にある「ジャンク」をひっかき集めて物語を生み出す力を指摘したが、それは村上自身もまた持っていた力、方法論であり、同時に様々なサブカルチャーの作り手たちが発揮していた力でもある。例えば映画監督・庵野秀明やロックバンド〈筋肉少女帯〉の大槻ケンヂのような作家たちは、膨大な文化記号をサンプリング/ミックスし一つの流れを生み出すことで、自分なりの物語を語ろうとしていた。オウム事件は、こうしたサブカル的想像力がぶつかった一つの壁でもあり、村上が本作(筆者註:『アンダーグラウンド』1997年)以降、自らの物語を、より深く根源的な形で模索することとも関連性を見出せる。
出典:マガジンハウス「BRUTUS 特集 村上春樹 上 『読む』編」 2021年10月15日号 p.55
なるほど、確かにこの後、敏感なクリエイターたちは揃って「物語を使って物語を解体する」かのような作業を始める。『エヴァンゲリオン』シリーズも、オウム事件後まで続いたことからその文脈の中に配置してよいだろう。『エヴァ』のメタフィクション的な要素は、しばしばフェリーニ映画と並べて評されるが、その演出は寺山修司のそれに近似する。
スタジオジブリでは2001年『千と千尋の神隠し』及び、2002年『猫の恩返し』において、主人公の少女が物語の世界に迷い込むが、最後には現実に帰るという形をとっている(もちろんこれを通過儀礼と読むことも可能だ)。これは2002年の『海辺のカフカ』も例外ではない。しかし、村上作品では、主人公の日常の中に物語が紛れ込んでくる作りが通例になっている。物語の主人公は普通、自分がその登場人物であることなど疑わないが、村上作品の主人公は現実と虚構の間に揺れるのが常である。これは『フリクリ』にも通じる要素だ。

また宮崎駿は、『千と千尋の神隠し』で、これまでの記号的ヒロインとは打って変わって、倦怠感のある少女・千尋を主人公に置いて見せた。『猫の恩返し』の主人公・ハルについては、彼女の「実在感」を称賛している。これらのことから、宮崎駿はこの頃、少年少女のリアリティの探究に走ったと見られる。これは何を意味するのか。
「#猫の恩返し」の試写📽が終わった時、宮崎駿監督は誰よりも先に、森田監督に拍手👏を贈ったのだそう❗️ハルという女の子の実在感、アニメーションの映像技術を賞賛したそうです。#猫の恩返し #金曜ロードショー #スタジオジブリ pic.twitter.com/01bvbJJ0bO
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) August 20, 2021
オウム真理教事件によって、若者の魂は、内面世界の探究の道としての「信仰」も閉ざされる。閉塞感が更に加速した頃、1997年に、元少年Aによる神戸連続児童殺傷事件が発生する。これを皮切りにして、少年少女の非行は社会問題化していく。これもまた、クリエイターたちは見逃すことができなかった。
元少年Aの事件の翌年、少女漫画原作のアニメ『彼氏彼女の事情』が、庵野を監督としてGAINAXにより製作される。

概要
“仮面優等生”の事情を持つ主人公2人の恋愛と成長、コンプレックスとの対峙、そして周りを固める個性豊かなキャラクター達の人間模様が描かれる作品。
出典:
TVアニメ版では、高校生である主人公の恋愛模様と、その周囲の仲間たちの心情が、庵野秀明の演出マジックによってコミカルかつ繊細に描写されている。ストーリー自体に大きな改変はなく、台詞も原作に極めて忠実であることで知られる。
しかしアニメ版には、教師・川島を演じる清川元夢による、原作にはないナレーションが度々挿入される。しかし、筆者には今それを確認する手段がないため、引用できないのが残念だ。
そのナレーションの特徴としては、話の内容には直接関係がない、アニメ放送当時の世相を述べていることだ。その中に、「少年犯罪」あるいは「少年少女の非行」というワードが含まれていたことは記憶に確かである。このアニメ化には、そのような時代背景にあって、改めて少年少女たちの心情を照らす試みがあったと考えてよい。このことから、当時の庵野監督やその周囲には、少年少女の非行が大きな問題意識の一つとして掲げられていたことが察せられる。
またオウム真理教事件と少年少女の非行は、それぞれ完全に独立したトピックではない。というのは、オウム真理教は、多くの若者が信者として取り込まれていったことも問題視されているからだ。この若者をめぐる問題意識が、GAINAX内では『彼氏彼女の事情』を転機として、後に鶴巻監督によって『フリクリ』へと結実してゆくのである。
“私だけに見える神様” 〜リリイ・シュシュのすべて〜
行き場を失くした若い魂たちは、救いを求めた。少なくとも、当時の大人たちは、物語の作り手は、そのように解釈した。それを象徴するかのような一作が、2001年に公開された、岩井俊二監督『リリイ・シュシュのすべて』である。
その以前にドラマ『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』でみずみずしい恋愛を描いたのと同じ監督作品とは思えぬほどに、『リリイ・シュシュ』は、現実の少年少女の生き地獄を凝縮したかのような、陰惨な内容に満ちている。奇しくもそんな岩井が、『フリクリ』を評価したという(残念ながら、いつどのような理由で評価したのかは定かでない)。しかし岩井は、自らが『リリイ・シュシュ』で描いた同時代の少年少女たちの慟哭を『フリクリ』の中に見抜いたのかもしれない。
〜暴力〜
マミ美は『フリクリ』というラジカルポップな作品の中にあって、その世界の闇を一身に引き受けた影の主人公だと筆者は考える。

マミ美は常に高校の制服を着ているが、実際に登校している描写はない。第2話では、マミ美が河原でいじめを受けているところをナオ太のクラスメートが目撃している。これらのことから不登校とも推測できる。喫煙シーンも、アニメーション的にはロックな画面作りに貢献しているが、現実的には非行少女の表現である。
「すごいことなんてない。ただ当たり前のことしか起こらない」
ナオ太のモノローグである。その直前のシーン。夕方、マミ美はいつもの河原で、いつものようにナオ太の耳を噛んで言う。
「マミ美はこうしないと溢れちゃうの」
「溢れちゃうって、どうなっちゃうんだ?」(ナオ太)
「きっと……すごいことになるの」
先述したように、マミ美はナオ太に、元恋人であるタスクの姿を重ねている。これは、ナオ太がハル子に母親を重ねる構図と相似する。しかし、マミ美の現実は辛く耐えがたい。相手がナオ太では不十分なのである。ナオ太は「普通」に辟易しているが、マミ実はもはや「普通」を憎んでいる。この点では、『チェンソーマン』のデンジやコベニの立場に近い。コベニの台詞を再び引用する。
「それが普通でしょ? ヤな事がない人生なんて………夢の中だけでしょ……」
さらに一歩進んで、マミ美もまた「すごいこと」を心の奥で望む。しかしナオ太の憧れがヒロイックなのに対して、マミ美の憧れは、常に負の方向を向く。また、ハル子の出現で運命が大きく動き出すナオ太に対し、マミ美の世界の時間は、タスクとの別れ以来、止まり続けているのである。
第2話で、マミ美による小学校への放火のエピソードが描かれる。動機は学校が嫌いだからと言う。また、小学校時代に校舎が焼けたとき、タスクが助けてくれた過去もある。それが二人の出会いだった。よって、マミ美にとって火は特別なシンボルでもある。そのため放火は、自暴自棄からの行為であると同時に、タスクに対する依存の表出ともとれる。だからナオ太との別離は、タスクへの依存を断った、マミ美なりの成長の結果なのである。ここにも、ハル子との失恋で成長するナオ太との相似関係が見出せる。
また、第4話で人工衛星が街に落下するとき、ナオ太は「力」を使って出したギターをバット代わりに、それを打ち返す。これは野球の試合でバットを振ることさえしなかったナオ太の成長を描く場面であると同時に、マミ美とのすれ違いの転機でもあった。マミ実は人工衛星を「恐怖の大王」に見立て、街への落下を望んでいたからだ。
このように、『フリクリ』はマミ美という影の主人公を通して、行き場を無くした若者たちの魂が向かう先をも描いてみせている。
同じ第4話の中に、本作で最も衝撃的な暴力シーンとして、先述したナオ太の父親殺しがある。結果的には、ナオ太がバットで撲殺したと思った相手が、実は父親の姿を模したロボットだった真相が判明し、何事もなかったように物語は再開する。しかし、実際にナオ太に殺意が芽生えた事実は消せない。当該場面は珍しく重い雰囲気に包まれており、ナオ太がバットを振る寸前に、すでに床に伏している父親の映像が浮かぶ(その時点ですでに殺しており、遅れて実感したという見方もできる)。この辺りの演出などからは、実際に人が人を殺す瞬間の意識の流れを汲み取る意図が感じられる。このことから、残虐シーンではあっても、単なる猟奇趣味からではないことが察せられる。
〜信仰〜
オウム事件後、若者の魂が「宗教」から離脱したと言っても、当時の若者がオウムに傾倒した現象を問う作業は欠かせなかった。山本直樹の漫画『ビリーバーズ』などはその好例である。ちなみに山本は代表作『レッド』を通して、連合赤軍の運動もリアルに描写している。両作共に、若者たちが和やかに活動する一面が描かれており、彼らを「異常者」として他人事にはせず、「どこにでもいる若者たち」として真摯に扱っている。
放火エピソードの第2話からだが、マミ美はゲームの中に登場する炎の神「カンティード」を崇拝していた。第1話でナオ太の頭から出現したロボットに外見的特徴の類似を見つけると、マミ美は「カンティード」をもじって「カンチ」と名付け、「様」呼びで慕うようになる。

“神様を見た/私だけに見える神様。私だけのために舞い降りた黒い翼の天使”
ここで注目すべきは、マミ美の「神」がゲームというサブカルチャーの媒体から発している点だろう。(また、これは今から見ると、『フリクリ』に心酔する当時のファンを、鏡に映した姿のようでもある)。
山本直樹『ビリーバーズ』の中でも、主人公たちの属す団体「ニコニコ人生センター」の教祖が、ゲームの元開発者であり、修行にそのゲーム内容を流用しているという設定がある。ここでは、ゲームのファンがその作者を社会的ヒーローに祭り上げたという過程にも触れられている。
『リリイ・シュシュのすべて』では、中学生たちの暴行を中心に、万引き、売春、自殺、強姦の様子が際どく描かれる。そんな現実の中にあって、主人公の雄一は言う。
「僕にとってリリイだけがリアル」
「リリイ・シュシュ」とは、作中に登場する女性歌手の名である。雄一は彼女の非公式のファンサイトを運営するほどの「信者」である。ただし、作中に彼女が直接登場することはなく、ファンサイトの書き込みの内容を通してでしか、観客は彼女の姿をイメージできないようになっている。よってその姿は、ほとんど「信者」たちのイメージが作り上げた虚像に過ぎないのである。また、ここでも「女神」が音楽というサブカルチャーに由来する点も挙げておく。
オウムに傾倒した若者たちの心を、一概に言い当てることなどは当然不可能である。ただし、「麻原の、周囲にある『ジャンク』をひっかき集めて物語を生み出す力」が、サブカルチャーを希求する多くの若者の心を魅了したのは確かだろう。そして同時に、サブカルチャーの中に自分のイメージを幻視する力というのは、いつの時代の若者たちにも自然に備わっているものだ。スターやアイドルのファンがわかりやすい例である。沼は深いが、その入り口は広い。あの時代、オウムという沼の入り口が「たまたまそこにあった」というだけで片足を突っ込んでしまった若者の姿は、決して他人事ではない。
〜音楽〜
最後に、『フリクリ』を語る上で、音楽に触れなければ嘘になるだろう。
音楽といえば、1979年に登場したウォークマンが音楽シーンを一変させたことは有名だが、それは物語にも少なからず影響を及ぼした。1983年にはすでに、村上春樹の長編『ダンス・ダンス・ダンス』で、ウォークマンを持つユキという13歳の少女が登場している。80年代の新たな価値観を描いた本作で、恋愛や友達作りなどよりも「音楽聴いてる方が楽しい」とユキは言う(この時期、『AKIRA』や歌手・尾崎豊などにも若者のアナーキーな新秩序の世界観が見出される)。
(追記:『ダンス・ダンス・ダンス』では、先の項目と関連する、世間からのイメージに塗り固められ、虚像としての人生しか歩めぬ苦悩を抱える若き俳優の姿も描かれている。)
音楽それ自体は魂の外側への発散だが、聴く側にとっては必ずしもそうではない。音楽を聴く行為は、外界を遮断する役割も担う。ウォークマンで音楽が持ち歩く物になったことで、その傾向は一層強まる。家の外にいながらも、イヤホンやヘッドホンで耳を塞ぐ若者の姿は、彼らの内向性のシンボルとして、多くの作品に描かれることになる。偶然にも、それはこの試論で取り扱ってきたいくつかの作品の主人公にも該当する。
寝床でもカセットプレイヤーを手放せない碇シンジ。

CDウォークマンでリリイ・シュシュの曲を持ち歩く雄一。

『海辺のカフカ』の田村カフカも、「録音のできるソニーのMDウォークマン」を常に持ち歩いている。
では、『フリクリ』で音楽はいかに扱われたか。
まず、ナオ太が音楽を聴いているシーンは存在しない。若者の内向性のシンボルとしての音楽は、『フリクリ』の劇中からは徹底的に排除されているのである。

しかし、音楽的な要素自体はかなり色濃い。音楽に光宗信吉とロックバンドthe pillowsを迎え入れた本作は、OPがない代わりに劇中でボーカルが流れ、また、ご機嫌なベースやドラムの重低音が物語を彩る。ギターが登場人物のアイテムとして登場するのも象徴的だ。このことは、この作品自体が一つの音楽であることの表れである。
そして、「音楽で魂を守る内向的な若者」の役割は、視聴者に割り振られることになる。この「音を奏でる者」とそれを「聴く者」という関係が、長年にわたって『フリクリ』とそのファンの間の世界を、一つの空間として完結させてきた主要因であることは、ここまで来れば明白である。(完)
・第5話次回予告に登場するその他キーワードの一部
flimsy claim n.冷やかし半分の苦情.悪質な苦情の常習者.
flight'y clip'per n.1 快速帆船. 2 軽率な人.不似合いな職業についた人の蔑称.
flint cleaver n.打製石器の一種.肉裂き包丁.
・『チェンソーマン』第二部は2022年初夏、ジャンプ+にて連載予定。TVアニメは2022年、MAPPA制作で放送予定。
・『リリイ・シュシュのすべて』に登場する歌手リリイ・シュシュのCDアルバム『呼吸』は実際に販売されている。
・2018年、the pillowsの山中さわお氏は『フリクリ』について当時「本当に意味がわからなかった」「『この作品に意味を求めちゃいけない』って思うようになりました」と述懐している。
