
政治・経済、現代文、英語で大学を受験して、本当に良かったと思う
いきなりですが、私が大学を受験したときに使った科目は「政治・経済」「現代文」「英語」です。これが、本当に良かったという話を、今日はしたいと思います。
1:なぜ、良かったのか
いきなり結論から言いましょう。なぜこの3科目で受験をしたとこが良かったのか。それは、大学入学後の学びにすごく活きてきたからです。
さらに言うと、大学を卒業後、社会人になってからの学びにもバシバシ効いています。
例えば、大学に入ると、たくさんの文献に触れることになります。私の場合はキャリアデザイン学部というところでしたので、キャリアカウンセリングの専門書や、社会学の専門書に触れる機会がありました。
そんなとき、専門書は難しいな…と避けがちになるところですが、高校時代に現代文で慣れておけば、大学で学びやすくなるのです。
難しそうでも、思いきって格闘しながら読んでみると、色々な学び・気づきがあるものです。
さらに私はいま社会人で、個人的な興味から株式投資や不動産投資の学習をしているのですが、ここでは、政治・経済の基礎知識が活きてきます。
実は、高校生の科目でも、大学受験レベルになると、それなりの知識を要求されます。ケインズや、ピケティ、シュンペーターやマクロ経済スライドなどの用語をカバーしています。(興味のある方は調べてみてください)
2:受験勉強とはかくあるべき(だが…)
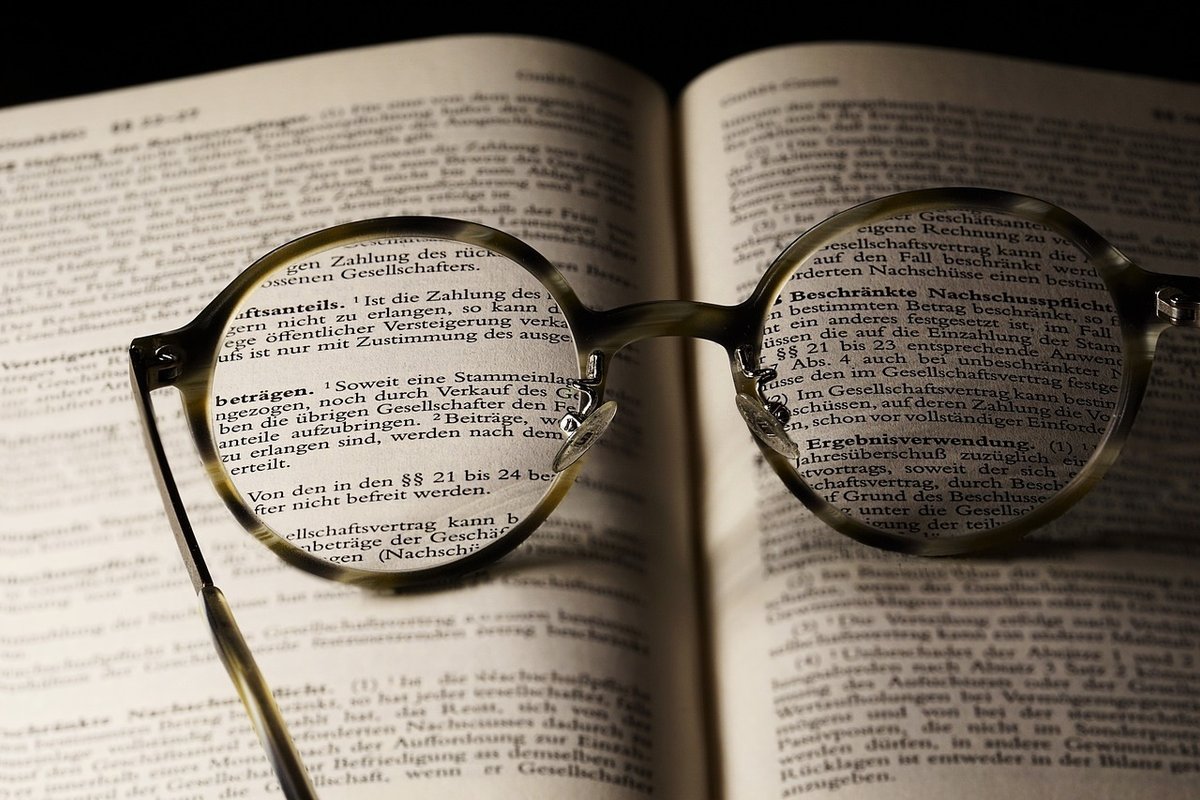
私は前々から思っているのですが、大学入試の問題は、その後の学習で使うことを出題すべきです。文系学部で、化学や数学をほとんど使わないのに、入試科目でそれを問うのはナンセンスです。
いま述べた、私が入試で使った科目は、もれなく、その後の私の学習・人生で活きています。そういうことを、入試のために勉強すべきではありませんか。
入試のためだけに勉強するのではなく、入試のために勉強したことが、その後の人生にもそのまま活きるのが理想です。
ですが、現実はなかなかそうなっていない。それどころか、私が所属していた高校では「政治・経済」を履修することができなかったのです。詳しくは忘れましたが、社会科は「世界史」と「地理」を必修で選択する必要があり、それを選択すると「政治・経済」を履修できないような仕組みになっていたのかな。
選択科目くらい、自由に選ばせてほしいものです。
3:将来を見据えた人生設計

ではなぜ、私は「政治・経済」を受験で使ったかというと、高校2年生から3年生になるタイミングで、通信制高校に転校したからです。
通信制高校は、通いの高校よりも、カリキュラムの自由度が高いです。そのため、私はすでに取り終わった単位を除いて、自由に取りたい科目を履修しました。
私立文系学部に行くのに、数学や化学・生物の上級科目を履修するのはナンセンスです。理系科目は最小限で、難易度を落とし、文系科目を中心にした履修をしました。
こうした計画は、すべて意図的に計画したことです。高校での学びが、そのまま大学の学びや将来に活かせるようにしたところ、すごく良かったという話を、今日はしました。
人生をデザインしましょう。方法は、色々とあるものです。
関連記事↓
いいなと思ったら応援しよう!

