
晩秋の吉野山1 下千本~大駐車場から蔵王堂まで
11月7日は立冬です。
なので、昨日(11月6日)訪れた吉野山に、桜の花はありません。また、紅葉にもちと早かった。
本記事は、そんな何もない吉野山の「下千本(しもせんぼん)」界隈のリポートです。(以前にも同じような記事投稿したかも)
歩いたコースは、題にあるとおり、「大駐車場(観光駐車場)から金峯山寺蔵王堂まで」の約一キロ。そそくさ行けば徒歩二十数分の道程です。
が、今回は、観光拠点の蔵王堂まで、まっすぐすたこら行かないで、横道に迷うことを楽しみとしました。
「へえ~こんななんだ」
と思える新鮮な景を探して。
以下、写真で綴る晩秋の下千本界隈です。





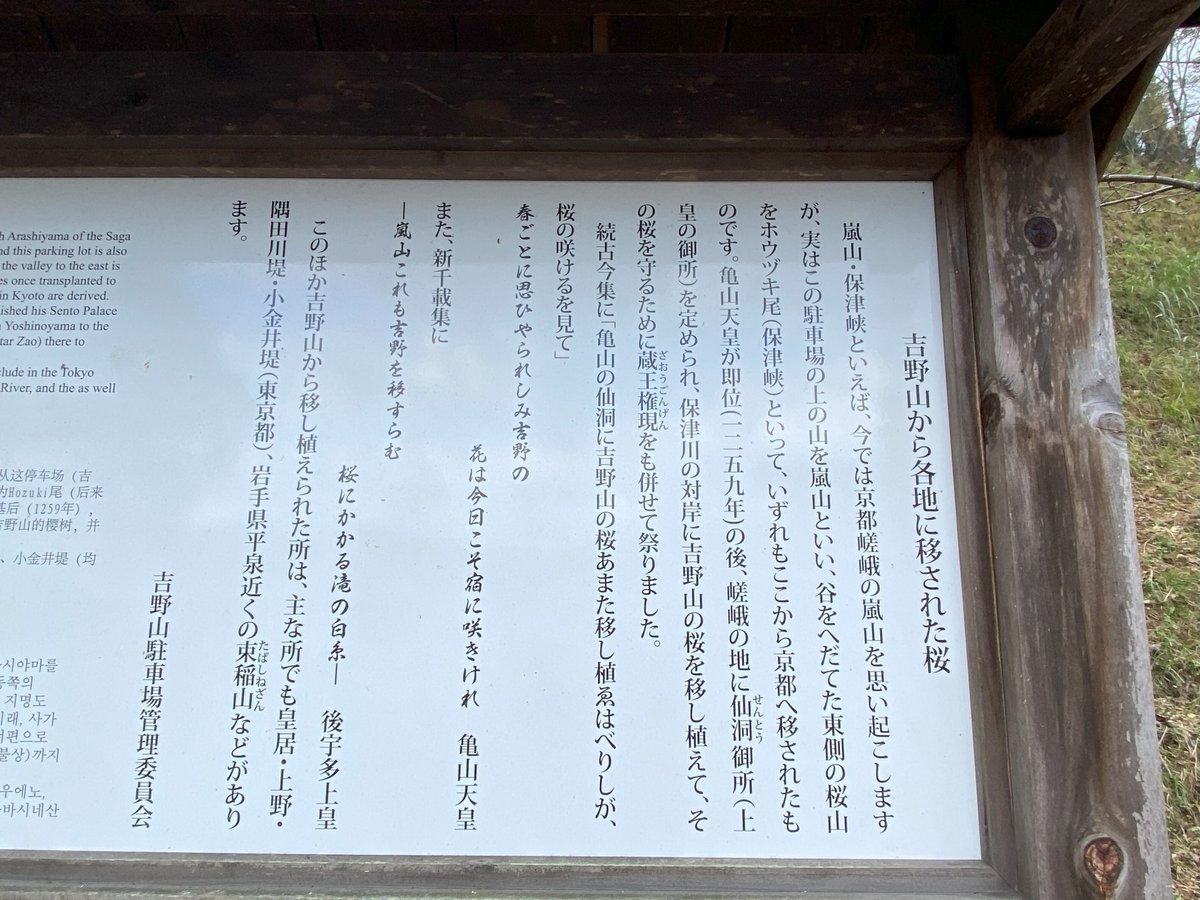



















































歩く道のその先に、巨大な覆屋が見えてきました。二王門です。
国宝・金峯山寺二王門保存修理工事が行われているのです。令和十年度竣工予定だそうです。
覆屋の中に二王門。その向こうに、見えませんが国宝・蔵王堂があります。


国宝・蔵王堂の「日本最大 秘仏本尊 特別ご開帳」のリポートは次の記事にて。
つづく。
2024.11.7(訪れた日2024.11.6)
