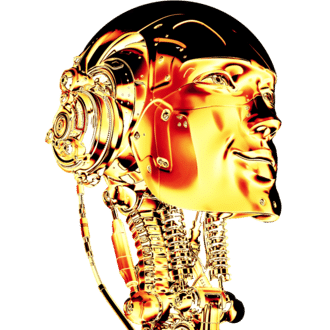テクノロジー「親父ギャグ効果」

【おやじギャグの文化】
おじさんのとっておやじギャグは
若者との会話のきっかけを作る
おやじ特別な切込みなのですが
逆にダメージを与える事が多いです
でも世界中でおやじギャグがあり
ユーモアの1つとしての文化を築き
おやじギャクの専門書まであって
ギャグとして認識されてます
ギャグとして成り立ってる訳は
正しい言葉や意味の規律を破り
常識的な解釈と違う意味を持たせ
意外な言葉にしてるからです。
例えば
1つの文で2つの意味を持たせる
「この金おっかね~」と言うのは
常識的な解釈と違う解釈になります
普通1つの言葉に1つの意味を持たせ
言葉や文を作るのですがこの場合
1つの言葉に2つの意味があるので
そのままの解釈じゃなくなります。
しかもギャグが面白いという
ギャグの掟の規律違反すら犯し
精神的ダメージを負わせる物が
おやじギャグになってしまうのです
さらにおやじギャグを極めし者は
つまらなさ過ぎて笑いを取り
ここまでくれば職人芸として
おやじギャグを言っても大丈夫です

〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓
【ギャグの特訓】
おやじギャグが相手に
ダメージを与えてしまう事は
本人もよく解っていて
その上でおやじギャグを言います
その理由は
大昔から続く進化の過程上の本能で
経験が浅い若者に対し試練を与え
強くしようとする本能なのです。
そうする事により
子孫を残せる確率を上げ
長く生き続けられる経験を積ませ
精神を向上させようとするのです
ここ数年の研究では
おやじギャグに対し子供が
どう反応して良いか困らせる
試練を与えてると言います。
更に父親の授業参観のとき父親が
みんなの前でおやじギャグを言うと
その子が恥ずかしい気持ちにり
精神的ダメージを食らいます。
子供に恥ずかしい思いをさせて
それに慣れさせ恥ずかしがらずに
素直になんでも言える精神を
身に着ける特訓だと言います。
そして精神の回復力を高め
ネガティブな感情に負けない様に
感情のコントロールをさせ
すぐ立ち直れるようにしてるのです

〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓
【教育】
デンマークのオーフス大学が行った
今回の研究で父親の役目を
「子供をわざと困らせてやる事は
親の大切な役割の1つです」
「具体的に言えば伝統的に
恥ずかしい事を子供が見ても
恥ずかしさを感じなくなるまで
徹底してやることが重要です」
要約すると多分父親の役目は
いつも子供の前で恥ずかしがらず
明るく真剣に素直に振舞って
子供と本音で接しろという事です。
更に研究者たちは
「何年にも誰の目も気にせず
目を疑うような恥ずかしい
ユーモアに触れさせてください」
「そうすれば子供は
恥ずかしさに免疫がつき
恥ずかしさに怖らず自分らしい
生きる力が湧きます」と述べます。
おやじギャグがつまらない原因は
古臭さと安直さと作りのセンスが
とても単純で解りやすいので
知的を感じないからだと言います
でも子供の時聞いたおやじギャグを
今で覚えてる人が多い理由は
当時こんなギャグでもすごく面白て
爆笑してた事があるからです。

いいなと思ったら応援しよう!