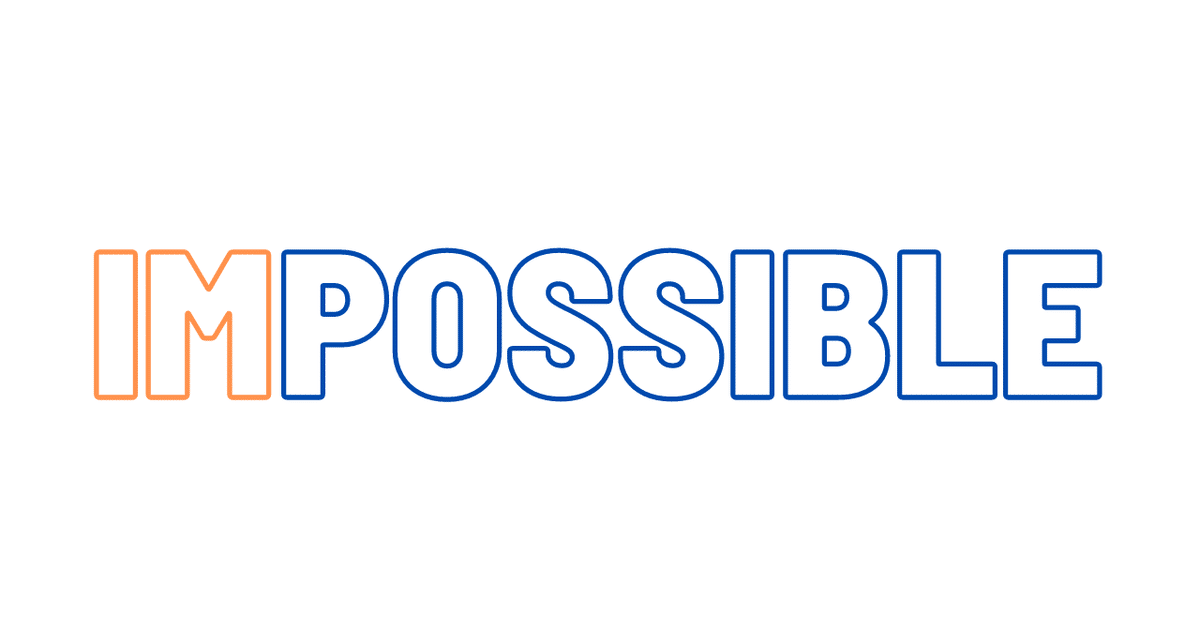
できっこないをやらなくちゃ
先日、不登校の生徒さんたちと対面授業を行ってきました。
ここでは6月から週一回授業を行っていて、授業を経て元素周期表の元素たちを覚えたり、中学生の範囲ではないですが原子量と分子量を計算できるようになったり、化学反応式を完成させられるようになりました。
折角、原子量と分子量の計算ができるようになったので、自分が好きな実験を提案してみると生徒さんたちは快諾してくれました。
その実験は「気体を可視化」するというものです。
空気を可視化するって一見すると難しいですよね。
不可能なことのように思えます。
水の中に入れても気泡として確認できますが、今回は空気中で可視化します。
風船を使うのもひとつの手かと思います。
ただ、風船のゴムの部分の質量が意外とあるので、もう少し軽いもので可視化したいです。
そうなってくると気体を可視化するために何が良いか。
自分が行き着いた暫定ベストな方法はシャボン玉をその気体で作ることでした。
見える化の大切な部分も伝えられるので、自分の中では鉄板の実験なので使い古しています。
酸素、窒素、水素、二酸化炭素のスプレー缶があるのでそれらにストローのようなアタッチメントをつけて、先端をシャボン液につけてシャボン玉を作って可視化します。

シャボン液に浸していきます。
空気より軽ければシャボン玉は上に行き、空気より重ければシャボン玉は下に行きます。

この実験は分かりやすくて楽しいのでおすすめです。
空気の分子量はざっくりと窒素が80%、酸素が20%として計算すると28.8ぐらいになります。
従ってそれぞれの気体の分子量が28.8を境に上がる下がるが決まってきます。
水素分子の分子量は1×2 = 2
窒素分子の分子量は14×2 = 28
酸素分子の分子量は16 × 2 = 32
二酸化炭素の分子量は12 + (16 × 2) = 44
水素でシャボン玉を作ると「ふわっー」と上に上がっていきます。
窒素は分子量28なのですがシャボン液の分、質量が加算されているのでゆっくり落ちていきます。
酸素は分子量32なので、スーッと落ちていきます。
二酸化炭素は分子量44で他の気体と比べるとかなりの速さで落ちていきます。
割れにくいシャボン玉液の配合(今回は水:洗濯糊:洗剤:グリセリンを使いました。ガムシロップ入れてもいいのですが、ベトベトになるのでやめました。)や注意事項は黒板で共有し、
「この部屋にあるものをなんでも使っていいので、今日のテーマについて調べていってください」と伝えました。
「そう言われましても・・・」そんな感じで一部の生徒さんは戸惑っていました。
レールが敷かれたところを進むことに関しては得意な人が多いのですが、いざレールがなくなった時に自分で考えて行動していくことに自信をもてていない生徒さんが多いと感じています。
それがもし「自分で考えて選ぶ機会が少なかった」ことが原因だとしたら、理科の勉強の中で「自分で考えてる選ぶ機会」を増やすことは生徒さんの役に立つのではないかなと感じてこんなことをしています。
理科だけで全てを解決することはできないと思いますが、少しでも機会を提供できるならこんなにやりがいのあることはないなと感じます。
この内容も生徒さんにお話して、「失敗しても全部こちらで対応するから思い切りやってみて」と話をすると覚悟が決まっていくというか、顔が変わっていくんですよね。
「じゃあやってみようかな」
好奇心の強い生徒さんは「早く動きたい」と思っている感じがひしひしと伝わってきます。
そしていざ動き始めてしまえばあとは夢中で実験に取り組んでくれます。
この回は全員真剣に取り組んでくれていました。
「失敗を怖がらずにチャレンジできる環境」はやっぱり成長になくてはならないものだなと改めて生徒さんたちに教えてもらっています。
できることが増えるのはいくつになっても楽しいものなので、そこの部分を刺激しつつ、生徒さんの成長をサポートしていければと思っています。
「チコちゃんに叱られる」で、子どもが走り回るのは「早く育ちたいから」という回があったのですが、それをみてやっぱり子どもって本能的に「成長したい」とか「できることを増やしたい」という想いがどこかにあるんだろうなと感じました。
自分の実力で引っ張り上げるなんて大それた事は思わず、元々心の奥底にあるその部分をうまく刺激していきたいなと思います。
「人が成長する場面」はやっぱり何回見ても嬉しいですし、この仕事の醍醐味だなと感じます。
今日も生徒さんに気付きをいただけました。
感謝です。
最後までご覧になって頂き、ありがとうございました!
いいなと思ったら応援しよう!

