
センスは知識からはじまる
1.問題意識
今日の毎日投稿は、クリエティブディレクターの水野学氏の本でである『センスは知識からはじまる』を読んで考えたことを記事にしたいと思います。水野学氏がどんな人物であるのかについては、前の記事を参考にしてください。
問題意識:センスとは何か。センスをどう磨くか。
2.調査

本書のもくじ
第1章 センスとは何かを定義する
第2章 「センスのよさ」が、スキルとして求められている時代
第3章 「センス」とは「知識」からはじまる
第4章 「センス」で、仕事を最適化する
第5章 「センス」を磨き、仕事力を向上させる
(1)センスとは何か



(2)「へぇー」を見つけることにヒットが隠れている
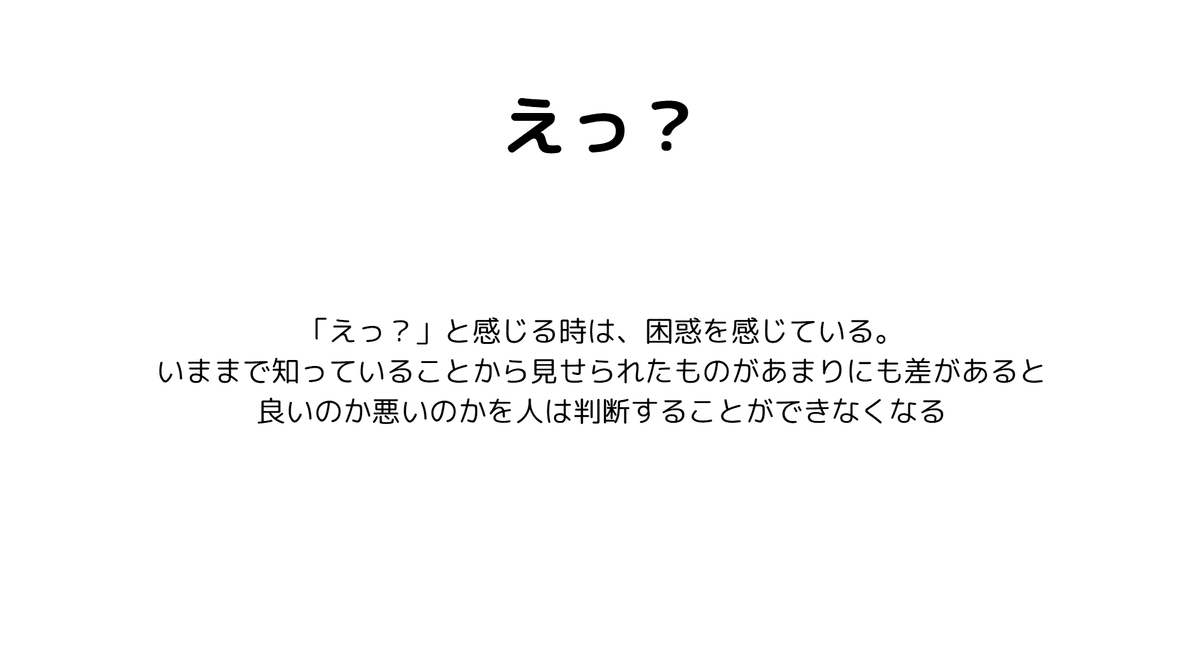


(3)効率良く知識を増やす方法


(4)デザインを構成する要素

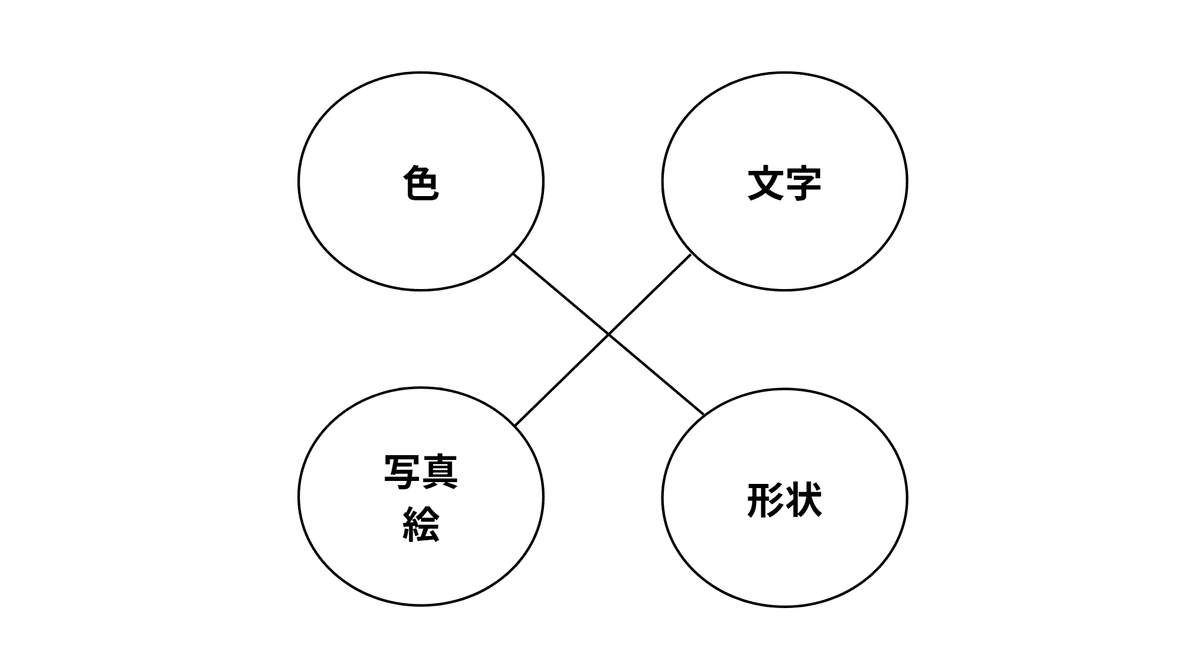
(5)クリエイティブ活動の7段階

アウトプットとしての制作物を出す前に、王道から調べる。流行を調べて共通項を調べる。普通を知ることで、疑問を抱き、仮説を導き出す。仮説に基づき、新しい制作物に対するプロトタイプを制作し、顧客の反応を見て検証する。結論としての制作物を繰り返しアウトプットし続けて、精度の高い花を咲かせれるようにしていく。

出典:グッドデザインカンパニーHP

水野学氏のクリエイティブ活動と、末永氏のアート思考による「アートの植物」に同一性を見出した。そのため、図解化してみました。

出典:https://note.com/yuru2creative/n/n83a4826e4d74
<まとめ>
・企画とは、アイディアではなく「精度」こそが重要なんだよ。(5頁)
・センスのよさとは、数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力である(19頁)
・センスとは知識の集積である。これが僕の答えです。(74頁)
・センスのよさとはミステリアスなものでもないし、特別な人だけに備わった才能でもありません。方法を知って、やるべきことをやり、必要な時間をかければ、誰でも手に入るものです。(7頁)
・斬新なものを生み出した場合、たとえ成功するとしても、それには相当な時間がかかることを理解し、長期的な視野を持つことが必要です。(50頁)
・今の時代は、「美意識」と「センス」が企業価値になる。(62頁)
・どんなにいい仕事をしていても、どんなに便利なものを生みだしていたとしても、見え方のコントロールができていなければ、その商品はまったく人の心に響きません。(70頁)
・センスに自身がない人は、自分がいかに情報を集めていないか、自分が持っている客観情報がいかに少ないかを、まず自覚しましょう。(95頁)
3.考察
本書は思考法の本である
本書を読んだ時に感じたのは、本書は「思考法」に分類される本だということです。また、デザインやセンスというものに対する向き合い方・考え方について記載がなされている本でした。水野氏の経歴を見ていると、美術大学を卒業した社会人経験(サラリーマン経験)を数年しますが、すぐにやめて独立して、デザイナーとしての人生を歩む形になります。本書は、2014年に出版され、水野氏は、当時41歳であると記載されていますが、「美意識・センス・デザイン・クリティブ」というものに対して、これまでとことん考えて言語化そして可視化されてきたのだと感じました。それほど、いままで、「センスとは何か」や「センスを磨くためにはどうすれば良いか」はたまた、「クリエイティブディレクターとはどんな存在か」などを言語化されている本であると感じました。約180頁ほどの図解も何もされていない本ですが、思考の過程などがイメージできるような本でした。
プレゼンのセンス
水野学氏は、お客さんに対してプレゼンを行うときに、汎用的なプレゼンのテンプレート資料を使用しないようです。紙芝居のように極力シンプルに伝えたい内容のみを1ページに数行の文章が書いてあるだけの数枚のスライド資料に落とし込んで提案を行うようです。ときには、「手紙」のように、ときには、「紙芝居」のように、ときには、「絵本」のようにして提案を行うようです。本記事では、その水野氏のスタイルを参考にして、記事の作成を試みました。また、多摩デザインスクールのプログラムにて、講師がプレゼンする際にも、そのプレゼン資料はどこか水野氏がデザインのプレゼンを行っているときと同じような「共通項」を見つけました。それは、通常の会社などのプレゼン資料などであれば、タイトルがあり、目次があり、出典があり、などなど、情報がてんこ盛りですが、二つに共通するのは、1枚のスライドに1つの情報のみ。後の情報は、話し手がその情景や意味をいイメージしてもらうように、聞き手の方を見て話しているということでした。これは僕としては、大きな発見でした。
4.新しい問題意識
水野氏が独立研究科の山口周さんと共著で書いた『世界観をつくる』という本があるようである。次は、これを読んでみたい!

いいなと思ったら応援しよう!

