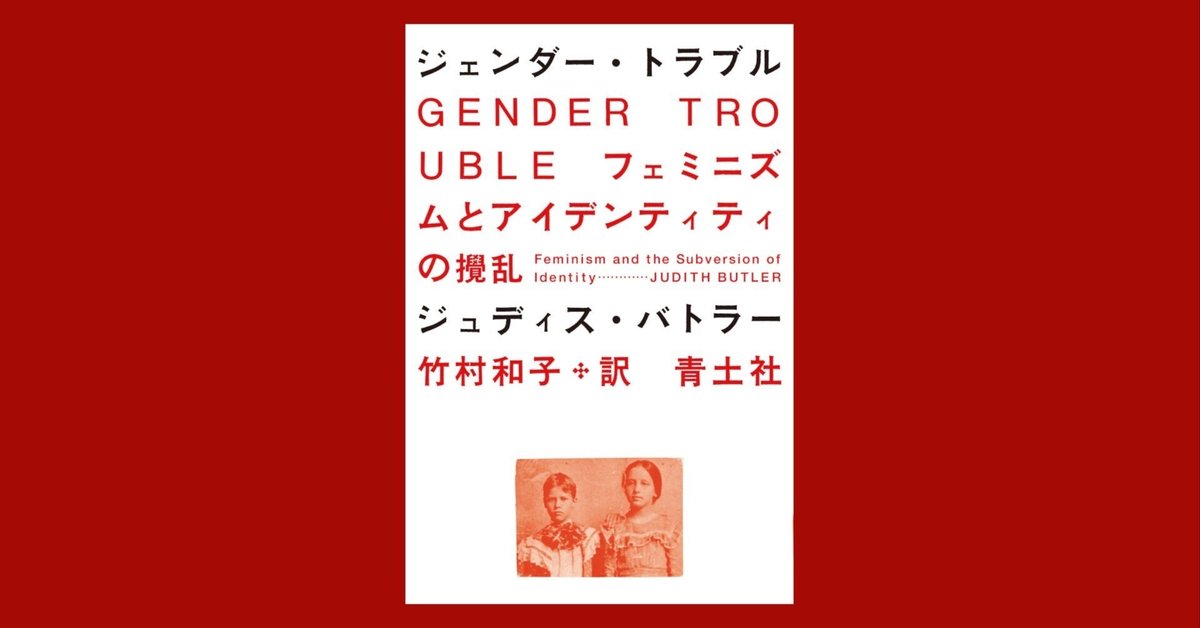
精読「ジェンダー・トラブル」#025 第1章-5 p45
※ 全体の目次はこちらです。
今回から第1章「〈セックス/ジェンダー/欲望〉の主体」の「五 アイデンティティ、セックス、実体の形而上学」を1ページずつ精読していきます。
またアイデンティティは自己同一的で、時を超えてつねに同じで、統一されていて、内的首尾一貫性を備えたものだという前提を基礎づけているものは、何だろう。さらに重要なことだが、こういった仮定はどのように、「ジェンダー・アイデンティティ」についての言説を特徴づけているのか。
アイデンティティと言えば、どうしてみな、それが揺るぎないものだと考えるのでしょうか。
〈揺るぎないものをアイデンティティと呼ぶのだ〉という人もいるでしょう。ですが、あなたであることの証がどうして揺るぎないものである必要があるでしょうか。
このような〈アイデンティティ=揺るぎない〉という「仮定」を置くことで、カッコつきの(つまり法的なものとしての)「ジェンダー・アイデンティティ」ーーひとが男もしくは女であることーーもまた揺るぎないものとなります。一瞬たりとも、男が女らしくなったり、女が男らしくなったりはしないのです。
このような前提は、どのようにして可能となっているのでしょうか。
また、〈ひとが男もしくは女であること〉がその人にとって揺るぎなくなるとき、法構造が生み出さす言説にはどのような特徴が生じてくるのしょうか。
「ひと」が理解可能となるのは、ジェンダーの理解可能性の認知可能な基準にしたがってひとがジェンダー化されるときだという理由だけで、「アイデンティティ」の議論をジェンダー・アイデンティティの議論に先行させるべきだと考えるなら、それは誤りである。
「ジェンダーの理解可能性の認知可能な基準」とは、ようはストレートの男女のことです。法構造は LGBT のような男女以外の〈その他〉の人は理解できませんし、〈その他〉の人は排除され隠蔽されるので(#003 参照)、認知できません。だから基準として残るのはストレートの男女だけとなるのです。
私たちは性別不詳の猫の姿は想像できますが、性別不詳の「ひと」の姿は想像できません。「ひと」は、その人が男か女かに「ジェンダー化」されて初めて「理解可能」になります。
これを障害物走にたとえると、男か女かという「ジェンダー・アイデンティティ」のハードルを乗り越えた先に、「ひと」の「アイデンティティ」という最終ハードルが見えてくる、と言うことができます。
性のない「ひと」を前提とする考え方にとって、あくまで本体は「ひと」であり、ジェンダーは「ひと」の属性に過ぎません。だから、重要なのは最終ハードルである「アイデンティティ」であり、「ジェンダー・アイデンティティ」ではない、となります。
「それは誤りである」とバトラーは言います。
(#026に続きます)
