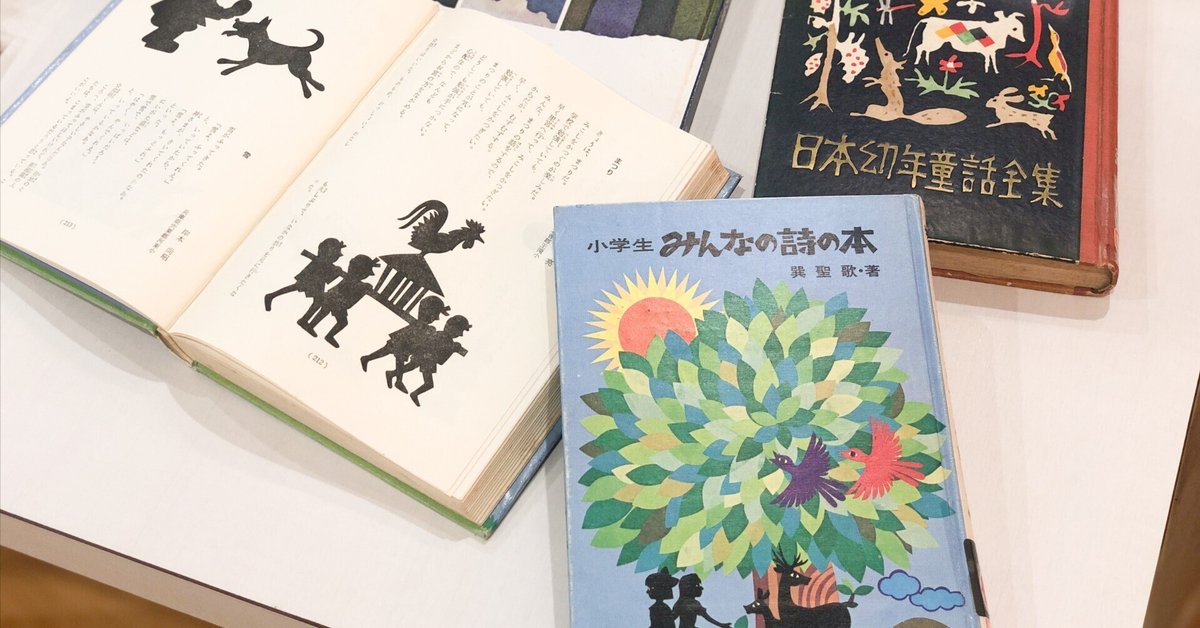
「巽聖歌」というひと ー新美南吉のために
地域の偉人というのは、「町民性」を表す顔だな、と思う。
ふるさとや郷土を知るには、その土地の偉人の人柄から学ぶと、奥行きが出る。
紫波町の名誉町民を知る、今回は「巽聖歌」編です。

♪「かきねのかきねのまがりかど
たきびだたきびだ おちばたき
あたろうか あたろうよ
きたかぜぴいぷう ふいている」♪
一度は口ずさんだことがあるでしょうか。
この童謡の歌詩を書いた方の名前は、巽聖歌(たつみせいか)。
岩手県紫波町で生まれ、
晩年は東京の日野市で過ごした紫波町の名誉町民です。
巽聖歌は、小学校しか卒業していなくて
文学の世界に何も繋がりはなかったのに
雑誌への投稿という手段だけで文学を学び
文章を磨き、作品の力を認められて世に出た人です。
北原白秋に認められるなど恵まれた出会いはありましたが
文学だけで生活して行けるようになるまでには多くの苦労がありました。
巽聖歌は自分の文学の才能を信じ大正・昭和の児童文学界で活躍。
また『ごんぎつね』などの作品で知られる新美南吉の作品を世に出すことに尽力されました。
雑誌の投稿から詩人の道へ
巽聖歌は、岩手県紫波郡日詰町に、7人兄弟の末っ子として誕生。
幼くして父親を亡くした聖歌は、日詰尋常小学校を卒業したあと
中学校に行くことができず、鍛冶屋で働きます。
文学への強い興味を持っていた聖歌は『少年』という雑誌を愛読し、
作文や童謡などを書いて投稿しましたが、なかなか雑誌には採用されません。しかし16歳のときにはじめて作文が優秀賞に選ばれ、文学の世界で仕事をしたいという夢を持つように。
18歳の時には自作の童話を、『少年』を出版していた時事新報社に送り、就職を依頼。一度は入社を認められ、それを頼りに上京するも、若すぎるということで見送りになってしまう。(作品があまりに大人びていたので、まさか18歳が書いたものと思われなかったらしい)

実際に時事新報社で働き始められたのはそこから3年後のことでした。
長年の憧れ『少年』の編集部で働きはじめ夢に向かって一歩を踏み出してまもなく会社の経営不振をきっかけに、聖歌は20歳のときにふるさと・日詰へ戻ることとなります。
失意の中、聖歌はふるさとで、7月のある日に、田んぼの水の取り入れ口にいるオタマジャクシを見て「水口(みなくち)」という童謡を作ります。
「野ぜりが 咲く田の みなくち
蛙の こどもら かえろよ
尾をとる 相談 つきせず
あかねの 雲うく みなくち」
その作品は、日本を代表する詩人・北原白秋に絶賛され、聖歌は童謡詩人として名前を知られるようになりました。
童謡詩人として駆け出すきっかけとなったのが、今でも紫波町の至る所で
見られる初夏の風景だったのです。

その後は生きていくためにさまざまな仕事を経て、北原白秋の弟 北原鐡雄が経営する出版社に就職。働きながら精力的に文学活動を続けるうち、童話作家となる新美南吉(にいみなんきち)と出会ったのは、聖歌が26歳の頃でした。
新美南吉と巽聖歌
巽聖歌を語る上で欠かせないのは、『ごんぎつね』『手ぶくろを買いに』などの名作で知られる童話作家・新美南吉。

中でも『ごんぎつね』を、小学校の国語の教科書で読んだことのある方は多いのではないでしょうか。『ごんぎつね』が掲載され、日本中の子どもたちに読まれるようになった立役者が巽聖歌なのです。
受験のため上京した新美南吉は東京・下北沢にあった巽聖歌の下宿を訪ねます。8歳差ながら二人はすぐに仲良くなり、お互いを兄弟のように慕いました。
聖歌は南吉に東京外国語学校の受験を薦め、無事入学を果たした南吉は上京。聖歌の結婚を機に南吉が寮に入るまでの五ヶ月間、二人は中野区上高田で一緒に暮らしました。
南吉は身体が弱く、病気がちだったため大学卒業後、仕事にはついたものの
「喉頭結核(こうとうけっかく)」にかかり、病気が悪化し床に臥します。
そのとき聖歌夫妻は自宅に南吉を引き取って看病しました。
その後南吉は一度故郷に帰り、仕事をしたり、療養しながら創作活動も続け、体調が落ち着いた頃、愛知県安城市の女学校で、長年の念願であった
英語教師となります。四年間の幸せな教員生活では、多感な少女たちに大きな影響を与えながら、自身も多くの作品を遺しました。
しかし病気が再発したとき、南吉は聖歌に、自分の作品原稿をすべて送り
長くは生きられないので、亡くなった後のことはおまかせしたいと手紙を書きました。そして南吉は、29歳と7ヶ月の若さで他界します。
その後聖歌は、約束を果たすべく、生涯をかけ、南吉の童話集を刊行し続けます。また託された原稿のみならず形見として教え子や知人たちの
手にわたってしまった原稿や書簡などを返却してもらうため、一人一人訪ねて周りました。そうして収集した原稿も刊行し、南吉の作品が全国的に広く読まれる基礎を築きました。
聖歌が『ごんぎつね』の教科書掲載を推薦したのは、本を買ってもらえない子どもにも南吉の作品を読んでもらうことができるのではないか、という想いがありました。「日本中の子どもたちに自分の童話を読んでもらいたい」と最期の手紙に書いた南吉の願いは、聖歌の手によって見事に果たされているのです。
「中野区」と「日野市」と「紫波町」
巽聖歌の代表作となった童謡「たきび」の舞台となったのは
実は、聖歌と新美南吉が暮らした家があった中野区上高田です。
近所の鈴木さんという大きな農家のお宅のそばをたびたび通っていた聖歌は
屋敷の中の焚き火の様子を見ていたのだと思われます。
「かきねのかきねのまがりかど
たきびだたきびだ おちばたき
あたろうか あたろうよ
きたかぜぴいぷう ふいている」
歌詩に登場する「かきね」とは、紫波町でよく見られる、大きな農家の邸まわりを囲う「家垣根(いぐね)」と呼ばれる屋敷林のこと。
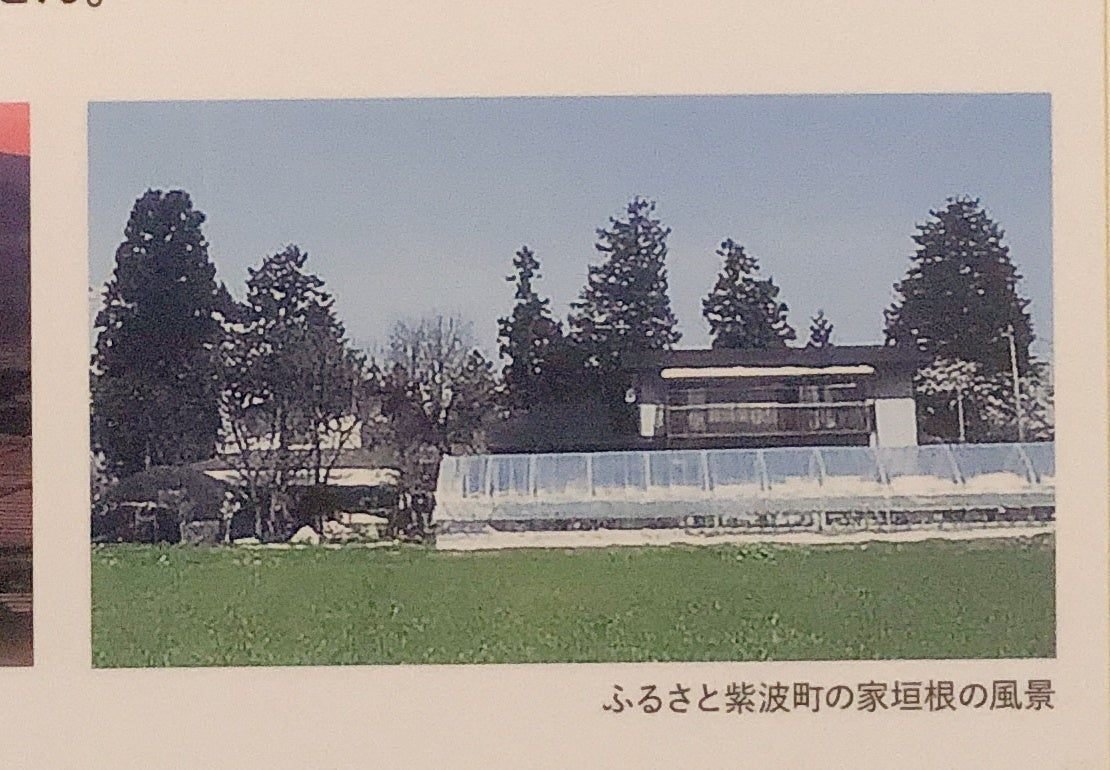
家垣根は、さまざまな植物が生い茂り、鳥や小さな生き物もいて子どもたちの遊び場でもあったそうで、聖歌にとっても懐かしいふるさとの風景が「かきねの かきねの」というフレーズに投影されています。
「北風ぴいぷう」というユニークな響きは北国の、身を切るような
冷たい風を表しているそう。
そして聖歌は、後半生の25年間を東京・日野市旭ヶ丘で過ごしました。
当時の旭ヶ丘は今よりも自然豊かな場所で聖歌は自宅の庭で野菜を育て
山羊や羊を飼って生活していたそう。
聖歌は、母校である日詰小学校をはじめ紫波町内や日野市内でも、多くの校歌の作詩を手がけています。
「たきび」はJR豊田駅の発車メロディにも採用され、毎年12月にはたきび祭が行われるなど、聖歌の作品は今もなお日野市民にも深く愛され、それぞれの地の美しい自然を多くの詩に込め残しています。巽聖歌の生誕の地である紫波町と、晩年を過ごした地である日野市は、その縁から2016年に姉妹都市となりました。
地域の偉人は、「町民性」を表す顔
昨年、放送されていた連続テレビ小説(朝ドラ)『らんまん』と関連して
紹介した名誉町民「須川長之助」。
世界的な植物学者マキシモヴィッチ博士の裏方の存在として尽力し
学名に「チョウノスキー」という名をいくつも残した人です。
植物学者でもなく農家であった長之助は、出稼ぎとしてマキシモヴィッチの死後は農業に専念し、本格的な採集旅行に出ることはありませんでした。
信頼を寄せる先生の右腕として働きながら謙虚に無名を貫いた須川長之助。
巽聖歌は晩年まで、自身の縁ある地について想いの深い詩を多く作り続けました。一方で弟のように可愛がり、早逝した新美南吉の遺した作品を、苦労しながら生涯をかけて世の中に出したその功績も、あまりに大きい。
自分自身のことだけではなく、信じた大事な人への使命感を全うするその実直さと、自分の郷土に寄せる愛のまなざしは、どこか二人に共通しているように思えるのです。
「地域の偉人」と聞くと、「なんかすごいことをした人」という認識でそれ以上を知る機会がないことも多いのですが。誰か一人の人生を知るってすごく面白いことだなとつくづく思います。

一般企画展示「詩人 巽聖歌 紫波町と日野市の架け橋」
展示期間 2023/12/1(金)~2024/1/30(火)
「たきび」の作詞家で知られ名誉町民である巽聖歌。没後50年にあたり、詩人として歩んだ足跡や関係者からのインタビューを本と合わせて紹介します。
そしてこの時代の出版物の装丁の美しさ、可愛さよ。豊かな時代だなぁ。

いいなと思ったら応援しよう!

