
34 春風亭小朝の芝浜
34 春風亭小朝 芝浜㊤
-------------------
「え――ッ! これって夢!?」
ボクは思わず、その落語家の姿を二度見した。
2017年7月17日──。
CBC『ゴゴスマ』の生放送へ向かう新幹線の車内での噺。
この日は、新刊『藝人春秋2』の上下巻、その長編のラスト、あとがきの推敲を重ねていた。その題は「芝浜」。
この立川談志師匠の十八番を巡り、泰葉と談志が最期に奏でた秘話を描いていた。
しかし、今から半年前と言えば、前代未聞の自家製ゴシップ告発ユーチューバー・松居一代と共に、海老名家告発ブロガー・泰葉からも目が離せなくなっていた時期だった。
泰葉、イラン人と交際――。
入稿前のこの急展開をどこまで本に反映するのか大いに悩んでいた。
程なく列車は山手線の〝芝浜〟新駅の工事現場を過ぎ品川駅へと到着すると通路を挟んだボクの隣にでっぷりとした男が座った。
ボーダーシャツにダメージジーンズという若々しい装い。
しかし刺繍の入った派手なキャップの下からのぞく金髪で、すぐにそれが春風亭小朝師匠だと気が付いた。
何たる偶然だろうか! たった今〝金髪豚野郎〟と原稿に書いたばかりだ。
ご挨拶しようと席を立ちかけた時、師匠もボクに気が付き、
「あー!! どうもこれは……」
と、ニコリと会釈して下さった。
「御無沙汰しております!」
次の瞬間、推敲の過程で抱いた師匠への非礼が頭をよぎりボクは通路に中腰になり、改めて話し掛けた。
「師匠、失礼ですが、私(わたくし)今、御迷惑をかけておりませんか?」
「ん?……それは何の話かしら?」
師匠が目をパチクリさせる。
「泰葉さんについて……」
「あらー、そちらにまで何か御迷惑をお掛けしておりますか?」
「いえ、今は連絡を取っていませんが、彼女が快復されてから、しばらくは親しくしておりまして……」
「では、何かお被害が?」
「いえ、それはありません……。
が、現状、ボクは不介入でして、ましてや師匠のお立場も考えておりますと、なにかと申し訳なく……」
ここまでで、話を聞く師匠の表情のニュアンスで「皆まで言うな」という圧を感じ、話を打ち切って自席に戻った。
その後、師匠は雑誌に目を通すとイヤホンを付け目を閉じた。
ボクも執筆作業に戻ったが、後日、本が世に出た際、人伝てにこの本の泰葉と談志の話が小朝師匠の耳に届くような仁義が後先になる事態は避けたかった。
師匠の隣席の女性が降りた瞬間を見計らい、意を決してパソコンを持ち、再び中腰で近づいた。
「少々お時間下さい。師匠に前もってお話ししたいことがあります」
「どうぞどうぞ、お話ください」
「かいつまんで申し上げますが……。今、『藝人春秋2』という本を書いておりまして、その最後は『芝浜』と題して晩年の談志師匠と泰葉さんについて触れております」
「へー! そう。それは(泰葉に)会ってお書きになっているの?」
「以前にお会いして、お話は直接、泰葉さん本人からお聞きしました」
「何についての話を?」
「お亡くなりになる間際の談志師匠が泰葉さんを呼んで『芝浜』を演じる話を……。で、小朝師匠も少し出てきます。実はその原稿がこのパソコンにありまして、ご迷惑でなければ、事前に読んで頂きたいんです」
あまりにも唐突な申し出に師匠は目を細めてボクを凝視し、
「出版前の原稿を私が読むことまでは及びません。どうぞ何でも、ご自由にお書きになって下さい。今回の騒動の件に関しても私の方では一切のコメントを出しておりませんし、今後もその予定はありません」
と淡々と答えた。
そして一転、人懐っこい笑みを浮かべ、小声で「宜しければ、こちらへお座りになりません?」と、ボクを空いた隣席へと招いてくれた。
「ということは、貴方は談志師匠のお話を書くのね……。もうすぐ亡くなられて七回忌ですね。私も師匠には大変可愛がって頂きました。亡くなられた後、ご遺族やお弟子さん、それぞれに想い出話があり、皆さんがそれぞれにお書きになっている」
「ボクも読んでいます。それぞれの談志像に違いがあるんですね」
「そう。それも、人それぞれの解釈です。
師匠はふたりきりで話す時と、大勢の前で話す時では別人でした。人を見て話を使い分けていらした。ひとりひとりに談志という魔法をかけていらっしゃったと思うの。だから一概には言えないんです。このことは、落語界の外部の人にはなかなか分からないでしょうし……」
生前も逝去後も、この世に数多くの関連本が出版されたことが物語るように立川談志とは多面的で矛盾撞着の存在である。
しかし、こと立川談志について最も多くの本を著した人物は誰あろう立川談志本人でもあった。
「師匠は晩年に自慢できる弟子ができて嬉しかったと思いますよ」
「志の輔、談春、志らく、皆、大看板になりましたよねー」
「ただ、私としては少しばかり不満があります。なぜなら立川流創設前の高弟たちも頑張っていましたから。師匠のお言葉を汲む者も、また師匠の振る舞いに翻弄された人もそれぞれですが……ま、これも何かの縁です。水道橋さんに私が知っている談志師匠についてお話ししますね。しばらくお聞きになって下さい」
そう言うと、小朝師匠は高座に上がるが如く新幹線のシートに深く座り直し、薄目を開け往時を思い浮かべるようにして語り出した。
「師匠は落語少年のような人でした。以前に師匠の同級生だった方からお話を聞いたことがあるんですねぇ。柳家小さん師匠に弟子入りする時、その方は、松岡少年(談志)から『一緒に行ってくれ』と頼まれたそうです。その方の話がイイのォ。『あいつはほんとに勉強しなかったんだよなぁ。頭はいいけど勉強は嫌いだった。それが、ある日いきなり、小さんの弟子になるから、オマエも一緒になれって言われてさ。こっちは落語なんか何一つ知らないのに、ついて来てくれって言うんだもんなぁ~』って。あの向こう気が強い談志が臆して照れて、ひとりでは行けなかったっていう少年時代のこのエピソード、私は大好きなんです。あんな師匠にもウブな時代があったんだなって。微笑ましいでしょ?」
ボクに目配せする小朝師匠。
「似たような話で……私が二つ目になりたての頃。談志師匠とふたりきりになったとき、いきなり師匠が話し始めたの。若い頃、自分がどうしたら良いか分からなくて、当時、知り合いだったテレビのプロデューサーのところへ菓子折りをもって挨拶に行ったんですって。そしたら帰り際に『坊や、こんなことしなくてもいいんだからね』って、その人に言われて涙が止まらなくなったんですって」
「鬼の目にも涙ですね」
「師匠にも、こんな修行時代があったんだなーって。それを、協会に入った頃、まだ10代で子供だった私に、わざわざ話して下さる師匠のそんな感性が素敵でしたね」
ふたりとも10代半ばで入門したからこそのお話だろう。
まるでユーチューブで独白するかのような小朝〝ひとり会〟をボクはカップルシートで独占していた。
(つづく)

(イラスト・江口寿史)
第34話 春風亭小朝 芝浜㊦
2017年7月17日──。
ボクは新幹線の車内で、品川から乗車して来た春風亭小朝師匠と会い、思い掛けない時を過ごしていた。
落語が冬の時代の1980年、春風亭小朝25歳は、36人抜きという落語協会の序列のなかで空前絶後の大抜擢で真打昇進を果たした。
あの頃、ボクは17歳だった。
NHK『600こちら情報部』で32歳の高田文夫が上野の鈴本演芸場から真打披露口上をレポートしていた姿を今でも思い出す。
協会の大抜擢に応え、天才・小朝はアイドル化し「横丁の若様」として落語界の未来と期待を一身に背負っていった。
その渦中に『THE MANZAI』にも出演。人気漫才師たちを相手に〝逆色物〟の立場で明石家さんまとコンビを組み、実に流暢な漫才を披露したこともあった。
先日の『M―1グランプリ』で審査員を務めた小朝師匠の的確な採点と批評は、過去からの実践的な見識に裏打ちされたものなのだ。
その小朝師匠の話が続く。
「実は談志師匠に稽古を付けられたのは一回だけ。それも議員会館でスーツに赤いバッジのままなの」
「談志師匠が、70年代に自民党の参議院議員だった頃の話ですね」
「そう。あの時に『品川心中』を教えてもらったのが唯一ですよ」
今日の奇縁、またも「品川」であった。
「小朝師匠、これは純粋に芸論ですが、今、ウチの殿(ビートたけし)が執筆中の本の中で、談志師匠の十八番だった『芝浜』の論評をしていまして……」
「うーん、そこねー。昔から、賛否両論がありましてね。長く談志師匠のブレーンだった日活映画の藤浦敦監督は談志のベストは二つ目時代の『大工調べ』と断言してましてね、山藤章二さんは師匠が『芝浜』をやると席を立ちましたからねー」
かつて『芝浜』の高座を聞いた石原慎太郎が歯切れの良さ〝のみ〟を誉め、同席した三木のり平は「なんで押しばっかりなのかね。引きがない、間がない」(『談志 名跡問答』扶桑社)
と言い放ち、それを聞いた談志師匠が落ち込んだという逸話もある。
一方、談志師匠も談志師匠で志ん生師匠の『芝浜』に対しては「酷いよォ…(『談志百選』講談社)
と、いつも手厳しかった。
「もちろん、世評はありの上で、観客それぞれの好みということが大前提ですよ……」
小朝師匠が大局的に論じる。
そして、その小朝師匠こそ小学生の頃に寄席で談志師匠の『芝浜』をソフトクリームが溶けるままに見入り、その後の人生を決めた人でもある。
「これは大久保のお宅で談志師匠からお聞きした話ですが、志ん朝師匠に『お前(父親の名跡)志ん生になっちゃえよ』ってある時、談志師匠が言ったそうなんです。
「志ん生襲名ですか?」
「そう。『それなら兄さん、口上に並んでくれる?』って訊き返されて『並んでやる代わりに、もっと落語上手くなれ!』って談志師匠が激励したと……いかにも師匠らしい逸話でしょ?」
二世の志ん朝よりも、この世界に無縁で飛び込んだ俺の方が落語に対する情熱が強いと、よく対抗心を口にしていた談志師匠だったが、それは期待の裏返しでもあったろう。
「その時です、私が『志ん朝師匠はどうしたらもっと上手くなるんですか?』と訊ねた途端、談志師匠が目の前のテーブルをバンと叩いて『俺だってわからねンだ!』と声を荒げたの。怒鳴った後、すぐに照れたようなグレたような顔になりましたが、その急激なテンションの上がり方は尋常ではなくて、今まで見たこともないほどでしたね」
その時の緊張感を再現する話術、それは高座さながらだった。
「談志師匠ほど芸を観察し、盗み、研究してきた方はおりませんが、本人には志ん生にも志ん朝にも敵わないことも分かっていたはずです。私も晩年のイリュージョン(談志独自の落語観)は落語から逃げているのではと思いました。ま、演者が自分で批評すると言い訳になりますし、本来、芸は演じてしまえば説明などしなくても良いはずです」
まるで自問自答しているかのように小朝が虚空を見て語る。
「確かに、小朝師匠は批評をしないタイプですね。今、ボクが書いている『藝人春秋2』は、そういう表現者の実践と批評への葛藤をテーマにしています」
小朝師匠がふと話を変えた。
「そう言えば、水道橋さん、今でもあの日のことは思い出します。貴方達と舞台で競演した時のこと……」
それは1998年6月27日に新宿シアターアプルで開催された、高田文夫50歳を祝した「文夫クン祭り」という一大イベントだ。
前座で若手の松村邦洋、春風亭昇太、浅草キッドが、それぞれモノマネ、落語、漫才を披露し、前半のトリがなんと立川談志師匠。中入り後、ビートたけし&高田文夫のトークを挟み、大トリが春風亭小朝師匠という豪華な顔ぶれだった。
この日の打ち上げでは、中野坂上の小さなカラオケスナックで談志師匠と殿が競って脱ぎ合い、全裸で触わりっこをしたのは伝説だ。
「あの時のふたりの脱ぎっぷりは、私、忘れられないですよ」
「本当に夢のような一夜でした」
「夢と言えば、まさに師匠とふたりで〝夢の寄席〟を作るって話をした時がありましてねー」
小朝師匠が懐かしそうに語る。
「根津のマンションで談志師匠と私のふたりだけ、その時、師匠が、『なぁ小朝、〝夢の寄席〟を考えてみるか』って突然言い出して。何かのチラシの裏に昼席、夜席と書き始めて『まず俺とオマエな』って。そして、何人かを書き足して……」
まるで野球やプロレスのオールスター戦を夢想する昭和の少年だ。
「『あぁ、三枝も入れてやらねぇとな。そうだ、小三治はどうする?』って師匠が聞くの。『師匠、そこはやっぱり入っていただかないと』って返すと『そうか、じゃあ入れてやるか』って無邪気に笑うんだけど、その顔がとてもチャーミングなのよ」
そう言って笑うキューピー頭の小朝師匠も実に可愛いらしかった。
その時、ボクの降車駅である名古屋駅到着のアナウンスが流れ、小朝師匠が我に返り居住まいを正した。
「ゴメンナサイねー、なんか、私、ひとりではなし続けたみたいで」
「とんでもない。師匠とふたりきりなんて夢のようでした。でも、今日のお話は『週刊文春』のボクの連載でいつか文章に……」
「どうぞお好きになさって下さい。余談ですが、その本は文藝春秋から出版されるの?」
「はい『週刊文春』の連載なので」
「そう。ご存じないでしょうけど、私、文藝春秋を作った、あの菊池寛の小説を今、連作で落語化しているんですよ。偶然すぎるわねー」
「そこにも繋がりますか! やはりボク書きます、頑張って年末までに年末に書きます!」
「年末に?どうして年末だい?」
「だって、師匠、この噺、夢ンなるといけねぇから……」
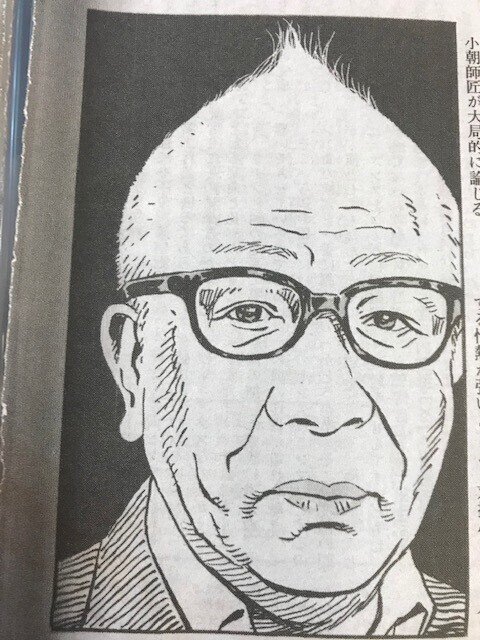
(イラスト・江口寿史)
【その後のはなし】
小朝師匠は落語家としてますます円熟味を増す一方、NHK大河ドラマでは2015年の『軍師官兵衛』で明智光秀役を演じて以来、5年ぶりに大河に再登場し、今度は明智光秀の敵役として天皇の弟の高僧・覚恕(かくじょ)を演じ、そのオドロオドロシイ怪演は「さすが!」と話題となった。
2020年、46年ぶりに誕生した山手線の新駅は「芝浜」「芝浦」「JR泉岳寺」などを推す声があがったが、結局「高輪ゲートウェイ」という最も〝粋じゃない〟名前になってしまった。しかし、僕の心の中で永遠にこの駅は、あの日の小朝師匠との語らいの思い出とともに「芝浜駅」と呼ばせてもらおう。
泰葉さんはパキスタン人の男性と交際をするなかで、イスラム教への入信を決めたと宣言したそうだ。
爆笑問題の太田光をして「彼女のパワーなら、イスラム教・シーア派、スンニ派に対抗して新しい〝ヤス派〟を作るんじゃないか!?」と洒落のめしたが、ボクとしても兎にも角にも幸せになって欲しい。
神に祈る。アーメン。
いいなと思ったら応援しよう!

