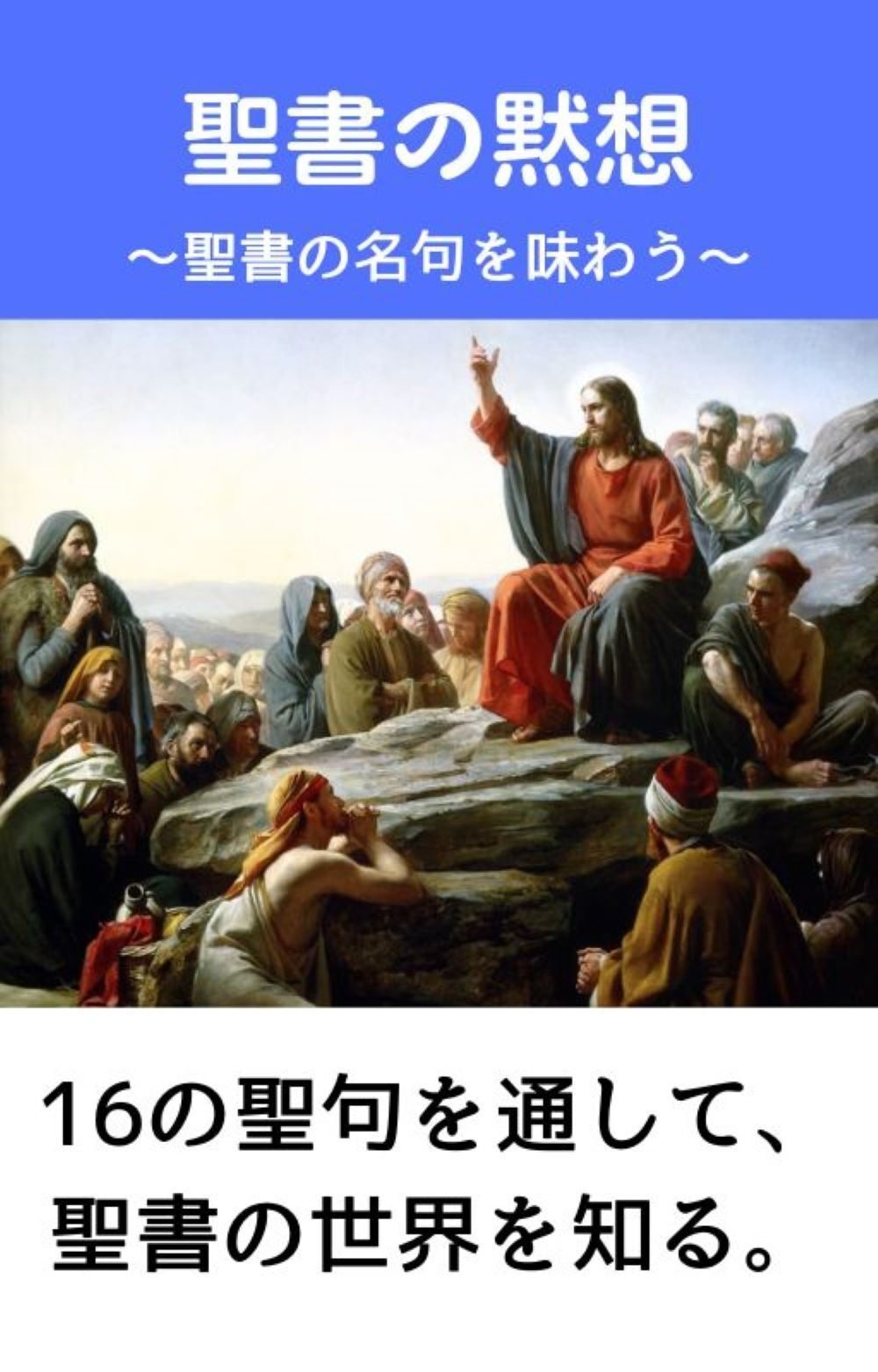ヤコブ書の精神
言語の構造
言葉には様々な次元があります。第一に,日常的に使う言葉です。こうした言葉を,日常語,あるいは,第二次言語と呼びましょう。第二に,より深い意味を表現する言葉があります。話者の思想を表現する言葉です。こうした言葉を,本質語,あるいは,第一次言語と呼びましょう。最後に,根源的な意味を表現する言葉があります。話者の思想体系の中心に位置する言葉です。こうした言葉を,根源語,あるいは,言語アラヤ識を呼びましょう。
(注)アラヤ識とは,仏教でいう無意識の領域です。すなわち,言語アラヤ識とは,無意識に根ざした根本思想という意味です。
第二次言語
日常語である第二次言語の特徴は,必ず相対する言葉が存在することです。では,ヤコブ書における第二次言語には,どんな言葉があるでしょうか?例えば,「信仰πιστις(ピスティス)」と「行為εργα(エルガ)」です。この二つの語は,因果関係にあるといえるでしょう(信仰→行為)。あるいは,「貧者πτωχος(プトーコス)」と「富者πλουσιος(プロウシオス)」です。読んで字のごとく,これらは対立する概念です。このように,日常的な第二次言語には,ほとんどの場合,対立語が存在するのです。なぜなら,これらの言葉が,相対的概念だからです。
第一次言語
では,ヤコブ書の思想の中心に位置する言語とは,一体何なのでしょうか?ヤコブ書の本質を表現する言葉には,三つあります。
第一に,「完全τελειος(テレイオス)」です。この言葉は,何らかの目標に達した状態ではなく,人間が真理に向かって前進することを意味しています。もっと具体的に言えば,行動によって,身体全体によって,律法を成就しようとする態度です(1-25,2-8,3-2)。
第二に,「律法νομος(ノモス)」です。ヤコブ書における律法とは,モーゼ律であると同時に,キリストの律法でもあります。他者の人格を守ると同時に,自己の人格を実現すること。人格的自由を重んじ,神の愛を実行によってこの世の具現化することです(1-25,2-10~12,4-11)。
第三に,「実行ποιητης(ポイエーテース)」です。実行とは,言行を一致させることであり,心の誠実さを意味しています。王陽明のいう知行合一です。神の正義の実行,キリストの御心の実践こそ,完全な人間の特徴なのです(1-22・23,1-25,2-8,4-11,5-15)。
これら三つの語は,互いに関連しています。そうです,完全・律法・実行こそ,ヤコブ書の言語世界における三位一体なのです。では,この三位一体の根底には,いかなる精神が宿されているのでしょうか?
根源語
完全・律法・実行の根底に存しているのは,ヤコブ書著者の根本精神です。その根本精神を一言で申し上げれば,「偽善を避けよ!(3-14),神に服従せよ!(4-7)」です。イエスが最も嫌った罪は,偽善でした。同じように,ヤコブ書著者が最も憎んだもの,それが偽善だったのです。罪人である人間が,自分を義人のように喧伝すること。福音を耳で聞いて口で語り合うが,決して実行しないこと。誇らしげに正論を語り,正義の物差で他者を裁くが,その物差を決して自分には適用しないこと。こういった態度を,イエスやヤコブ書著者は嫌いました。
その証左に,ヤコブ書著者が好んだ珍しい言葉があります。例えば,ヤコブ書2-9に登場する「προσωπολημπτειν(プロソーポレーンプテイン)」です。意味は,人を差別すること,分け隔てることです。また,ヤコブ書1-8と4-8に登場する「διψυχος(ディフュコス)」です。意味は,二心の者,神と富に仕える者です。さらに,ヤコブ書2-9に登場する「παραβατης(パラバテース)」です。意味は,律法の違反者です。このように,偽善を憎むヤコブの精神を理解する時,言語の意味連関組織全体が生き生きと把捉できるのです。
総括
そもそも,なぜヤコブ書は成立したのでしょうか?ヤコブ書著者は,パウロ書簡とマタイ伝の影響を受けつつ,なぜ使徒ヤコブの名を借りて文書を執筆したのでしょうか?私はこう考えています。当時,キリスト教世界には,二つの派閥がありました。「信仰至上主義をとるパウロ派」と「行為至上主義をとるマタイ派」です。パウロ派は「信じるだけで救われる」と主張し,マタイ派は「行為によって救われる」と主張しました。信仰と行為の対立です。
その時,ヤコブ書著者はこう考えたのです。信仰と行為は対立するものではない。むしろ一致すべきものだ。不誠実な者,偽善者だけが,信仰と行為を分離するのだ,と。こうして,信仰と行為を弁証法的に止揚すべく,ヤコブ書を執筆したのではないでしょうか。ヤコブ書の根底に存するのは,福音に対する誠実さ,イエス・キリストの生涯と教えに対する誠実さなのです。ヤコブ書の精神は,「至誠にして動かざるものは,未だこれ有らざるなり」と説いた吉田松陰に通ずるものがあります。

いずれにせよ,パウロ派とマタイ派の分離を統合し,信仰と行為を合一させたヤコブ。後年,そのヤコブの精神を受け継いだ者こそ,使徒ヨハネでした。ヨハネは,「愛(アガペー)」によって,信仰と行為を高次の次元で統合したのです。
聖書の内容に関する参考文献です。ご興味のある方はどうぞ。