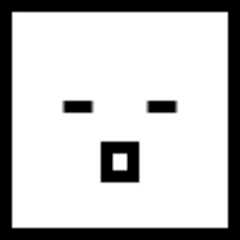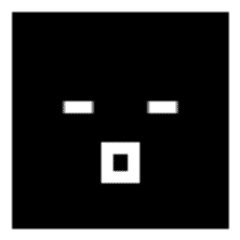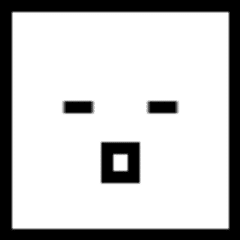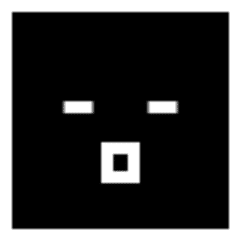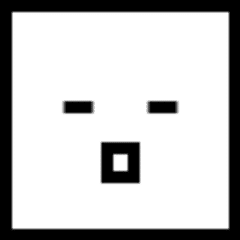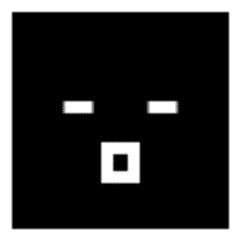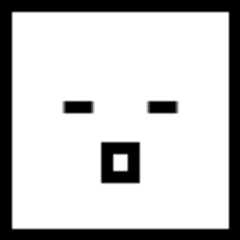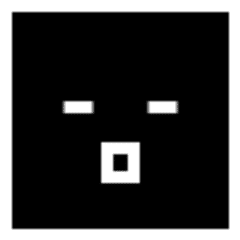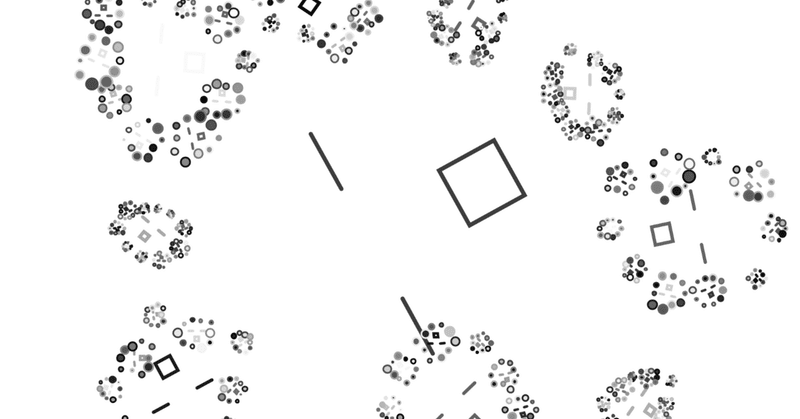最近の記事

middieーー二つのVaporwave、音と音楽の間の「きく瞬間」の探求ーー
音日記8日目。久しぶりに書く。 多くの創作者はそうだと思うが、作ったものの多くは人目に触れることはない。だが、一回一回の創作が実験で、そこには複雑な「思考」が常に伴っている(「伴う」、ということが重要で、創作が思考に基づくのでも、思考が創作に基づくのでもない)。それはプロセスと呼んでもいいのだが、それを紐解き、アーカイブ化しておくことには意味があるかもしれない、少なくとも、創作者当人としては、頭の整理になる。そういう感じで、この「音日記」を細々とやってみているのだと思う。 僕の創作/思考の中心に常にあるのは、音楽でも音でもなく、「音楽と音の間」や、「音から音楽への/音楽から音への移行」であるらしい、ということが最近明確になってきた(というか、そのような移行に「音楽」を感じるということかもしれない)。あくまで論理的・概念的な区別をするなら、音楽は、時間性や物語性、記号、形相、表面(聞こえ)、ポップネスといったことに関わり、対して、音(≒サウンド・アート)は、空間性や同時性、物体、質料、深層(因果)、ファイン・アートといったことと関わる。むろんこれには(特に最後のポップ/ファインということに関しては)疑わしい部分があると思われるかもしれないが、その具体例について考えてみるのなら、そのことは、むしろその部分が(音楽と音の間という観点からして)重要であることを示していることに気づくだろう。たとえば(これは今の私の関心の一つなのだが)、非-ファイン・アート的という意味でポップな、(音を使った非-音楽作品という広い意味での)サウンド・アートとして、ゲーム内アンビエンスを上げることができるかもしれない。MinecraftやMini Metroのそれを念頭においているのだが、これについてはまた別の機会に書きたい。いずれにしても、「音と音楽の間」とはだから、音を時間化・リズム化したり、音楽を空間化・物体化、あるいは質料化したりすることに関わっている。 「音楽と音の間」とは言い換えるのなら、「きく(聞く/聴く)瞬間」のことである。絵画や写真を見せられた時、一瞬何がどのように描かれていたり映ったりしているのかよく分からない、ゲシュタルトが定まらない、そういう瞬間がある(これは「みる瞬間」)。でも一度「見える」ようになってしまうと、逆説的に聞こえるかもしれないが、僕らはそれを見ることはできなくなってしまう。美術展に行くと、人が、「これは何を描いているのかしら」「〇〇じゃない?」などと話しているのを聞くことがあるが、その「〇〇」が確定した時点で、僕らはそれを記号としてしか見ることができなくなってしまう。その作品ををそれ自体、それ全体でみることが困難になってしまう。逆に言えば、だからこそ作品は、それに抗うことのできるような「みる目」を必要としているのかもしれないし、(いきなり自己批判になってしまうが、)そのような目を信頼せずに、作品それ自体で「きく瞬間」や「みる瞬間」を持続させるようなものを作ろうとすることは、単に絶望的な試みであるだけでなく、鑑賞者の能動性を奪い取ってしまうことなのかもしれない(そしてまた僕自身にそのような能動性が欠けているのかもしれない)。例えばフランシス・ベーコンの絵画はそのようなものだと僕は思う。こういった(モダニズム的と、あるいは非-社会的といってもいい)作品は、芸術というよりもドラッグやポルノに近いのかもしれない。無論、そう言うことに意味があるのは、芸術が常にそういったものと切り離しがたい関係や緊張を持っていることを認める限りにおいて、だと思うが。いずれにせよ、僕はそれをあまり悪いことだとは思えない。「きく瞬間」において、聴く主体としての人/聴かれる客体としての音(楽)という分離は宙吊りになり、人は音と一体になる。そういう状態に惹かれる人と、そういう状態を恐れて記号や物語を盾にする人とがいる、という好みや状況の問題である気もする。無論好み(美学=感性)の問題こそが倫理や政治の根幹の大問題なのだが......。とはいえこれに関して、一つの今日的な例を挙げてみよう。今のように急速に成長する以前の生成AI(GANを使ったもの)が生成するイメージはしばしば不気味で、まさに「フランシス・ベーコン効果」と呼ぶ人もいた。こういったことは画像生成AIに限ったことではないだろう。すでに多くの人がこの不気味さを忘れて、あるいはそもそも知らずにAIで楽しんだりそれに頼ったりしているように見えるが、僕はこのナイーブさに不安を覚える。結局、「知覚する瞬間」を作り出すことは、技術やメディア、素材(メディウム)を、既存の記号や目的や物語から解放することによって、それらに内在している力能を再付与し、それらとの別の共存の仕方を探ることであって、その意味ではやはりアクチュアルな課題ではあるのだと思う。 さて、長くなってしまったが、そろそろ曲についても書いていきたい。私は以前、友人と共同で、Lars, Lucy & 8legionsという自動演奏楽器を用いるアーティストについて掘り下げたことがあったが、今ようやく、この「音楽と音」という観点から、そのLarsや、後書きで取り上げた、MIDI的なコンポジションを演奏するJacob Mann Big Bandや、物理モデリング楽器を使うMotion Graphicsのようなアーティストについてうまく語ったり考えたりすることができるし、それは重要なのではないか、と思えてきた。こういったアーティストについて元々考えていた共通項はやはり「音楽ともの/機械」ということなのだが、改めて考えてみたときに、「Vaporwave以後」というワードが浮かんできた。そうして、(もちろん以前から少しは聴いていたものの、)改めてvaporwaveに関連する曲を聴いてみたり、今更だがユリイカのvaporwave特集などを読んだりして、なんとなくイメージができたので作ってみたのが、今回の「middie」という、曲と言えるのかもよく分からない何かである。 正直なところ、こうして聴いたり考えてみたり作ってみたりした時に、vaporwaveはこれほど「難しい」ものだったのか、という感想を抱いた。それは、思想的・批評的な観点からいって難しい、捉え所がない、論点が多すぎる、という意味でもあるし、作るのが難しいというか、どうやって、というかどこまで作っているのだろう(要するにどこまでサンプリングとかを使っているのか)、どういう(不)真面目さで作っているんだろう、といったことがよく分からない、という難しさというか不安でもある。 無論vaporwaveという括りはあまりに雑漠としており、僕はこれには少なくとも、似て非なる二つの種類があると感じた(これも雑に思われるかもしれないが)。つまり、(クラシカルな)vaporwaveやmallsoftのように、アナログ(連続的)な素材=サンプルに、「外側」から働きかけるという「オーディオ的」な方向性。それから、future funkやutopian virtualのように、内側からコンポーズしていくような、「MIDI的」な方向性。(これはどちらかというと聴感の問題であって、実際の創作においてオーディオ/MIDIどちらがメインであるかというのはあまり重要ではない。)この二項は、これまで述べてきた、音/音楽とか、素材/記号といった対に概ね重なると僕は考えている。いずれにしても、僕は、この「二つのvaporwave」の橋渡しがしたいと思った(それは、論理的に考えてそうとかいうのではなく、あくまで感覚的に、要するに、そういう音(楽)が聴いてみたい、と思ったということである)(あるジャンルの創始者とされる人物自身はそのジャンルに縛られていないという意味において、「原点にして頂点」というのはしばしば真実であるが、OPNはまさにこの二つの側面に股をかけているように思える)。 vaporwaveの重要さ、衝撃、といったものは色々とあると思うのだが、僕はvaoprwaveやmallsoftの功績の一つは、音楽(店で流れるmuzakやテレビやラジオから聞こえる流行音楽)や、パソコンやゲームや携帯の起動音や効果音、サイン音といった「人工的」な音/音楽もまた「環境音」や「物音」であるという事実を、論理的にではなく、直感的に理解させたというところにあると思っている。だがfuture funkやその他多くのvaoprwaveは、その事実が指し示す方角に向かうのではなく、そうした音を「音楽」の側に回収してしまうか、少なくともその事実の提示に留まっているように僕は感じた(無論、これはたとえばfuture funkがダメだとか批評性がないとか言っているのではなく、あくまで「音と音楽」という観点からの、そして僕の観測範囲内の話である)。 対して、James FerraroやGiant ClawやCryptovolansのようなutopian virtual的な(僕は正直このジャンルの外延がいまいち分かっていないのだが)、というかMIDI的なアーティストは、一方では、MIDIは単なる再生機であり、それによって作られたものが「音楽」に聞こえるのはあくまで「結果として」、つまりMIDIという技術に対して外在的、偶然的なことであるのだが、他方では、それはやはり音楽のために設計されているが故に、あえてそこから外そうとしない限り、適当に音を配置しても必然的に「音楽」的な何かになってしまう、というMIDIという技術のアンビヴァンレンスと、それが故に生じる音と音楽との間の揺れを、今の時代にあえてチープな音を使ったり、器械的な編集を行うことで、つまりその結果を「楽曲」にしようとするトリートメントをあえて外すことで聞かせる、提示する、ということを行なっているのではないか、という点が重要に感じられる。この方向は、その「あえて」という緊張が失われる可能性に常に晒されている。そうなればその音響体は、「そういうジャンルの楽曲」になってしまう。 MIDI感たっぷりのカラオケ音源や、昔のゲームのBGMなどは、utopian virtualの曲ではない(実際には聞き分けることが難しい場合もあるかもしれないが。そしてutopian virtualはまさにそういった曲の「音楽もどき」性を誇張しデフォルメしたパロディであると言えるだろうが)。それはなぜかといえば、それらの音源が、何か特定のジャンルの曲をやっており、またそのことが聞いて分かるからであろう。逆に言えば、utopian virtual的な方向性が音と音楽の間に留まるためには、単に特定のジャンルであることを避けるだけでなく、「単にMIDIという技術に従っただけのジャンルのないもの」という否定神学的なジャンルをも避ける必要があり、そのためには、(utopian virtual的なものも含めた)特定のジャンルに取り組みつつ、それを絶えずMIDI的に逸脱させるようなことをしなくてはならないということになるのか。しかしこれは「アキレスと亀」のような状況ではないか。 このことに対する結論はまだない。いずれにしても私は、vaporwaveやmallsoftには、「外側」からオーディオにエフェクトをかけたりすることしかできないという無力があり、futurefunkやutopian virtualには、「音楽」や「ジャンル」という物語に従属してしまうという無力があると感じたし、だからこそ、「内側」(MIDI)から作りつつ、同時に「曲」を、外側からエフェクトがかけられうる「音(響)」として扱うことでそこから逸脱し続ける、という戦略をとることで、両者の橋渡しをし、まだ聞かれたことのない「瞬間」、音楽未満音以上の、たとえば「ハイパー・アンビエンス」などと呼ばれうるような「何か」、いわば音楽のシミュラクルを作り出せるのではないかと思った。(繰り返すようが、このような「批判」は音と音楽の間という観点からして、であって、私は上に挙げたようなジャンルの音楽をリスペクトしているし、もちろん別の面白さもたくさんあると思っている。)この橋渡しは、オーディオもMIDIも関係なくとにかく最終的な「聞こえ」としての音楽を生産するために使われるDAWという機械を暴露し、批判する行為の一つになるのかもしれない。 今回作った短いプロトタイプがこうしたことを示しているとか、実現している、などというつりはない。というのは、やはりvaporwaveという事象はあまりに複雑であり、ここでは言及できていない様々な具体的な要素があり、そういった懸案事項に足を取られないためにも、とりあえず何かを作ってみる必要を感じてなんとか作ったのがこれであるからだ。そしてもちろん、この試みは始まったばかりであり、これはスタートに過ぎないので、ここから他にも色々やってみる必要があるし、まだまだ書きたいこともある。とはいえ、この音源でやろうとしたことやここで書こうとしたことが誰かにアイディアを閃かせて引き継がれていったら面白いなと思うし、そういう気持ちで作ったり書いたりしている(僕は決してバリバリ作る・作れるタイプではないし、割と飽きっぽいので、そう願ってしまう)。 最後に、この音源をどのように作っていったか大まかに書き残しておきたい。 最初に、FMシンセのエレピや、Linn Drumの音色を使って、「80年代風」な4小節のループを作った(あくまで「風」である。もっといえば、これは、実際の80年代の音楽というよりも、vaporwaveによって作られた「80年代風」をイメージして適当に作った「80年代風風」のものである)。また、そのエレピに複雑なアルぺジェーターをかけたパートと、そのパートに反応して音がなるホワイトノイズのパートなど、「80年代風」の音源には通常入っていない音も入れた。 次に、マスターに、リバーブや音質を低下させるビットクラッシャーやEQを挿し、オートメーションで好きなタイミングでonにできるようにする。onにするとmallsoft的な音像になる(群衆の音などを加えてもよかったのかもしれない)。加えて、最近Logic Proに追加されたグリッチ・プラグイン「Beat Breaker」なども挿す。これもまた、「80年代風」ではない、「現代風」の音像を作り出す効果がある。その他、あるパートだけにかかるリバーブなどもある。エフェクトの順序はかなり重要である。たとえばマスターにかかるmallsoft的音像のためのエフェクトと、グリッチエフェクトは、前者が先にかかれば、mallsoft的な音響体は他の音楽や音でもあり得る単なる「素材」になるし、逆に後者が先にかかれば、それはmallsoft的なサウンドになるというよりは、単に「現代風」なトラックにかかっている、というようなものになるかもしれない。 この曲は基本的に常にこの4小節のループが、またそれに対して色んな段階で諸々のエフェクトがかけられたヴァリエーションが、(ミュートされた状態で潜在的に)走っていて、その上でその一部が聞こえるようになっている、という仕組みになっている。だからその「作/編曲」作業は、そのミュートをどのように外していったり、外したものをどのように加工するか(たとえば一部のパートのテンポを変えてポリリズミックにしたり、一部分を繰り返させたり)、ということを、結果を聞きながら、その複雑性を調整していく(要するに「音楽」になりすぎないようにする)ノンリニアな即興のようなものになる。

micro planetary machine α
「音日記」七日目。宇宙的な、機械が奏でる、雅楽、みたいな。 今回は、前からなんとなくやろうと思っていた、非-平均律的に自由に音が動き回り、交わり、重なり、すれ違うようなコンポジションのアイデアを試してみた(ピッチはMIDIのピッチベンドで動かしている。)。 とはいえ、いきなりぐちゃぐちゃ音を動かしてもよく分からなくなってしまうから、まずはコードを想定して、それを元に動かすことにした。 Dm7 → Em7 ( → C#m7)。 平行移動(コンスタント・ストラクチャーといったりもする)のシンプルな進行。ただ、それぞれのパート(声部)を、同じ音程で同じタイミングで平行移動させても面白くない。そこで、まず移動する音程をバラした。 D → B(長六度上) F → E(半音下) A → D(完全四度上) C → G(完全四度下) その上で、さらになり始めるタイミングや音程が変わり始めるタイミングをずらした。また、それぞれの声部で周期の違う連続的に増減する速度によって点滅するように発音させたり、それぞれ違う周期でパンを動かしたり、(それに合わせて)それぞれ違う周期で音量を動かすことで、いくつかの惑星が頭の周りでぐるぐると回ったりどこかに行ってしまったりするような効果を作ることを試みてみた。 あとは、平均律で、タイミングを見定めながら、エレピを加工した音でコードのアルペジオを入れたり、(リリース・カット・)ピアノのメロディなどを入れ、ピッチ変化するパートとの微妙な不協和音・共鳴を生み出すことを試みた。 シンセの音作りやリバーブなどのミックス的な要素はあまりいじれていないし、コンポジションに集中しているとついついそういったところがいつもなおざりになってしまうところが、今の僕の課題ではあるかもしれない。 とはいえ、なんでも、慎重に、一個づつやっていくことは重要だ。僕はすぐ、もっと複雑にしたくなってしまって、結局自分でやっていることの正確な把握ができなくなって、創作を持続を頓挫させてしまう。息切れしてしまう。 そういう時に、やはり、足場となる理論や論理、言葉を持っていることは強みになると思うし、だからこそ、僕は、上に書いたように、自分のやっていることを言葉にして、確認するし、それは決して、何かをひけらかしているわけでも、理論に囚われたりしているわけでもない。あくまで過程、ではあるのだ。 今回のピッチを動かすというアイデアも、別に、形式的にそれを目的化しているわけではなく、あくまで、自分がぼんやりとイメージする音像にどうしたら近づけるだろうか、と考えた時に、そういった、新奇にも思えるアイデア(ピッチを動かしたり、テンポを動かしたりという)が出てくるだけなのだ。 ところで、この曲でやったように、様々なパラメーターが動きつつ、ある程度調和している、という状態を普通にMIDIやオートメーションだけで作るのは無理があるのではないか、と半ば諦めていたことがあって、だからこそ、僕はプログラミングを使った音楽とかにも挑戦してみていたんだけど、(それはそれでいいとして、)やはり、諦めずに、一つ一つ積み重ねて自分の追求する音像に近づこうとすることに意味はあるんじゃないか、と今また思い直しはじめている。 音の粒子、惑星、プランクトンが、入り乱れ、なんらかの形=リズムやネットワークを創発し、変化し、また不安定になり、というような音像。音と音楽の間。そんな音楽を誰が求めているのかは知らないし、僕がなぜそういう音楽を作りたいと感じるのかは分からないけど、今はそのような連続性を、手動で、アナログに作り出してみたいと思うのだ。

planktone(s)
「音日記」六日目。短いけど、小さくて可愛らしい、顕微鏡でプランクトンを覗くような、曲ができたのではないだろうか。 リズム=形がはっきりとする前に、色んな音が浮遊しながら登場・通過していく。何か起きそうだけど、何も起きないかもしれない。 僕が音楽をはじめとする諸々の創作でやろうとしていることを考えてみると、それは思いのほか、至って単純かつ軽薄で、「快」を作ることなのではないかと思われてくるが、さらに僕にとって何が快となるだろうか、と考えてみると、それは「重なり」あるいは「同時性」とでも呼べるものではないか、と感じられる。 僕がいう「重なり」や「同時性」は、例えば音楽においては、すぐに思いつくような、同時に別の楽器を鳴らしたり、ハーモニーを作ったり、DAWの画面上で複数のMIDIやオーディオを再生する、といった操作を単にやるだけでは(必ずしも)達成されえないし、あるいは造形芸術においては、単にいくつかの要素を文字通り「重ねる」だけでは表れてこないし、はたまたアニメーションなどにおいても、いくつかのオブジェクトがそれぞれ「同時」に動いていたりするからといって、表現されているとは限らないような、そんなものだ。 何かが「同時」であること。それは、「同時である」と言われている以上、そこにおいて複数の何かが別々であることを含意しているが、それと同時に、何かが「同時である」と言われうるのは、それらがなんらかのやり方で中継され、繋がっており、ある種のまとまりを形成しているからだ。 離れていると同時に繋がっている。あるいは、すべてのものがそのように浸透し合っている。このようなあり方は、僕が以前のエッセイ(「バッファーと創作」)で書いた、バッファーや、そこにおいて生まれる「リズム」にも通ずる。 おそらく、そのような事態自体は、いつでもどこにでも、ある。そのエッセイで書いたように、「私」はそのように構成されているし、その私はまたそのような事態において、何か(例えば行為)を構成する。(ついでに書いておくと、ドゥルーズ(&ガタリ)が用いる「構成平面」「存立平面」という概念を、僕はこうした見方において捉えている。) だが、同時に、現実世界(として私たちに把握される領域)は、むしろあまりにも多くのことが同時に起きており、そこでの同時性はホワイトノイズのように捉え難く、またそれだけでなく、私たちはそういった「曖昧」な相互浸透という事態を言葉=概念によって切り分けて捉えることにあまりにも慣れてしまっている(例えば、「これは指」「これは手」「これは腕」...というように)ので、そういった認知のプロセスを欺き、そこから身を引き剥がし、またそこにおいて「現実世界」からある程度切り離されたビオトープ的な空間へと入場させるような、ある種の狡知(あるいは技巧、アート=技術、マニエール、マジック...)を駆使しないと、それ(相互浸透=同時性)をそれとして感覚することができないのではないか。複数種類のプランクトンを培養し、それを抽出してスライドグラスに滴下し、必要ならば染色などを施し、カバーグラスをかけ、「ステージ」に載せ、丁寧に倍率を合わせること...。「バイオ・アート」、というよりも、生気の技術としての実験、研究、創作...。触知可能な平面ーーただしそれは完全な「平面」となっては何も動きがとれないし、だからこそ厚みをもった平面なのだがーーを創作すること...。 最初に戻ろう。ではなぜ、そういった形で創作される同時性や重なり、浸透が、快をもたらすのか。それは、そういった事態においては、諸々の何かが(現実的、日常的にはまとまっている)諸々の何かから切り離された上で、ある場において、自由に、開放的に動き周り、また場合によってはそこで新たな出会いや出来事を迎え、そこにおいて、re-mediation=改善・修正=繋ぎ直しという形で、ある種の「マッサージ」を生じさせるからではないか(マクルーハンは自らの有名な文言をまさにre-madiateして「メディアはマッサージである」と言った...)。そしてまた、そこにおいて、まとまりを形成していたその何かの中で形成された無数の微小な閉鎖された空間、この隙間や孔に溜まっていたゴミや老廃物が排出されると同時に、その隙間を形成している壁が何かと接触し刺激されることによって、不快感として経験される「行き渡らなさ」とでもいえるような状態が解消されるからではないか。 このような意味で、例えば小説においては、(人物同士や人物と事物など以前に)何よりも、言葉同士が出会っている、また、文が出来事している、(そしてそのことによる快というものもある)ということができるのではないだろうか。 出会い...。そうした快の創作は、根源的な部分で、エロス的、あるいは欲望的な問題とも繋がっているだろう。その場その時の特異な「対面」=「キス」を創り上げること。非人称的な性(非-性的な性)における心地よい交わり、接触、愛撫を生み出すこと...(そしてもちろんこういった問題はコロナ禍の現在においてアクチュアルである)。 セルフ・プレジャー、自己-満足としての創作。誰がこれを否定できようか? そしてまた、こうした創作観においては、(客観的なそれではない)「時間」さえも、結果として創作されるものであると考えられる。例えば朝、時間が早く過ぎ去るように感じられたりするように、音楽でも絵画でも、それらはそれら独自の時間制、時間帯、朝や夕方、あるいは深夜を作り上げるのではないだろうか。だからこそ、(僕の曲がこれまで述べてきたような点に関してうまくいっているかどうかは別にして、)曲の客観的な短さというのはやはりそれ自体としては問題にならないし、逆に、どんなに時間がかかったとしても、それは、その結果起こる「タイム・スリップ」あるいは「タイム・トリプ」によって、どうでもよいことになるのではないだろうか。そして、それはある種の救済ともいえるだろうか。僕らはそれを目指しているのだろうか?
マガジン
記事

idea1120
日々の創作のドキュメンテーション、あるいはそれへのコメンテーション。「音日記」四日目。 前回は、DAWにおける音と音の外在性、に言及したけど、今回は逆に、もっと音と音が緊密に関係づけられているものを。 まず、プロジェクトのテンポ自体が常に変化していて、BPM=120から240まで移行した後に、30まで下がる。多くのトラックがこれに影響を受ける。 キックは、テンポとは独立して、加速しては減速し、また加速し、という感じで鳴る(それに応じてフィルターのかかり具合も変わる)。 エレクトリック・ピアノは、四つのコードを繰り返していて、それ自体はテンポに従属しているけど、どのタイミングで発音されるかは、キックによって決まる。 ハイハットも、キックと同様にテンポとは独立して加速したり減速するけど、発音するかどうかはキックによって決まる。 ピアノは、エレピと同じように、一方ではテンポに従属しつつ、他方ではハットによって発音タイミングが決定される。 アルぺジェーターを使ったパートは、入力されるコードはテンポに従属しながら、何分音符を基準にしてアルペジオするかは、テンポとは独立した周期によって、増減される。 複数の速度が並列しながらも、それらがなんらかのやり方で連絡をとり、あるいはまた共通の速度に関係させられていることで、まとまりを保持し、環境音のような、非反復的な、だが全くランダムというわけではない変異を生む。 だがそれはむしろ、それぞれ違った経験や人生を歩み、それぞれ違った速度をもつ人々の、それぞれ違う頻度をもった投稿が、その速度や頻度を横切るように一直線・等間隔に並べられる、SNSのタイムラインにも似ているかもしれない。

水域
「音日記」三日目。 今回のはまあまあいい感じにできたと思う。 その必要があるかどうかは別として、曲を長くするのは、難しい。 少なくとも、僕は、一定のテンポや拍子、パートなどを、意図的に排除するというわけではないが、少なくともそれを確固としたものとしては前提しない、というやり方で曲を作ってみているので、とりあえずの全体像、みたいなものを先に作ってしまって、その後でディティールを考える、みたいなことができない。 繰り返すようだけど、僕は明確な規則や秩序、繰り返しが曲中にあることを避けているのではなくて、ただ、そういったものがあくまで曲の流れの中で、自ずと生成、創発しつつ、いつ崩れてもおかしくない状態でなんとか留まったり、やはり崩壊してしまう、という物音=音楽ができないかと思っているのだ。 ところで、DAWはそういった音楽を作るのに、実は適しているのかもしれない。 DAWは言ってみれば、音声を、指定された時点において、同時並行的に再生できるマシンにすぎない。そこにおいては、同時的な音も、時間差をおいて鳴る音も、互いに外在的であり、その意味において、それらが重なったり、連続して聴こえたり、ましてやビートやリズムを形成し、「音楽」に聞こえてくるのは、偶然ともいえる。 (まあ、サイドチェインみたいな例外もたくさんあるし、もっと音楽を、音と音どうしを内在的に構成したいという部分があったからこそ、僕はプログラミング言語を使った音楽にも手を出してみたのだった。) とはいえ、もちろん、道具には、それを作った人や集団の思想(ものの見方・聞き方)が多かれ少なかれ反映される。DAWには、「音楽とはこういうものだろう」「音声はこのように扱うのが多くの人の役に立つだろう」という思想が反映されている。DAWは、原理的には、ほとんどどんな音楽でも作れるかもしれない。けれど、何かが可能であることと、その何かを可能にするに至ることができることは違う。DAWにおいては、適当に音を並べても、音楽になってしまうのだ。それはもちろん、DAWの仕組みの問題だけではなくて、例えばなんてことのないオブジェクトが美術館に置かれることで「アート」になったりする、そんなところにもみられるような、別の力も働いていたりもするだろう。 とにかく、僕は、アドホックに音を選び、トラックを増やし、ファイルをコピーしたり切り刻んだりし、エフェクトをかけてみる。何か物足りなければ「そこ」に音を「置いて」みる。僕が、音(楽)像を、「念頭に置く」必要はない。コンピュータが、ソフトウェアが、そのかわりをする。その都度、まさに即興=演奏=作曲=演算を行う。僕はそれに伴走するのだ。 それはまるで、スキューバダイビングのようだ。あるいは、足場のない建設のようだ(マインクラフト?)。

free_composition1111
日々生まれては誰に聴かれることもない音楽未満の何かをドキュメントする「音日記」、二回目。 曲が作りたい、となるのはなぜだろう。そしてその欲望は、他人の曲を聴くことによっては満たされない。むしろ聴くことによって増殖しさえするかもしれない。 まあそんなに身構えることはないだろう。でも僕は曲を作るのが怖い。 一度作り始めたら一定の形が確立されるまでは中断できないのではないか。あるいは、今作ったフレーズを、うまく発展させることができずに、諦めてしまうのではないか。イメージや、ありえるフレーズやコード、その組み合わせの可能性だけが増殖して、手に負えないのではないか。 僕はギターやキーボードをやってはいるし、それは曲作りにも活かされているし、そもそも昔はバンドでやるための曲を書いていたりもした。 だけど楽器の練習も最近はあまりできていなくて、そちらにも不安がある。おまけに、一個の楽器だけで曲を作るのならまだしも、パソコンで音を重ねたりする前提で曲を作るとなると、色々手間がかかったりもする。まあ、これに関しては、もっと機材の環境などを整えていく必要があるのだと思う。 今回は、とりあえず、とことん無理をせず、ちょっと頑張ったり頭を使ったりするような動作も排して、音を置き、コピー&ペーストし、切り裂き、引き伸ばし、それをまたコピペし、という風に、ものすごく「雑」にやってみた。 耳で聴いて、悪くなければそれでいい。 意外と、何をやっても音楽になってしまうものだ。 そうやって、抵抗を減らして、次第に、大胆かつ丁寧に、作業を進められるようになれたらいいなと思う。
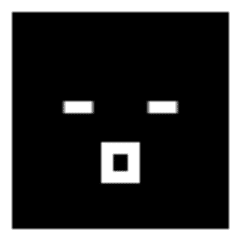
rhythmpattern106
テストです。 今日作ったビート。 こうやって、日々作られては誰に聴かれることもない「音楽未満の音楽」を載せて、所感や解説を書き残しておく、というドキュメンテーション、いわば「音の日記」をやってみてもいいかもしれない、と思ったのです。 今回のビートは、(普段の僕の音楽はどれもそうですが)断続的に、拍節、テンポ感、リズムが変化していく、ということを、キック・スネア・(オープン/クローズド)ハットのシンプルな組み合わせ(+ヴェロシティ)でやっています。 割と、僕はこういったシンプルな音でも、その構成=コンポジションのやり方によっては、全然聴くに堪えると思っているのですが、どうでしょう。 とはいえ、繰り返しをできるだけ作らないようにする、というのは、なかなか難しいことです。「繰り返しを作らない」という行為、これを繰り返さないために、あえて繰り返しを入れる、という操作さえ必要になります。 また、人間が作業している時に使うメモリーにも限界があるでしょう。 大まかな構成とかを作ってから作ったほうがいいのかもしれない、とも思います(それが当たり前なのかもしれませんが、頭から即興的に作ることの価値、というのもあるかもしれない、と思ったりもするのです)。 そしてまた、「リズム」という現象はとても難しいですし、いつでも複雑です。 例えば、キックの位置によるリズムというのがあり、それとは別に、キックのヴェロシティによるリズム、というのがある。そしてまた、キックとスネアの組み合わせのリズムがあり、キックとハットの組み合わせがあり、キックとスネアとハットの組み合わせもまた別にあり、またスネアにもハットにもヴェロシティがあり、それだけでなく、例えばスネアの音とキックの音が区別されるのと同じように、ヴェロシティの中にも区別=レイヤーが発生することがある。例えば、ヴェロシティ=120のキックと、ヴェロシティ=40のキックの音で、違うリズムを刻むということができる。 それでいて、それらが全て「音」=振動であるというレベルにおいては、それらのリズムは混ざりあって一つの大きなリズムを成してもいる。 こんなことを意識しながら音楽を聴いたり作っている人はあまりいないのかもしれませんが、それでも、身体はこうしたリズムとその複雑さに直に共振しているのではないでしょうか。 リズムの語源「リュトモス」には、「かたち」という意味があります。 歌は、(「音量」や「ピッチ」といったパラメータとは本来は関係なく)ある身体を声帯の「かたち」でもって音=リズムとして発し、直接、他の人の身体と共振させる、そんな試みともいえるでしょうか。 身体を必要としつつもそこから逃れ出て別の身体と交歓し、同時にまたその別の身体をもその身体から脱出させる。音楽は、それが一般的な意味での「歌」を含んでいなくても、そんな抽象的な歌=リズムを目指している、あるいは目指すような自律性を持つ限りにおいて、単なる「音」と区別されるのかもしれない。 ...たった数十秒の曲を作るだけでも、色々考えることができるものですし、もちろんそれを言葉に還元し尽くすことはできないものですね。