
軽症患者だけど、指定難病の登録者証を申請してみた ~マイナカードに紐付いたら追記予定~
どうも、こんにちは。
胆道閉鎖症の患者本人で、患者家族会の運営委員の橋爪徹です。
胆道閉鎖症は、1万人に1人の難病といわれています。生まれつきまたは生後間もなく、肝臓と十二指腸を結ぶ胆管がつまってしまう病気です。

胆道閉鎖症に生まれた私は、幸運にも42年間、自分の肝臓で生きて来れました。生後間もない時期は修羅場もあったようですが、物心ついてからは大きな入院は数えるほどで、成人してからは一度大きく体調を崩したのみ。ほぼ健常者に近い生活を送ることが出来ています。
そんな私は、指定難病に胆道閉鎖症が含まれてからも、然るべき重症度基準に該当せず、医療費助成を受けることが出来ません。受けることが出来ないだけならまだしも、国に指定難病患者として私個人を認知されていません。症状がずっと重くなってほぼ寝たきりにならないと医療費助成は受けられないし、自分を指定難病患者であると証明できる公的書面は何もないので、制度から置き去りにされています。(もしくは、いざ必要となったとき、支援や福祉にアクセスするのに手間と時間が掛かる)
せめて、私のような軽症者も指定難病患者として国に認知してほしい。然るべき時に、然るべき支援や福祉にスムーズに繋がれるようにしてほしい。軽症者も含めて、私たちの情報を研究などに役立ててほしい。それを担保する”指定難病であることの登録制度”を作ってほしい。
登録者証の実現は、患者会の長年の要望でもありました。
登録者証が現実の制度に
世論の高まりと政治の動きもあり、ついに登録者証が実現することになります。
議論の過程として、日付の古い記事にはこんなものがありました。(コロナ禍で具体的な法改正は遅れてしまいました)
登録者証実現の第一報は、医療特集に熱心な読売新聞のスクープかもしれません。私も以前、「医療ルネサンス」の取材を受けて、上野公園でインタビューされた記憶があります。
2022年9月の第一報から1年以上が経った2024年4月、ついに登録者証の申請受付が開始されました。
申請方法 ~準備編~
登録者証は、自治体の窓口で申請が出来ます。受付は都道府県単位だったり、市町村単位だったり、マチマチです。私の住む八王子市は都が管轄です。「登録者証 ●●(お住まいの都道府県or市町村名)」で検索すると自治体ごとのページが出てくると思います。4月に申請受付が始まっていますので、何かしら情報が公開されているでしょう。
2024年6月時点で、東京都は、かなり具体的に申請から交付までの案内が開示されていました。私の実家がある静岡県や、在住経験がある愛知県は、実際の手続き方法などが曖昧で、窓口に行かないと分からない雰囲気でした。分からないことがあれば、問い合わせ窓口に電話を掛けてみるといいでしょう。(本稿執筆時点では、静岡県は東京都並に詳細な案内が掲載)
登録者証は、紙ではなく原則マイナカードへの紐付けによる交付となります。マイナカードを作っていない人は、例外として書面でもらえます。全国共通の対応だと思ったのですが、岡山県はマイナカードを持っていても、紙で発行することができる模様です。該当地域にお住まいの方は問い合わせてみて下さい。
申請に必要な書類は、以下の通りです。(東京都で私が申請する場合)
臨床調査個人票
登録者証(指定難病)申請書
個人番号に係る調書(指定難病用)
申請書や調書は、自治体ごとに必要の有無が異なり、書式も違うでしょうから、ここでは詳しく触れません。東京都ではエクセルファイルをダウンロードして記入。印刷して持参すればOKでした。

重要なのは、「臨床調査個人票」です。いわゆる診断書に当たるものです。軽症者の方は、臨床調査個人票もしくは、「非認定通知書」が必要です。この通知書は、指定難病の医療費助成に申請したけど、基準に当てはまらず不承認になった際の書面です。東京都の場合は、『非認定理由が「軽症かつ高額の要件を満たさないため」と記載されたものに限る』ということでした。私は、軽症で認定されないことは明白なので、初めからチャレンジしていません。よって、自動的に臨床調査個人票を入手することになりました。
臨床調査個人票は、掛かり付けの病院で医師に書いてもらいます。私は成育医療研究センターに通っていますので、書類の発行について調べました。
3ヶ月に1回の通院のため、書類をもらうためだけに病院に行くのは大変です。よって、郵送による申し込みを選択しました。ひな型は、厚労省のホームページから胆道閉鎖症を検索して、PDFフォーマットをダウンロード。(No.296)
PDFを紙に印刷して、証明書発行申込書と一緒に郵送します。結構な枚数の紙! 掛かった費用は、文章発行費用が2500円、返送料700円(ゆうパック)でした。
数日後に返ってきた封筒には、パソコンで入力された臨床調査個人票と、私が家で印刷した無記入の臨床調査個人票……

なんとなく予想してましたが、こちらが印刷した紙は無駄になりました。主治医によっては、紙に直接記入したい先生もいるのでしょうが、この辺りは効率化&エコに出来ないものでしょうか。

申請方法 ~いざ自治体の窓口へ~
臨床調査個人票が届いたら、東京都側の必要書類を準備して、八王子市保健所に向かいます。

申請窓口は、自治体によって異なります。健康福祉部や福祉保健部、保健センター、保健相談所……などなど。東京都だけで見ても、こんなに違います。登録者証について紹介している自治体のページにリストがあることが多い模様です。

私はフリーランスで仕事をしているため、平日にいつでも動くことが出来ます。木曜のお昼に行ってみたところ、待ち時間なしですぐに受付けてもらえました。最初対応してくれた窓口の方は専門ではなく、奥からすぐに出てきた担当の人に代ってからは、サクサク手続きが進みます。
登録者証は、マイナンバーカードへの紐付けになり、書面の発行はないことを説明されました。4月から始まっているとあって、説明は手慣れた感じで躓く様子もありません。後日、東京都から登録証を発行しましたという手紙が届くとのこと。手紙が届けば、マイナポータルでチェック出来るようになると思われます。
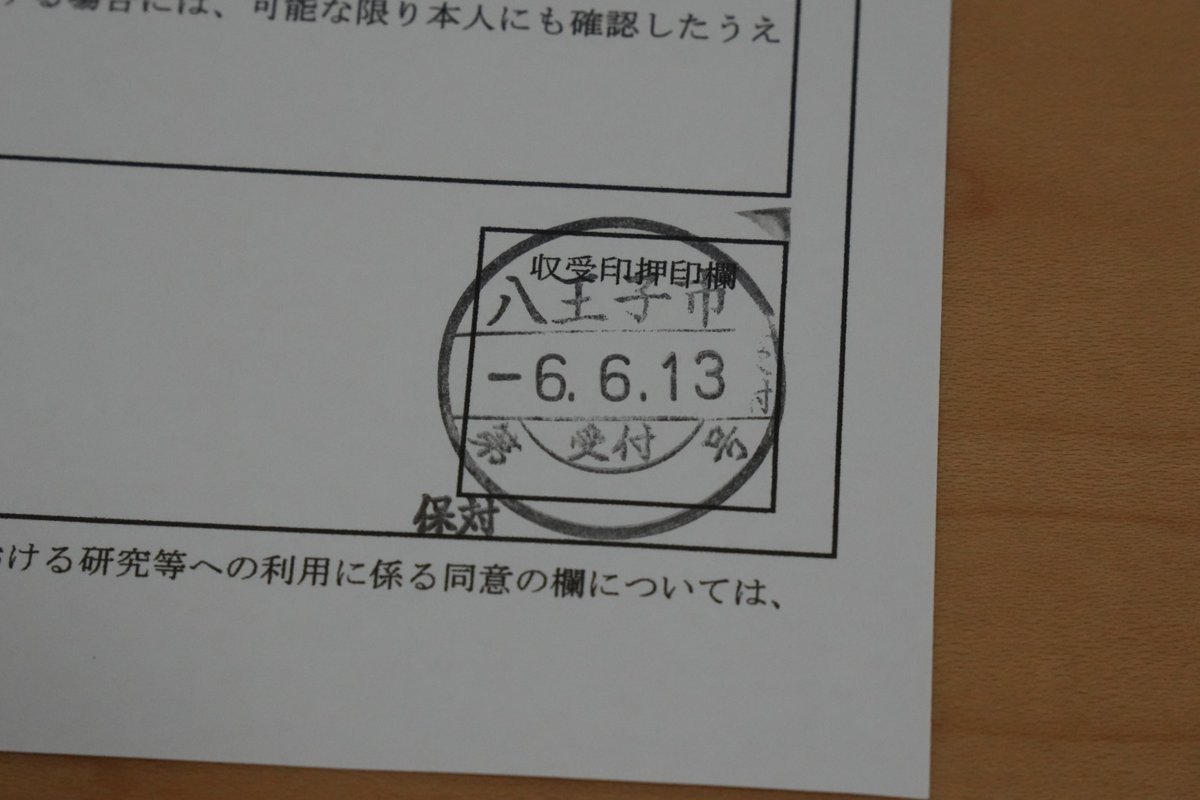
ちなみに登録者証に有効期限はありません。つまり、免許証のような更新手続きはありません。ザッと調べて見たところ、情報ソースが見つからず、ようやく長野県のサイトで『有効期限がないため、一度交付された場合、更新の手続きは必要ありません』の文言を見つけました。
まとめと登録申請のススメ
ということで、登録者証交付の申請手続きをレポートしてみました。
軽症患者の方は、臨床調査個人票さえ主治医に書いてもらえれば、あとの手続きは簡単です。文章発行費用も、それほど高額ではないでしょう。

秋ごろ、マイナカードへの紐付けが完了したら、本記事をまた更新したいと思います。この記事が参考になったという方は、友人知人の指定難病の方に教えていただけるとありがたいです。軽症者の方でも登録者証を申請することで、情報が集約され今後の研究に役立つことが期待されます。
逆に特定医療費(指定難病)受給者証を持っている方が、登録者証の交付を受けることで、医療費助成が不承認になった後も「指定難病の患者であることの証明」ができるというメリットはあまり知られていないと思います。
というか、申請受付は4月に始まってるのに、なかなか周知が進んでないと思うんですよね……
かくいう私も受付けが始まってることを知ったのは、5月になってからでした。
病院のケースワーカーが来院した患者にお知らせするとか出来ないものか。お医者様が複雑怪奇な制度を全部理解して、説明するのは負担が大きすぎます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは、また!
いいなと思ったら応援しよう!

