
このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」
執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。
今回のテーマは「食欲と肥満の関係」です。
●脂肪は必要なエネルギー
摂取カロリーと消費カロリーのバランスにより私たちの身体は過剰なカロリーを脂肪として蓄積し、必要であればエネルギー源として使います。
食べ過ぎれば太るというのは当然なことかもしれませんが、なぜ食べてしまうのか?
それは、食べたいもの、美味しいものがたくさんあるからという見解が一つです。
もう一つは動物には食欲があり、食欲があるからエネルギーになるものを摂り、生命を維持するようになっているからです。
体脂肪過多の状態は肥満といわれますが、それ自体は病気ではありません。
それが影響をして糖尿病、高血圧、脂質異常症などの疾患の原因となることはあるので、できれば未然に予防改善ができるとよいことはあると思います。
しかし、わかっていても食べてしまい、摂取カロリーが増えていくことがあります。
そこには食欲をコントロールしている身体の仕組みがあります。

肥満となる体脂肪増加のもとは身体の表面でわかる皮下脂肪と内臓周囲についている内臓脂肪です。
どちらも脂肪細胞の集まりでできています。
霜降りの肉のサシも脂なので脂肪細胞の集まりです。
大人の身体には数百億個の脂肪細胞が存在するといわれ、細胞自体は球体のかたちでかなり大型、脂肪をためることを専門にしています。
脂肪細胞は中性脂肪を蓄積しますが、これは体内のエネルギーが不足したときに他の細胞にエネルギー源を供給するためです。
食事をすると糖質からのブドウ糖やタンパク質からのアミノ酸、中性脂肪などの栄養素が血液中にたくさんあるため細胞はそれらをエネルギーとして活用します。
血中のエネルギーが不足すると脂肪細胞にためこんだ中性脂肪を分解して血中に送り、筋肉などの細胞のエネルギーとして使われます。
寝ている間は食べていることはないので必要なエネルギーは脂肪細胞によって賄われています。
朝食を食べるとそれがエネルギーとなり、余剰分は中性脂肪としてたくわえます。
エネルギーが足りない時には供給し、余っている時には貯蔵するということを繰り返しています。
脂肪は1kgあたり約7000kcalのエネルギー源で、フルマラソンを走る程度にあたるとされています。
●美味しいものを食べ過ぎる感覚
医学や生物学の研究ではネズミがよく使われますが、飼育箱のなかではエサと水をいつでも好きな時に食べたり飲んだりしてもよい環境になっているそうです。
好きな時に飲食できる環境でもネズミはほとんど太らないそうで、毎日ほぼ同じ量のエサを食べていることが観察するとわかるそうです。
エサを取り上げた状態にすると当然、体重は落ちていき、その後エサを戻すとその前よりも多い量と食べて、元の体重に戻ります。
しかし、その後は食べる量が減り、それ以上の体重の増加がないといいます。
ネズミは自身の適正体重をわかっており、体重の増減に合わせて食べる量と調整していることがわかります。
ネズミの食欲は体内のエネルギー量に合わせてコントロールされていると考えられます。
人間とネズミの食欲の違いはあるのでしょうか。
ネズミはシンプルに体重によって食べる、食べない調整していますが、人間は体重以外に気持ちの部分が発達しているといえます。
ご飯を食べて満腹感があったとしても、美味しそうなケーキがあれば「別腹」といって食べてしますことがあります。
これはケーキを食べることの幸福感を得たいことで、エネルギーが足りていても食欲が生じるからです。
食欲の研究で3歳児と5歳児の食事量を観察したものがあります。
3歳児に小盛、中盛、大盛の料理を与えて「好きなだけ食べていいよ」とすると、それぞれで食べる量は変わらなかったそうです。
同じことを5歳児に行ったところ、大盛になると小盛以上の量を食べてしまったそうです。
これは3歳児ではネズミと同じように適正な量を食べる能力を持っており、5歳児になるとこの能力が低くなり、目の前のものを食べたいという欲求が強くなっていることが推測されます。
他の研究も加えてみていくと人間の食欲は4歳ごろから精神的な刺激によって強弱を起こすと考えられています。

専門の研究者はこのような精神的な刺激によって起こる食欲を「快楽性の食欲」、体内のエネルギーの減少によって起こる食欲を「恒常性の食欲」と呼んでいます。
恒常性とは体内の環境が一定に保たれている状態のことで、体温や血圧、心拍数などを調整する能力です。
食欲には脳の視床下部という部分が重要であることがわかっています。
視床下部の領域の一部の働きが悪くなると食べる量が増えていき、また別の領域を破壊すると食べる量が減って痩せていくことが研究ででています。
これが「満腹中枢」と「空腹中枢」でお互い協調して摂食行動をコントールしていると考えられています。
●適正体重と幸福感で起こる食欲
▼恒常性の食欲が起こる仕組み
食欲に関わるホルモンの1つがレプチンです。
レプチンは脂肪細胞から放出されて、視床下部に届き、摂食を抑制します。
また交感神経を活発にさせて蓄えられている中性脂肪の分解を促進する役割もあります。
食べる量が増えて体脂肪量が増えるとそれに比例して脂肪細胞から分泌されるレプチンの量も増えます。
そこで食欲が抑制されて食べる量が減り、増えすぎた体脂肪量が減少します。
また、食べる量が減って体脂肪量が落ちてしまうとレプチンの量が減り、食欲が増進されて食べる量が増えます。
これにより体脂肪量は適正な量に戻るようになります。
これにより日々の食欲のベースラインを決めているとされます。
しかし、体脂肪過多の状態が続くとレプチンが効きにくくなる「レプチン抵抗性」という状態が生じることがわかっています。
本来はレプチンが食欲を抑えますが、その効能がなくなり体脂肪量が増えすぎても食べる量を抑えることができなくなるといったことが起こります。
体重、体脂肪量全体にはレプチンが作用しますが、食事の前後の空腹感と満腹感は別の器官によるもので調整されます。
それが胃や腸などの消化管から分泌される「消化管ホルモン」と「迷走神経」です。
ホルモンの1つがグレリンです。
グレリンは唯一、空腹感を生じさせ摂食を促進させます。
これは食事の前に増加して、食事によって減少します。
また朝食、昼食、夕食の時刻近くになると増加して、空腹感を高めてエネルギーを確実に補給させるための仕組みだと考えられます。
食事を食べ損ねてしまったときなどでは、いつの間にか空腹感がなくなることがあります。
これはグレリンが自然に減少して空腹感がなくなったと考えられます。
迷走神経は消化管と脳をつなぐ神経です。
食べ物が消化管に入ったことや動きを感知して脳に情報を伝えます。
その情報が視床下部に伝えられることで空腹感や満腹感を生じさせる役割をしています。
ホルモンや栄養の情報を感知することで一定の食欲と食べる量が決まることが恒常性の食欲がつくられていると考えられます。
動物や小さい子供はこの仕組みを使って体重をコントロールしています。
しかし年齢を重ねると「食べたいもの」の欲求の影響を受けて摂食することで、太ってしまう過程に入り込みます。
肥満状態が続くとレプチン抵抗性が生じ、恒常性の食欲が狂ってしまい、体脂肪が過剰になっても適正に戻すことができなくなってしまうのです。
▼食欲は幸福感を求めるものでもある
「快か不快か」は脳の扁桃体という部分で判別されています。
たとえば食べたときにお腹を壊したというものがあれば、その後それをみたときに不快な感じを生じることがあります。
食べ物や自分にとって危険なものなどを避けるにはこの不快な反応によって、避けることができるのです。

反対に快楽の感覚では報酬系といわれる脳内システムとやり取りをしていると考えられます。
「依存症」といわれるものは報酬系のシステム内で生じる快楽を求める症状にあたります。
このシステムではドーパミンというホルモンが放出され快楽を引き起こすことがわかっています。
食欲においても、この食べ物は有益なもとと判別されることで快楽性の食欲が生じると考えられます。
栄養素の中では砂糖などの甘味、脂質が報酬系を活発にさせるといいます。
栄養素によって報酬系の反応には違いがあり、だしなどのうまみ成分には報酬系を活発にする効果はほとんどないとされます。
甘いものや脂肪分の多いものに対して幸福感、満足感があるのは報酬系システムの働きが関与しているのです。
お腹いっぱいで身体は必要なエネルギーをとっていても気持ちの部分で食べたくなるのは脳が報酬を求めている、それが積み重なると摂取カロリーが増えて体脂肪として蓄積する、体脂肪量の増加によりレプチンが効かなくなり食欲が過剰になるといったことが、体脂肪過多にしてしまう要因となると考えられるのです。
●予防のためには食べたものを認識する
体重を適切に維持するための「恒常性」と幸福感を得るための「快楽性」が食欲の増減に関連します。
食べ過ぎるという点では「充分に食べた」ということを脳で認識する必要があります。
何かをしながら食べる「ながら食べ」をすると食事量が増えるといわれていますが、それは食べたことがあいまいになり、脳がどれだけ食べたかを記憶しづらくなるためと考えられています。
食べたものについてメモを取る、記録するといったことはダイエットの方法の1つにありますが、それは自分の食べた量やどういったものを食べたかを脳で考えさせることにつながります。
また、「今日も食べ過ぎなかった」ということが達成感として認識できればそれを次も求めることができます。
食べ過ぎるサイクルから離れることができる一助になればと思います。
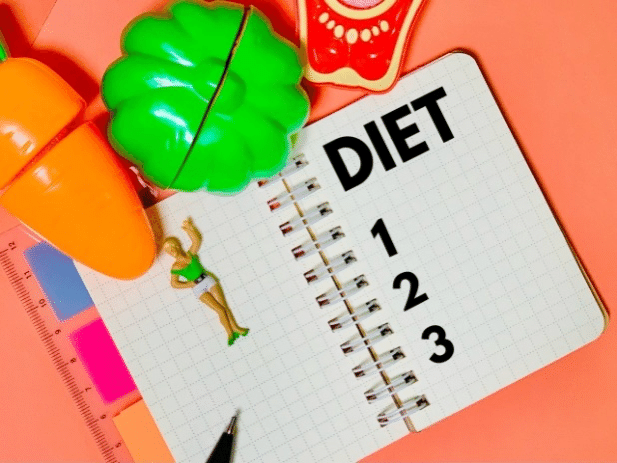
●まとめ
身体とって安全で大きな害がなければ食べてはいけないものはないのかもしれません。
しかし脳がそれをどう感じるかによって食べ過ぎたり、やめられなくなったりすることが起こるとされています。
身体の不調や疾患に近づきそうなときは「食べていること」にも目を向けてみましょう。
・食欲は「恒常性」と「快楽性」。
・食欲を調整するレプチンの働きを保てるようにしましょう。
・脳に食べたことを記憶させることは食べ過ぎのコントロールに役立つ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ストレッチ専門店ストレチックス
https://stretchex.jp/
本部著書&公式ブログ 監修・執筆
本部研修トレーナー 渡辺 久進
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!
> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <
▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!
▼ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」全国書店・アマゾンで発売中!
#ストレッチ専門店
#ストレッチ整体
#ストレッチマッサージ
#ストレッチトレーニング
#ストレッチジム
