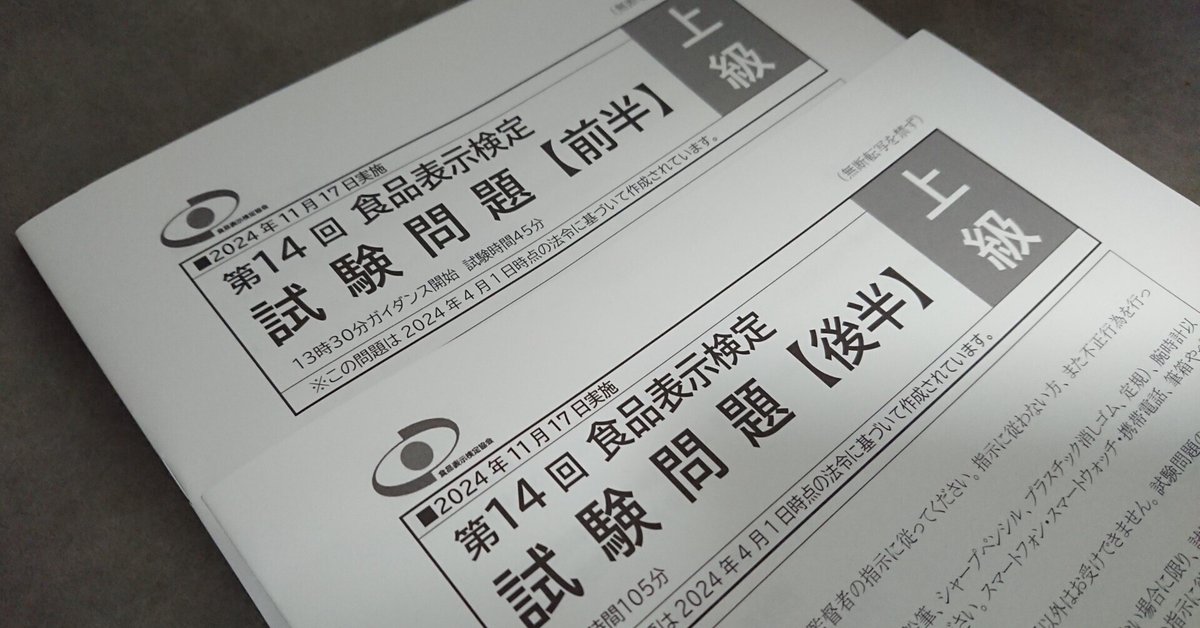
「第14回食品表示検定上級」の振り返り
◆合格発表
本日、「第14回食品表示検定上級」の結果が発表されました。

例年、合格率が10%台ということもあり、手ごたえも怪しく不安だったのですが、無事合格しました。
90点を超えたのは意外だった。ほっとした。
受験前はとにかく不安で、試験の情報を集めようとネット上を徘徊しまくったのですが、受験者が少ないこともあってか有用な情報がほとんど見当たりませんでした。
だもんで、今後の受験者の少しでもお役に立ちたい!との思いから、試験の傾向や私の勉強方法なんかをざっとまとめておきたいと思います。
設問の詳細は規約でSNS投稿が禁止されているので、モザイクだらけの所感となります。
また長文、乱文乱筆、誤字脱字、冗漫な表現、素行の悪さについては大目に見てください。
※追記※
2025年から上級試験もCBT形式に変更となるようです。
当記事はPBT(筆記)を想定して書いたため「手書きの練習」などズレた記述が随所にありますが、何卒ご容赦ください。
--
◆問1 択一問題(1点×35問)
問1は全35問の4択問題です。
大半が「次の文章から不適切なものを選べ」です。
終盤に数問、適切な語句を選ぶものや虫食いが出題されます。
試験範囲は関係省庁が公開している質疑応答集(Q&A)が中心です。
消費者庁の「食品表示基準Q&A」はもちろん、有機JASや特別栽培農産物、酒類業組合法、牛トレーサビリティ、米トレーサビリティなど、関連制度のQ&A集からも出題されます。
100ページ以上ある資料の中から、ほんの1~2行の文言が選択肢に出てくることもあるので、公開資料の最新版はできる限り収集して一度は目を通しておくと良いです。
私も膨大な量の資料に目を通しましたが、それでも見覚えのない内容が2、3問ありました。
本当にどこから出題されるか分かりません。
今年は公正競争規約に関する出題がありました。
条文までは覚える必要はないと思いますが、親法が景品表示法であるということや、どの業界に公正競争規約があるかとか、アウトラインは把握しておいたほうがいいでしょう。
虚を突くような設問がある一方で、特別用途食品を規定している法律など「今さらこのレベル出す?」みたいな初歩的な問題もいくつかありました。
食品表示基準の条文と消費者庁の資料を読み込むだけでも、25点前後は取れるかなという印象です。
問1のみ、試験翌日に正答が公開されます。
私は自己採点で34点でした。
合格するためには80点以上、つまり全体で失点を20点以内に抑える必要があります。
私は小論文と表示作成に自信がなく、どうしてもここで稼ぎたかったので、最も勉強時間を費やしました。
というか、問1対策で詰め込んだ知識は問2以降にも使えるので、ここに時間をかけて損はないはずです。
--
◆問2 小論文(15点)
お題について800字以内で記述する設問です。
文中に3つの指定キーワードを盛り込む必要があります。
毎年のように講評で指摘されている、
「文頭の段落下げ」「適宜改行」「指定キーワードに下線を引く」
以上3点は最低限守りましょう。
これらの不備で減点されて、結果79点だったら目も当てられない。
マジでこれで不合格になった人いると思う。
今年のテーマは「原材料の表示」、指定キーワードは「最も一般的な名称」「複合原材料」「特色のある原材料」でした。
お題は例年、「横断的義務表示事項」からの出題が多いです。
過去には「安全性に重要な影響を及ぼす事項」「表示禁止事項」という変わりダネな回もありましたが、今回で14回目ということもありネタ切れの感は否めません。
数年前に「名称の表示」が出題されていたりと一周した感じもあるので、そろそろ「原材料の表示」とか出るんじゃねえの、いやさすがにないかとグルグル想定していたのですが、ズバリでした。
ということで今後も「添加物」とか「アレルゲン」なんて超メジャーな事項が出題されてもおかしくないです。アレルゲンはサンプル問題で使われてるから出ないだろうと考える人が多いでしょうが油断禁物。練習もかねて一度は書いておきましょう。
小論文の勉強方法は、ダイソーで20×20の原稿用紙を買って来て実際に10本ほど小論文を書きました。もちろん用意した文章を本番で一言一句そのままアウトプットできるわけがないので、「このテーマで出題されたら、こんな内容を書こう」くらいの準備になります。
ここで最も重要なのは、「鉛筆で800字書くことに慣れる」です。
鉛筆で文章を書くなんて何十年もしていなかったので、その練習のつもりで何度も書く練習をしました。パソコンで作った文章を丸写しするだけでも、1文字1~2秒×800字=20分以上かかります。本番で推敲しながら書くことを考えれば、倍の40~50分は欲しいです。
もしヤマが外れても、横断的義務表示事項の勉強をしっかりしていれば、それなりのものは書けると思います。
尚、わたしは「小論文は最後に回す」と決めていたので、
先に問3,問4を解いてから、残り50分弱で取り掛かりましたが、めちゃくちゃギリギリでした。
結果は、焦りと緊張でボロクソの殴り書き。文字数も約750字と若干ショートした上、構成は雑で字も汚い。指定キーワードとそれにまつわる重要事項を強引に捻じ込んで何とか形にした感じ。手ごたえは15点中7、8点でした。
うろ覚えですが、何年か前に合格された方がブログで「自信がなくても最後まで書き切ったほうがいい」というようなことを言っていました。
採点基準が不明なのですが、誤った記述をせず、最低限の体裁が整っていれば、ある程度の点数は付くと思います。
--
◆問3 表示チェック(4点×5か所)
2つの食品表示中に合計5つの誤りがあり、それらを指摘して正しい表示に訂正する記述問題です。
個人的には、この設問が最もイージーだと感じました。
なぜなら中級テキストの範囲で対応できるからです。
問4の対策で賄えますし、特別意識して勉強もしませんでした。
あえて意識して対策するとしたら、
・「基本的には表示禁止だが、条件を満たせば表示可能」
・「表示の省略が可能だけれど、表示を禁止するものではない」
という事項を押さえておくと罠を回避できます。
いかにも禁止っぽい「~無添加」とか。
あとは、栄養成分表示(別記様式3)のルールをしっかり把握しておくことでしょうか。
この設問は前提条件にほとんど答えが書いてあるようなものなので、まずそこをしっかり読むことが大切です。うろ覚えでも前提条件で思い出せたりします。
ここの採点方法は、単純に1問4点×5だと思います。1箇所でも記述不備があれば0点。簡単な分、ケアレスミスに注意したいところです。
--
◆問4 表示作成(15点×2問)
前提条件に従って実際に表示を2つ作成する設問です。
勉強方法は、食品表示基準と中級テキストを読み込んだ上で、対策セミナーの模擬問題1問、そこで配布された過去2年分の問題を繰り返し解きました。
仕事で日常的に表示を作成している方は、作成自体の練習は不要かもしれませんが、ここも鉛筆で手書きなのでその練習はしておいた方がいいでしょう。
当日の持ち物で指定される定規はここで使いますが、なければフリーハンドでもいいとアナウンスがあります。緊張で手が震えると思うので持って行くことをオススメします。
今回の試験では、
「米トレーサビリティ法に基く産地表示は原材料名欄に表示する」
「製造所固有記号の応答義務は、製造所の所在地をすべて表示する」
という前提条件がありました。
完全に虚をつかれましたね。
表示のルールとして存在することはもちろん把握していましたが「実際にどんな文言でどの位置にどのように表示するか」は、この設問を見てうろ覚えだったことに気付きました。
選択肢があれば答えられるけど、実際に書いてみろと言われたら「思い出せねえ!」みたいなことがあります。
結果、どちらも微妙に間違った表記をしてしまいました。
それ以外のミスは2点、
・添加物の「リン酸塩」をなぜか原材料側(/の左側)に書いてしまう
→完全なるポカ。泣いた。
・配合表の「Lーアスコルビン酸Na」を見落としていた
→試験終了間際の見直しで判明して鳥肌。手書きのため、該当箇所以降の記述を消しゴムで全部消して書き直すしかないが時間がない。がやるしかない。ラスト10秒から答案回収までの記憶がない。震える手で「酸化防止剤(V.C)」と歪んだ文字を書いたのは覚えている。
その他は覚えている限りミスはなかったはずですが、採点基準が不明なので、これらのミスがどう採点されるのか不安でした。合格率の低さからも相当厳しい採点基準なのだろうと。
過去の講評で「加点狙いで任意の表示事項を記載しても加点はしない」というコメントから推察されるに、表示不備1箇所につきー3点とかではなく、表示全体の完成度を評点するものと思われます。
なので自己採点で表示ミスが複数あっても、それをもって大幅な減点を覚悟することもないかと思います。
◆総評
私の場合は、採点基準が明確な問1・問3で稼いで、変数の大きい問2・問4は祈るばかりという作戦でしたが、それが奏功したようです。
設問ごとの感触をまとめると、
・問1:ほぼ満点
・問2:殴り書きで750字、最低限の内容を盛り込んだものの汚字。
・問3:満点
・問4:明らかなミス2箇所、怪しいところ2箇所
って感じで、結果91点。
失点の内訳がちょっと想像つきません。特に小論文。意外と良くて12,3点取れたのか?あの内容じゃ考えづらいけど。
合格率の13.8%という数字は例年並みですが、受験者数は過去最低で500人を割っています。
初級・中級は年2回、毎回3000人前後が受験して合格率50%前後で推移しているので、上級もこれから盛り上がってほしいですし、そういう普及活動も地味にやっていきたいなと思っています。
もし上級の受験を考えておられる方で、試験について何か知りたいことがあれば、コメントいただければできる限りお答えします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(了)
