
腸脛靭帯炎になった最近のトレーニングの話
お久しぶりです。
今回の記事は、年始早々に膝を痛めてからの約1ヶ月のトレーニングについてのお話です。
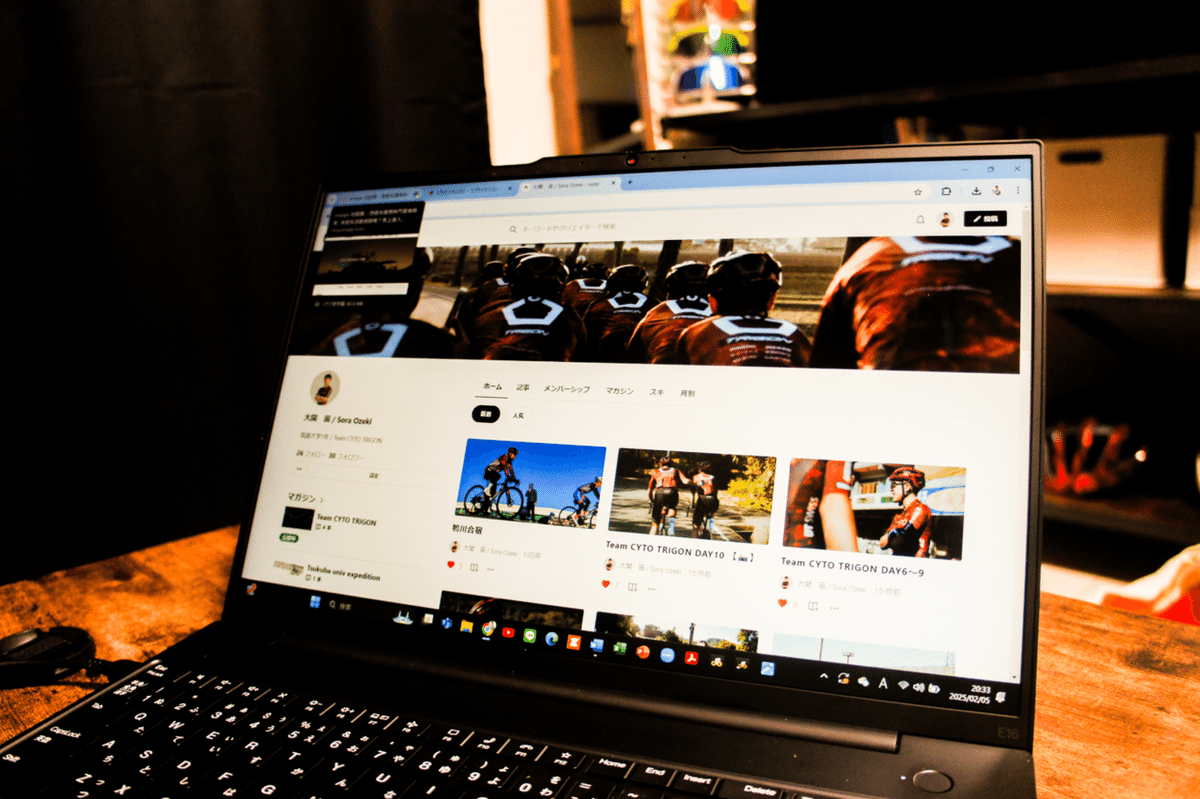
腸脛靭帯炎とは?
腸脛靱帯症候群(ITBS)は、ランニングやジャンプなどの動作時に膝の外側に痛みを感じるスポーツ障害です。 特にランナーに多く見られるため「ランナー膝」とも呼ばれます。 原因は、下肢の形態異常や筋力低下、柔軟性の低下などの背景に、過度なトレーニングや不適切なフォーム、疲労回復不足などが加わったオーバーユースです。
(Googleより)
なぜ発症したか?
経緯としては、今シーズンから海外チームで競技を行っていくことになり、そこで新しいバイクを年明け前に受け取った。サドル高は合わせたもののハンドルリーチや全体のポジションは全く同じではなく今までとは少し違う踏み方で海外での練習を行っていたが、バイクを受け取った次の日のメニューがフォトデイ+レース走ということもあり慣れないポジションでの違う踏み方で膝に痛みが出てしまったと考えられる。そこから海外滞在時に乗り込み練習が重なり腸脛靱帯症候群(ITBS)につながってしまったと思う。

発症後のトレーニング
帰国し2日後くらいに4.5時間の練習に行くも最後の1時間あたりで痛みが急増し、全く踏めない状態に。2日ほど時間をおいてから、膝のちょっとした痛みや違和感を抱えたまま前回の記事でも取り上げた鴨川合宿に参加したがやはり踏むこと(脚を回すこと)ができなかった。鴨川合宿が終わりすぐに自転車競技に流通している整体に行きひざを見ていただき腸脛靱帯症候群と発覚した。
医師の診断では「z1強度で毎日1〜2時間ほど軽く乗ってほしい」とのことだったのでリカバリー強度でトレーニングを続けることにした。
そのトレーニングを続けながら週に2回ペースで整体に通うと1週間ほどで痛みが消え踏める状態へと改善。

この期間に変えたポイントとしてはセルフケアの時間と膝の痛みを和らげるストレッチを増やしたこと、クリートの位置を外よりから内よりに変えたこと、そしてブラケットの握り方を変えたこと、身体のメンテナンスにお金をかけるようにしたことの主に4つである。セルフケアやクリート位置は競技を行っている人なら言わずもがな気にしている要素であるし多くの情報が出回っているので今回は書かないこととする。
ブラケットの握り方でペダリング時の体全体の筋肉の使い方が変わった。今までの握り方はよくありがちな親指、人差し指で握り肘が張り、肩に力が入ってしまうスタイル。また手首が内旋し肘が内側に入っているよくありがちなもの。


小指、薬指に力を入れて握ることにより肘の緊張がとけ、さらには背中に力が入り体全体でペダリングできるようになった。
また、意外と軽くみている身体のメンテナンスにお金をかけること。自分自身も今までは整体やマッサージにお金をかけていなかったが、怪我してしまってから重要さに気付いたのでオススメしたい。
膝が改善されてからのトレーニング
冬季の乗り込みを再開。週に15〜25時間を目安に乗り込みを続けている。


だんだん踏めるようになっているし、実際に最大パワーも更新。日々の入念なセルフケアとブラケットの握り方で気持ち良く乗り込みをこなせている。カフェライドの日としっかりz2の上で踏む日、LSDの日と分けてメリハリをつけながら競技部の仲間たちと楽しくトレーニングを行なっている。


2月中旬に出場予定の学連の明治神宮クリテに向けて、だんだんインターバル練習も入れつつ調子を上げていきたいところである。
今回の記事はここまで!最後まで読んでいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう👋
#BEACYTOIST #ACCOMPLISHBEYONDGOALS #trigon #ensage #garmin #maxxis #dtswiss #heroic1 #kplushelmet #vightoptics #betery #thule #忠欣 #dynamicbikecare #casterbike #mrbike #ambitiouscyclist #flatourfast #engineeringper #yamaichiriceadventure
