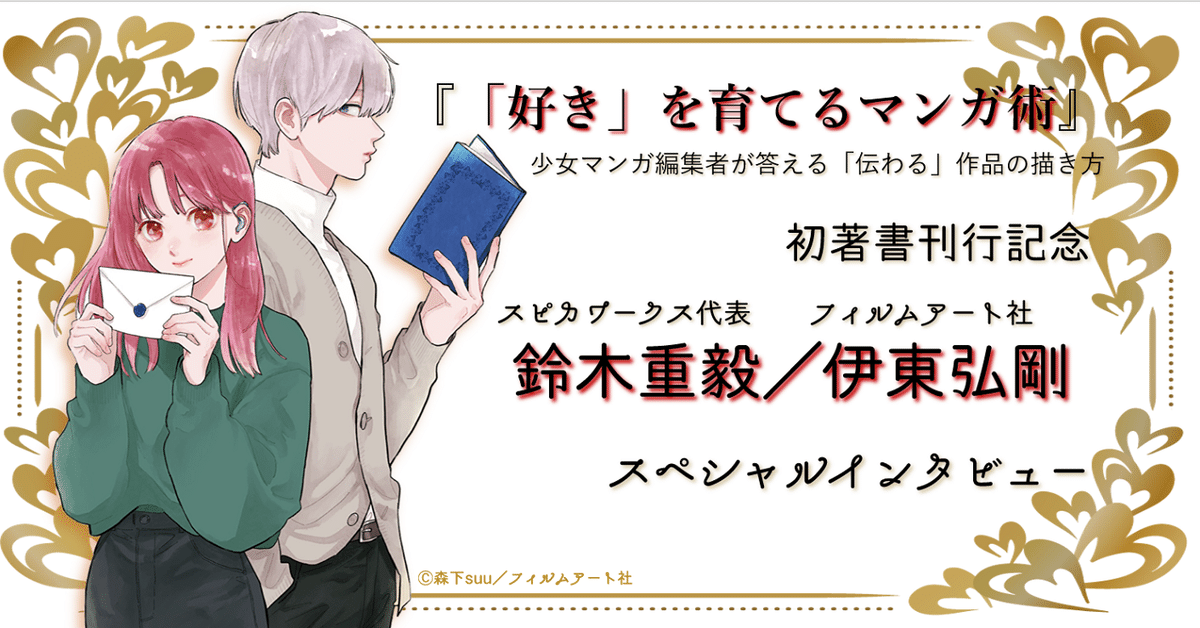
『「好き」を育てるマンガ術』刊行記念 鈴木重毅/伊東弘剛 スペシャルインタビュー
2023/9/26(火)、弊社代表・鈴木重毅(しーげる)の『「好き」を育てるマンガ術~少女マンガ編集者が答える「伝わる」作品の描き方』が、いよいよ発売されました! 代表にとって本作は、初の著書となります。

◆❖◇◇❖◆『「好き」を育てるマンガ術~少女マンガ編集者が答える「伝わる」作品の描き方』内容紹介◆❖◇◇❖◆
どうしたらキャラが立つ?
物語の膨らませ方は?
読者をキュンとさせるにはどうしたらいい?
スランプの解消法は?
担当作の累計発行部数4000万部超えの
敏腕編集者が、あなたの創作のお悩みに答えます!
森下suuインタビュー、編集者座談会も収録
この発売を記念してスピカワークスでは、本作の担当編集者であるフィルムアート社・伊東弘剛さんと代表に、スペシャルインタビューを行いました! 伊東さんには編集者としての経歴から代表を知ったきっかけや執筆を依頼するに至った思いまでを、代表には初めての著作に対する感想と、書き上げてみての気持ちを聞いてみました。
インタビュアーはスピカワークスの広報Tが務めました。代表の初単行本とともに、ぜひじっくりお読みください。
◆❖◇◇❖◆◆❖◇◇❖◆◆❖◇◇❖
◇担当編集者:伊東弘剛さんインタビュー
◆編集者としての出発点
インタビュアー・広報T(以下、T):まずはプロフィールからお伺いしますね。伊東さんの編集者としてのはじまりは、どういったところからだったのでしょうか。
伊東弘剛さん(以下、伊):現在勤務しているフィルムアート社は、4社目になります。元々はKADOKAWAグループ内のWEB系の媒体で働いて、その後、Webメディアの「映画ナタリー」に立ち上げスタッフとして入りました。当時は編集ではなくWEBのライターを6~7年担当して、それからデザイン雑誌『MdN』へと移り、雑誌編集者に。その雑誌がなくなったタイミングで、フィルムアート社へ転職して書籍編集者になりました。
T:大学卒業時は、編集者やライターを志望していましたか?
伊:大学は美大で映画学部に所属していたので、入学当初は「映画を作りたい」と思っていました。当時はギャラリーのアシスタントや演劇祭のスタッフをやっていたこともあり、「作る現場」にいたかった。ただ、「どうしてもこれが作りたい!」というものが自分の中に見当たらなくて。どちらかと言えば、自分が好きだったり関心があったりする作り手さんたちがものづくりをする環境を、セッティングする側の人になりたいと考えるようになりました。だから大学の卒業時には、編集者か学芸員になりたいと思うようになって。でも学芸員は狭き門で、難しい。そう思って編集者の道を選んだものの、希望の編集部には入れずライティングの方から始めた、というのがこれまでの経歴です。
T:編集者になるまでの道は、かなり厳しかったんですね。そして在学時は作り手側にあった伊東さんの気持ちが、環境とともに徐々に変化していき、結果としてサポートをする立場に回っての今、と。
伊:そうですね。思い出話をすると、在学時に僕が習っていた先生が、諏訪敦彦(すわのぶひろ)監督という、ちょっと特殊な作り方をする映画監督で、脚本をほぼ書かないんです。「アウトラインのようなものだけ少し書いて、あとは協働していく」タイプで、神様的な位置に作り手/監督がいるのではなく、様々な人の協働の中から作品を作っていく人だったこともあって、「自分がイニシアチブをとらない形で作ることもできるんだ」「自分が作り手として表に出る以外の方法もある」といった気持ちを、より強く持ちました。
T:モデルといいますか、見本となる背中があったんですね。
伊:そうです。それで最初に作った本が、その諏訪監督の本でした。
T:なんと! 学生と先生の関係から、編集者と作家の関係に。それはフィルムアート社さんに入られてからのことですか?
伊:コロナ禍の直前、2019年に入社してから企画書を書きました。
T:入社後は、フィルムアート社さんが主に出版されている映画や美術、芸術系の書籍を担当されていた?
伊:はい。先ほどお話したように最初に編集したのは諏訪敦彦監督の本で、諏訪監督がそれまでに書いていた批評やエッセイ、インタビューなどを集め、そこに7万字ほどの書き下ろしを加えたもので、全部で500ページくらいになりました。
T:初めてにしていきなりの大著!(笑)。そうして映画の本を作られた後は?
伊:僕が入社する前からフィルムアート社が力を入れていた創作術の本も、仕事の柱になりました。最近は発表するメディアが増えたことも手伝ってか、どのジャンルでも作品数が増え、広く、あるいは深く届けるためには切り口が重要なように感じています。ですから、創作術の本でも切り口があるものを作っていきたいと考える中で、「鈴木さんとご一緒したいな」と思ったのが、今回のきっかけです。あとは、僕の好きな森下suu先生を担当されている方、という点も大きかった(笑)。森下suu先生にインタビューのご出演と装画のご制作をお願いでき、この形で実現できてよかったなと思っています。

◆代表に執筆を依頼したきっかけは
T:代表に声をかけて、創作術の本を作ろうと思われたのはいつ頃でしょうか。
伊:2021年に開催されたIMARTがきっかけです。コンパスの石原史朗さんと対談されているのを拝見しました。そのトークの内容が面白く、かつ話を伺いながら「ずっと現役でいたい方なんだな」と感じて。その時に「少女まんが勉強会」と「まんが編集の会」の話もされていて、「ご自身で作品を作りたいだけではなく、もう少し広く、マンガの状況や業界を良くしたいと思っていらっしゃる方なのだろう」と関心を持ちました。
T:2年越しの反響を、こんな形で確認できるとは! 代表、よかったですね(笑)。
弊社代表・鈴木@しーげる(以下、鈴):何事もやっておくものですね。
伊:その時にスピカ賞のお話もされていて、「若手の方がデビューできるきっかけを、自分で会社を立ち上げて作っている」のが素晴らしいなと思いました。自分が良いと思うものを真摯に作られているだけでなく、若い人にチャンスを作ったり、自分の漫画編集者としてのノウハウも惜しみなく提供されている。こういう人なら、作り手に寄り添った良い本が作れるのではないかと考え、依頼しました。
T:スピカワークスや、鈴木の存在を知ったのもIMARTがきっかけですか?
伊:IMARTでしたね。「しーげる」という名前は知っていたかもしれません。でもその名前が『となりの怪物くん』や『好きっていいなよ。』といった作品とは繋がっておらず、『ゆびさきと恋々』でようやく認識した感じです。あだ名を先に知って、IMARTでカチッとハマりました。
T:代表にとっては初の著作です。依頼される時、重視した点はどのあたりでしょう?
伊:長く「ヒットメーカーである」ことは大きいポイントでした。それはメディアミックスをたくさん経験しているとか、複数の漫画家の方と何作もヒット作を出されているとか、経験値の高さの証明でもあるように思って。また実際にお願いをする前には、まんが編集の会に個人として入ったり、少女まんが勉強会の動画を観たりしました。結果、「この感じで答えてもらえたら、具体的かつ説得力のあるものにできる」と手ごたえを感じました。
◆作り始めてみての印象は
T:実際に作り始めて、印象に残っていることはありますか。ちなみに、漫画編集者と本を作られるのは初めてで?
伊:初めてでした。鈴木さんとやっていて印象に残ったことは……最初に作っていただいた質問表でしょうか。弊社で出している本を参考に、「質問があって、回答があって、まとめがある」という構成を考え、鈴木さんに「手始めに、質問を50個くらい作ってみてもらえますか」とお願いしたんです。そうしたら120個くらいの質問が帰ってきて(笑)。
T:事前の企画書には「全部で30〜50くらいの質問で」と書いてありますね。
鈴:これは「編集者として頼まれたら多めに返せ」の原則に基づいての結果です(笑)。
T:編集者魂!(笑)
伊:「たくさん来たな!」が最初の印象でした。加えて若手の、たとえば少女まんが勉強会の参加者の方にもその質問を見せて、実際にヒアリングした内容を反映くださっていたので、この段階から具体的に漫画家志望の方や新人の方にどういうものが届くのか、調査のうえまとめようとしてくれたこともすごく印象に残っています。
T:ターゲットと目的の明確化ですね。
伊:そうですね。その後は、タイトルに入っている「好き」という、本書にとって「コア」となる部分が、どう作品化したらマンガを読んでいる人に「伝わる」ようになるのかを具体的かつ説得的に書いていただく作業が続きました。実は最初に原稿をもらった時点では、「『好き』という言葉は抽象性が高いのではないか」と、少し危惧していて、次回の原稿で指摘して調整していこうとしていたのですが、次の原稿をいただいた時には、「『好き』をどう具体的にするか」といったことが書かれていて。僕が言うまでもなく、ミクロな視点を持ちつつマクロな視点もしっかりキープし続けてくださった。だから最初から最後まで安心していました。
T:初めて執筆する著者としては、抜群の安定感……!
伊:編集作業が終わってメールを見返したら、僕は鈴木さんに対して「面白かったです」「具体的にしてください」「説得的に書いてください」の三つくらいしか言っていなかった(笑)。この本を作るうえで一番怖かったのは、編集者の方が書く本ということで、読者の方から「でもあなたは描いていないでしょ」と言われることでした。ですので、「漫画家さんの『例』はしっかりと書いてください」といったオーダーや、「納得できる解説にしてほしいです」といったお願いをしていて。それが「具体的にしてください」と「説得的に書いてください」の意味でもあったのですが、それ以外はあまり言うことがありませんでした。鈴木さんはレクチャーや講演に慣れていることもあり、言葉の選び方も面白い。「ネームにも旬がある」とか、「共感も『シンクロ』と『肩入れ』がある」とか、どういう言葉で伝えれば若い描き手の方や志望者の方へ届くかがわかっている、と思いました。原稿が来るたび「面白い言い回しだな」と、楽しんで編集させていただいた感じです。
T:作業を通して、代表はどんな編集者だと思われましたか。
伊:「漫画家さんのことを第一に考えている方」だと感じました。執筆中に「漫画家さんの『例』はしっかりと書いてください」とお願いした時、鈴木さんは該当する漫画家さんに内容をすべて伝えて、許可を取っていて。漫画家さんのマイナスにならないよう、すごくケアをされていました。今回収録されている森下suu先生のインタビューでも、事前にしっかり質問表を作ることで、できるかぎり負担をかけないように努めていました。漫画制作以外の負担を減らすことで作品に集中してもらおうとしているのだと思いましたし、信頼できる方だなとよりいっそう感じましたね。
◆少女マンガと伊東さん
T:では最後の質問となりますが、これまで読んだ少女マンガで、お好きな作品があれば教えてください。
伊:幼い頃は近所に新古書店があったので、新旧に関係なく、いろいろな本を読んでいました。萩尾望都先生や山岸凉子先生、大島弓子先生から影響を受けています。
T:それはご自分で、棚から選んで?
伊:そうですね。よしながふみ先生、くらもちふさこ先生も読んでいました。お二人とも同じくらい好きです。よしなが先生は、中学生くらいの時にドラマで「アンティーク(=『西洋骨董洋菓子店』)」がやっていて、原作を読んだらマンガも面白くて、そこから芋づる式に。萩尾先生は『ポーの一族』を友達に借りた気がします。
T:漫画を読むお友達がいらっしゃったんですね! ちなみにご家族の女性陣からの影響は?
伊:くらもちふさこ先生は、姉から教えてもらった覚えが……。『海の天辺』が大好きで、コマ割りがすごく印象に残っていて。そうそう、あとは森下suu先生の作品も、感情表現を丁寧に描かれるところが大好きです。最近読んだ作品だと、ウオズミアミ先生の『冷たくて柔らか』や高野ひと深先生の『ジーンブライド』、ヤマシタトモコ先生の『違国日記』が好きでした。
◇著者:鈴木重毅(しーげる)インタビュー
◆初めての執筆は
T:伊東さんから今回の本のお話があった時、どんなふうに受け止めましたか?
鈴:単純に嬉しかったです。同業の編集者の方が「本にする価値がある」と思ってくれての依頼ですから。
T:今までに「本を書きたい」と思ったことは。
鈴:あまりなかったですね。昔から自分の中に「頼まれていないことをこちらから語る」思想がなくて。ただ、『デザート』で編集長をする少し前頃から、漫画家さんや志望者さんから相談されることが多くなり、しばらくしてそれらの質問がどれも似ていることに気づいて、「個別に回答していると手間もかかってしまうし、回答を待たせている間に誰かが小さなことでつまずいてしまうのはもったいないな」と思って、自分のnoteで漫画家さんについて書く時は、それを念頭に置いていました。
T:「誰かの悩みに応える」が基本にあったんですね。ちなみに今回の執筆作業は、どんな感じで進んだのでしょうか。
鈴:伊東さんからは最初に「書きやすいところからで」と言われていたことにくわえて、伊東さんが進行の感覚を掴むために「このQ&Aは先に欲しい」というリクエストがあったので、まずはそこから書き始めました。だいたい7つくらいの質問でした。2回目の時も同じく、項目の順番は関係なく、バラバラに書いて出しました。
T:全体が歯抜けで埋まっていく感じだったんですね。
鈴:最初はそうだったんですけれど、質問が55個あって、ひとつがだいたい2000~3000文字くらい。それを1か月半ごとのスパンでとなると……。3度目で「これ、書いた内容の繋ぎ方を忘れちゃうな」と気づきました。
伊:(笑)。
T:本としての流れ的に、ですか?
鈴:そうです。例えば先に7部の質問に対する答えを書いてしまうと、それよりも前の部に載る質問を回答する時に、以前回答した質問が、ここではまだ触れていない流れだったかどうだったかがわからなくなってしまうんです。
T:それは確かにありそうですね。張った伏線が分からなくなるのに近そうな。
鈴:なので途中からは、順番通りに書いていきました(笑)。
T:なるほどー。その問題は、伊東さんも途中で気づかれました?
伊:どちらかと言うと僕が気にしていたのは、「順番に書いていった時に、途中でつまずいて先へ進まなくなる」ことでした。それが最初の方から起きてしまうと、良くないなと。なので、原稿の提出が途切れないことを重視して、まずは鈴木さんが書きやすいところから進めてほしいと考え、先に鈴木さんがおっしゃっていたようなオーダーにし、書き終わり推敲していくタイミングで整えていこうと考えていました。ですが、鈴木さんがご自身でこの進め方の難点に気づかれてからは、部単位でまとめて回答してもらった記憶があります。
◆執筆作業の感想
T:2021年6月にお話を受けて、書き始めたのはいつ頃からでしょうか。
鈴:2021年11月の提出が最初ですね。その前にも、質問内容の擦り合わせのためにやり取りをしていました。
T:では執筆期間は2年以上。本当に長いマラソンでしたね。
伊:いや、本当にお疲れ様でした……! 2022年は、年末にも一度提出してもらいましたよね?
鈴:そうですね。あれは、僕が年末に全ての営業が終わってからの方が落ち着いて書く時間を取れるので、年末に出させてもらっただけの例外ですが。毎回、いくつかの締切をいただいて、質問もある程度まとまった単位でもらっていたので、最終的には11回に分けて回答を提出しました。最初の4回はすごくスムーズに進んで、そこから5回目の提出の間が、結構時間をもらいました。
T:その時期は、どの部分を書いている時に当たりますか?
鈴:4部ですね。お話の構成やネームについての部分は、講義などで漫画の絵を使って説明する分にはスムーズなんですけど、全部を文章で説明するとなると格段に難しかった。だから最終的には、絵も入れてもらいました。
T:そんな執筆作業の中で、楽しかったこと、もしくは発見したことを教えてください。
鈴:楽しかったことは、やはり日頃とは逆の経験ができたことです。「人が見て、チェックしてくれることがこんなにも嬉しいことなんだ!」といった楽しさがありました。
T:へ~! ダメ出しなどに怖さを感じず?
鈴:ダメ出しは、もっとくれても良かったくらいです(笑)。「人の目にどう映るのか」というのは、普段経験できないことだったので。もちろん、作家さんに案をぶつけて、それを採用する・しないを決めてもらう時に少しはありますけれど、「自分の名で世に出るものを他の人がチェックしてくれることはなんて楽しいんだろう」と思っていました。
伊:ダメ出しに関して言うと、Q&A方式だったこともありますが、事前にしっかりQを設定することができたので、そこでの解がどういうものになるのか、ある程度目星をつけられたんですよね。鈴木さんからの解も大きく外れることがなくて。なので特に大きなダメ出しもなく、基本的には先ほど話した「具体的に」と「説得的に」の二点だけお話しました。
鈴:そうそう、回答を提出した後に伊東さんからもらうお返事が面白かったです。「そういう考え方もあるな」と思うことが多くて。この本の中にも書きましたが、「自分の意図が相手にどう伝わっているのか」がわかるのは、とても楽しいことでした。あと「発見」の意味では、今まで文章をたくさん書いてきたつもりでも、マンガ雑誌の読者のテンションに合わせた記事を書き続けてきたこともあって、自分の文章がものすごく口語寄りになっていることがわかりました。癖ですね。
伊:でも本文の中で、その部分はあえて残しました。口語調のほうが鈴木さんの人柄が出るので。
T:普段書いている文体や、媒体に引っ張られることはありますよね。執筆していて苦労されたところはそのあたりに?
鈴:そうですね。他人の文章をきちんとした文章にまとめ直すことには慣れていますが、自分が一から書く文章は難しいなと実感しました。たとえばインタビューの文字起こしをする場合、記事には実際にインタビューをした内の10分の1くらいしか使えないことがあるので、割と圧縮して文章にしますよね。だからきちんとした文章になりますが、今回の場合、1つの質問に対して2000~3000文字というのが、自分にとってはやや多く感じていたので、それに合わせて内容を膨らませていくにつれ、口語調になってしまいました。多いものを少なくしていくと「この言い回しはいらないかな」と切っていけるのですが、今回の場合は如実に癖が出ましたね。ライターさんを尊敬しました。
伊:いや、でも鈴木さんは、どんどん上手になっていかれたと思います。この本を読者の方がどう活用するかにもよりますが、創作術の本として読むと、それぞれの章がかなり短く具体的にまとめられ、かつ段階的になっているので、何かにつまずいてしまった時の救急箱的な存在、起き上がるための手助けをできるような本になっていると感じています。
◆本を書き上げてみて
T:この本を書き上げての感想と、著書を持つことに対しての率直な感想を教えてください。
鈴:書き上がって……、ホッとしました(笑)。これは伊東さんにも途中で話していましたが、原稿の提出を初めて遅らせた時があって。それが4部のあたりだったんですけれど、上手く書けなくてバラバラで書いていたやり方を、順番通りに書くよう変更したんですね。それで「間に合いそうにないかもしれない」と思った時に、日ごろ作家さんに締切を迫っている側の人間なのに、自分が締切に間に合わなかったらどうしようと焦りました。編集者としては雑誌の編集長までやったので、なるべく伊東さんに迷惑をかけない、赤字の入らない原稿にしようと思ったのですが、全然で(笑)。何度もやり直して、最後までしつこく赤字を入れさせてもらいました。
伊:(笑)。
鈴:あと自身の著書を持つことについては、なかなかな緊張感がありますね。世の中に、自分の名前で本が出るということなので。この内容が確定して残り続ける、しかも有料じゃないですか。noteやブログは無料のものもありますし、後から編集が利く。でも本はそうではないし、この本自体への責任感もあります。今回の執筆を通して、本を作る側の緊張感や最後まで書き直したくなる気持ちを痛感しました。
T:編集者の方が作家側の立場に立つ機会は、なかなかありませんよね。
鈴:そうですね。とても貴重な体験だったと思います。
T:それでは最後に、本に込めた気持ちと、本を手に取ってくれた方へのメッセージをお願いします。
鈴:少しでも誰かの役に立てれば嬉しいです。漫画家さんのお話を聞いていても、過去の自分や新人の編集者さんもそうかと思いますが、聞きたいことが聞けないままでいるとか、何を聞いていいのかがわからない方がたくさんいます。そういう人の力になればいいなと思って書きました。とはいえ、この本に書いてあることがすべてでも、正解でもないので、みなさんなりのやり方を見つけてほしいですし、この本の内容と比較して、自分のやり方に自信を持ってもらうのでも良いなと思います。それぞれの方に、良いように使ってもらえたら嬉しいです。
T:ありがとうございました! たくさんの方に、この本が届くといいですね。
◆❖◇◇❖◆◆❖◇◇❖◆◆❖◇◇❖
担当編集者&著者の二人によるインタビュー、楽しんでいただけたでしょうか。編集さんがどんな思いで代表に声をかけ、編集されたのか。そして代表が初著書にどんな思いを込めて世に送り出したのかを、少しでもお伝えできたならば幸いです。
『「好き」を育てるマンガ術』が、描き手のみなさまに長く広く届き、執筆活動の一助となることを、心より願っております!
★☆ Twitterは、弊社・契約作家さんの情報を中心に発信中 ☆★
→ スピカワークス (@spica_works) | Twitter
★☆ Instagramも随時更新中!→ スピカワークス Instagram ☆★
