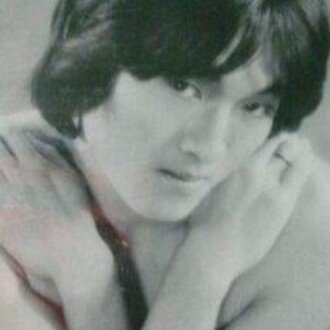『男はつらいよ』寅次郎の分身としての博
僕は『男はつらいよ』シリーズの熱心なファンであったわけではない。それでも、テレビでかかったときは自然とチャンネルを合わせているし、何作かはレンタルビデオで観ている程度のファンであることを最初にお断りしておきたい。内容的にもルーティンに則ったシリーズなので、作品をごっちゃに記憶していたりするわけだが、本来プログラムピクチャーというのは、そういう観方も正しいと自分に言い聞かせている。
やはり好きなのは、森川信が「おいちゃん」を演じた初期作品である。寅が厄介ごとをもちこんでくるたびに、「バカだねえ…」とぼやくところなんか、それだけでも笑いを誘った。シリーズを通して「おいちゃん」は都合3人登場するが、寅と取っ組み合いのできる、おいちゃんは初代の森川だけであろう。森川は浅草軽演劇の出身。主演の渥美清はフランス座のボードビリアン、おばちゃん役の三崎千恵子は新宿ムーランルージュのレビューガールだったことを考えれば、初期シリーズの醸し出す軽妙な笑いは、軽演劇の流れからくるものだったのかもしれない。

海外でもファンが多い同シリーズだが、わけても日本文化に造詣の深いジャック・シラク仏大統領(当時)は、シリーズ全作を自宅にコンプリートしているほどの大ファンで、渥美が死去(1996年)したときは、『男はつらいよ』に重ね合わせ、「古き良き日本の制度が終わった」というメッセージを発している。「古き良き制度」とは、家族を意味するのはいうまでもない。欧州でもまた伝統的な家族というものが過去の遺物になりつつある時代であった。
サザエさん一家とともに、日本のノスタルジックな家族像の象徴とも思われる、とらやファミリーだが、実際は、決してスタンダードな家族構成であるとはいいがたい。そもそもとらやを構成するのは、おいちゃんとおばちゃんの夫婦だけである。さくらは結婚独立しているし、まして寅は年に一二度舞い戻ってくる渡り鳥であって、彼にとってとらやもまた人生の止まり木に過ぎないのだ。おいちゃんからすれば、寅は死んだ兄の息子。本来ならとらやを継ぐべきは寅であり、そのへんの遠慮が、寅の暴走を許容する要因でもあるようだ。さらにややこしいのは、寅が妾腹という設定である。初期シリーズでは、とらやと寅のそういった微妙な関係が見えて興味深い。
寅は無学な男だが、決してバカではない。むしろかなり理屈っぽい思考をする人物である。特に、第15作で、自分のぶんのメロンがないと知った寅がとらやの面々にネチネチ悪態をつくシーンなどでは、彼の論理の組み立て方がよくわかる。
そんな寅の最高の理解者といえば、義弟の博ではないか。思えば、博は寅の代弁者、寅の特異な論法をおいちゃん、おばちゃんに解説伝達する“通訳”の役目を担っている。「義兄さんの言いたいのは……ということではないでしょうか」といった具合に。
博も、とらやのファミリーでありながら、立場上はやはり客分であり、風来坊の寅とどこか似ている。ともに父親に反発して家を出たという境遇も一緒だ。大学教授の息子らしく博も地頭はかなりいい。
いわば、博は寅の分身ともいえるし、寅を実直な堅気にした存在、遊牧民である寅が定住し農耕民族になったとしたらと想像させる存在でもある。小さな印刷工場で地道に働く博にとって時に自由人の寅はある種の憧れの存在であろう。それは、妻子をもたぬ渡世人・寅が博に向けるまなざしと表裏なのである。

もし、シリーズを再見する機会があれば、ぜひ博に注視してみてほしい。
初出・『昭和39年の俺たち』2025年1月号

いいなと思ったら応援しよう!