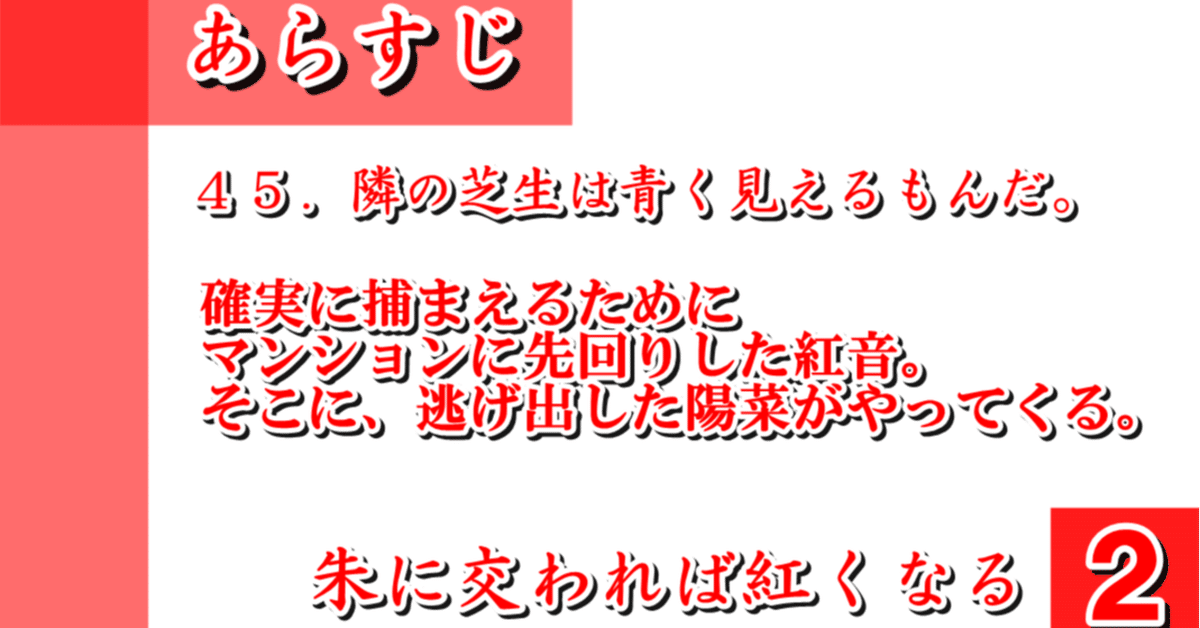
45.隣の芝生は青く見えるもんだ。/朱に交われば紅くなる2
本編
「はぁ……」
紅音(くおん)は一つ、ため息をつく。
場所はマンションの一階エントランス。
この建物の一角には、佐藤(さとう)家の部屋がある。
結局、あの後紅音は、陽菜(ひな)を見つけることは出来なかった。
反応が遅れた、というのもある。
自らの荷物を回収してからのスタートだったため、最初からハンディキャップのある状態だったというのも大きい。
ただ、それらよりももっと大きな理由はお互いの真剣度相にあった。紅音は今になってそう思う。
あの時、陽菜は間違いなく全力で逃げようとした。
では、紅音はどうか。
もちろん、中途半端に追いかけるフリをしていた訳ではない。紅音なりに、真剣に、陽菜を追いかけていたのは事実である。
ただ、その中にどこか“油断”があったのは事実である。
どうせ、そんなに真剣に逃げてなどいないはずだ。
いくらバリバリの運動部とは言え、こちらも運動神経は良いのだから追いつけるに違いない。
荷物だってあちらの方が多いのだから、いずれ追いつける。
どれもほんのわずかな油断に過ぎない。しかし、積もり積もれば大きな差となる。結果として紅音は一度たりとも陽菜の姿を補足することが出来なかった。
そこで、紅音が取った手段が先回りだった、というわけだ。
「ちょっとずるいけど……いいよな」
紅音はぽつりと、そう呟いた。誰が聞いているわけでもないのにも関わらず。
いや、違う。
誰も聞いていなくてもよかったのだ。
だって、これは自分を納得させるための言葉だから。
そうでもしないと、自分で自分を納得させられなさそうだから。
「はぁ…………」
再びため息。
流石に、帰ってこない、ということは無いと思うが、ある程度時間を置いてから帰ってくるという可能性はある。
そして、そうなった場合、紅音には部屋へと入る手段がない。運が悪いことに、文(ふみ)は今日、遅くまで返ってこないという。
そのため、陽菜が返ってこない限り、紅音はずっとここで待ちぼうけなのだ。別に自宅に帰ってしまっても問題は無い。
佐藤宅に置きっぱなしになっている荷物だって、大したものではない。後日陽菜に言って、返してもらえばいい。流石にそれを拒むほど嫌われてはない……と思いたい。
「はあああぁ…………」
三度ため息。
陽菜は逃げ出した。
それは間違いない。
ではその理由はなんだ?
直接の原因は、間違いなく月見里との勝負に負けたからだ。それは誰が見ても明らかだ。
ただ、それだけであそこまでの拒絶を見せるというのはちょっと異常だ。
紅音との勝負に負けた時だって、ああはならない。せいぜいが思いっきり悔しがりながら、「覚えてなさい!」とかませ犬らしい台詞を吐き捨てて逃亡するのが関の山だ。
そこには今日のような拒絶が含まれることは決してないはずだ。ましてや相手は月見里だ。しかも条件は陽菜にとっては超絶不利なもの。それで負けただけでああも悔しがるというのは一体、
「……あ」
「お」
瞬間。
目が合った。
陽菜だった。
「……!」
後ずさろうとする陽菜。紅音は手をかざして、
「待った待った。行かないでくれ」
「…………なんでここにいるのよ」
なんで、と来たか。
その理由などいくらでもある。陽菜の感情を一切考慮しなくてよいのであれば、まず紅音のスマートフォンと、その他もろもろの荷物はまだ、佐藤家の部屋に置きっぱなしだ。少なくともそれを回収してからでなければ帰れない。このままだと月見里たちに連絡一つ取ることが出来ない。
が、それ以上に重要なことがある。
それは、
「そりゃ、逃げられたからな」
「っ……!」
固まる。
逃げた、という自覚はあるようだ。
ただ、それを突き付けるだけではなんの意味もない。
だから、
「取り合えず中、入らないか?ここで立ち話しててもなんだろ?」
陽菜はそんな提案に応じず、
「なんでまだここにいるのよ……なんで、あの子のところに行かないのよ……」
「あの子?」
「月見里(やまなし)さん。それと、あの先輩たち。一緒に特訓してたんでしょ?今日も、一緒に特訓するつもりだったんでしょ?だったら行きなさいよ。ここにいちゃ駄目でしょ」
どういうことだ。
確かに、紅音は月見里たちと特訓をしていた。それは間違いない。そして、彼女たちの連絡を実質無視するような形で陽菜と一緒にいた。それは事実である。ただ、もしそうだとしても、
「そりゃ、先輩たちと練習するつもりではあったけど……でも、それとこれとは」
「関係無くてもよ!」
いつにない大声。陽菜は続ける。
「だって、あんた……あの子の友達なんでしょ?だったら、そんな……中途半端な……駄目よ。そんなの。私にかまけてないで、あっちに行かなきゃ……」
なんだ。
一体何を言っている?
そりゃ、月見里とは友達だ。でも、
「だからと言って、佐藤を放っておいていいってことにはならんだろ」
「……っ」
そうだ。
紅音にとって月見里は、いまや大事な友達だ。それは間違いない。
ただ、それとこれとは話が別である。
今までずっと、憎まれ口や、負け犬の遠吠えは吐いてきても、ここまでの悔しがり方と、拒絶を見せたことのない陽菜。それを放っておいていいというわけではない。
もちろん、紅音にとって陽菜はかませ犬寄りのライバルだ。それは間違いない。今後も試験の度に紅音は陽菜に勝ち続けるつもりでいる。
けれど、それ以外はどうだろうか。
今日一日……いや、昨日からの二日間。紅音は一つだけ分かったことがある。
彼女は、佐藤陽菜は、一人の年頃の女の子に過ぎないのだ。
何を馬鹿なことを、と思うかもしれない。それこそ葵(あおい)あたりには「そんなことも分かんないなんて、まだまだだな~」なんて言われてしまうかもしれない。しかたない。紅音にとってはそれだけ難しいことなのだ。
紅音から見た陽菜は成績優秀だけど高慢で、紅音の顔を見れば煽り倒し、負ければ捨て台詞と共に消えていく存在だ。
だけど、世の中に、そんな人間など存在しない。
RPGの村人ではないのだ。テンプレの台詞だけを吐き、テンプレのお嬢様言葉をしゃべるお嬢様など、この世にいるわけがないのだ。
高慢で、自信過剰で、お嬢様言葉で、かませ犬の佐藤陽菜は、紅音の見ていないところではただの女の子なのだ。
片親を特異な理由で失い、自らの好きだった野球を諦め、学業の推薦で高校に進学し、ソフトボール部でエースを勤め上げ、勝負に負ければ悔しがる。そんな普通の女の子、なのだ。
その陽菜が、苦しんでいる。
力を貸すのに、理由なんているはずがない。
紅音はぽつりぽつりと語り掛ける。
「最初はさ、すげー嫌なやつだと思った」
「…………え?」
「まあ、そりゃそうだよな。いきなり話しかけてきたと思ったら「あなた、名前はなんですか?」からの「あら、あなた、成績が悪いんですのね」だもんな」
「そ、それは……」
陽菜は口ごもる。流石に素で言っていたわけではないらしい。そりゃそうだ。あれを本心から言っていたらトンデモ傲慢女だ。
「……今何か悪口を言われた気がするんだけど」
「気のせいだ。とにかく。最初はなんだこいつって思った。すげー嫌なやつだとも思った。だから負かせてやろうと思った。そのたっかい鼻っ柱をへし折ってやろうと思った。で、結果として、それは成功した。それで話は終わりのはずだった。」
「…………」
沈黙。紅音は更に続ける。
「けど、話はそれで終わりじゃなかった。俺は奇しくもそのすげー嫌なやつと話す機会を得た。そしたら、見えてなかったことが色々分かった。言葉遣いだって、普段はあんなエセお嬢様みたいな感じじゃないって分かった。野球にも、思い入れがあることが分かった」
陽菜が、
「で?だから私に同情してるってこと?」
そうなのかもしれない。
ただ、それはあくまで一面でしかない。
それと同じくらい重要なのは、
「俺はな、うらやましかったんだと思う」
「うらやましかった?なんでよ」
「母親」
「…………は?」
「昨日のこと、覚えてるか?俺が一日時間を潰さなきゃいけなくなったって言ったの」
「う、うん。けどそれが何か」
「その理由が、母親なんだ」
陽菜はなおもつながらないという塩梅に、
「……どういうこと?」
「別にお互いを嫌悪しているとか、そういうわけじゃない。仲が悪いっていうのもちょっと違う。けど、少なくとも一つ屋根の下で生活したいとは絶対に思わない。それが俺と母親の関係性なんだよ」
陽菜は困惑を隠せずに、
「え、ちょっと待って。母親でしょ?一緒に暮らしてないの?」
「暮らしてない。普段は俺と、妹の優姫の二人暮らし」
「じゃ、じゃあ、親御さんは」
「別のとこに暮らしてるよ。仕事がらそっちの方がいいんだとさ。一緒についていくって選択肢もあったけど、俺と……優姫はこっちに残ったんだ」
「それは……仲が悪いから?」
紅音は苦笑しながら、
「さっきも言ったろ?仲が悪いわけじゃないって。ただ、一緒に暮らすにはちょっと厳しいってだけで」
「それは……」
陽菜はその先を言葉にしなかった。
言いたいことは分かる。
それは仲が悪いというのではないか。
事実、そんな感想を貰ったのは一度や二度ではないし、言いたいことは分からないでもない。
ただ、それは違うのだ。
仲が悪いわけではない。
決定的に“合わない”
ただ、それだけのことなのだ。
例え美味しいものと美味しいものでも、混ぜたら美味しくなるとは限らない。それは素材が悪いのではない。混ぜたことが悪いのだ。紅音と母親──西園寺(さいおんじ)いろはは、そういう関係性なのだ。
「だからうらやましかったんだよ。佐藤と、文さんの関係性が。だから」
陽菜は紅音の言葉をぶった切るようにして、
「力になりたかった。そういう訳?」
「……そうだ」
陽菜はひとつ大きなため息をついて、
「私からしたら、あんたこそ何でも持ってるように見えるけどね」
「俺がか?」
「そう。あんたはそんな自覚無いと思うけど、あんたの周りには人が集まるのよ。今回だってそう。月見里さんだけじゃなくて、先輩方も一緒だったんでしょ?幼馴染には八雲(やくも)さんだっている。それ以上何を望むのよ。妹と二人暮らしで家族と別居できる環境があるならいいじゃない。それ以上必要なものなんてないんじゃないの?」
沈黙。
紅音がしみじみと、
「お互いの状況をさ、交換出来たらいいのにな」
陽菜が吐き捨てるように、
「隣の芝生だからそう言えるのよ。実際に入れ替えたら上手くいかないもんよ」
そう結論付けて、
「…………はぁ。中入る?ここでずーっと立ち話しててもなんでしょ」
「それ、俺がさっき言ったんだけどな」
「うるさいわね。締め出すわよ」
「ごめんなさい締め出さないでください」
二人は目を合わせて苦笑する。
何もかもが解決した空気。
これで一件落着。月見里や、先輩方には明日、謝りを入れればいい。
大丈夫。皆いい人だ。きちんと誤れば許してもらえる。そうしたら、陽菜も仲間に入れるように頼んでみよう。陽菜だって、最初は戸惑うだろうけど、野球好きだ。きっと先輩方と仲良くなれるはずだ。そうだ。それがいい。きっと、それで全てが丸く、
「あのぉ…………」
声だった。
男の声。少し頼りなさそうな弱弱しい声。
だが、それは確実に紅音たちに向けられていた。
「はい?」
振り向く。
そこには一人の男性が立っていた。くたびれ気味のコートにやや緩んだネクタイ。スーツもところどころしわが散見され、とても「立派な社会人」ぽくはない。冴えない中年刑事と言われた方がまだしっくりとくる。
誰だろう。
少なくとも紅音の知り合いではない。紅音にはこんな年のいった友人はいない。年上といってもせいぜいが冠木(かぶらぎ)くらいのもんで、その年齢差は兄弟姉妹にちかいことがほとんどだ。ただ、目の前にいる人物はどちらかというと父親に近い年齢に見え、
「……………………父さん?」
「……え?」
時が、止まった気がした。
関連記事
・作品のマガジン
作品のマガジンです。目次や、あらすじなどはこちらからどうぞ。
