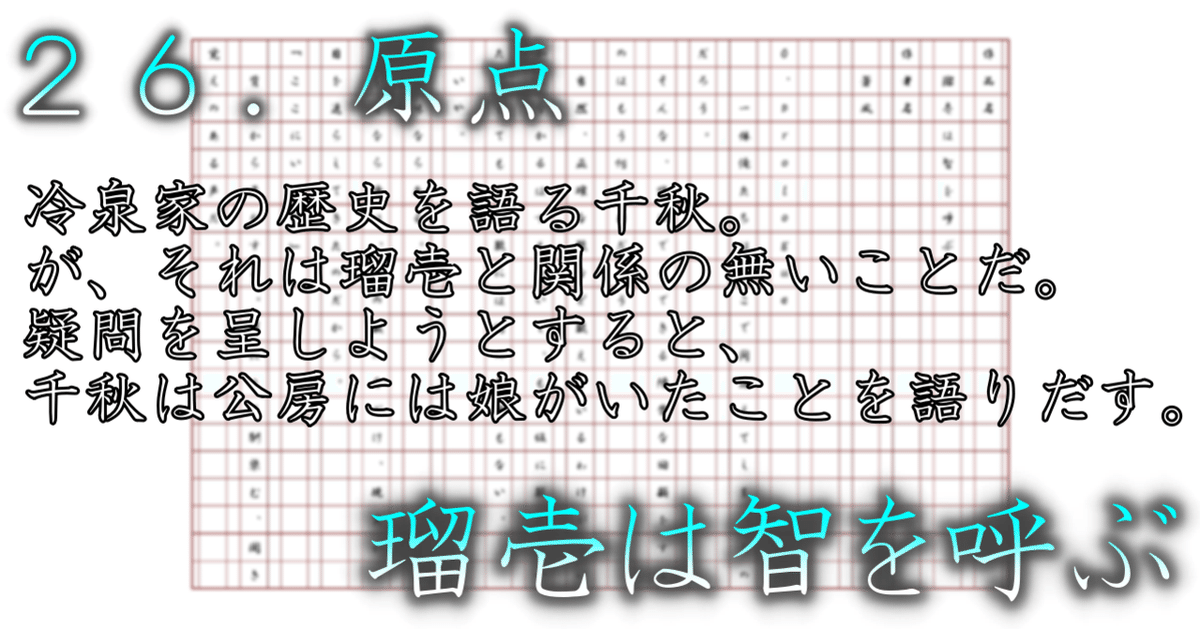
26.原点/瑠壱は智を呼ぶ
前回のあらすじ
晩餐も終わり、ゆっくりと話を始める千秋(ちあき)。彼女が語りだしたのは自らの実家、冷泉(れいせん)家の歴史だった。
やがて、その話は一つの事実へとつながりを見せる。冷泉千秋と花咲夏織(はなさき・かおり)。元をただせば二人は全く同じ血筋だというのだ。
本文
壮大な話だ。瑠壱(るい)からしてみればまさに歴史上の出来事と全く変わりはないし、正直なところ人生でそんな話に少しでも関わり合いになる機会があるとは思ってもいなかった。
が、そんなことよりも気になるのは、
「ひとついいか?」
「なんだろうか?」
「その……二人の血が実は遠いところで繋がってるって話は分かりました。その経緯も理解しました。だけど、それって俺と関係あるんですか?正直とても関わりがあるようには、」
千秋は遮るように、
「息子が、二人だ」
「聞こえな……はい?」
「さっき言っただろう?公房(きみふさ)には二人の息子がいたと」
「それは……まあ。意見が食い違ったってのも聞きました」
「そう。公房の息子……つまりは冷泉家を継承する人間の話は今の通りだ。が、事はそれで終わりじゃない。公房にはもう一人、娘がいたんだ」
「娘……ですか」
嫌な、予感がした。
虫の知らせといってもいいかもしれない。
優姫(ひめ)が不思議そうな顔で、「お兄?」と呟く。やはり、付き合いが長いと、この緊張は隠しきれないものなのだろうか。
千秋は話を続ける。
「そう。この娘……つまりは公房の長女にあたるんだが……彼女はかなりのお嬢様だったらしくってな。それこそ身の回りの世話は一から十まで全て従者にやらせるような徹底ぶりで、下手をすると一人では着替えも出来ないようなありさまだったらしいんだが、彼女もまた、冷泉家の版図を拡大するために嫁に出されたらしい」
そこで言葉を切って、
「相手方の家は冷泉同様、出版社を経営している家だった。こちらも冷泉よりは家柄が劣っていたが、財政状態は冷泉よりも更にひっ迫していたらしい。公房としては、娘を嫁に入れる形で出版社の吸収をしやすくするという狙いがあったらしくてな。基本的にはその経営は冷泉の支配下に置かれていたそうだ」
夏織が紅茶のお代わりを貰いながら、
「公房さんってあれだよね?ちょっと親バカっていうか、娘大好き過ぎだよね?危ない関係だったんじゃないの?」
とだけ呟く。千秋はそんな言葉を「単なる親バカなだけだろう」と一蹴したうえで、
「そう。公房は娘にはかなり甘くてな。その家の経営を一任していたらしい。が、さっき言った通りの箱入り娘だ。金銭感覚なってあってないようなもんだから、あっという間に資金繰りに苦慮するようになったらしい」
優姫が、
「それって……」
漸く思い至ったらしい。
ここまでくれば瑠壱たちからすれば耳に覚えのある話だった。
千秋は更に話を続ける。
「親ばかといえども流石に全てを見ているわけではないからな。気が付いたときは資金繰りはどうにもならないところまで悪化し、借りてはいけないところから借金をし、法外な利子が膨れ上がっていたらしい。流石の公房もこれには激怒してな。借金はなんとか肩代わりしたものの、親子としての関係、更にはせっかく嫁に出してまで手に入れたその出版社との関係性までもを切り捨ててしまったらしい。その後のことに関しては……正直私も知らないことが多いのは確かだが、一つだけ言えることがある。公房の一人娘。彼女には一人息子がいた。癇癪を起し、資金繰りに困る状態でおかしな浪費を続ける母親のもと、救いの手も差し伸べない冷泉家に対しての負の感情を蓄えながら育ったその男は、今、冷泉本家を脅かさんとして敵に回ってしまっている。その名前は、」
瑠壱は後をつぐようにして、
「──西園寺(さいおんじ)、権太(ごんた)」
「そうだ。西園寺権太。君と、優姫くんの父親に当たる人物だ」
正直、途中から想定はついていた。
瑠壱が物心ついたころに一つ、不思議に思ったことがある。それは、父親の実家というものに行ったことが無いことだ。
小学生時分には「自分の祖父母」についてきちんと認識していないことに対して、一抹の寂しさと、好奇心に近い興味を抱いていたのをよく覚えている。
が、結果としてその知識欲は満たされることは無かった。権太は一度たりとも瑠壱たちを父方の実家に連れて行ってくれたことは無かったのだ。
そんな行動を不思議に思い、何度も疑問をぶつけたが、返ってくるのは不機嫌な対応と、苛立ちだけだった。
ただ、その中から得た情報がいくつかあった。
権太の母親は、どうしようもない浪費癖を持っている。
それが西園寺の家を潰しかけた。
やつの実家はいくらでも助けを出せたはずなのに、一度もそれをしなかった。だから縁はこっちから切った。
全て、今千秋から聞かされた情報と一致する、間違いない。夏織だけではない、瑠壱や、優姫もまた、元をただせば同じ一人の人物につながるのだ。
冷泉公房。
千秋たちの、曽祖父に当たる人物だ。
千秋は背もたれに思い切り体重を預け、大きくため息をついて、
「正直、最初に苗字を聞かされた時点で頭に引っ掛かってはいた。が、いくらなんでもそんな偶然があるはずがない。そう思った。“あの男”と同じ苗字を持っている人間が『間違いだらけのハーレムエンド』を知っていて、しかも主題歌の着メロアレンジで気が付くだと?あまりにも話が出来過ぎている。そう思った。だが、調べてみればその「信じがたい内容」はただそこに横たわるだけの事実だということが発覚した。だからこうして声をかけた」
沈黙。
やがて千秋が話を再開する。
「西園寺権太の力は凄かった。西園寺が営んでいた小さな出版社を短い期間で再生し、拡大し、冷泉とも「協力関係」を築くまでにしたてあげた。それだけなら、冷泉家や、私も気にすることは無かっただろう。単純に「凄いビジネスの相手が出てきた」くらいだったかもしれない。が、ことはそこで収まらなかった」
間。
「やつの手法は狡猾でな。内部の人間を少しづつ味方につけていくという一見地味ながら一番効果的な作戦を取る。いくら一族経営だった企業とはいえ、その意思決定にはその外にいる重役も絡んでくる。気が付いたときには、その「外部の人間」は全て、権太の味方にまわっていた」
間。
「後は簡単だ。やつは犯罪に手を汚したりすることもなく、冷泉本家の経営する出版社の実験を握ってみせた。そして、その権力を元に「流行を作る」とでも言わんばかりの経営に舵を切らせた。その一翼を担わされようとしているのが『間違いだらけのハーレムエンド』というわけだ」
優姫が、
「それって……お兄が好きな」
千秋が首肯し、
「そうだ。そしてそれは私も好きな作品だ。いまやちょっとした伝説となったあの作品を、権太は復活させようとしている」
優姫が疑問をぶつける。
「え?復活させようとしてるんならいいんじゃないんですか?だって、お兄も、千秋さんも好きなんですよね、その作品?」
千秋は「ああ」と受け答えたのち、
「もちろん、好きさ。だが、それは、あの作品が原作者の意向をきちんと反映した者であれば、の話だ」
「どういうこと?」
夏織が紅茶のカップに信じられない量の角砂糖をぼたぼたと落としいれながら、
「権太はねー前に受けた作品の名前とかを借りただけの別作品をね、有名作家に書かせるつもりなんだって」
「なっ……!?」
瑠壱は思わず反応をする。それを見た千秋が、
「……最初聞いたときは私もそんな反応になったさ。だって、そうだろう?そんなことに何の意味がある。あれは、原作者……関わった三人の熱量があってこそ成立する作品だ。それを何も知らない作家に託すなど、あってはならない。そこにリスペクトがあればまだいい。ただ、やつのやろうとしていることは、そうじゃない。そこにあるのはただ「名作の名前を借りて、作品を売ろう」という魂胆だけだ。そんなものを許すわけにはいかない」
そこで千秋は瑠壱に向き合い、
「西園寺。聞くところによると君は、あの山科(やましな)……月見朱灯(やまなし・あかり)と仲が良いそうじゃないか?」
山科。
月見里朱灯。
久々に聞かされたその名前はどこか遠い現実のように感じられた。
「聞くところによれば、メインヒロインの声優をつとめた彼女は『まちハレ』を非常に気に入っていると聞く。それに西園寺。君もまた『まちハレ』に魅入られた一人だ。そこで一つ相談がある」
「……なん、でしょうか」
平静は、装えなかったと思う。
だが、千秋はそんなこと全く気にもせずに、
「君……いや、君たちにはある人物にコンタクトを取ってもらいたいんだ」
「コンタクト……ですか?」
「そうだ。『間違いだらけのハーレムエンド』の制作に関わり、大筋のシナリオを手掛けた人物だ。今は……藤ヶ崎大学に籍を置いている。名前は、」
ひとつ息を吸い、
「──橘宗平(たちばな・むねひら)。私の姉、冷泉千春(ちはる)の親友だった男だ」
