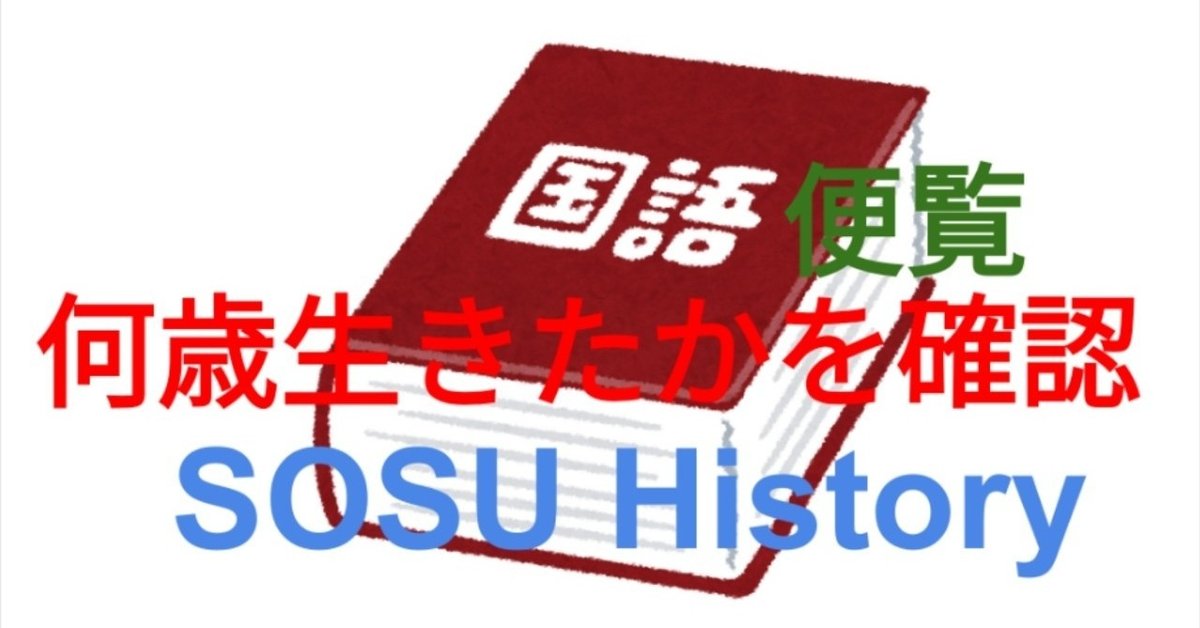
SOSU History - 国語便覧の思い出
今回は、僕の子供時代の数字好きエピソード「SOSU History」を紹介します。
SOSU Historyの記事が一覧になったマガジンはこちら
前回、分厚い本が何ページなのかを確認していたことについて書きました。
詳しくはこちら
さて、ページ数よりもっとマニアックなことを確認していたことがありました。
よく見ていたのが、「国語便覧」。
歴史的な文学や作家などを紹介しているわけですが、
僕が確認していたのは、
作家の生き様や作品ではありません。
「何歳まで生きたか」です。
誕生日は覚えていませんが、
「作家が〇〇年〜〇〇年まで生きた」というのをチェックしていました。
例えば、
夏目漱石
→1867年(慶応3年)〜1916年(大正5年)
森鴎外
→1862年(文久2年)〜1922年(大正11年)
芥川龍之介
→1892年(明治25年)〜1927年(昭和2年)
井伏鱒二
→1898年(明治31年)〜1993年(平成5年)
などなど。
上の生没年は頭の中にありました。
便覧を見ていた当時、
この人は早く亡くなってしまったのか〜
とか
この人はすごく長生きしたんだな〜
ということしか考えていませんでした。
上に書いたように、
芥川龍之介は35歳くらいしか生きていません。
しかし、井伏鱒二は95歳まで長生きしました。
誰が長生きして、誰が早く亡くなったかに興味津々だったのです。
また、「生まれたときの元号の年」より「亡くなったときの元号の年」が小さいときは短命だったのかな〜という考えもありました。
芥川龍之介の場合、「明治25年〜昭和2年」
亡くなったときの元号の年(=2)が生まれたときの年(=25)よりも圧倒的に小さいので、「若かったんだな〜」と思ったものです。
(もちろん、井伏鱒二のように例外もありますが)
こうして、今はだいぶ忘れていますが、
作家たちの生まれた年と亡くなった年を確認して、何歳まで生きたのかを入念にチェックしていたのでした…。
小さい頃から国語便覧を読む、真面目な子ではありませんでした。
とても変わってましたね笑。
まあチェックしてたおかげで、作家の名前は覚えられましたが…笑。
国語便覧が愛読書だった小学生時代のお話でした〜
素数はいつも、あなたのそばに。
Let's enjoy SOSU!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
