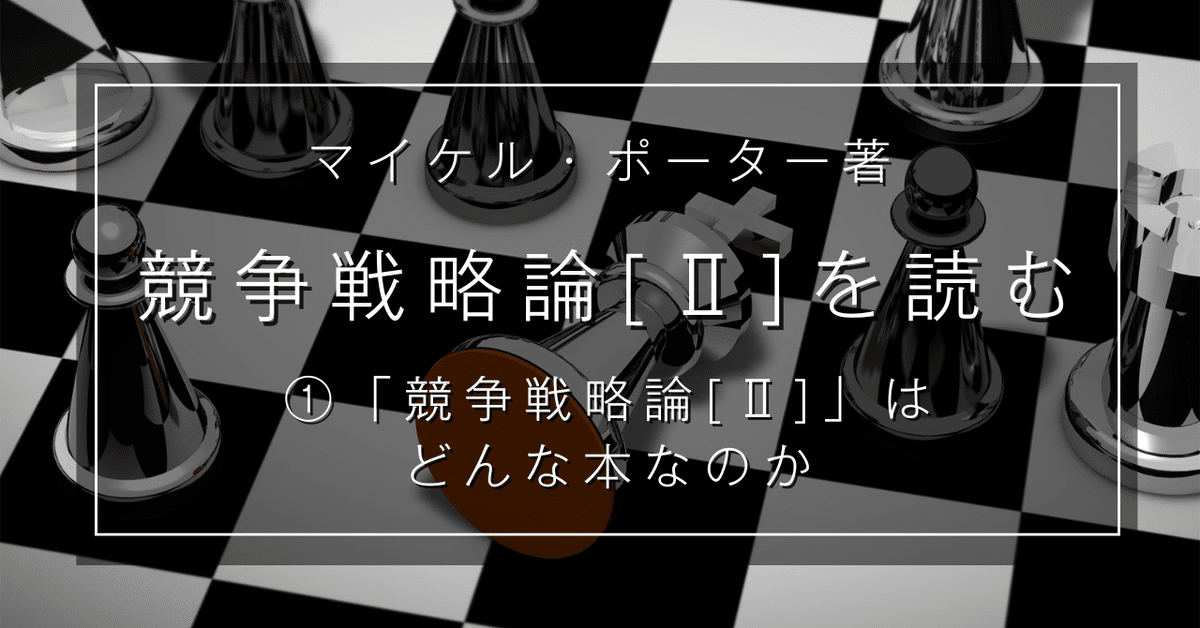
競争戦略論[Ⅱ]を読む - ①「競争戦略論[Ⅱ]」はどんな本なのか
さあ、水曜日だ。
毎週水曜日はマイケル・ポーター著「競争戦略論」をベースに、ボクの気づきや思考をアウトプットするシリーズを展開している。
競争戦略論[Ⅱ]について
さて、なんだかんだ言ってる間に、17週かけて「競争戦略論[Ⅰ]」を読み終えてしまった。
これまで読んできた、マイケル・ポーターの「競争戦略論[Ⅰ]」は非常に学びの多かった本だったと感じている。本来は大企業向けに書かれた本だと思うが、ちょっと嚙み砕いて考えると、中小企業にも当てはまる箇所が多かったと思う。
「競争戦略論[Ⅰ]」は1980年に初版が出版されており、世界中で「名著」と呼ばれているビジネス書であるが、著者のマイケル・ポーターはその後1999年に、[Ⅰ]の続編として「クラスター理論」という考え方を中心にした「競争戦略論[Ⅱ]」を出版している。
ある国の競争力は、その国の産業においてイノベーションを起こし、グレードアップしていく能力によって決定される。著者は、競争優位の確立、保持のためにクラスターという概念を導入している。クラスターとは、特定分野における関連企業、専門性の高い供給業者、サービス提供者、関連業界に属する企業、関連機関(大学、規格団体、業界団体など)が地理的に集中し、競争しつつ同時に協力している状態をいう。
クラスターの大切さは、経営にも、政府にも新たな課題、役割を生じる。例えば、政府の場合、競争力を育むためのマクロ経済政策についての理解は深まりつつあるが、政府がより決定的な影響力を及ぼすことができるのはミクロ経済であり、最優先課題は、クラスターの質を向上することである。その他に、企業の長期的な競争ポジションを強化するための投資行動にも触れ、著者の永年にわたる、ワールドワイドな実証研究の成果が示されている。
競争戦略論[Ⅰ]との違い
競争戦略論[Ⅰ]が個々の企業の競争優位に焦点を当てていたのに対し、[Ⅱ]は、より広範な視点から「競争」を捉えている。[Ⅱ]では、業界全体の構造、国家レベルの競争優位、環境問題、都市問題などにも触れられているようだ。
つまり、企業が持続的な成長を遂げるためには、単に自社の競争優位を構築するだけでなく、業界全体の構造や、国家レベルの競争優位、そして環境問題や都市問題といったマクロな視点も考慮しなければならないということであり、それはボクが毎週火曜日に書いている環境関連の記事にも関連する内容であるだろうと思っている。
中小企業が競争力を高めるための理論
例によって、まだこの本の中を一切読んでないところからスタートだ。この本がどんな展開になって、ボクがどんなインスピレーションを受けるのか、今のところ全くわからない。そして、[Ⅱ]の方が[Ⅰ]よりも大企業向けの内容になっているのではないだろうか…という気もしなくもない。
だが、きっとその中にも中小企業に役立つエッセンス(中小企業が競争力を高めるための理論)を見つけ出すことができるだろうと思っている。
(続きはまた来週)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ここまで読んでくださってありがとうございます。
これまで書いた記事をサイトマップに一覧にしています。
ぜひ、ご覧ください。
<<科学的に考える人>>
