
世界遺産検定2級を1か月で取得しました
2024年12月8日に実施された第58回世界遺産検定にて2級を取得しました。この記事では、私が大学の授業と並行しながら2級の取得に至るまでの勉強方法などを記録として残しておこうと思います。
この記事では、
・そもそも世界遺産検定って何?
・満点は狙わないけど、安全に2級を取得したい
・ほかの勉強と並行しながら取得したい
といったことが気になる人におすすめです。
ちなみに私の点数は68/100でした。なので、高得点を狙いたい!という方はこちらの方の記事がおすすめです。
受験の動機
私は現在大学の学部1年生です。1年生なのでフル単で授業を取り、なおかつ課外活動などもあってそれなりに充実していましたが、大学入学以前は仕事をしていたこともあって忙しいとはあまり感じていませんでした。この時間を活用してほかに何かできないかと考えていたとき、たどり着いたのが世界遺産検定でした。
部活やサークルなどのあらゆる選択肢の中からなぜ世界遺産検定を選んだかというと、とにかく勉強したかったから、です。改めて文章にすると意識高すぎて眩暈がしそうになりますが、そもそも仕事を辞めて大学に来た理由も、自分の持つ知識や技術をさらに進化させたかったからです。そのための国家試験も別で勉強中なのですが、学部の授業でも国家試験の勉強でも同じようなことを学び続けるのは飽きてしまいそうだったので全く別のジャンルが良かったのです。そんなとき、息抜きでYouTubeを見ていたときに「ドロピザ」というチャンネルに出演する凌さんという方が世界遺産検定1級を取得していることを知りました。そのチャンネルは漫画の考察系動画をアップしているのですが、世界遺産に基づいた考察が多く、すっかりはまっていました(ここに登場するお城は世界遺産の〇〇と似てるし、○○建築の建物が多いからこの国の舞台は〇〇国……など)。ここでは関係ないので省略しますが、世界史や世界遺産の知識って持ってるとかっこいいかもと感じたのが受験のきっかけです。
世界遺産検定とは

世界遺産検定は、NPO法人世界遺産アカデミーが主催する検定試験です。試験は年4回(うち公開会場試験は3回)実施されていて、例年3月、7月、12月ごろに公開会場試験があります。

公開会場試験は日時が1日しかありませんが、CBT試験は期間が約3週間あるので、公開会場試験の日程がどうしても合わないという方はこちらをおすすめします。が、公開会場試験より700円~900円ほど割高なので可能であれば会場で受けた方がいいと思います。
検定は4級、3級、2級、準1級、1級、マイスターの6段階で構成され、準1級までは受験資格がありません。1級を取りたい人は2級取得後に、マイスターを取りたい人は1級取得後に受験する必要があります。
この資格を持つ芸能人もかなり多く、あばれる君さんや鈴木亮平さんなどは1級を所持しています。最近ではSnow Manの阿部亮平さんもテレビで話していました。
出題内容は以下の通りです。

英語の問題も出るの!?と思った方、安心してください。2級は全60問なのですが、英語の問題はたった1問です(詳細は後述)。
2025年1月現在、受験料は公開会場試験であれば6,500円です。3年前に取得した人の記事をみると5,900円と書いてあるので、まあまあ値上げしています。さらに公式テキストが2,420円、公式問題集が1,760円なので合わせて10,680円です。高い……。しかし、今後さらなる値上げや遺産数の増加を考えれば、取りたい人はなるべく早く受験した方がいいですね。

世界遺産検定を取得するメリット
この資格は世界遺産に詳しくなれるだけではなく、いろんな場面で有用であることがあります。公式HPに記載されている例を2つ紹介します。
旅行で便利
世界遺産検定に合格したら、認定証が届きます。この認定証を対象施設で提示すると、入場料割引やオリジナルグッズなどの特典が得られます。2025年1月現在でこの特典が得られる施設等は23件ですので、詳しくはこちらをご覧ください。
進学、就活において有利
世界遺産検定を持っていると、全国300近い大学や短大で入試において判定優遇・点数加算されることがあるそうです。また、就職活動においてはこの資格が強みとして扱われる企業もあり、特に旅行・観光業界を目指す方は持っておいて損はありません。
私の勉強法&アドバイス
基礎知識&日本の遺産をしっかり覚える
世界遺産検定は学校の授業でいうと歴史、社会の科目なのでほぼ暗記ゲーです。そのため、いかに効率よく頭に叩き込むかが重要になります。
世界遺産検定の問題は
・基礎知識20点
・日本の全遺産25点
・文化遺産35点
・自然遺産10点
・その他(時事ネタ等)10点
以上100点満点で構成されています。
基礎知識は公式テキスト第5版では約20ページで構成されています。つまり1ページ1点。コスパ良く合格を目指したい!というのであれば、この2項目は完璧にしておく必要があります。世界の遺産は300件完璧に覚えてもMAXで45点ですが、日本の遺産は2025年1月時点で26件なので1遺産覚えれば確実に1点です。そう考えると、日本の遺産はしっかり押さえたいですね。ページ数で考えても、世界の遺産と比べると全然少ないです。

英語の問題は、公式テキストに記載してある英文の赤文の一部が穴抜きになっていて、そこに当てはまる英単語を選択肢から選ぶという問題です。英語が得意な人は問題ないと思いますが、そうでない人がたった一問(2点)のためにわざわざ英単語を覚える必要はないと思います。なので私は捨てました。
時事ネタに関しては、公式HPの公式教材欄に「○○年新情報」というPDFファイルがアップされています。そこに記載してあることからの出題が主なので、それを押さえておけば問題ないはずです。
ちなみに出題の傾向は
・直近の世界遺産委員会の開催地
・そこで登録された遺産名、その特徴
が多い気がします。
公式過去問題集を完璧になるまで解く
公式過去問題集は前年度の試験3回分(180問)+例題10問が掲載されています。解いていくと、たった3回分の内容でも同じような問題が何問か出題されていることが分かります(特に基礎知識、日本の遺産)。
その後公式テキストを少しずつ進めましょう。しかし全部覚えようとするとまず無理なので、基礎知識は太字赤字+登録基準、世界遺産の関連機関、文化的景観について抑えていればまず大丈夫です。日本の遺産も太字赤字を抑えるべきですが、それ以外の文章からも平気で出題されたりするので時間があれば重点的に読むべきです。世界の遺産は過去問に出た箇所+太字赤字が覚えられれば完璧です。が、それを300件覚えるのは至難の業なので興味がある部分を中心に覚えるのでいいと思います。何より大事なのは、勉強のモチベーションを保つことです。
目次を活用して暗記する
私が受験後に知った方法なので実際にはやっていないのですが、河野玄斗さんが世界遺産検定1級を取得する動画でこの方法を紹介していました。
その方法は、目次の遺産名を見てそこから重要なキーワードを思い出すというものです。この方法であればキーワードや保有国まで覚えられ、テキスト1冊で完結するので手軽に勉強できますね。詳しくはこちらの動画をご覧ください。
私の場合
私は過去問に比重を置いて勉強しました。なぜそうしたかというと、問題の傾向をつかむためです。まずはそこを完璧にして過去問は満点を常にとれるように勉強しました。この時点で公式テキストは流し読みする程度でした。その後過去問が9割以上で安定したら、公式テキストに取り掛かります。ここでは、いかにアウトプットをするか?ということを考えました。赤シートを持っていればよかったのですが、私は持っていなかったので「穴埋め問題を自分で作る」方法を取りました。
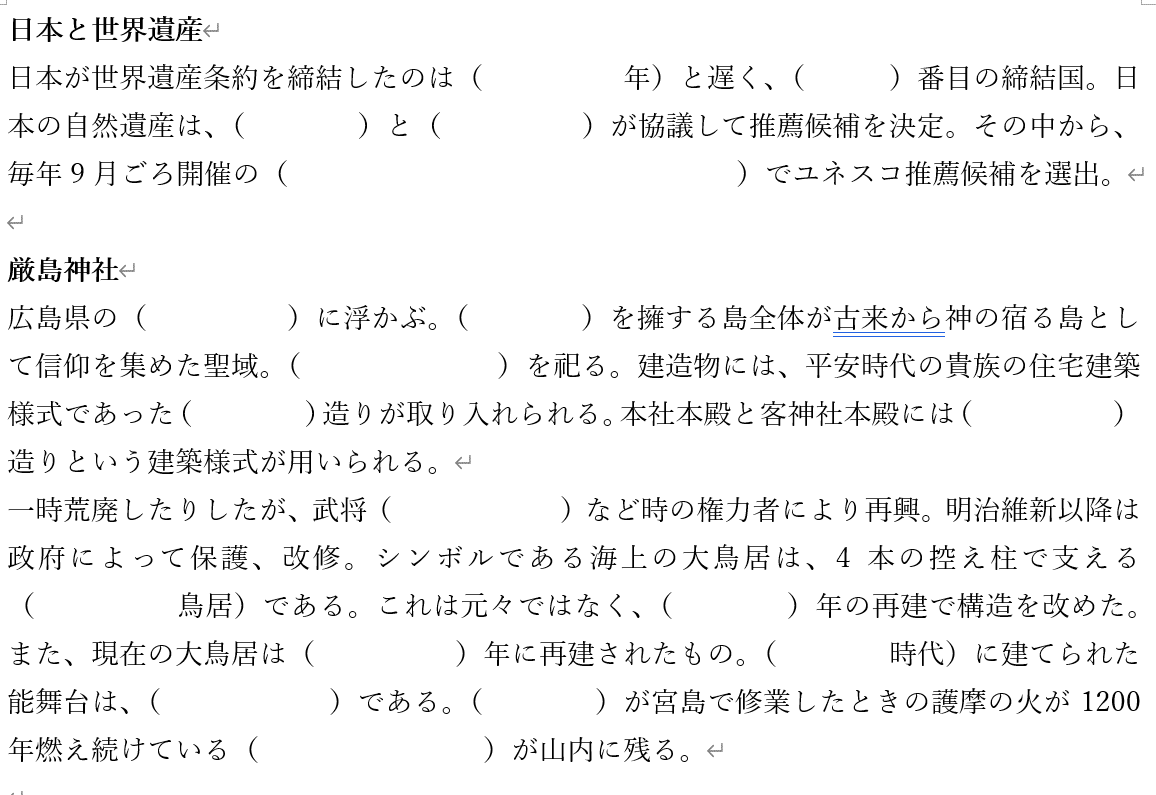
同じ感じでたくさん作って、1日1枚は必ず解くようにしていました。基礎知識+日本の全遺産、好きな世界遺産+時事ネタは網羅していたはずです。これを全部完璧になるまでやっていればよかったのですが、途中から作るのに飽きてしまいました。作る手間があるので、これで全部やろうとするのは無謀でした。
勉強開始~合格判明までの流れ
覚えている限りの受験当日(12月8日)までの流れです。
試験約2か月前
Amazonの履歴をみたら、約2か月前に教材を買っていました。私が今回の受験でかかった総額は10,100円です(受験料6,500円+中古テキスト2,000円+公式問題集1,600円)。
試験約1か月前
1か月間テキストと過去問題集を放置。ちょうどこのあたりから家族が体調を崩し、一時帰省したりと忙しかったのは覚えています。
帰省後から過去問をやり始めたので、この時点で「合格できるか微妙だな」……など思い始めていました。
試験20日前
このあたりから大学の中間テストが始まったので、そっちの勉強と並行してやっていました。自作穴埋め問題を1日1枚はやるようにして、バイト中も勉強していました(ゆるいバイトだったため)。受験票が家に届いて、試験日が近づいている実感が湧きます。このあたりから本格的に勉強をやり始めた気がします。
試験10日前
とりあえず基礎知識と日本の遺産を集中的にやり、息抜きで世界の遺産に手を付けるような感じで勉強していました。改めて過去問を解きなおし、抜けている知識を入れなおしたりなどもしました。
試験5日前
公式HPから時事ネタを収集します。テキストにはない新たな日本の遺産「佐渡の金山」は絶対出るな……など、傾向も予測して覚えました。この時点で基礎知識や日本の遺産は8割覚えた感じでしたが、世界の遺産は3割くらいしか覚えてなかったはずです。
試験当日
早起きして世界の遺産を中心に詰め込みます。過去問や自作の穴埋め問題を解きつつ、試験に向かう準備をしました。試験会場には30分前くらいについたのですが、既に15人ほど着席していたので特別早い方ではなかったです。問題は順調に解くことができたのですが、やはり世界の遺産が難しかったという印象です。さらに予想していた佐渡の金山に関する問題も出たので、そこは難なく解けました。
試験5日後
公式HPに回答が掲載されたので自己採点をしました。そこで無事合格点を超えていたのでひと安心。
以上が私の受験記です。そして年が明け1月22日に結果通知がマイページに掲載されました。受験を終えた感想としては、やはり詰めが甘かったかなという感じです。日本遺産は容赦なく太字でも赤字でもないところから出題されていて、そこの部分を見落としていた甘さが出てしまいました。また、自然遺産は4/10とかなり点を落としているので自然遺産をもう少し重点的にやった方が良かったなと感じました。

今後の勉強
約1か月世界遺産の勉強をして、率直に楽しかったです。世界史の勉強自体が久しぶりだったので不安もありましたが、公式テキストに写真も多く、楽しんで勉強することができました。
さて、無事2級に合格することができたのでいよいよ1級を目指して勉強したいと思います。次回の1級公開会場試験は2025年7月13日(日)と執筆時点から半年ほど先になるため、しっかり勉強をして臨みたいです。
この記事を読んで世界遺産検定が気になった人は、ぜひチャレンジしてみてください!
