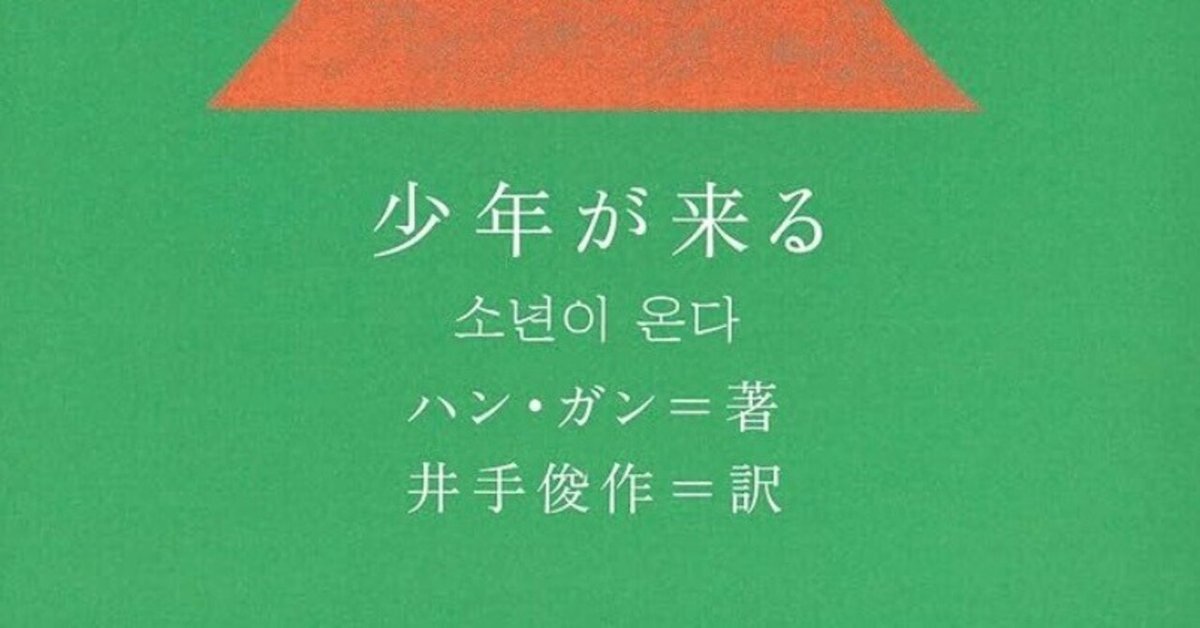
ハン・ガン『少年が来る』書評
ここ数年、日本では現代韓国文学がよく読まれているが、そのきっかけは2011年に刊行が開始されたクオンの「新しい韓国の文学」というシリーズである。その劈頭を飾ったハン・ガン(韓江)の『菜食主義者』は英訳版が2016年のマン・ブッカー国際文学賞を受賞し、これを契機に彼女への関心は全世界で一気に高まった。
ハン・ガンは1970年、大韓民国の光州生まれ。父のハン・スンウォン(韓勝源)、兄のハン・ドンリムも作家という「文学一家」で育った早熟な才能は20代前半で開花し、延世大学を卒業した1993年には文芸誌「文学と社会」に詩が掲載され、翌年には短編小説「赤い掟」で小説家としてもデビューした。2005年に「蒙古斑」(『菜食主義者』を構成する連作中編の一つ)が李箱文学賞大賞を受賞したことで、韓国内での評価は決定的なものになった(同賞は1988年に父のハン・スンウォンも受賞している)。
日本でも『菜食主義者』以後、『ギリシャ語の時間』、『少年が来る』、『すべての、白いものたちの』といった主要作品が相次いで紹介され、短編集『回復する人間』やエッセイ集『そっと 静かに』も刊行されている。いわば日本における現代韓国文学ブームの立役者というべき存在である。
ハン・ガンの多くの作品では、登場人物の(心身の)〈傷〉からの回復が描かれる(「回復する人間」という題名の短編も書かれている)。『菜食主義者』の表題作は突然に肉が食べられなくなったヨンヘという女性の物語だが、彼女の〈傷〉は夫や実姉、その夫といった親族との関係を歪ませるだけでなく、それぞれの者が抱えていた〈傷〉をもあからさまにしていく。『ギリシャ語の時間』は発話ができなくなった女と視力を失いつつある男の出会いの物語だし、自伝的な『すべての、白いものたちの』には作家自身の個人史における〈傷〉が赤裸々に描かれている。
〈傷〉とそこからの回復という主題は、ハン・ガンの端正でミニマルな文体ときわめてよく合っている。だが彼女が描こうとしているのはたんなる個人の〈傷〉ではない。これらの作品を丹念に読むと、20世紀の韓国社会が経験したいくつもの試練――日本による植民地化、同じ民族同士が戦った朝鮮戦争、米軍側でのベトナム戦争への参戦、長く続いた軍事政権による統治――が、登場人物の心と身体に複雑な陰影を落としていることがみてとれる。
そんなハン・ガンが韓国の社会自体が構造的に抱える〈傷〉という主題に真正面からとりくんだ意欲作が、2014年に発表された『少年が来る』(日本では井出俊作訳で2016年刊)である。
1980年5月に全羅南道の中心都市・光州で起きた、学生・市民による民主運動と戒厳軍によるその弾圧、いわゆる「光州事件(光州民主化運動)」は戦後の韓国の政治社会史の転換点になった。『少年が来る』は光州事件を題材にした一種のノンフィクション・ノベルであり、彼女の他の作品とはかなり異なる印象を与えるが、ハン・ガンの作家的資質はこの作品でもっとも大きく開花していると私は考える。
もとより光州は、彼女が生まれた場所である。ハン・ガンの一家は光州事件が起きる前にソウルに転居し、彼女自身はこの出来事を直接には経験していない。だが一家が光州で暮らした家にあとから住んだ家族は、光州事件で末の息子を失っていた。『少年が来る』はその少年――中学3年生のキム・トンホ――をはじめとする光州事件で命を失った者たちの無念を、そして生き残った者たちが抱えることになる〈傷〉を、人称を効果的に切り替えた文体で綴っていく作品なのである。
最初の2章は1980年5月の光州が舞台だ。一章「幼い鳥」は、〈君〉と二人称で呼びかけられるトンホの物語。民主化運動が始まった数日後、光州市はすでに戒厳軍に包囲され通信も交通も遮断されている(チャン・フン監督による2017年の映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』でも印象的に描かれていた)。一時退却した軍の再突入が噂されるなか、旧式の銃で武装した学生と市民が全羅南道の道庁に立て籠もる。身元不明の遺体の集積所となった尚武館でボランティアとして働くトンホは、その夜いったん家に戻るが、年長の若者とともに道庁に居残ることを決意する。
二章「黒い吐息」は、トンホの家(じつはハン・ガンの一家が以前に住んでいた家)に寄寓する一家の息子、チョンヘの一人称で綴られる。トンホが道庁に残ったのは、軍に襲われた際にチョンヘを見殺しにした自責の念からだった。チョンヘはすでに死んでいるが、トンホの思いは彼に十分に届いている。
光州事件にかかわった最も年少の世代の視点から描かれたこれらの章に続くのは、最後まで道庁に立て籠もり、生き残った年長者たち――「チンス兄さん」「ウンスク姉さん」「ソンジュ姉さん」――のその後だ。三章「七つのビンタ」はウンスクの5年後の物語。彼女は編集者となり、光州事件を題材とした戯曲の出版を進めている。当局の検閲をかいくぐり上演されたその劇には、亡きトンホの面影が宿っている。四章「鉄と血」は籠城時に指導的役割を演じたチンスの同志の一人称による語りで、事件後に逮捕されたが恩赦で釈放され、廃人のようになってしまったチンスの死が明かされる。五章「夜の瞳」は、ソンジュに二人称〈あなた〉で語りかける物語。事件から22年後、彼女は当時者としての証言を求められている。取り調べ時に受けた屈辱から癒えることができず躊躇するが、彼女は最後にやはり証言を残そうとする。六章「花が咲いているほうに」はトンホの母の視点で語られた30年後の物語で、エピローグでようやく作者のハン・ガンと光州事件との深い関係が明かされることになる。
『少年が来る』が1980年と現在の韓国をつなぐ通路であるように、ハン・ガンの存在自体が、韓国の近代文学とポストモダン文学が相互乗り入れする回路になっていると私は考える。いま日本でよく読まれている韓国文学は、村上春樹をはじめとする日本のポストモダン文学に強い影響を受けた世代(そうした作家を多く輩出した雑誌の名から「文学トンネ」世代とも呼ばれる)が中心だが、ハン・ガンは彼らよりもやや年長の世代である。むしろ彼女は、韓国の民主化運動を担ったムン・ジェイン(文在寅)大統領らが属するいわゆる「386世代」のエートスを、彼らより年少でありながら濃厚に共有している。
だからといってハン・ガンの文学に、朝鮮半島で起きた政治的、社会的事件が直接的に反映しているといいたいわけではない。チンスの同志だった男は、彼らを「殺しに来た者」たちに「済州島で、関東(注:関東大震災の際の朝鮮人虐殺を指す)と南京で、ボスニアで、全ての新大陸でそうしたように、遺伝子に刻み込まれたみたいに同一」の残忍性が受け継がれていると語る。人間自体にこうした絶望的な性質があることを、ハン・ガンは知り尽くしている。そうでありながら、なおもこう書かずにおられない。ソンジュが彼女の同志だった「ソンヒ姉さん」にどうしても伝えたい言葉――「どうか死なないでください」。
時も場所も超えた普遍的な祈りが記されたことで、『少年が来る』という小説は永遠の命をもつことになった。
初出:Kotoba No.41 2020年秋号(2020年9月4日発売)
