
多様性の押しつけ:もう決して、ピカソやキムタクは生まれない
ふとインスタを見ると、友達がバンクシーの絵をストーリーにあげていた。

正直、僕は彼の絵の良さが全くわからない。話題づくりは上手くても、肝心な芸術の才能が感じられないからだ。
天才の不在
それは個人的な好き嫌いかもしれないが、現代にピカソや岡本太郎のような生前から多くの人々が認める「天才」はいるのか、ふと考えてみる。

音楽でいえばモーツァルト、ファッションでいえばココ・シャネルのような存在。いくら考えても思い浮かばなかった。
いまはいわゆる「谷間の世代」なのか?そんな確証はない。背後には、なにかシステム的な問題があると直感した。もしかすると、人々の好みが多様化しすぎているのかも。

考えてみてほしい。ここ最近、周りの人達と共通の話題が見つけづらくないか?
テレビ離れが進み、みんなが同じドラマを見ることは少なくなった。今では音楽アプリが自分好みの曲を教えてくれるし、ソーシャルメディアのフィードは一人ひとり全く違う。

いま、キムタクと同じレベルの才能を持った役者がデビューしたとして、当時と同じような社会現象はおきるのだろうか?
それぞれが全く違う方向を向き、価値観が絶えず細分化されていく。そんな世界に、大多数の人々が認める「共通の存在」が現れることはあるのか?
偽りの多様性
みなさんの中には、こう思う人もいるかもしれない。そもそもそんな存在は必要なのか。みんな違って、みんな良いじゃないか。
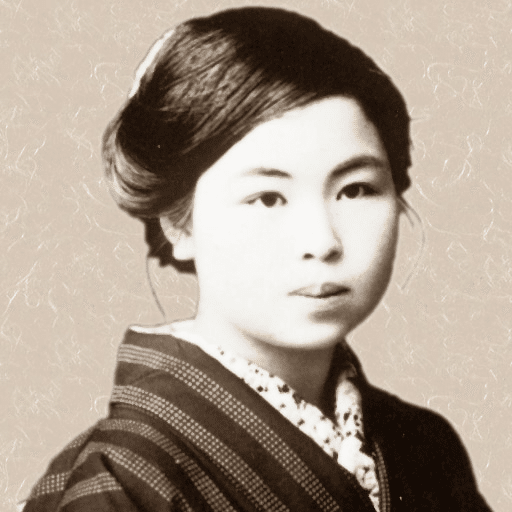
たしかにその考えには一里ある。しかし僕はこの現象の背後に、より大きな時代のうねりがあると考えている。
それはすなわち、多様性の押し付け。
「みんな個性がある。違いを認め合おう。あなたにしかできないことがあるはずだ。」
こんなことが声高に叫ばれて久しくなった。20世紀の大量生産主義やマスメディアの衰退、そしてインターネットの普及につれて。

一昔前はテレビや新聞など、消費者が内容を選べないメディアがほとんどだった。自分が興味のない情報に嫌でも触れることが多かっただろう。
対して2020年では、多様な媒体で好きなものを、好きなときに、好きなだけ触れられる。
そうなると「みんな違って、みんな互いに興味ない」社会ができあがる。
しかし一歩引いて考えれば、僕たち人間のDNAは99%以上一緒。共通点のほうが圧倒的に多い。

人間を二人並べれば両者の違いばかり目につくが、その隣にリンゴや森、そして蛇や鹿を置いてみれば「ヒト」同士の差なんて微々たるもの。
黒人の命は重要だ (Black Lives Matter)。よりも「人間の命は大切だ (All Lives Matter)」と考える方がよっぽどシンプルで本質的ではないか。

ツイッターやフェイスブック、もしくはニュースアプリのフィードに表示される「自分が好きな情報」だけを見て物事を判断するのは、とても危険ではないか。
自分は大丈夫、と思ったみなさんに知ってほしい事実がある。2016年のアメリカ大統領選直後に、異なる政治的見解を持つ国民同士がお互いのフィードを交換した実験。

「嘘だと知っている情報を見るなんてバカバカしい」「自分が攻撃されている感じがする」など、参加者は自分の価値観にそぐわない情報に拒絶反応を起こしたという。
これは政治に限った例だが、他のトピックに関しても同じことが言えると思う。みなさんも他人とフィードを交換してみたら同じように嫌悪感をおぼえるか、最悪の場合つまらなくて寝てしまうはず。

受け入れずして思想をたしなむことができれば、それが教育された精神の証である。
- アリストテレス
好みの情報にしか触れたくない、自分の価値観を否定されたくないと願う人の性。それを肥やしに儲ける一部の企業。
現在進んでいる価値観の分断は、アルゴリズムと人間の心の弱さから生まれた「偽りの多様性」だ。
懐メロの価値
僕はなにも、みんなが同じ情報を受け取れば良いとは思っていない。
でも、ある程度は自分と異なる視点・信条に根ざしたインプットを意識的に試みる必要性があると考える。
本当の多様性とは、相互理解や広い知見から育まれるものではないのか。そして、今こそ普遍的な価値観の重要性が見直されるタイミングかもしれない。
例えば「懐メロ」。先日、同年代の友達数人とドライブしたときの話だ。

みんなが最近聞いている曲はヒップホップやKPop、EDMなどまとまりがない。
しかし嵐の「Hapiness」が流れた瞬間、車内の空気が変わった。10年以上前の曲だし、誰も嵐ファンではない。それでも何となく歌詞はおぼえてるし、何より懐かしい。

これをマスメディアによる洗脳と捉えることもできるが、今でこそバラバラの趣味を持つ僕たちには新鮮な一体感を与えてくれた。
よりどころ
さて、話を戻そう。人類共通の「よりどころ」が今後生まれる余地はあるだろうか。

短期的にいえば、その可能性は非常に低い。パーソナライズド・メディアによる分断は進んでいくだろう。
バンクシーはピカソのような巨匠になれないし、キムタクのように伝説的な人気を得る俳優も出てこない。「オーダーメイド」されたフィードの中で生きる人々が増えていく。

これは個人の才能が劣っているからではない。「みんなに知ってもらう・認識しつづけてもらう」ことがが非常に難しいシステムのせいだ。
マスメディアという生産者が力を失ったことで、アイコニックな存在は絶滅危惧種となった。
しかし長期的にみれば、ふたつのシナリオがあり得るように思う。
まずは多様性の押し付けに対する反動。歴史をみれば、発散と収束は交互に訪れる。

例えばどんな文明にも「地方豪族が繁栄→統一国家が成立→内戦や侵略で崩壊」というループは共通しているものだ。ちょうどサインやコサインのグラフのように。
大衆文化からパーソナライゼーションを経て、何らかの統一運動が巻き起こる可能性はある。年々増えるプラットフォーマーへの訴訟や制裁は、その序曲といえるだろう。

最近90年代や80年代のファッションや文化が人気を博しているのは、若者が新しさよりも「共通の根っこ」を無意識に求めているようにも見える。
対してより早く起こりそうなのが、人工知能による人間の嗜好の攻略。ありきたりな印象を与えたら申し訳ないが、この筋書きは無視できない。
すでに始まっている分野は映画や音楽。

ネットフリックスのオリジナル作品は膨大な視聴データをもとに制作されるし、スポティファイは曲のメロディ自体を解析することでユーザーの本質的な好みを把握しようと試みている。
拍車をかけるように、若者世代はより良い体験のためなら自分のデータを提供しても構わないと考える調査もある。

AIが描いた絵。約5000万円で落札された。
その結果、AIが「人間の好みの最大公約数」を見つければ次のピカソが誕生するわけだ。
しかし、そこに感動は生まれるのだろうか。人間の主張が入らない、データに裏打ちされた作品は何をもたらすのか。
答えは誰にもわからないけど、ひとつだけ確かなことがある。普遍性と多様性は必ずしも対立しない。

根っこが同じだから個性を認められるし、違いがあるから共通項を見つけると嬉しくなる。
ダイバーシティが強調されているからこそ、普遍的なよりどころを探してみる。
いまの時代に求められているのは、こんな視点かも。
参考情報
この記事を書いた人

Neil(ニール)
ecbo (荷物預かりプラットフォーム) とプログリット (英語コーチング) でUI/UXデザイナーとしてインターン。現在はIT企業でデザイナー。 ハワイの高校。大学では法学を専攻。もともとはminiruとしてnoteを運営。
よろしければ、スキ・シェア・フォローお願いします 🙇
感想や今後のアイデアなど、コメントも待ってます 🙌
いいなと思ったら応援しよう!

