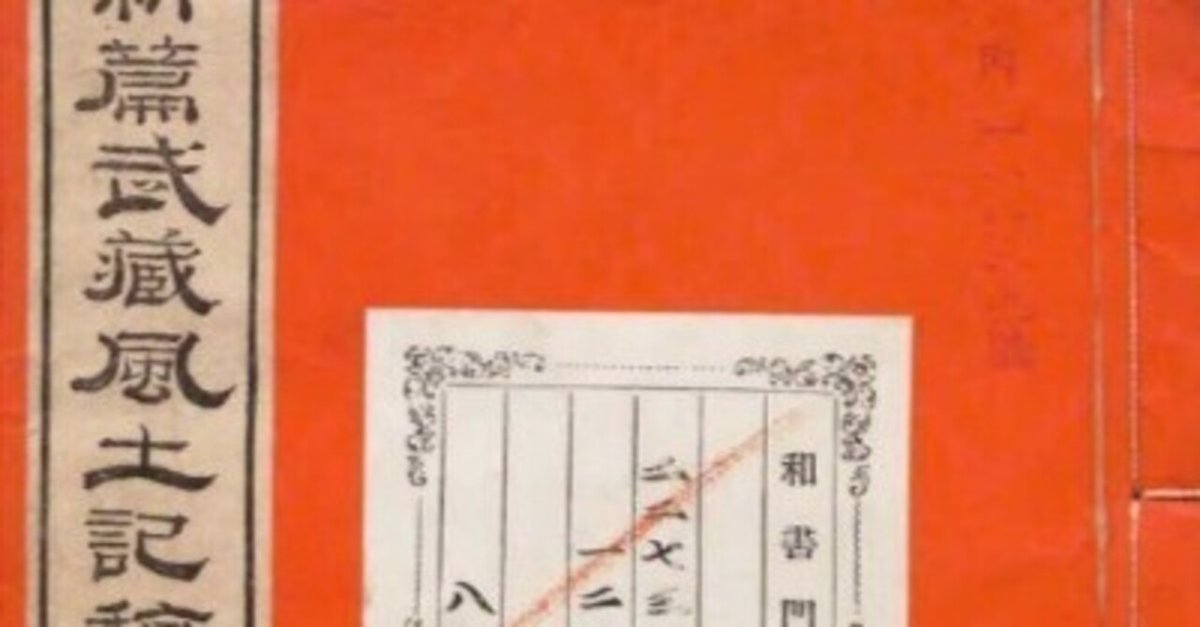
根津神社考9(新編武蔵風土記稿)
さて、前稿で一段落させた根津神社考。
次の神社に取りかかってみたいところだが、なかなか目星が付かず。
しばらくは、うまく本編に載せられなかった根津神社のお話で間をつなぎたい。
今回とりあげるのは、以前記した御府内備考や同続編と同じ文政期(1818年~)に作成された「新編武蔵風土記稿」。
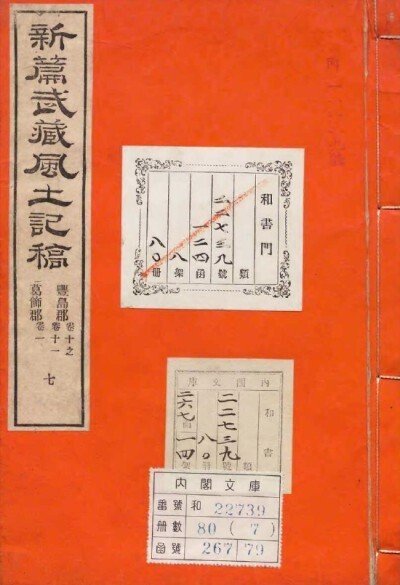
内務省地理局(1884)
幕府の命で、昌平坂学問所が文化7年(1810年)から起稿した官選地誌で、文政13年(1830年)に完成した。江戸の中心部は「御府内備考」として別立てされることとなったため、同書は武蔵国の江戸郊外の地誌である。
宝永3年(1706年)にすでに現在の位置に遷宮していた根津権現については、御府内備考に入ることになったからか、同書には「根津権現社蹟」として、遷宮前の千駄木の「跡地」についてのみ記載がある。
新編武蔵風土記稿巻之十九豊島郡之十一(文政13年(1830年)完成)
根津権現社蹟 村ノ東南ニアリ。九百十五坪余。按ニ根津権現始ハ千駄木今ノ太田摂津守ノ下屋敷中ニアリシヲ萬治年中被下屋敷ニ賜ヒシ時同所東ノ方今植木屋六三郞カ構ノ処ニ移サレ其後当初ヘ転シ寳永三年今ノ社地ヘ移サレシヨリ当所ヲ元根津ト唱フト云当所ニ鎮座ノ頃ハ村民八左衛門六左衛門次郎右衛門三左衛門利兵衛等五人ノ持ニテ祭事ノ時ハ本郷ニアリシ昌泉院ノ住僧ヲ請ヒ法楽セリヨリテ寳永三年御建立ノ頃昌泉院ヲ移サレテ別当職に補セラレシトナリ故ヲ以テ当所モ彼院ノ持ナリ稲荷ノ小社アリ社前ニ延寳三年ノ石燈籠及ヒ寬永九年ノ庚申塔ヲ立
(大意)
・下駒込村の東南にある。面積は915坪余。
・根津権現は、はじめは千駄木の太田摂津守下屋敷の敷地の中にあった。
・万治年中(1658~1661年)に下屋敷になったとき、東側の、今(=本書編纂時)の植木屋六三郎の店があるところに移され、その後、当所(社蹟の場所)に転じた。
・さらに、宝永3年に今の社地(現在の根津神社の場所)に移されたので、この社蹟は「元根津」と呼ばれている。
・ここに鎮座していた頃は、駒込村村民の(山下)八左衛門、(青木)六左衛門、(野口)次郞右衛門、(岡田)三左衛門、(奥田)利兵衛ら5人の負担で本郷昌泉院の僧に頼んで祭事を行っていた。
・宝永3年(1706年)に現在の根津権現が建立された際、昌泉院を移して別当に任じたので、この地も昌泉院が管理している。
・元根津には、稲荷の小社と、延宝3年(1675年)の石灯籠、寛永9年(1632年)の庚申塔がある。
根津権現の移転
根津権現(ねづのごんげん)の移転の経緯については、拙稿でも紹介してきた。軽くおさらいすると、①最初は千駄木の太田摂津(備中)守敷地の林のうちにあったものが、②団子坂を挟んで北側に移転され、③麟祥院領になったので更にその隣地(=元根津)に移され、④宝永3年に現在の社地に遷宮した。
この風土記稿でも、「太田摂津守敷地内」→「植木屋六三郎が構の処」→「当所(根津権現社蹟・元根津)」→「今の社地」へと移転したとしており、おおむね同じ内容が書かれている。
植木屋六三郎が構の処
このうち「植木屋六三郎が構の処」は本稿で初出であるが、武州豊島郡駒込村古来伝聞記の記載と照らすと「三崎といふ所へ行道の坂の下口左りの方野道の右角」にあたると考えられる(青丸の部分)。

国際日本文化研究センター所蔵
この千駄木団子坂の辺りは、江戸中期以降、菊などの栽培を行う植木屋が建ち並び、幕末から明治にかけては菊人形の名所であった。
その頃の地図をみても、青丸で囲った「元根津ト云」の脇に「植木ヤ多シ」の文字が見え、そのことがうかがえる。

(嘉永2年(1849年)~文久2年(1862年))
ここで名前が挙がった植木屋六三郎こと森田六三郎もその植木屋の一人。
ねづのごんげんが隣の敷地や今の社地に移った以降に、六三郎がここに植木屋を構えたということである。
この森田六三郎の植木屋、結構すごい店で、茘枝(ライチ)の結実に成功したり、浅草花やしきの生みの親だったりする。公式地誌に名前を書けば、読者が分かるくらいの有名店だったということだろう。
文京区千駄木三丁目南遺跡
この辺りに森田六三郎の植木屋があったことは、発掘調査でも確認されている。
ここには現在、東洋大学の国際交流宿舎があるが、この建設にあたって「文京区千駄木三丁目南遺跡」として発掘調査が行われている。調査では、1400件を超える植木鉢の破片が見つかり、中には植木屋六三郎の号「帆分亭」の押印があるものもみつかっており、ここが風土記稿にいう「植木屋六三郎の構の処」であると分かるという。詳細はこちら。
根津権現社蹟・元根津
植木屋六三郎のところから北隣に移された場所が「根津権現社蹟」。更にその後、宝永3年に今の位置に遷宮したため、跡地は「元根津」と呼ばれるようになった。現在の文京区立本郷図書館の辺りである。
この頃には、この元根津の敷地に「稲荷ノ小社」と、その社前に「延寳3年ノ石燈籠」「寬永9年ノ庚申塔」があったという。
これは東京市史稿に掲載された根津権現関連の図面の一つで「元根津」を示すもの。

原典不詳だが、地図右側(南側)の隣地に「百姓六三郎」の文字が見えるので、時期的には風土記稿と同じ頃かそれ以降のものと考えてよかろう。
高サ八尺(2.4mくらい)の鳥居の先に、たしかに「稲荷」の文字が見える。鳥居の手前左右にあるのが「延宝3年(1675年)の石灯籠」だろうか。くずし字が読めない。誰か読んで。
元根津は、遷宮後も根津権現の別当昌泉院の管理に置かれていたとある。
この敷地、後の昭和7年の本郷区の地籍台帳でも根津神社が所有者となっており(67ページ、本郷区駒込林町40参照)、明治以降も根津神社の管理下に置かれていたようだ。いつ頃までお稲荷さんがあったのだろうか。
村民八左衛門六左衛門次郞右衛門三左衛門利兵衛等五人の持にて…
御府内備考続編と同じ内容。同じ「神社書上」をベースに編纂されていると思うから仕方ないが、武州豊島郡駒込村古来伝聞記の「青木六右衛門」は、やはり「六左衛門」である。もう。。。
寛永9年(1632年)の庚申塔
庚申講については、他に詳しい説明があるのでここでは触れないが、江戸時代には庶民の間で非常に盛んになり、各地の路傍などに庚申塔がたくさんつくられた。元根津の敷地内にも同様に置かれていたということだろう。
これらの庚申塔は、明治以降、道路拡張などに伴ってどかされたものが各地の寺社などに残されており、今の根津神社の境内にも、6つの庚申塔が背中合わせにされて保存(?)されている。

文京区教委の案内によれば…あれ?

⑤梵字・庚申供養・寛永九年壬申(一六三二)・都島(庚)馬米村施主七名。
あった。「寬永9年ノ庚申塔」は、これではないだろうか。
寛永9年(1632年)ということは、万治・寛文よりも前なので、ねづのごんげんがここに来るより前に建てられたものだ。そして、元根津の地にねづのごんげんとともにあったが、ねづのごんげんが現在の社地に遷宮した際に元根津に置いて行かれ、その後、また合流したということになる。
どれどれ。たしかに「寛永九年壬申」と見える。
しかしさすがに全部は読めないな、ともう少し調べたら、書誌学者三村竹清氏の大正5年の日記(不秋草堂日暦)にスケッチが付いていた。ありがとう国会図書館!

寛永九年壬申
■(梵字)奉造立庚申供養一結衆二世成就攸
初春廿二日 都嶋凍馬米村
(下部)
与兵衛 四郎右衛門 妙元 宇佐右衛門 婦中 浄雨 長左衛門
庚申塔には、右に映っているもののように青面金剛や三猿が掘られているものがメジャーだと思っていたが、江戸時代初期の頃にはこうした文字による「板碑型」のものがみられるそうだ。案内板によれば都内で2番目に古いものとのこと。
頭の梵字は「キャ」と読むそうで、十一面観音菩薩を表すそうな。
おお、ねづのごんげんの本地仏である。なんだかこれは納得。
細かいところでは「都嶋凍馬米村」の読みについて、この日記では「練馬か不明」としているが、別の資料(注)で、これは「トシマゴオリコマゴメムラ(豊島郡駒込村)」と読むとの説を得た。もちろん、こっちの方がしっくりくる。
(注)大正・昭和期の画家で医師の木下秀一郎氏の随筆。なんかしれっとこれらの庚申塔がここにある経緯が書かれてたりする。文面が軽い。
ということで今回はこの辺で。たった数行だけど、思いの外膨らんだ。
「新編武蔵風土記稿」は、武蔵国の江戸中心部を除いてすべての範囲に及ぶ地誌。東京埼玉あたりにお住まいの方は、近所の寺社を調べてみてはいかがだろうか。
(謝辞)
本稿の植木屋六三郎のくだりの執筆に当たり、次のサイトで勉強させていただきました。他の記事も含め、むちゃくちゃ面白いのでおすすめ。勝手にリンクしちゃう。
