
渥美清
最後の付き人が見た 渥美清 最後の日々 「寅さん」一四年間の真実... https://www.amazon.jp/dp/4396317751?ref=ppx_pop_mob_ap_share
フランス・パリで「男はつらいよ 寅さんシリーズ」が全48作(渥美清の没後、「編集」でもう1作公開されたが、それは除く)上映され、毎回満員の大盛況。
フランス人にもとても強く支持されているという。
これを契機に、パリでの「日本商業映画」の上映も増えて行くという。


僕は若い頃、「男はつらいよ 寅さんシリーズ」の「笑い」が嫌いだった。


中学の頃、「筒井康隆」や「メル・ブルックス監督の映画」の「スラプスディックな笑い」にハマって以来、「寅さん」を代表とする「日本的なウェットな笑い」に強い「拒否感」を持っていたからである。

実際、「11PM」のAD時代、「生放送後」のゲストとスタッフの飲み会で、あの「パッチギ」を撮った映画監督・井筒和幸さんと「筒井康隆の笑い」を認めるか、認めないかで、深夜から朝方にかけて、2時間あまりも論争した。
もちろん、僕は「筒井康隆」支持派。
若気の至りである。
そんな僕だが、この年齢(64歳)になって来ると、無性に、「男はつらいよ 寅さんシリーズ」を観たくなる。


喜劇王「チャールズ・チャップリン」を映画評論家・淀川長治さんは絶賛していたが、僕はやはり、「ハロルド・ロイド」の「笑い」が好きだった。
そこには、「押し付けの御涙頂戴」は無く、純粋に「ドタバタで笑わせる事」に徹底していた「ロイド」の「精神」を見たからである。
余談だが、「刑事コロンボ」のどの話かは不明だが、「ロイドが住んでいた豪邸」がロケ地として使われている。
プチ・トリビア。





「寅さん」を演じた「渥美清」の「原点」は「浅草フランス座」。
だから、「フランス人」にも「渥美清」の「笑い」が受け入れられたのかも。


Amazonで偶然見つけたこの本。
「渥美清」の最後の「付き人」が、「肝臓癌」になっても、「寅さん」を、「死の1年前」まで必死で演じ続けた「渥美清」。
その映画では決して見せなかった「裏顔」、すなわち、「田所康雄(渥美清の本名)」の「素顔」を描き綴っている。
※渥美清が「金田一耕助」を演じた映画「八つ墓村」





著者は、様々な「示唆のある言葉」を「渥美清」から語りかけられ、その「珠玉の言葉」を「メモ」に記して残して来た。
その「メモ」が執筆の原点になっている。
「インバウンド」がみるみる増加して、地球上の様々な国の人々が「美しい憧れの国・日本」にやって来る。
「黄金の国・ジパング」だ。
そんな国の「日本人」に半世紀にわたって愛され続けた「男はつらいよ 寅さんシリーズ」と「渥美清」。
今、「日本人」はその功績を讃えながら、「後世」に残して行くべきではないか❓
「日本の文化」は「稀有な存在」だと思う。
「いろんな国の文化」を巧みに取り入れながらも、その根本は絶対に揺るがない。
「日本人」は「インターネット」や「スマホ」を見るのを止めて、「遊び心」のある「生活」に戻ってみないか❓
「日本文化」をゆったりと感じながら、「時間の流れ」に耳を澄ますのも気持ちいいものだ。
「コスパ」なんて必要無い。
「ダイパ」なんて必要無い。
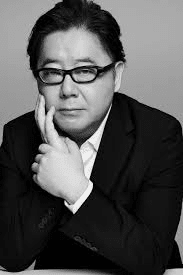
「秋元康」は公言している。
「私は『昭和』という時代が好きで好きでたまりません。私は『昭和』という時代にもらった貴重な財産の『ローン』を返す為に、『令和』という今を生きているのです」
全くその通り。
秋元康は1955年生まれ。僕は1960年生まれ。
彼の「最初の記憶」は、父親に連れて行ってもらった「東京オリンピック」だという。


僕も1964年の「東京オリンピック」の時、4歳。
兵庫県西宮市に住んでいた。
微かだが、「テレビ」に映し出された「白黒」の「東京オリンピック・開会式」の様子が僕の記憶にはある。
「赤」と「白」のユニフォームを纏った「日本選手団」。
「記憶」に「色」が付いたのは、「テレビ」で観た後、「アサヒグラフ」などの雑誌で写真を見たからだろう。
「渥美清」、生前の彼に「松竹大船撮影所」で会ってみたかった。
山田洋次監督に会えただろうし、木下惠介監督、山田太一にも会えたかも。


「映画の撮影所」はあの頃、「夢の工場」だった。
「渥美清」、「日本を代表する喜劇人(コメディアン)」である。
若い頃、「肺結核」で「片肺」を摘出していた「渥美清」。
「晩年」、「肝臓癌」を患い、それが「残された肺」に転移して、「薬を服用」しながら、「男はつらいよ」の撮影に臨んでいたという。

1996年8月4日、「渥美清」逝去。享年68歳。
亡くなって、もう28年が過ぎている。

生まれたのが、1928年(昭和3年)だから、ウチの父親と同い年。あの手塚治虫とも同い年。
今、この本を読んで、「渥美清」という人をとっても好きになった。
