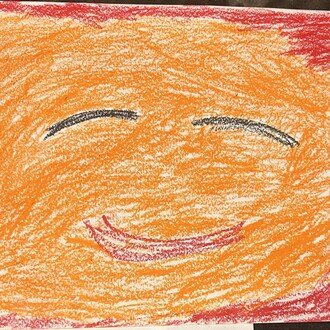【年長】とても良かった「おはなしドリル」
我が家には300冊を超える子供向けの本(絵本・図鑑・児童書)があります。
0歳の頃からずっと読み聞かせを行い、最近は長男6歳が自分で本を読む事も増えてきました。
今までの本に関するnote↓
1.ワークを導入したワケ
長男は最近、
「かがくのおはなし」や「学校では教えてくれない大切なことシリーズ」「幼年版ファーブル昆虫記」等、小学生向けの本を気に入ってよく読んでいます。
でも「本当に中身が頭に入ってる?」「本当に理解できてる?」という事が気になるのです。
実は「眺めてるだけなのでは?」という気もするのです。
感想を聞くと
母「この本どうだった?」
子「面白かった」
母「どんなところが?」
子「ここの顔が」 「バーンってなるところ」
母「……………」
正直「そこ?」って思うような感想が多く、能動的に読書してるのではなく、ただボーッとしてるのでは?と気がかりでした。
小学生受験の時も、話を最後まで聞けていなかつわたり、RISU算数や算数検定の問題に取り組む時も文章題の意味を理解できていなかったり、「国語は全ての教科につながる」という説は本当だなぁと早くも実感していました。
2.我が家にお迎えしたワーク
せっかくの読書、きちんと読めるようになってほしい!と思い、お気に入りの大型書店で幼児向けから小学生向けまで1時間かけて色々探し回った結果、「これは良いぞ!」と思ったドリルがこちら↓↓

リビングの棚に入れておくと、見つけた長男が「あー!これやりたい🤩」とものすごい食いつきが良かったです(笑)
・植物
・動物
・危険生物
・伝記
・恐竜
・プログラミング
等、長男の好きなジャンルのお話がいっぱい。
3.ワークの中身
1回分見開き1ページで構成されていて、上にお話、下に4問程問題があります。
記述式、選択問題、穴埋め問題など、形式も様々です。
4.取り組み方
①タイトルを読む
②日付を書く
③問題文を読む
④お話しを読む(問題の答えを見つけたら赤ペンでチェック)
⑤解答する
という順番でやっています。
最初は③と④を逆にしていましたが、難易度が上がってくると先に何を聞いてるのか理解しないと上手く答えを拾えなくなりました。
先に問題を読むのは邪道という考え方もあるかもしれませんが、読書をするときにも目的を持って読んだ方が記憶に残りやすいので、これからの読書にも活かせるようにこの方法に変えました。
[目的を持った読書の例]
・月が日によって形が変わる理由を知りたいから月の本を読む
・強い恐竜を知りたいから恐竜の本を読む
など。
5.ワークに取り組んだ効果
①一語一句しっかり読めるようになりつつある
(まだまだゴニョゴニョ誤魔化しますが💦)
②答えを探しながら読めるようになった
③漢字が少し読めるようになった
(人間、月、日等)
④音読み、訓読み(という言葉は知らないけど)があることを知った
(食べる、食事等)
⑤読み方が同じだけど、違う漢字があることを知った。
(同じ「しょく」でも、植物、食事があるなど)
このドリルは低学年向けなので、フリガナはあるものの漢字も沢山登場し、解答欄も漢字で書かないと足りない大きさだったりします。
漢字は副産物でしたが、今から無理なく楽しみながら漢字にも触れられて良かったです。
何より長男が楽しんでいるので買って良かったです✨
いいなと思ったら応援しよう!