
ID番号のつけ方にもドラマが!(疫学研究の裏側9)
疫学研究はどんなふうに進められているのか。「3世代研究」を例に、研究のリアルをご紹介する「疫学研究の裏側」シリーズをお届けしています。
前回の8回目では、対象者を女性だけ、そして学生世代の若年者は栄養士養成校の学生だけ、という偏った集団で調査をした、その意味を紹介しました。
得られた結果を対象者となった調査参加者以外の人にも広く当てはめられれば、社会全体で活用できます。とはいえ、疫学研究はどこまでいっても「研究に参加したその対象者ではどうだったか」ということしか語ってくれません。その得られた結果と同じ結果をほかの人たちに当てはめられる可能性が高いのか、低いのか、といった確率的な考え方で、研究結果は使うものだと思ってほしいです。そして、研究結果を使うためには、「その対象者での結果はこうだった」と自信をもって示せている必要があります。その研究自体が丁寧さに欠けて、信頼度が低くては、結果を当てはめる以前の問題になってしまいますからね。
さて、参加者リクルートの戦略・注意点(疫学研究の裏側6)、参加者への接し方(疫学研究の裏側7)、対象者選定の意味(疫学研究の裏側8)を解説してきましたが、研究の進捗としては疫学研究の裏側5で示しているスケジュールの9~11月ごろ、共同研究者の先生方への参加呼びかけと実際の研究参加者の参加募集のあたりをお伝えしていました。そして使える研究費の予算から、学生7000人(7000世帯、つまり3世代の合計は2万1千人)ほどの調査はできる見込みで参加者の募集をしていました。各校の学生参加者の合計がだいたい7000人となった11月末ごろ参加募集を締め切りました。
このあとは、各校で調査が実施できるように、細かい準備を進めていく段階になりました。各校の現場では、質問票を配布して回収します。その後調査事務局で確認作業をして、不備がある参加者の質問票は各校に返却するため、各校では再度対象者の方に質問票を配布して回答をやり直してもらってまた回収する、というということお願いすることになります。そこで重要になってくるのが「ID番号」管理です。
●参加者の状態はID番号で管理する
各校で、共同研究者の先生方には、どの学生が調査に参加しているかを知っておいてもらう必要があります。さらに、その参加者には質問票を配布したか、時期がきたら提出してもらってそれを回収したか、調査事務局から再調査のための質問票の返却があったらそれを渡したか、そして回収したか、など、共同研究者の先生方には、各質問票が今どのような状態になっているかを管理していただくことにしていました。もちろん、事務局でも、事務局に質問票が返却されたかどうかなどを確認して進めます。そのときに、「どの参加者の」と個人ごとの管理のためにはID番号が重要な役割を持ちます。共同研究者の先生方と事務局の間では、各参加者の状態をやりとりするときに、参加者に固有のID番号をつけておいて、このIDでやりとりし、状態をリスト化して管理するようにお願いしていました。
●倫理的配慮と調査実施の効率化の考慮
個々の参加者の状態のリストを作るとき、ID番号でなくても、参加者の氏名を記載して管理することはできます。けれども、個人情報保護の観点から、調査員が個人を特定できるような情報はなるべく持たないほうがよいのです。倫理審査のときの申請書類にも、「参加者はID番号で管理するので、研究者は個人情報を取得しない」というふうに記載することを求められ、実際にそのように運営できるように工夫するように助言されます。そのために、研究事務局では、参加者の氏名は取得せず、IDで管理していました。
とはいえ、現場の共同研究者の先生方は、参加者のお名前を知っていますし、どの人が何番のIDで参加しているかは知っておかないと、質問票を配布したり回収したりすることができません。そのために、共同研究者の先生方には氏名つきの参加者のIDリストを持っておいていただき、必要に応じて使ってもらうことにしました。
●戦略的につけると事務処理が効率的に!
では、ID番号をどうつけたかというと、たとえば「101-〇〇〇〇〇〇」というふうに、3桁の学校番号とそれ以下は学籍番号というIDを調査実施中は使いました。
始めの学校番号は、事務局でつけることにしました。今回の参加校は、調査開始の時点では88校ありました。1~88で学校固有のIDはつけられそうです。そのとき、経験のなかった私たちは、普通に1~88の番号をつけようとしていました。そのとき、すでに調査を何度も実施したことのある先生方、先輩方からいただいたアドバイスとして、最初の番号が1で1桁、10以降は2桁になると、不便なことがある、ということでした。たとえば、途中から桁数が変わってしまい、一覧表にしたときに表記がずれて管理しにくい場面があること、パソコンの仕様によっては、「順にソート」という操作をして1、2、3…10、11、…20、21、…と並べたいのに、1、10、11、…、2、21、…、3と並んでしまうことなどです。すごい!経験者ならではのご意見です!!
そこで、学校番号は101から初めて188まで、北から南にかけて順に附番し、全校で3桁の番号を使いました。そして、ハイフンの後ろの個人番号は、各校で普段から使っている学籍番号を使っていただくことにしました。ただし、英字はその後質問票を機械で読み取るときに読めないので、英字はぬいてもらうか、別の数字に変えてもらって、数字のみで附番してもらうことにしました。
●ミスを防ぐための配慮
個人IDに学籍番号を入れたのは、参加者のみなさんが普段から馴染みのある番号を使った方が、参加者ご自身も入力の間違いが減り、共同研究者の先生方も管理しやすい、と考えたためです。学籍番号を使うというところは、個人を特定できるように感じられるかもしれません。たしかに、共同研究者の先生は、その学校で使われている学籍番号と参加者の氏名を知っているので、個人を特定できます。それは質問票のやりとりや管理のために必要なことですので仕方ないです。ただし、共同研究者の先生は、封筒の中に入っている質問票を見ないので、各参加者がどのような回答をしたのかはわかりません。これによって、個人の特定の回答を知り得ない状態になっています。倫理的配慮できているということになります。封筒は、ちゃんとシールがついていて、封をできるものにしていました!
そして、事務局では、回答を見ますが、学籍番号を見ても、その個人の氏名は提出してもらっていないのでわからないわけです。この状態であれば、やはり倫理的配慮はできている、となります。

学校番号と学籍番号を書いてもらうことにしました。(3世代研究のマニュアルより)
●最終的には匿名化データへ!
一方で、これは最後の話ですが、研究を実施するときに、調査で得られたデータを共同研究者の先生方に配布したら、学籍番号のままだと個人が特定できてしまうのでは?と思われますよね。そのとおりで、そうならないように、最終データを配布するときには、事務局で、個人番号のIDを配布用IDに附番し直して、それで配布しました。このように、個人を特定できない番号に附番することを、疫学用語で「匿名化」といいます。学籍番号とはまったく違うIDにしたので、データを見ても、共同研究者の先生方でも参加者個人を特定できないようになっています。
ちなみに、IDの付け方としては、今後地域別に解析したいとか、ある状況の県の学校だけ取り出したい、とか希望があれば、最初からIDに意味付けをもたせて附番する方法もあるということでした。たとえば、3桁のうちの最初の2桁を県の番号1~47のどれかにしておいて、最後の1桁を学校固有の番号にする、などの方法です。今回は、ID番号を見てどの地域の学校なのか、が想像できないようにしたかったのでこの方法はとっていませんが、データ解析をするときにやりやすい方法を追求する、ということが、IDひとつとっても色々あるんだな、と学びました。しかも、解析するときにデータを目の前に考えるのでは遅くて、こうした準備の段階で今後の解析をやりやすくするための工夫ができるものなんですよね。
●まとめ
調査を実際に実施するときには、どの参加者が今どういう状態なのか、という把握が必要です。一覧表(リスト)などを使って、ID番号を附番して管理することも多いと思います。そのときに、事務作業を進めやすくする必要があります。対象者のことを、IDを見るだけで状況がわかるようにする工夫は、調査の準備の段階から考えることができるんですね。一方で倫理的配慮も必要になります。
IDひとつとっても、そのつけ方にはドラマがある!の意味、わかっていただけたでしょうか。こんなふうに、その後の作業の効率アップのために、事前の準備を綿密に行うことが、ていないな結果を得るためにはとっても大切になってくるんですね。
「研究の裏側」シリーズの初回はこちら
「研究の裏側」シリーズの続きはこちら
【メールマガジン】
信頼できる食情報かを見きわめるための10のポイントをお伝えしています。ぜひご登録ください!
https://hers-m-and-s.com/p/r/sPWrxMBU
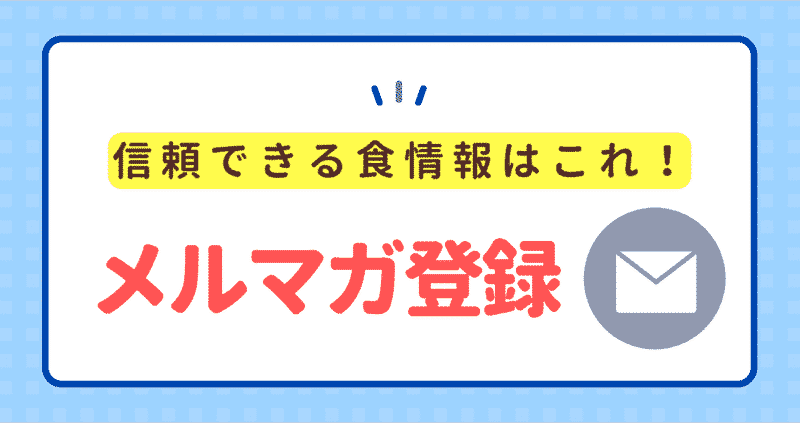
すべての100歳が自分で食事を選び食べられる社会へ。
一生で味わう10万回の食事をよりよい食習慣作りの時間にするための
お手伝いをしていきます。
また読みにきてください。
記事がよかったら「スキ」リアクションをお願いします!
励みになります!
【食情報・健康栄養情報を見きわめるためのコツ】
この5つのステップで、信頼できる食情報・健康情報の候補を簡単に抽出できます。
