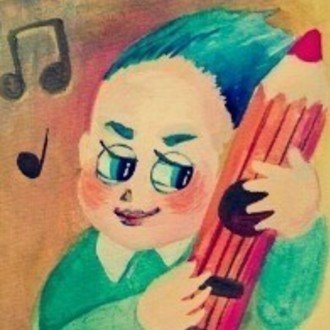【心の詩歌】【公開記事】氷河期世代はきつかったのか
「氷河期世代」と言われる、就職難だった世代があります。多くの若者たちが、厳しい状態に陥りました。
氷河期世代が終わってしばらく経った現在も賃金の水準は回復していません。
氷河期世代の被害者性を「アピール」とみなして不快に感じる現代の若者もいるようです。
私の感覚では、氷河期世代悲劇は賃金低下そのものではなかったように思います。
長いデフレのあいだ物価も低かったからです。生活はどうにかなりました。
しかし、氷河期世代は不当な労働環境にいました。求人の少ないなか、彼らはブラックな労働から逃れられませんでした。
それを「サービス残業」の観点から調べてみました。
サービス残業は、企業側では記録に残しません。
そこで、二つの政府統計を用いることにしました。
「賃金構造基本統計調査」と「労働力調査」です。
賃金構造基本統計調査は、事業所を対象としています。つまり賃金を支払う側が答えた調査です。
労働力調査は世帯を対象としています。つまり労働者側が答えた調査です。
企業が労働させたと行っている時間と、労働者が労働したと言っている時間、二種類の労働時間の食い違いがサービス残業であると推定しました。

ここでは2006年から2023年の統計を調べてみました。
2006年当時はサービス残業(推定)が非常に多かったということがわかります。
2019年の2.4倍ほどの時間です。
また、2020年から、労働力調査の就業時間が賃金構造基本統計調査の就業時間よりも短いという逆転現象が起きています。
こちらは、2020年1月15日に国内感染者が発生した新型コロナウイルスの影響と考えられます。
たとえば自宅待機命令などによって、労働者は就業時間と思っていなくても、企業側は就業させた時間とみなしている場合があるかもしれません。
この記事の計算は厳密なものではありません。差を計算した二つの調査は対象者が別々だからです。
しかし、このような数値的確認をするにあたり、元にした統計資料自体は政府統計を用いており、元数値だけは信頼性が高いです。
「e-Stat」というサイトで政府統計をダウンロードできます。
目的の数値を探すのはそれなりに手間ですが、自宅で調べ物・考え事ができる時代になりました。
(この記事は、マガジン「心の詩歌」の月初無料記事です。「心の詩歌」は、詩や短歌の紹介、社会問題、哲学などを題材としています。)
参考資料
【1】厚生労働省:賃金構造基本統計調査
「雇用形態、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」
上記は「正社員・正職員」「正社員・正職員以外」で表が分かれているため、人数を掛けて平均を取った。
【2】総務省統計局:労働力調査
「農林業・非農林業,年齢階級,週間就業時間(◯◯区分)別就業者数(2006~2011)」
「農林業・非農林業・年齢階級,月末1週間の就業時間別就業者数(2013~2023)」
※「◯◯区分」の「◯◯」には数値が入っているが年によって異なる。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?