
プリキュアで描かれた「障害」と介入について。あるいは、「理解できない他者」と共にあること。
◯「理解できない他者」に対して、我々は何を言うことができるのか
先の記事で『プリティーリズム』シリーズは「理解できない他者」を描いていて、それが良いという話をした。私はこのアニメが描きだしたこの独特の距離感が好きだし、価値のあるものだと思っている。
しかし、違う視点からも考えてみよう。実際のところ私たちは、(家族などの特殊な関係を除けば) 生活のなかで他者のことを簡単に理解できると思い込んでしまうことなどあまりないのではないだろうか。ましてや自分と相手が同じ存在であると思われるような場面に遭遇することなどないし、あったとしたらそれはきっと「奇跡の出会い」だ。むしろ、私たちはよく「相手は相手だから…」「相手の事情があるから…」などといって、相手に対して介入することを避けてしまったりする。そういう場面のほうが日常には多い。そうすることで避けられるトラブルがたくさんあるからだ。そして、それが時に、よくない帰結を生むこともある。
例えば、重い病にかかった人や苦しみの最中にいる人が、怪しげな似非科学などにはまって、明らかに不当な形で金銭を搾取されていたとする。私たちはそれに対して何を言うことができるだろうか。「何かを言わなければならない」、と思う人は多いだろう。実際に「何かを言うことができる」という人もいるかもしれない。しかし、「あの人が幸せなら」と考えて躊躇ってしまったりすることが、私たちにはある。その人物の苦しみを知っていればいるほど (そして、その苦しみを私はわかってあげることができないと思うほど)、声をかけられなくなってしまうことが、私たちにはある。
何年か前、摂食障害について勉強しているときに、いろんな学会やイベントで、会場のロビーに似非医学の業者のブースが大量にあるのを見て驚いたことがある。ある業者は、百万円もするオルゴールを会場で売っていた。それを聴くと過食症も拒食症も治るのだそうだ。シンポジウムの運営委員会には、自由診療や混合診療を強く訴える医者も参加していた。(…)
そういうものが全体として、「本人がそれがよいと言うなら」「本人が望むなら」という論理で外からの批判や介入を排除している構造があった。これは、「本人がよければそれでよい」という論理に基づいた支配の構造だと思う。
だが、確かに当事者本人の意志は、最大限に尊重されるべきである。
ここのところで私はいつも声がでなくなる。
(岸政彦『断片的なものの社会学』「海の向こうから」)
一度まとめておこう。実は、私たちは他者を「理解できない存在」として扱うことで、他者を「尊重」すると同時に、他者から「距離」を置きながら生きているのではないか。そして、そのように距離をとってしまうことが、ときにあまり良くないことに利用されてしまうことがあるのではないだろうか。
そうすると、次に問題となるのは「理解できない他者」に対して「どう介入するか」(あるいは、そもそもそれは許されるのか) ということであろう。
こうした問題について考えないまま「理解できない他者を描くことの意義」を論じていくと、極端な個人主義であったり相対主義であったり、とにかく片手落ちの状態に陥ってしまいかねない。そしてそのような個人主義や相対主義は、極端に自己責任を強調する立場と裏表の関係にあったりする。「相手は理解できないのだから関わらなくても (関わらないほうが) 良い」という形で他者との分断が招かれてしまうことがあるし、実際に先日の記事もそのように読まれたところがあった。
しかし、繰り返しになってしまうが、そうした分断を招いてしまうと、その先に待っているのは「自己責任の強調と、それを利用した搾取」であろう。他者から過剰に理解されてしまう苦しさから逃れようとして、今度は自分ひとりで自分を背負っていくという苦しさや、関わりたいと思う相手から拒絶されることの苦しさを抱え込み、またそれを利用する人々を呼び寄せることになってしまうのである。こうした社会もまたある種の苦しさに満ちているだろうし、何よりそのようにして自己責任を強調する社会は「強者にとって生きやすく、弱者にとって生きにくい」。
だから、この問いから逃げてはいけない。他者が「理解できない」ものであると認めた上で、それに満足するのではなく、もう一歩踏み出し、「では、どう関わるのか」を問わなければならないのである。
そこでこの記事では、『プリキュア』を取り上げつつこの問いに接近していくことにしたい。ただし、先に断っておきたいのだが、何か明確な答えのようなものは提示できそうにない。では、この記事では何を書くのか。答えを出せないとしても、問いから逃げないこと。そして、他者を理解できないとしても、そこから去らないこと。これを書いてみる。
他者への介入を重視する『プリキュア』は、上で述べた問題に対してはっきりと答えを与えてきたわけではない。ときおり、明らかに問題のある介入の描写をしてしまうこともある。そのことは認めておこう。そして、それゆえに、作中で使われる言葉が無責任で浮いたものに感じられてしまい、これを批判したくなる人もいるかもしれない。ただし、これこそが大事だと私は思うのだが、『プリキュア』は少なくともこの問いから逃げたりはしていない。答えは出せないし、失敗することもあるけれど、それでもこの問いに向かい合ってきた。決して、単純な世界だけを描写してそれで済まそうとはしてこなかった。また、同じようにして他者とも向かい合ってきたし、そこから逃げることを良しとはしてこなかった。そういうことを見ていき、その意義を論じたい。
* * * * *
◯ 過剰なコミュニケーションと、拒絶の可能性
『プリキュア』シリーズは、「大人の理屈」に「子どもの真っ直ぐな力」を対置させることでその位置を確立してきたように見える。例えば、「お前は戦術を知らないし経験がないから私には勝てない」という正論には理屈を超えたメチャクチャな友情と馬鹿力で応え、「お前は一人じゃ何もできない。所詮自分のために相手を必要としているのだ」という理屈には「一人じゃ何もできなくて何が悪い。私が私のためにパートナーを探して何が悪い」と応えてきた。「騙されるほうが悪い」という敵には「騙すほうが悪いに決まってるじゃない」と言い切り、「放っておいてほしい」という人には「また来ます」と伝える。大人なら正論だと思ってしまったり、一歩引いてしまうような場面でも、真っ直ぐにぶつかり、ときに理不尽なまでの力で状況をひっくり返す。そういう、「言える強さ」を売りにして、独特の面白みを演出してきたという側面がある。
他方で、その「まっすぐに他者と関わる」という姿勢には常に、「他者から拒絶されるかもしれない」という可能性がつきまとう。相手に対して踏み込んでいく行為は、ときに相手にとって救いになりうるかもしれないが、相手の心を土足で踏み荒らしてしまうことにもなりえるのだから。
そうした場面は、初代プリキュアの頃から描写されていた。例えば、主人公の一人である雪城ほのかと、敵が扮した存在であるキリヤとの関わりは印象的だ。ほのかから「もっと人の心を大切にしてあげて!」と言われたキリヤは、「じゃあ、アンタに僕の気持ちがわかるのか! 心ってなんだ?僕の心っていったい何だ!あるとすれば、どんな心だよ!! ……人のこと、何も知らないくせに、偉そうなことを言うな!」と悲痛な調子で叫ぶ。
話が長くなるので詳しいエピソードの内容には踏み込まない (気になる人は初代『ふたりはプリキュア』の18話を見てほしい)。ただ、この話のなかで描かれるすれ違いのシーンはとても印象的だ。
やはり、ここでも我々は「他者の理解できなさ」の描写を、見て取ることができる。キリヤとほのかはこのあと距離を縮めていくことになるし、少しずつ惹かれ合っていたからこそこういったすれ違いが起こってしまったということはもちろん考慮しておくべきだ。ただ、ここで確認しておきたいのは、『プリキュア』もまたその初期の段階から、理解できぬ側面を持った存在として他者を描き、その他者によってコミュニケーションが拒絶される可能性があるということから目を背けては来なかったということである。
* * * * *
◯「いますぐ足を治してくれる? 私を踊れるようにしてくれる? ……何も出来ないくせに、『助ける』なんて簡単に言わないで!」
そして、その「理解できぬ他者」という問題が、ときに介入の問題と関わることがある。そのときにこそ、プリキュアの存在意義が大きく問われることになる。ここではその最たる例として映画ハピネスチャージプリキュアを取り上げることにしよう。
この映画は、宣伝のため冒頭の映像がここで無料公開されている。だから未見の方はぜひ一度見てほしい。冒頭の数分だけで、この映画が大きな挑戦をしようとしていることがわかるはずだ。

冒頭のシーンを見てもらえればわかるように、この映画ではまず、プリキュアたちがテレビのなかの存在であるということ、そして画面を通じて「みんなが幸せ」というイメージを伝えてくる存在であるということが、ややメタ的に提示されている。敵が出て、必殺技を使って、みんなが幸せになる。そういう、テレビ本編で毎週流されるテンプレ展開は、冒頭の数分で終わってしまう。その映像を見たうえで、映画限定のゲストキャラである少女「つむぎ」は、こうつぶやくのだ。「みんな、幸せ……? 私は、全然幸せなんかじゃない」。彼女は、「みんな幸せ」なテレビのなかの世界から、疎外されているのである。
彼女が幸せになれない理由は、彼女の障害にあった。ある日バレエの練習中、つむぎの足は突然動かなくなってしまう。全く力が入らず、リハビリをしても効果はなかった。彼女は永遠に踊れない少女になってしまったのである。バレエに励んできたつむぎは、その現実を受け入れることができない。見舞いに来た友人も拒絶し、やがて彼女は独りになってしまう。床に置かれたバレエシューズと静かに存在感を放つ車椅子が象徴的だ。
そして、だからこそ彼女は、プリキュアである「めぐみ」が安易に発する <「幸せ」にするためにあなたを「助ける」> というメッセージを、許すことができない。
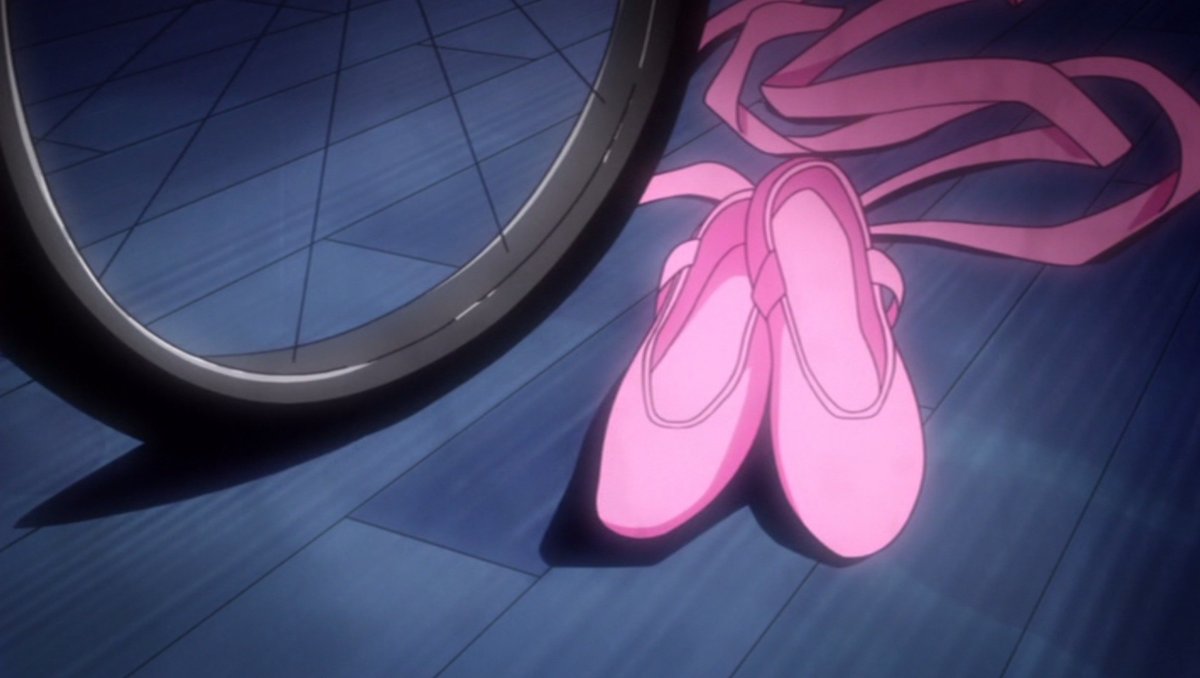
「ムリだよ……プリキュアにだって出来ないことがある。みんなを幸せになんてできっこない。」
「そんなことないよ。頑張れば、誰だって幸せに」
「私はダメだった!……頑張ったけど、ダメだった」
そうした彼女の状況を利用するのが、「幻影帝国」幹部ブラックファングだ。彼はつむぎのために、つむぎが踊ることのできる「人形の国」を用意し、そのうえで「私がプリキュアに倒されてしまうと、この世界も消えてしまう」とつむぎを脅す。
「苦しいのはこの世界か? 踊れない、友もいない現実の世界のほうだろう? ここにいれば、つむぎ、お前は永遠に踊ることができる。」
こうしてつむぎは、自分の世界を守るために、プリキュアを倒すことを決意する。踊れない世界には、友達もいない。一人で家から出ることもできない。テレビから流れてくるプリキュアの「みんな幸せ」というイメージは、ままならぬ現実への悔しさを掻き立てるだけなのだ。それに対して、少なくともブラックファングは自分のための「居場所」を用意してくれる。ブラックファングさえ倒されなければ、つむぎはたくさんの友達 (人形) に囲まれた自分の国で、お姫様として踊り続けることができる。

「ここにいれば私は踊れる。もう踊れない現実なんかいらないの。私は、ずっとここにいたい。誰にも邪魔はさせない。」
「私は踊りたい。どんなことをしても。」
ハピネスチャージプリキュアが面白いのは、プリキュアにとっての敵である「幻影帝国」の存在が、市民の間でも広く認知されているというところだ。プリキュアと幻影帝国の戦いはテレビで中継され、市民はその動向に一喜一憂している。地球上に拠点を置く幻影帝国は各国への侵略を日々進めており、侵略を食い止められるかどうかは世界中に存在するプリキュアの活躍にかかっている。要するに、幻影帝国は社会的に広く認知された「悪」なのである。現代におけるテロ組織のイメージにも合致するかもしれない。
重要なのは、テレビでプリキュアと幻影帝国の戦いを見ていたつむぎもまた、おそらく幻影帝国がどのような組織であるのかを知っていたということであろう。つまり、彼女は幻影帝国が世界的に認知されたテロ組織であり、度々自分の街にも侵略を行っているということを知った上で、そこに居場所を見出し、プリキュアを倒そうとしているのだ。すると、この映画が提示する問題は、(障害という視点を外して考えてみても) かなり複雑なものであるということがわかる。テロ組織のような社会的悪に対して、そこにしか居場所を見いだせない少女がいる。そして彼女は明らかにその組織に利用されている。そういうときに、何を言い、どのような形で介入することができるのだろうか?
少なくとも「助ける」という言葉は、ここでは無力だ。

「私、あなたを助けたい!」
「どうやって? いますぐ足を治してくれる? 私を踊れるようにしてくれる? ……何も出来ないくせに、『助ける』なんて簡単に言わないで! 現実世界にいたってつまらない。この国は、私にとっては大切な居場所なの!」
この映画の前半を貫いているのは、強烈な拒絶のイメージだ。現実に帰ろうと呼びかけても、幻影帝国は悪であるということを伝えても、その言葉は全てつむぎに拒絶されてしまう。つむぎが踊れない少女であるということを知らず、「みんな幸せハピネス」「悩み事を解決しちゃう」などといった言葉をつむぎに投げかけてしまったキュアラブリー (めぐみ) はここで、自分が何も理解していなかったということ、一見容易に理解できそうな他者が実は「理解できない」側面を有しており、それに対して一方的に「助ける」といった言葉を投げかけることの無責任を、突きつけられるのである。このようにして、つむぎとめぐみの間に断絶が浮かび上がる。
「どんな人だって私には関係ない。だって私の願いを叶えてくれたんだもん」
「みんな幸せハピネスにするんでしょう? だったら私のために、人形になって?」
* * * * *
◯「助ける方法がないなら、放っておく?」
「摂食障害の自助グループにも、何度か顔を出していた。いろんな女性がいた。少数だが男性もいた。ある女性は、死んだ猫を公園の土に埋めて、数日おきに掘り返し、それが腐敗していく過程をずっと見ていたという。別の女性は、リストカットが高じて両手両足の爪を自分でペンチで抜いていた。そして、わずかに生えてきた爪に真っ青なマニキュアを塗って、うれしそうに私に見せた。私は、おー、きれいやな、と言った。
自分で爪を抜く女性に対して、そんなことはやめろ、というのは簡単だ。しかし、それに何の意味があるだろうか。私たちには、彼女の青い小さな爪を見て、きれいだね、ということ以外に、なにかできることがあるだろうか。
本人の意志を尊重する、というかたちでの搾取がある。そしてまた、本人を心配する、というかたちでの、おしつけがましい介入がある。」
(岸政彦『断片的なものの社会学』「海の向こうから」)
介入することの難しさについて、改めて考えてみよう。わたしたちには、相手のことを「助けたい」と思っても、助けられないときがある。むしろ、そういうときの方が多い。それほどにわたしたちは無力だ。そして、そういうときに、助けたいと思っていたその相手が、「自分のことを助けてくれる人」や「自分の居場所」をどこかに見つけ出すことがある。それは似非科学やカルトかもしれない。あるいは、自分を傷つけることに安心を見出すこともあるのかもしれない。
そういう場面で、相手に何かを言いたいと思って、それでも何も言えなくなってしまうことがある。なぜ何も言えなくなってしまうのか。他者とは私にとって常に「理解できない他者」であるということを、わたしたちはよくわかっているからなのではないだろうか。「私はあなたの考えていることを理解できない。あなたの苦しみを理解できるだなんて簡単には言えない。だから、あなたにとってその場所が大切だというのなら、その救いが必要なのだというのなら、私はもう何もいうことはできない」。そういう優しさを、わたしたちは持っている。だから、相手の意に反して介入し、居場所を奪ってしまうことを、わたしたちは多くの場合避けている。とくに障害の場合は、その理解出来なさが際立つかもしれない。私は「自分では相手の痛みの全てを理解することはできない」と思ってしまうかもしれないし、相手は「私の痛みをそう簡単に理解できると思ってほしくない」と思うかもしれない。そういう形で、「理解できない」という断絶が顕現しやすく、またそれを利用されやすい。
だが、繰り返し最初の問いに戻っていくことにしよう。本当にそれで良いのだろうか? 私たちは、相手に近ければ近いほど、相手に何も言えなくなってしまったりする。何か言いたいと思いながら、それでも声をかけない「優しさ」を持っている。しかし、そこで何も言わないことが、その「優しさ」が、本当に正しいのだろうか?

「助ける方法がないなら、放っておく? それでラブリーは平気?」
つぐみに拒絶されて「何もできないのに、助けられないのに、助けたいなんて言って、つむぎちゃんを傷つけた…」と泣くキュアラブリーに対して、キュアハニーである「ゆうこ」はこのように問いかける。初めてこの映画を見たとき以来、この言葉が私の中にずっと刺さり続けている。
助ける方法がないのであれば、放っておくのだろうか。他者の痛みを理解できず、他者に何もできないのであれば、何も言わず何もしないのだろうか。その間は、ないのだろうか。
まず、助けられないけれど、それでも放っておけないという状態がある。そして、何もしてあげられないけれど、そばにいるという方法がある。何もしてあげられないけれどそばにいて共に悩むことが救いになることもあるし、そういう風になれるなら、それは拒絶したり関係性を断つよりも、おそらくずっと良い。
我々は極端から極端に振れやすい。とくに一般論で話をしようとすると、そういうことになりやすい傾向にある。だから、「相手を理解できない」のであれば、相手を尊重して、相手との関わりから離れたほうが良いと論じてしまったりする。しかし、先日の記事を思い出してほしい。むしろ、「理解できない」けれど、それだからこそ「共にいる」という領域が存在していて良いはずなのだ。相手のことを理解できると思い込んで苦しいコミュニケーションに陥るのではなく、さりとて理解できない相手とのコミュニケーションから「尊重」を盾に逃げるのではなく、「他者として共にあること」。それが可能になる隙間が、あるはずなのだ。
ゆうこは、めぐみに「助ける方法がないなら、放っておく? それでラブリーは平気?」と尋ねる。そして、つむぎもまた人形の「ジーク」から、踊るために他者を騙し拒絶することで、本当につむぎは幸せになれるのかと問われる。こうして、つむぎを尊重し助けることを諦めて距離を取ろうとしためぐみと、踊りたいという自分の目的ためにめぐみを拒絶し排除しようとしたつむぎとの間に、<救う-救われる><倒す-倒される>の関係ではなく、「その場から逃げずに、共にいる」という関係の可能性が生まれていく。このようにして、この映画は二人を向き合わせようとするのだ。ここに、この映画の大きな価値がある。大人なら相手を尊重して一歩引いてしまうところで、引かない。これはプリキュアだからこそ描けた可能性であるだろうし、大切なものだ。
しかし、この関係の可能性は、ブラックファングの策略によって再び封じられてしまうことになる。そしてこの映画は、更に深い断絶の描写へと観客を誘うのである。これはこの映画の最も面白いところにあたると思うのでネタバレは避けるが、ブラックファングは、つむぎが自分自身を呪う存在になるように周到な準備をしていた。その策略のせいで、他者からの励ましや想い、他者の行動の全てがつむぎにとって不幸として感じられてしまうようになる。<私がいるから、私に近づこうとする人たち、私を助けようとしてくれる人たちが不幸になってしまう。私さえいなければ>。このようにして、つむぎは自分の存在自体を呪うようになり、自己と他者の全てから、目を閉じて耳をふさいでしまうのだ。彼女は、不幸の繭に囚えられ、他者を拒絶してしまう。

「私のせいで……?」
「そうだ! お前は不幸そのものだ!」
* * * * *
◯ そばにいて、祈りを捧げること。
だが、もう、めぐみはつむぎから逃げない。めぐみは、つむぎが引きこもる不幸の繭に飛び込んでいく。何かが出来るわけではない。「助ける」ための方法なんて何も思いつかない。しかし、それでも、他者を拒絶する繭のなかに飛び込んでいくのだ。そして、彼女は繭のなかで、何もできないけれど、つむぎに寄り添い、泣き、彼女の幸せを祈る。


「つむぎ、たとえプリキュアでもお前を幸せにはできん。踊れないお前はますます不幸になるだけだ!」
「そうだね。踊れない私は、不幸だとずっと思ってた。でも……私の幸せを願ってくれる友達がいる。力になってくれる友だちがいる。私は全然不幸じゃない。だから、こんな世界も、いらない!」
私は、この映画の介入の描き方や、この映画が提示する回答が100点満点のものだとは決して思わない。それでも、障害をテーマにしつつ「理解できない他者の苦しみ」という問題と向き合って、それに寄り添ったこと。そこから逃げなかったことに、この映画の価値はある。冒頭で「みんな幸せ」という言葉をテレビに写しそれを否定したうえで、そのようなメッセージを発することにおける問題にも真摯に向き合ったのだ。プリキュアが伝えるメッセージを反省しながら、それでもプリキュアだからこそ描ける他者との関わりを描ききったこと。ここに、大きな価値がある。
改めて、我々は「理解できない他者」に対して何を出来るのか。何をすることが許されているのか。これを、ある程度一般的な形でまとめて記事を閉じることにしよう。
やはり、他者は私にとって理解できない側面を持つ。このことは忘れてはいけない。相手の痛みを簡単に「理解できる」と思い込んで、それを「救ってあげよう」とする行為は、むしろ相手を理解できぬ存在に変えてしまうだろう。「そんなに簡単に理解されて、あなたの一方的な満足のためなんかに『救われる役』を押し付けられるのは御免だ」と相手が思えば、その相手は「理解されること」からなんとかして逃げようとするはずだ。こうして、コミュニケーションは終わってしまう。
しかし、しつこいようだが、「理解できない」から距離をとって尊重するという方法もまた、それがコミュニケーションの場から逃げる行為であるという点で変わりはない。そして、そういう「尊重」が搾取に利用されることがある。私たちは「それで本当に幸せなのか」と相手に問いたくなって、それでも私の介入が相手から望まれていないかもしれない、介入によって相手の居場所を奪うことになってしまうかもしれないと悩み、苦しんだりする。
そういうときに、「理解すること」も「助けること」もできないことを認めながら、それでも他者と共にいるということができる。何もできないけれど、それでも何かをしてあげたいと思うことはできる。そして、「理解」や「救済」のような押しつけではない形で、相手に寄り添うこともできる。そうした形で関わり合うことに、我々は可能性を見出しておこう。
もちろん、そのような形での他者との関わりは、とても弱い力しか持たない。その点でこれは、「祈り」のようなものなのかもしれない。だが、そのような、微かな祈りにこそ、私と他者との断絶を越えていく可能性を見出すことができる。過剰なコミュニケーションと過少なコミュニケーションは、それぞれ他者と共にあることから、私達を遠ざけてしまうだろう。だからこそ、ただ、側にいて祈るのだ。
それが届くかどうかはわからない。届かないとすれば、それにどんな意味があるのかもわからない。それでも、私達には、他者に対して祈りを捧げることが許されている。
そして、その祈りが、届くこともある。届いて、何かが変わることもある。他者に対して自分が求める変化を押し付けるのではなく、ただ届くよう願う。そうやって、人と人との間につながりを作ることが出来るかもしれないし、そういう形でなら「みんな幸せ」というメッセージを伝えることもできるかもしれない。
他者との関係から逃げ出すのではなく、そのような形で関係を築いていけるのであれば、それが最も良い。そういう単純なことを確認して、その弱さを認めつつ、ただ愚直にそうした関係を望み、「理解できない他者」から逃げない。そのようなあり方こそが、我々に求められる態度なのだと思う。

「私ね、バレリーナになりたい。私も誰かのために踊りたい。自分のためだけじゃなくて、たくさんの人に幸せになってもらえたら嬉しいな、って。」
「私たちはそれぞれ、断片的で不充分な自己のなかに閉じ込められ、自分が感じることがほんとうに正しいかどうか確信が持てないまま、それでもやはり、他者や社会に対して働きかけていく。それが届くかどうかもわからないまま、果てしなく瓶詰めの言葉を海に流していく。
そして、たまに、海のむこうから、成長した美しい白猫の写真や、『素晴らしいアレキサンダーと、空飛び猫たち』という本が届くことがある。
だからどうした、ということではないが、ただそれでも、そういうことがある、と言うことは出来る。」
(岸政彦『断片的なものの社会学』「海の向こうから」)
@@@@@@@@@@@ 以下、補足 @@@@@@@@@@@@
(補足1:『プリティーリズム』でも、こうした形での他者との関わりが描かれていた。「おとは」と「いと」のエピソードを挙げておこう。おとはは、苦しむいとに対して何も言うことができない。しかし、それでも彼女はいとの側から離れない。彼女は「何もできない」自分に泣きながら、何かアドバイスや励ましの言葉を贈るのではなく、ただ黙っていとに紅茶を入れてあげるのだ。ここには、「理解」ではない形で「寄り添う」という関係のあり方の良さが、描かれている。
私たちは、相手の苦しみを理解できないとしても、側にいることができる。側にいて、紅茶を入れてあげる程度のことができる。何か過剰なことを言うわけではない。むしろ何も言えないということに涙し、それでもなおそこから逃げない。理解できないということを受け入れながら、離れない。そういう形で、無力な祈りを捧げることが、私たちには許されているのである。そして、それこそが「理解できない他者」との適切な距離感なのかもしれない。)
(補足2:この記事は結局のところ、先日のプリティーリズムについての記事と逆の方向から論を始め、同じ結論へとたどり着くものであった。先日の記事では、「みおん」が理解という技法から二人をすくい上げ、そのうえで「あいら」と「みおん」がただ「りずむ」に寄り添うことに可能性を見出したのである。
こうして、2つの方向から同じ結論への記事を書くことで、少なくとも片手落ちの状況は脱することができたと思っている。「理解できぬ他者から逃げる」という形で読まれてしまったあの記事に対して、改めて「理解できなくても (できないからこそ) 共にいることができる」ということを突きつけることができた。)
(補足3:子ども向けの番組は、「困っている人を放っておかない」という規範を伝える傾向にある。だから、それがときに「他者の事情を考慮せず、過剰に他者に対して介入している」と批判されたりする。しかし、私が見るところ、子供向けの番組は様々な形で、そうした問題と向き合ってきていた。
例えば、子供向け番組の代表であるアンパンマンもまた、そうした問題に対して繊細な答えを提示している。
この映画で描かれているのは、介入することに必然性はないということ。それでもなお、そうしなければ生きられない人がいるし、そこに生きる意味を見出すこともできるということであった。この映画もまた主人公のドーリィーがアンパンマンの姿勢を徹底的に否定していくという点で、映画ハピネスチャージプリキュアとどこか似ている。否定され、拒絶される場面を描いた上で、それでもその拒絶に対してメッセージを伝えようとするのだ。)
(補足4:私たちは、他者を理解することはできない。しかし、理解できないということをとっかかりにして、他者に寄り添うことはできる。例えば、自分の孤独と他者の孤独をつなぎ、そこに微かな祈りを捧げることができる。
こうしたところから、他者とのあり方を考えていくこともできる。)
(補足5:本文中で頻繁に岸政彦「海の向こうから」を引用している。実は、映画ハピネスチャージプリキュアが公開された当時、ちょうど『断片的なものの社会学』がWEB連載されていた。たぶん、映画を見たのは「海の向こうから」が公開されたばかりのころだったのだと思う。映画館から出てすぐにこの記事を読み直したのを覚えている。そのせいか、映画ハピネスチャージプリキュアを見るたびにこの文章のことを思い出す。そういうこともあって結構この文章から刺激を受けながら構想を練ってきた。『断片的なものの社会学』、オススメです。)
